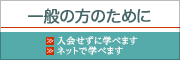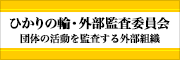上祐代表による内観解説
「内観の教え:仏教由来の内省法」
(1)内観の歴史:浄土真宗の身調べを改善したもの
内観は、自分を知るための一つの方法であり、元は、仏教宗派の修行であって、その後、自己探求・自己啓発の手法や心理療法として発達した。
内観の前身は、阿弥陀如来を信仰する浄土真宗(開祖親鸞)の一派に伝わる「身調べ」という修行法だった。この「身調べ」は、現在の「内観」から見ると、非常に荒っぽいものであり、それをそのまま真似ることは不適切である。しかし、ここでは、内観発祥の歴史を知るためにも、説明しておくことにする。
身調べでは、ひとりだけ隔離され、誰とも面会することが許されず、数日間の断水・断食・断眠という厳しい条件のなかで、「今死んだら自分の魂はどこに行くのか。地獄行きか、極楽行きか? と真剣に問い詰めて、身・命・財の3つを投げ捨てる思いで反省せよ」という指示を与えられて、今日までの自分の行いを反省するというものである。
2時間おきに信仰の先輩たちがかわるがわる来て、現在の心境を聞き説教し激励する。こうして信者に自分がいかに罪業深いかを自覚させ、仏の救いにあずからせようとするものだった。3日くらいで心身の限界に達するころには、個人差があるが、「宿善開発(過去世の一切の善業が花開いて阿弥陀仏の救いに与ること、一種の悟り)」や、「安心立命」と呼ばれる境地に達する人が多かったという。このような深い宗教的な体験を求めるのが「身調べ」だった。
この「身調べ」を吉本伊信(よしもといしん)という人が、難行苦行的な要素や、宗教的な色彩を取り除き、誰でもができる自己探求法として改良し、それを「内心の観察」という意味で、1940年に「内観」と名付けた。そして、当時から自己発見による自己啓発や悩みの解決法として用いられ「内観法」と呼ばれた。
また、心理療法の分野で、問題行動や心身の疾病のために用いられる場合には「内観療法」と呼ばれるようになった。1954年から少年院や刑務所の矯正教育として導入され、心理学や医学領域に導入されたのは1965年ころからである。
(2)内観のやり方
断水・断食・断眠という苦行的要素をなくし、朝5時~夜9時まで、1日16時間の内観を行い、それを7日間行う。集中しやすいように屏風でしきりをして、トイレ、入浴、就寝以外は、食事も屏風の中でとる。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、雑談などは禁止され、この間は集中して内観のみに専念する。
具体的なやり方は、3つのテーマにそって行われる。
そのテーマは、
①「してもらったこと」
②「して返したこと」
③「迷惑をかけたこと」
というもので、通常、はじめは母親を対象として行い、順次、父親、他の肉親などに対象を変えて、子供時代から3年区切りで現在まで3つのテーマについて想起する。
そして、①の「してもらったこと」と、②の「して返したこと」に、それぞれ2割ずつの比重をかけ(合計4割)、③の「迷惑をかけたこと」に6割の比重をかけて内観する。
この間、面接者が1時間~1時間30分おきに来て、3~5分ほど面接で内観の報告を行う。
また、日常生活のなかで行う「日常内観」というものもあるが、それは集中内観で得られた心理的変化を持続させ、さらに深化させる役割がある。
(3)内観の治療の効果とその仕組み
1.「してもらったこと」の想起による気づき
内観で「してもらったこと」を想起すると、他者から多くの愛情を注いでもらったことに気づく。それは他者に対する認知が肯定的なものに変化し、他者を受け入れることができるようになる。
このことは、自分は悪くないという思い込みが強く、被害者意識や自己正当化し、他者に対して恨みや怒りを持っている人が多い神経症性障害者(不安障害、恐怖症、強迫性障害、心気障害、離人症性障害)や行動の障害がある人の回復に効果がある。
さらに内観が深まり、愛されてきたことの発見が徹底していくと、大自然によって生かされてきた恩と恵みを自覚するようになるという。こうして内観者は周囲の他人や自然との一体感を感じられるようになり、防衛的な自己が解体されやすくなる。
また、「こんなにも多くのことをしてもらっていた」という充足感、愛されてきたことの実感は、他者から大切に育てられてきた存在として自己肯定感が生じる。愛情の充足感や自己肯定感によって、自他分離不安(母親との分離不安が元)が解消され、それによって自己執着から解放されていくようになる。アルコール依存症などの嗜癖行動者などは自己破壊行動をなくしていくことができる。
また、アダルトチルドレンなどのように親に対する被害感が強く、自分が生きることに存在意義や存在感のうすい場合にも、自己肯定感と他者肯定によって回復の大きな力になる。愛されてきたという発見によって、内観者は自分の対人関係で幼児的、退行的な母子関係や依存関係に気づかされ、「してもらったこと」に対する感謝と償いの自覚が呼び覚まされる。
2.「して返したこと」の想起による気づき
ここでは、「してもらったこと」の多さに比べ、「して返したこと」の少なさに気づく。他から多くを得て、他に与えたことの少なさに自己否定感が生じる。他者にしてもらうばかりで依存の強い未熟な自分、他者を無視した自己中心的な自分に気づく。また、自己の役割や責任など社会性の欠落も自覚させられる。
「して返す」という行為は「してもらったこと」のお返し、謝礼としての日常的、社会的な行為であるとともに、「迷惑をかけたこと」に対する償い、謝罪の意味も含まれる。しかし、それを「して返さない」ということは、未熟さの自覚と、「済まない」という罪責感が生じ、償いに気持ちは向かう。
3.「迷惑をかけたこと」の想起による気づき
上記の「して返したこと」の想起においてもすでに、「してもらったこと」の多さにくらべ「して返したこと」の少なさに罪責感、罪悪感を感じているが、さらに「迷惑をかけたこと」の具体的な事実を想起すると、予想外に多くの迷惑をかけた事実があったことに気づかされ、より強い罪責感を持つ。
それは、他者の苦しみを考慮できない自分の未熟さの自覚でもあり、自己否定や自己嫌悪などの感情を伴った罪責感を体験する。
しかし、一方で「してもらったこと」の想起によって他者からの愛情、恩恵に気づかされているので、こんな自分でも赦し支えてくれたことに感謝と謝罪や償いの気持ちも強化されていく。
内観による心理的な変化はまず、いかに自分が自己本位であるかの発見であるといわれる。その醜さに罪悪感さえ感じる。「罪意識」は内観療法の中核をなす体験で、愛を受けてきたことの発見と表裏一体となる体験だという。
内観における罪責感は、うつ病や神経症にみられるような病理的な罪意識でなく、逆に、精神療法の治癒の機転になる重要な要素である。この両者の罪意識の違いは重要である。罪意識は、自分を閉鎖し落ち込みをもたらすが、内観における罪意識は、他者に向けた謝罪という開かれたものである。
多くの迷惑行為にもかかわらず、それでも赦し支えてきてくれたということの気づきによって謝罪、償いの気持ちが生じてくる。「申し訳ありません」と内観者の内面では謝罪が繰り返される。ときには「どうかお赦しください」と指導する面接者に深々と頭を下げる内観者もいるという。この「開かれた罪意識」は自分を成長させる健康的な罪意識である。
こうして、他者肯定とともに自己肯定も強まる。そして、過去の罪を自分のこととして受け入れることができるようになる。
4.「愛されてきたことの気づき」と「開かれた罪意識」の相乗効果
こうして、「してもらったこと」の想起によって生じた「愛されてきたことの気づき」と、「して返したこと」「迷惑をかけたこと」の想起によって生じた「開かれた罪意識」は、内観を深め、その効果を高めていく二つの大きな要素である。
この二つの要素の相乗効果によって、認知の変化が認められる。
1 他者の慈愛によって支えられ許されてきたことによって生じる自己肯定感
2 自分を慈愛によって支え許してきてくれた他者肯定
3 その他者は大自然・宇宙にまで拡大される
4 他者によって生かされている感謝と歓喜
5 現実的・適応的、適正な考えや行動となる素直さ
このような認知修正によって、心身の症状の改善や消失が認められている。また、自己や他者の認知の修正は、心の充足と癒しの効果となるので他者を愛することができるようになる。
それによって、
①他を利する意欲・行動の促進となる。
また、他者に対する恨み・憎しみなどのマイナス感情や愛情の欠乏感がなくなることによって、
②反抗・反発などの問題行動の減少、消滅、
③謝罪・償いのための意欲、行動の促進、
④「して返す」(報恩)の意欲、行動の促進、
⑤責任と役割の実践・行動の促進
などが見られる。
このように心理的成長によって行動が是正され、現実への適応が可能になっていくのである。
(4)内観の普及
内観は、さまざまな分野で利用されている。治療を目的として利用される場合は「内観療法」と呼ばれ、矯正教育や学校教育で利用される場合は「内観教育」、企業研修や自己啓発の場合は「内観法」と呼ばれる。治療場面では、不登校、引きこもり、社会不安障害、摂食障害、各種依存症、うつ、人格障害、統合失調症、心身症、身体的心理的痛み緩和などに役立てられている。また、日本だけでなく欧米や中国・韓国をはじめとしたアジアにも内観は普及している。
(5)ひかりの輪と内観:いかに自分の暗部を直視するか
ひかりの輪では、内観と、それを生んだ阿弥陀如来への信仰や、浄土真宗の思想(特にその開祖親鸞)を研究し、特に、ひかりの輪の学習実践の大きな課題である、自と他の区別を超える悟りの実践のために活用している。
しかし、内観がいかに素晴らしくとも、それが成功するためには、普段は見ないようにしている自分の悪行を直視する必要がある。それに成功してこそ、他の悪行を自分の悪行を投影したものと理解する一元の悟り、自と他の区別を超えた意識が深まる。
しかしながら、競争社会で育ったわれわれは、自分が他人に対して優位であったり、劣っていたりするといった、自と他の比較について、非常に強くとらわれている。よって、自分の長所と他人の欠点はよく見るが、自分の欠点と他人の長所を見ることは苦手である。
また、特に、宗教の実践者の場合は、オウム真理教での経験でもわかるように、みずからの宗教的な実践を誇っている間に、プライド・虚栄心が増大し、そのために、自分の暗部を直視しないという問題も生じることがある。
こうした理由のため、内観の実践を始めると、自分の暗部を見ることに強い抵抗感を覚えて、それがうまく進まない場合がある。ある意味で、それまで自分が作ってきた自分の虚像が壊れてしまうような恐怖である。
こうした問題を乗り越えていく上で、阿弥陀如来の教えや、阿弥陀如来を信仰した親鸞が説いた教えは、参考になる一面がある。ひかりの輪は宗教ではなく、阿弥陀如来も親鸞も信仰しないが、謙虚さを学ぶための参考として紹介する。
親鸞の悪人正機の教えは、悪人こそ阿弥陀如来に救われるという意味となり、この逆説的な教えには、さまざまな解釈がある。しかし、それは、自分が悪人であることを率直に直視し、ザンゲ・反省し謙虚な心を培った者こそ、自分の中の仏性に近づき、阿弥陀如来に救われる機会があるとも、解釈することができる。これは、実践者が陥りやすい慢心を戒める上で非常に有効な教え・思想である。
また、親鸞の説いた絶対他力(他力本願)という教えは、ちまたでは誤解されているが、その本当の意味は、阿弥陀の善業に比較するならば、人の積むことのできる善業は非常に小さいものであることを強調する教えであり、これも実践者の慢心を戒めるものである。親鸞は、この思想に基づき、人と如来の間は絶対的に大きく、人の間の差はわずかであるとして、弟子を1人も持たないと語った。
また、親鸞の思想に限らず、阿弥陀如来は、すべてを平等に救うという性格が強い。法然や親鸞が強調した阿弥陀の誓願の第十八番には、心を込めて、阿弥陀の念仏を唱えるならば、それだけで阿弥陀の浄土に往生させる、というものがある。
この教えは、難しい実践ができない多くの民衆に、仏の慈悲・救済は平等であると感じさせ、大きな救いの希望を与えた。もちろん、この教えの意味合いを安直に解釈するならば、間違いが生じ、そんな実践で本当に救われるかという疑問が生じるであろうが、それはさておいて、われわれ実践者にとって最も重要なことは次のことではないかと思う。
阿弥陀如来の境地から見れば、無智のために現象に実体を錯覚し、さまざまな虚像に引きずられながら輪廻に惑う衆生は、皆が盲目の亀のようなものであり、人と人の間どころか、人と動物の間さえ、大差がないものと映っているであろうということである。これは、特に、自分が高度な学習実践をしていると考え、慢心を抱いていた学習実践者には、重要な戒めではないかと思われる。
阿弥陀如来は、別名として、アミターバ=無量光仏、アミターユス=無量寿仏とも言われ、無量の光=無量の智慧、無量の寿命=大宇宙の無数の寿命を生み出す仏の法力を象徴するともされている。この阿弥陀如来の無限の宇宙に広がる無量の智慧と寿命に比べるならば、人間は誰しもが、地球の人間界さえ正しくそのすべてを理解できず、わずか百年足らずで朽ち果てる点において、大差がないことは明らかである。
いかに若く美しい者でも、すぐに皆が老い醜くなるし、いくら富や権力を有する者も、すぐに老いては一切を失うし、宇宙に比べるとケシ粒のような地球さえも、その全体を所有・支配することができないものである。こうして、よく考えれば、人と人の間の優劣は、猿山の中での争いのごとき、空しいものである。
こうして、人と人の間の平等性を理解するならば、自分が他人に対して優位に立ちたいといったプライドや虚栄心などの空しさを理解でき、それがやわらぎ、自分の暗部を見るための準備をすすめることができるだろう。
なお、自分の暗部を見て、自分だけがひどい人間だというように卑屈になってしまい、落ち込んでしまい、前向きになれない場合がある。
その場合は、まず、上記の内観が説くように、自分に多くの罪があるにもかかわらず、他から愛され、支えられてきたという点を理解して、前向きに努力する気持ちを持つ方法がある。
他への感謝・称賛は、自分が劣っている、恵まれないといった気持ち、すなわち、卑屈・嫉妬といった否定的な心の働きを乗り越える力となる。感謝は、自分と他人の繋がりを意識させる心の働きであり、自分と他人を区別するプライド・卑屈・闘争心・嫉妬心を和らげるものである。
また、別の方法として、自分にある問題は、他人にもあるということを意識することで、過剰な卑屈の苦しみを和らげることもできる。
もちろん、これを間違って用いた場合、「俺だけではなく皆が悪いのだから、俺が反省する必要などない」などといった傲慢な考えに陥るので、そうではなくて、「自分も他人も、ともに努力して、問題を乗り越えていけるといいな」という、前向きな考え方に結びつける必要がある。
そして、自我に対する執着に基づいて、プライドと卑屈が生じるため、その二つはセットになっていて、プライドが強い人は、卑屈も強く、傲慢と卑屈の間を行ったり来たりしており、精神が不安定な場合が多い。
こういった問題を根本的に取り除いていくためには、これまで述べた方法に加えて、釈迦牟尼の説いた基本的な法則の修習は常に有効である。
まず、プライドや卑屈の土台となる「自分」というもの自体が、実際には存在しないものであり、人間の頭の中で、言葉によって仮設された概念に過ぎないということである。自分というものには実体がない、無我ということである。
次に、苦楽表裏である。プライドの喜びの裏側に卑屈の苦しみがあることや、闘争の勝利の裏側に敗北・嫉妬の苦しみがあること理解する。これによって、プライドと卑屈の双方から離れる、自我から離れるように努めるのである。
そして、最終的には、自と他の区別・比較を超えた、一元的な意識を瞑想などによって体験することが望ましい。こうして、空性・涅槃の寂静という本当の幸福を実体験をもって、かいま見るならば、日常生活で、自と他を区別して、プライドや卑屈に一喜一憂することの空しさを理解することができる。
<参考文献>
1.『内観療法』(三木善彦・真栄城輝明・竹元隆洋編著 ミネルヴァ書房)
上祐代表による内観の解説2
「ひかりの輪の内観:仏教と融合した新しい内観実践の思想」
(1)仏教と内観の一致点
1.自分が多くの人に支えられていることや、多くの幸福を与えられていることを認識し、感謝すること
仏教の教義と内観が一致するところは、日頃認識することが少ないが、実際には、自分が、肉親・友人知人をはじめとして、多くの人々に支えられて生きていること、多くの幸福をすでに与えられていることを理解することである。これは、仏教の教義においては、縁起の法、唯識の依他起性(えたきしょう)の教義に関係する。
現代社会に生きると、恒常的に欲求不満を作り出す構造を持つ資本主義社会の中で、「もっともっと」と求める(=貪る)心が強くなりがちで、すでに与えられているものの大きさを認識し、それに感謝することが非常に乏しい。こうして、感謝・満足よりも、貪り・不満が強くなってしまうのである。
仏教的に言えば、これは、学習実践上の重要な課題である貪りの止滅である。それは生きていく上で必要以上のものを貪らず、他と分かち合う(他に施す)ことである。そして、この貪りを止滅するためには、まず、貪りに際限がなく、執着をもたらすがゆえに、苦しみであることを理解する必要がある。
まず、貪りに際限がない理由は、人が感じる幸福・不幸が、比較によって生じる幻影であるからだ。例えば、今まで10万円の給料だった人が、給料が20万に上がると、上がった直後は喜びを感じるが、それに慣れてしまうと、それが当然のことになり、喜びがなくなり、もっともっとと求める心が生じる。再び喜びを感じようとして、もっと高い給料を欲するのであるが、その欲求が満たせないと苦を感じる。
さらに、給料が元の10万に戻ると、大きな苦しみを感じる。最初は10万円で足りていたのに、得たものに対する執着が生じるがために、失う時には、苦しみが生じるのである。これは、四苦八苦の教えに説かれているものである。
こうして、貪りは際限がなく、執着をもたらすがゆえに、苦しみをもたらす。このことを理解したならば、もっともっとと求めるのではなく、すでに与えられているものに感謝して貪りを止滅することが、真の幸福の道であることがわかる。
さらに付け加えると、単に与えられていることへの感謝と貪りの止滅だけではなく、自分より恵まれない他者と分かち合う慈悲の実践によって、貪りはさらに止滅していく。
そして、内観によって、いかに自分が支えられ、いかに多くの幸福を与えられてきたかについて、客観的に自分自身を調べて、それに感謝することは、貪りを和らげ、慈悲・利他の心を培うために、非常に有効な実践である。
2.感謝に基づいて恩返しの心構えを持つこと
感謝の実践が深まれば、それに伴い自ずと生じてくることが、恩返しの実践である。自分が支えられ、多くを与えられていることを認識すれば、自然と、自分も同じように他を支えて、与えることを考えるようになる。
ところが、人は、親については、支えてもらう、養ってもらうことを当然としているために、自分が親にして返したことについて考えてみると、驚くほど少ないことに気づく場合が多い。これは、親と同様に、自分が依存すること、甘えることを当然としている対象に対しても生じやすい。
よって、内観によって、親や親に類する依存の対象について、何をして返したかについて、客観的に自分自身を調べることは有効である。
また、仏教では、慈悲・利他の実践が強調されるが、その実践が、他を見下した傲慢な心の働きによって行われる場合がある。この場合、物質的な意味では、他に施しをしたとしても、慢心の貪りを生じさせている。
これを防ぐためにも、自分は様々な意味で他に支えられてきたのに、他にして返したことが乏しいことを自覚することが有効である。こうすることで、自分が偉いから他を利するというのではなく、他に多くを与えられてきたことに対する恩返しとして、他を利するという実践をすることができるからである。
そして、この実践は、内観によって、自分が他に迷惑をかけたことについて、客観的に調べることによってさらに深まっていく。感謝が少なく、不満が多い場合は、知らず知らずに、自己中心・身勝手な心によって、他に迷惑をかけているものである。
また、他に文字通り迷惑をかけていなくとも、他から与えられていること自体が、それは、他がなんらかの労苦を背負っているわけであり、他に迷惑をかけていると解釈することもできる。仏教の教義では、ある人の(煩悩的な)幸福は、多くの場合、その裏で他の苦しみが伴う場合が多いと説いている。
こうして、自分が他にかけた迷惑を認識すると、傲慢な気持ちで慈悲・利他の実践をすることはおろか、恩返しとしてそうすることさえも超えて、いわゆる贖罪=悪業の清算として善業を積ませていただくという極めて謙虚な心構えが実現する。
これは、非常に仏教的な生き方の実践となる。仏教においては、慈悲・利他の実践とか、善業・功徳を積む実践とは、それまでに自己中心的な心の働きによって積み重ねてきた悪業を清算して、自我執着を弱め、悟りのための土台を作る、自己の浄化の実践にほかならない。
3.三つのレベルの内観:仏教と内観の融合
ひかりの輪では、一般の内観をさらに発展させて、三つのレベルの内観のステージがあると考えている。
まず、第一のレベルの内観が、通常の内観であり、肉親や友人・知人について、してもらったこと、して返したこと、迷惑をかけたことを調べて、彼らに対する感謝と恩返しの実践を深めることである。
しかし、仏教的な悟りを求める場合には、このレベルの感謝と恩返しを超えて、第二のレベルとして、人類社会全体への感謝と恩返しの実践に入る必要がある。
私たちは、日々生活する上で、友人知人に限らず、無数の人々に支えられている。特に現代社会では、分業が進んでいるから、無数の人が互いに支え合って生活しており、自分や知人の力だけでは、1日として生活することはできない。
自分の衣食住から通勤・通学、そして学習実践などを支えている存在は、単に日本の1億人にとどまることなく、遠く外国から輸入される様々な食料や製品、物資や資源・エネルギーから、そして日本の輸出品を買う多数の外国、そして、モノに限らず、世界中を結ぶ金融・情報のネットワークに至るまで、経済のグローバル化が進んだ今現在は、地球の60億全体が相互に支え合って生きていると言っても過言ではない。
大昔は、東京がなんらかの原因で壊滅しても、日本の他の地域の人達は生活に困らなかっただろうが、今は東京の壊滅は日本全体の崩壊に繋がるだろうし、実際にアメリカの金融危機は、世界中を同時に大不況に陥れるほどに、人類社会の相互依存が深まっているのである。まさに、人類社会全体が相互依存の状態、相互に縁起・依他起性の状態である。
しかしながら、こうして人類社会全体に支えられているにもかかわらず、日本をはじめとする先進国においても、自国の利益の追求=貪りが強まっているために、人類社会全体に対する感謝の気持ちや、それに基づく恩返しは乏しい状態である。それは、10億ほどの先進国が世界の富や財の多くを独占し、飽食にふける中で、それと同じほどの途上国が貧困と飢餓・病苦などに苦しんでいることからも明白である。
さらに、仏教的な悟りを求めるためには、第三のレベルの内観として、全ての生き物、全ての衆生、万物への感謝と恩返しの実践が必要である。私たち人間は、人間社会だけで生きることができているのではなく、地球の生態系の中で、多くの生き物の犠牲の上に生きている。
それは、生き物に限らず、空気・水を含めた地球の生命圏全体、そして、遠くは太陽の光も必要不可欠であり、それを支える太陽系、そして太陽系を支える銀河系・宇宙の全体に支えられて生きている。
こうした大自然・大宇宙・万物に支えられて生きているという認識は、仏教が説く縁起の法や唯識の依他起性の教えや、大宇宙を、衆生を育む仏陀の母胎であると説く胎蔵界の思想にも通じるものである。
この認識が深まると、自分というものが、宇宙・万物・全体から生み出され、全体に支えられ、全体の一部として、全体と一体になって存在しており、自然の与える寿命が来たならば死んで、自分の体は他の生き物の体になっていく、といった認識が生じる。
これによって、自我に対する執着が弱まり、自と他の区別を超えて、無限の全体こそが本当の自分ではないか、といった認識も生じ、万物への愛・慈悲が深まっていく。こうした自我執着の弱まりと慈悲の増大こそが、まさに仏教の悟りのプロセスである。
そして、全ての衆生・万物への感謝に基づいて、万物に恩返しようとする心の働きは、大乗仏教で最も重要な心構えである菩提心と関係してくる。菩提心とは、全ての衆生の幸福のために、仏陀の境地を求めようとする菩薩の心である。
4.内観と聖地巡りの融合
以上のように、内観を発展させると、大宇宙・大自然への感謝と一体感に行き着くが、これを体験的に培うのが、聖地巡りであり、発展的な内観の実践と組み合わせることが望ましい。
発展的な内観の実践によって、理性を使って、自己存在の土台・根源として、大自然・大宇宙をとらえなおした上で、感謝と一体感をもって、大自然と向き合うならば、大自然と融合する仏教的な悟りの意識状態に近づきやすいということができる。
現代社会に生きる人は、実際には大宇宙・大自然に支えられ、その一部として生きているにもかかわらず、そういった自覚がなく、自分と自然を切り離して区別し、自分だけの力で生きているかような錯覚をなしている。
その結果として、他人や他の生き物・自然を害するような、自己中心的な生き方をして、地球環境問題まで起こしてしまっている現状がある。よって、仏教的な悟りを得るためには、こういった、自と他を区別し、自分と大自然を区別する心の働きを浄化し、大自然の一部としての自分を再認識することが望ましい。
そして、私の体験上は、例えば、上高地などの純粋な自然・聖地は、現代社会の人々が陥りやすい、そういった自己利益の貪りや、貪りに基づく争いの心が静まって、純粋な自然が有している、他との調和・慈愛の心を培う体験をしやすいと思う。
(2)内観と親子関係の問題
1.オウム真理教と親子問題
ひかりの輪においては、オウム真理教事件の総括を行い、その中で、元教祖や弟子たちの親子関係に関する問題が、オウムの問題の背景にあったのではないかという分析をなした。さらに、親子関係を含めた内観を行ない、スタッフ・会員が抱える親子関係の問題が、より明確になってきたように思う。
そもそも、オウム真理教の麻原元教祖は、その幼少期に親との関係において、不遇を経験したと思われる。ジャーナリストが幼少期の元教祖を取材した内容を出版しているが、そこには、全盲ではないのに、無理に全寮制の盲学校に転校させられた不満、学校の友達と違って親が休日に会いに来ることがなかった事実、親が自分に対する国の交付金を生活費に回そうとしたことへの怒り、元教祖が師事した宗教団体の代表に漏らした親への憎しみなどの事実が報告されている。
実際に、オウム真理教は、聖母(聖父)といった宗教的な概念がない。釈迦を生んだマハーマーヤ夫人や、イエスを生んだ聖母マリアといったような開祖の親を尊重する教義がない。実際に、マハーマーヤという宗教名は、麻原元教祖の妻(松本知子氏)に一時期与えられるなどしたが、元教祖を釈迦とダブらせるのならば、釈迦の母の名前は、元教祖の母に与え、知子氏には最初から妻の名前を与えただろう。
また、1990年頃、元教祖は両親に会い、「父親は地獄、母親は餓鬼の世界に転生するから、父親を地獄ではなく餓鬼に、母親を餓鬼ではなく動物に転生するようにポアしておいた。今生はもう会うことはないだろう」と私に語ったことがあった。
オウム真理教において、地獄・餓鬼・動物の三悪趣に転生する魂は、悪業多き魂とされている。元教祖が解釈したヨハネ黙示録では、キリスト(=元教祖)に従い、キリスト千年王国に入る、善業多き魂である聖徒(オウム真理教の信者)と、キリストと対立して地獄に堕ちる悪業多き魂が存在するが、元教祖の両親は、善業多き魂には含まれないことになる。
普通の宗教では、救世主を生んだ親は当然の如く尊重されるし、仏教教義でも、出家者を生んだ親には大きな功徳が返るという。オウム真理教でも、元教祖の子供を生んだ女性達は大きな功徳を積んだとされた。これらの事実からしても、元教祖自身を生んだ両親が、三悪趣に落ちるという位置づけであるのは特別に思われる。そこには、元教祖の両親に対する特定の思いが現れているとは考えられないだろうか。
そして、オウム真理教の教義の大きな特徴であり、最初の社会との対立の主因となったのが、苛烈な出家制度であった。(少なくとも成就者になるまで)親と子の連絡を禁じたこともあって、出家した子供の親による激しい反対活動が起こり、それがオウム真理教の一連の犯罪の原点ともいわれる坂本弁護士事件にも繋がった。坂本氏は、出家した子供の親達のために、教団を批判する活動をしたからである。
そして、オウム真理教が大量の出家者を得たということは、元教祖だけの人格によるものではなく、その信者となって出家した者においても、その全てではないが、元教祖と同様とまではいかなくても、親に対する感謝や尊重ではなく、否定的な感情があったのではないかと思われる。これは私が知る多くの出家者がそうだからである。
また、教団と親の対立は、そのまま、教団と社会全体との対立に繋がるものであった。親を含めた社会は悪業多き魂の集団であり、それを脱却してキリストたる元教祖に帰依し従う出家者こそが聖徒であり、救われるとされたからである。
2.現代社会全体に広がる親子問題
しかし、私の経験上、この親子関係の問題は、オウム真理教の信者だけの問題ではなく、日本社会全体を覆っている問題に違いないと思われる。むしろ、日本社会全体に広がる親子関係の問題の一部をオウム真理教の信者があぶり出したにすぎないだろう。
また、私のロシアに関する体験からすると、日本だけではなく、現代の人類社会全体に広がっている可能性もある。彼らの多くは、親子関係が昔よりも悪化していると証言しているからである。
もちろん、統計を取って、昔と比較したのではないから、昔と比べて多いとは断言できない。しかし、親子の人間関係に問題がある人の割合は非常に多いように思える。そして、子供側に親に対する尊敬・感謝が乏しいと思われる。
それを裏付ける1つのデータとして、読売新聞が実施した全国世論調査の結果によると、親を尊敬していない子は56%、一方、尊敬している子は37%となっているデータがある。半数以上が尊敬していないのだから、親を尊敬しない子の方が普通になっているのである。
特に、日本ではこの傾向が顕著なようだ。戦後に価値観が崩壊し、天皇や国家の権威とともに、親の権威が崩壊したことも一因かもしれない。財団法人日本青少年研究所による日・米・中・韓で中・高校生を対象にしたアンケート調査(2008年9~10月)によると、
①「親の意見に従う」と回答した子どもは、
日65.5%、米83.6%、中88.6%、韓83.3%で、
日本の低さが際立ち、
②「親によく反抗する」は、
日57.0%、米26.2%、中11.0%、韓44.9%で、
逆に日本が一番高くなっており、
③「親はよく私を叱る」は、
日66.5%、米36.3%、中33.5%、韓34.3%で、
日本の子どもはよく保護者から叱られていると認識されており、
④「親はよく私をほめたり励ましたりする」では、
日57.8%、米82.9%、中73.4%、韓74.7%で、
4カ国中で最低となっており、
⑤「親を尊敬している」は、
日64.1%、米89.8%、中97.0%、韓84.2%
で日本が最も低く、
⑥「親は私を大切にしてくれる」も、
日83.7%、米92.4%、中95.5%、韓91.9%と
日本だけが9割を下回っており、
⑦「自分はダメな人間だと思う」と回答した中学生の割合は、
日56.0%、米14.2%、中11.1%、韓41.7%で、
日本は5割を超えている。
歴史や文化が違えば、子育てや親子関係の在り方も異なるとはいえ、以上の調査では、日本の子どもは、親を尊敬できず、自分自身も尊敬できないという結果が出ている。
3.心理学や内観などを通した親子問題の分析
私が、親子関係について、心理学的な分析や内観などを通した経験からして、問題となる親子関係のパターンには、以下のようなものがあると思う。もちろん、これが全てではなく、一部であろうが、最近の指導の体験上、印象深かったものをまとめてみた。
1.親への尊敬・感謝が乏しく、他に絶対的な存在を求め、それに過剰に依存・服従する。
2.親への尊敬・感謝が乏しく、他にも誰も尊敬・尊重せずに、反抗ばかりする。
3.親に過剰に依存し(絶対視し)、自分に劣等感、自己嫌悪を抱く。
4.親への過剰な依存・絶対視は止めたが、逆に親が自分を不幸にしたと恨みを抱く。
5.親に対する期待が十分に満たされずに、常に不満・怒りを持つ。
まず、1については、オウム信者に多くみられるパターンだと思う。何かしらの理由で、親への尊敬、感謝がなく、恨みはなくても、多かれ少なかれ、親に失望している。
この背景としては、心理学によると、子供は、誰しも幼少の時には、自分が絶対的な存在、特別な存在、世界の中心でありたいといった、誇大妄想的な願望があり(専門用語では誇大自己とも言う)、その願望を満たしてくれる存在として親に深く依存をする、という説がある。
そして、この願望は、幼少の時に、親がそれを適度に満たしてあげて、成長するにつれて、自分も親も絶対・特別ではないという現実を徐々に受け入れさせ、それを卒業させるのが、子供の健全な発達には良いというのが心理学的な見解のようである。
幼児であれば、自己中心的な世界観で、あれこれ親に要求しても、それは昔からある自然なものであるし、そうした欲求も、親との狭い世界の中であれば、充足させることが可能である(例えば、子供がアニメのヒーローや、キリストになった、という遊びをするのに、親が付き合うなど)。そして、親に絶対的に依存するのも、自分では何もできない子供にとっては、生きるためにも自然なことであろう。
しかしながら、心理学的な見解では、幼少の時に、親にこうした願望を満たしてもらえないケースにおいて、大人になっても、誇大妄想的な願望を引きずって、現実的な向上欲求ではなく、誇大妄想的な傾向に陥る場合があるという(心理学的には誇大自己症候群と呼ばれる)。
そして、親の代わりに、自分が誇大妄想的な願望を満たすことができると思う対象を求めて、誰かがそうだと思いこめば(すなわち盲信するならば)、その対象に絶対的に服従し、そうでなければ、誰も尊重せずに反抗する傾向を示すという。
こうして反抗するのが、2のケースである。その理由は、その子供は、自分の絶対者願望を満たしてくれる存在のみに、価値を見いだしているからである。
もし、誇大妄想的な願望ではなくて、現実的な向上心がある場合は、対象が絶対ではなくとも、重要なことを学ぶことができる者ならば十分に尊重できるし、親についても、完璧ではなくとも、その良い点を認めて、一定の感謝・尊敬ができる。
しかし、誇大妄想的な願望が強いと、そういった健全な学習の姿勢や、他者への尊敬・感謝を持つことは難しくなるというのである。
また、現代社会では、様々なメディアの情報が、こうした誇大妄想的な欲求を増大させているという問題がある。例えば、アニメ・漫画・SF映画のフィクションの世界もそうだし、バランスを欠いた超能力・神秘主義や、破滅予言・陰謀論などを扱う精神世界の雑誌や書籍もそうであろう。最近は、パソコンゲームやインターネットでも、そういった大量の妄想的なフィクションの情報が増えている。
こういった情報が氾濫する現代社会の子供・若者は、場合によっては大人も、妄想的な世界観に陥りやすくなっていると思われる。
そして、オウム真理教の教義には、こうした妄想的な概念が多く盛り込まれていた。絶対神の化身であり、最終解脱者である教祖がいて、教祖に帰依すれば、自分が解脱者・超能力者になり、ユダヤ・フリーメーソンを中心とした悪魔が支配する社会との戦いに勝利して、20世紀末にハルマゲドンで滅ぶ世界を生き残って、キリスト千年王国に入ることができる選ばれた存在になる、といった教義である。
世紀末の予言が外れた今から思うと、これらの教義は妄想的と思えるが、当時信者となった者達はなぜ信じたのであろうか。自分のケースでもあるが、それは、教祖がキリストであるという確実な根拠を得たからではなく、オウム真理教に巡り会う前から、そもそもが、そういった世界に対する強い欲求・願望があったからではないかと思われる。
つまり、十分に信じる根拠があったから信じたのではなく、そういった世界があり、そういった教祖がいてほしかったので、それがオウム真理教にあると信じたということではないかと思うのである。
このオウム真理教の事例からもわかるように、子供の誇大妄想的な願望は、親と子だけが作り出している問題ではなく、親子を取り巻く社会全体の環境が影響していることはいうまでもない。親と子と社会の三者があいまって、問題を作り出しているのである。
次のケースは、親に失望するのではなく、親を過剰に肯定(絶対視)するケースであり、これが3のケースである。
1と2のケースは、なんらかの理由で、幼少の頃に、親によって、誇大妄想的な願望を満たせない場合に起こると述べたが、3のケースは、正反対に、大人になっても、親が、子供にとって、絶対的な存在であり続けるというケースである。
このケースは、子供の親に対する依存が強く、親の子供に対する支配欲が強い場合に起こりやすいと思われる。子供が親に依存するだけでなく、親がいつまでも子供を自分に縛り付けるのである。
この背景として、親は、子供を支配することで、自己存在意義を満たしている面があり、親の方も、実は子供に依存している心理状態にある。すなわち、親離れしない子供と、子離れしない親の組み合わせである。
よって、一見そうは見えないものの、親の本質的な性格が、子供と似ているのではないかと私は思う。この場合は、親がまず子離れをする必要があり、子供に自信を持たせたり、自分への過剰な依存・甘えを抑制したりするべきである。ところが、こうした親の場合、子供が自分に依存するように誘導している場合もあるかもしれない。
そして、このケースにおいては、例えば、実際には親が悪いのに、自分が悪いと思って、自分を責め、その結果、自分に不合理な劣等感を抱く場合がある。こうして、不当に自分を責める背景には、自分の存在意義を深く親に依存してしまっていて、親を否定すると、自分の存在意義が無くなるように感じてしまうという場合がある。
例えば、親に認められることで、自分の存在意義を満たしてきた子供は、親が間違っているとなれば、自分の存在意義を根底から否定しなければならない。よって、親を否定するよりも、自分を一部でも否定した方が、相対的には、自己存在意義を守ることができるのである。
この背景には、先ほども述べたが、なんらかの理由で、自分の存在意義を自分自身の価値・判断ではなく、親の価値・判断に委ね過ぎていることがある。
そして、それから抜け出せない理由としては、
①抜け出すためには、親によって満たしてきた自己の存在意義は放棄しなければならないが、それが放棄できないこと。
②親の価値・判断から自立して、自分の価値・判断で生きる上での自信のなさ・卑屈、その奥にある依存・怠惰などがあるだろう。
さて、先ほども述べたように、幼少の頃には、誰もが、親を絶対視し、親の価値・判断に自己を深く委ね、親も子供を良い意味で支配することが必要であり、自然であり、健全であるから、問題の核心は、子供が大きくなっても、依然としてそれを卒業しないということに尽きる。
心理学的には、子供が健全な発達過程をたどる場合は、反抗期というものを経て、子供は親の絶対性を否定し、自分の価値・判断で、自立して生きる過程を経る。その中で、重要なことは、子供は、親の絶対性を否定するだけでなく、自分自身も、多くの人間の一人であることを受け入れて、自己を相対化していくプロセスがある。
これによって、妄想的な絶対者願望ではなく、現実的な健全な自己向上欲求を持つようになる。そして、親に対しても現実的に見て、不完全ではあっても、自分を育てた存在として健全な感謝の心を持つようになるのである。
しかし、3のケースでは、子供や親の要因によって、この自立のプロセスがうまくいかないのである。そして、30歳、40歳になっても、親に依存し続ける場合がある。
さらに、このケースは、肉親の親に限らず、親の代わりに依存の対象とした者にも当てはまる。
例えば、前回の1のケースなどで、親以外に、自分の願望を満たす存在を見つけ、それに過剰に依存・服従する場合は、その存在について、同じことが起こる。例えば、実際には相手が悪いのに、自分が悪いなどと考えるのである。
これは、言うまでもなく、オウム真理教の信者と元教祖の関係に当てはまる。例えば、元教祖が主導した事件について、少なからぬ信者が、「自分たちのカルマが悪いから、元教祖が事件を起こさざるを得なかったのだ」と考えるケースがあった。
これは、信者にとっては、元教祖を否定すれば、自分の信仰=自分の存在意義の根本を否定することになるから、それよりも、元教祖を否定せずに、自分の一部を否定する方が、自己を守ることができたからである。
また、信者がこの状態から抜け出せない背景も、親への依存から抜け出せない子供の理由と同じであり、
①抜け出すためには、元教祖によって満たしてきた自己存在意義は放棄しなければならないが、それが放棄できないこと。
②元教祖の価値・判断から自立して、自分の価値・判断で生きる上での自信の不足があるが、その奥には、自信がつくほどに必要な努力をしな い依存・甘え・怠惰などがある。
具体的に言えば、元教祖に対する絶対的な帰依によって与えられるとされていた、キリストの弟子・選ばれた魂になること、解脱者になること、三悪趣に落ちず高い世界へ転生することといった願望について、それを放棄するか、ないしは、別の手段で得ようとする努力が必要となる。
そして、元教祖の教義としては、信者は汚れており、正しい判断ができず、グルに絶対的に帰依することによってのみ救われ、自分で判断してはならず、グルを裏切ると三悪趣に落ちる、などというものがあって、これが信者を呪縛し、その自立を妨げる要素となっている。
しかし、根本的な原因は、元教祖の教義が根本的な原因ではなく、必要な努力をなす労苦を嫌がる信者側の依存・甘え・怠惰である。依存したい者には、依存するべきであるという教義は、都合が良いものであるからだ。
しかし、依存・甘え・怠惰という煩悩の本質は、最初は楽だが、後からつけが回ってくるというものである。一方、自立は、最初は努力が必要で労苦があるが、後は楽になるというものであろう。これを踏まえて、自分の弱さに打ち勝たなければならない。
さて、このケースの1つの変形版として、ずっと依存状態が続くのではなくて、親の目から見ると、ある段階から突然、服従から反抗に移行する場合があるようだ。これが、4のケースである。
すなわち、段階的に反抗期を経験し、段階的に親も自分も相対化し、親への一定の感謝や尊敬をもって、健全な自立をするのではなく、ある段階まで全く反抗期がなくて、親から見ると、何でも言うことを聞く、とても素直で良い子であったのが、いきなり、反抗や非行に移行するケースである。
この場合、子供は、長らく、親に認められたいために(親に従って自己存在意義を満たそうとしてきたがために)、無理して自分を抑圧してきたことが、ある段階から、恨みのような感情に変わり、爆発する場合もあるようだ。
客観的に見ると、子供が自らの意思で親に依存してきた場合も、子供の方は、親が自分を無理に抑圧してきたという印象を形成する場合があるようだ。他人から見れば、過剰な責任転嫁であるが、こういったことは、子供に限らず、大人の世界にもよくある。
そして、これも、子供と親に限らず、オウム真理教の元信者と元教祖のケースにも当てはまる。自分の意思で元教祖に帰依したにもかかわらず、元教祖を否定した後は、自分が安直に信じた責任は十分に自覚せず、もっぱら教祖にのみ責任を転嫁し、教祖を一方的に恨むというケースである。
しかし、(特に幹部信者などの場合は)単純に騙されたと主張するばかりで、自分が安直に信じて教祖を祭り上げたという反省がなければ、本当の意味で自分が変わることはできない。
帰依している時は、教団を弾圧する社会が悪いと安直に主張して、帰依をやめたら、自分を騙した教祖が悪いとばかり主張するならば、今も昔も、常に自分は被害者の位置づけであって、問題を他人のせいにしてばかりである。
こうして、脱会しても、人格は変わらないという問題はよくみられる。わかりやすく言うと、オウムは脱会したが、オウム人格は変わらないという現象である。脱会するのは、一瞬の手続きだが、本質的に人格を変えるのは辛抱強い努力が必要である。
この背景には、先ほどのケースと同じように、やはり依存・甘え・怠惰があるといわざるをえない。真に幸福になるには、自分の問題点を反省して、辛抱強く努力して、成長していくほかはないのである。
最後に5番目のケースは、親を絶対視してはいないが、親に対する期待が十分に満たされないために、常に強い不満・怒りを持つ場合である。
2のケースとの違いは、親に失望し、突き放しているのではなく、依然として期待していることである。4のケースとの違いは、4のケースは恨みであるから、もう相手への期待はないが、2のケースの不満・怒りは、依然として強い期待が背景にある。
そして、私の経験上、こうして、常に不満・怒りを持っていると、場合によっては、憎しみのレベルにまで至る場合があるようだ。
しかし、実際に、どんな親も不完全な人間であるから、いろいろな欠点があるのは仕方がないことである。そして、先ほど言ったような状態で、精神が歪みやすい現代社会においては、相当に人格が崩れている親もいるだろう。そして、その親のもとで育った子供が親になり、その子供がまた親になっている時代である。
具体的には、会員や一般の人の相談を受けていると、父親で言えば、女癖・酒癖が悪い、母親や自分に暴言を吐く、暴力を振るうとか、いろいろな事例が出てくる。
確かに、そういった問題はない方がいいに決まっている。しかし、私が相談を受けた体験上は、そういった親の人格は、直ちには改善されそうにない場合も少なくない。
さらには、子供が単に不満や怒りをもって親を責めても、親にもいろいろあるだろうから、必ずしも良い方向には行かない場合がある。仏教的な因果の法則(カルマの法則)からすれば、自分の不満や怒りの心・波動が相手に伝わって、相手に投影され、相手からも反発が返るだけとなる場合もある。それでは、建設的・前向きな行為ではないだろう。
そもそも、本当に相手を変えようとする場合は、相手をよく理解し、辛抱強く賢いアプローチ=慈悲の実践が必要であり、その中には、相手の向上を祈りつつも、無理な期待はしないという心構えが含まれる。
子供にとって、これは大変なようだが、ポイントは、本当の意味で大人になるには、必要な努力であるということだ。親に求めるばかりで、自分側の努力がない場合は、子供はいつまでも子供であり続ける。
そして、その背景には、繰り返しになるが、必要な努力を避ける依存・甘え・怠惰があり、それから脱却できないならば、その自分の未熟な人格の投影を親に見続けることになりかねないのである。
さて、この5のケースも、親以外の強い期待・依存の対象に当てはまるものである。例えば、団体の内部での学習仲間同士の関係にも、これが当てはまらないかについて、よく検討してもらいたい。
4.内観と親子問題の緩和
次に、こういった問題に対する内観の実践の効果を考えてみよう。まず、この5のケースにおいては、特に内観が有効であると思われる。
というのは、確かに、親にはいろいろな欠点があるだろうが、内観を通して、自分が親に実に様々なことをしてもらってきたことや、自分も親にいろいろ迷惑をかけてきたことなどを認識することによって、バランスの取れた見方ができるようになることが期待されるからである。
逆に言えば、通常は、強い期待を背景に、普段は、親のしてくれないこと、親の欠点ばかり見ており、内観の実践でもしなければ、親の長所・恩恵を客観的に見たり、自分側の欠点を客観的に見たりすることはなかなかできないと思われる。
自分の欲求が強いと、与えられていない部分ばかりを見て不満に思うが、仏教的には、それは貪りの心の働きである。また、その場合は、相手と同様に、自分にも欠点があることが理解できなくなるが、それは、自他を区別する無智である。
相手の問題について、自分では正しいことを言っているつもりでも(仮に言っていること自体は正しいとしても)、その時の心の働きが、無智・貪りに基づいており、相手のことを思って(慈悲に基づいて)いない場合が少なくない。
この場合は、相手の反応も、自分の心の投影として否定的なものになる可能性があるし、何よりも、こうした期待を背景とした不満・怒りを募らせるだけでは、自分自身がなかなか成熟していかないという不利益がある。
次に、1と2と4のケースにおいても、内観は有効であると思われる。その前に、もう一度、1と2と4のケースを列挙すると、以下の通りである。
1.親への尊敬・感謝が乏しく、他に絶対的な存在を求め、それに過剰に依存・服従する。
2.親への尊敬・感謝が乏しく、他にも誰も尊重せずに、反抗ばかりする。
4.親への過剰な依存・絶対視は止めたが、逆に親が自分を不幸にしたと恨みを抱く。
これらのケースの根底には、自己の誇大妄想的な願望が背景としてあることは、前に述べた通りである。1のケースは、教祖などに依存し、その願望を満たそうとしており、2のケースは、満たすための依存の対象が見つからないので、誰も尊敬しない状態であり、3のケースは、依存したが満たされなかったことによる恨みの状態である。
しかし、この誇大妄想的な願望は、前にも述べたとおり、子供の時ならばともかく、成長する過程では、卒業すべきものである。言うまでもなく、現実の社会では、幼稚で、妄想的で、傲慢で、自己中心的なものである。
これに対して、内観の実践は(特にひかりの輪の仏教的な内観の実践は)、自分が、いかに実際に肉親や知人を含めた他に支えられているか、いかに万物に支えられているかという事実を理解していくから、自己の絶対性ではなく、自己の相対性(他との支え合いで自分が成り立っていること)の理解を促進する面がある。
すなわち、内観とは、物の考え方において、子供から大人になる効果があると思われる。妄想的な自己存在意義を求めて、自分や特定の他者を絶対視・特別視するのではなく、自分を多くの人間の一人として受け入れて、その中で健全な自己向上欲求を持つことである。これは、内観の権威である人も述べていることである。
こうして、内観に基づいて、他への感謝と謙虚さを培うならば、自己中心を脱却して、他と調和した生き方をするきっかけとなる可能性がある。そして、前にも述べたが、この考え方は、仏教では、縁起の法や、唯識の依他起性の思索・瞑想でもあり、自我意識を弱めて、全体と一体化する効果を持つ。
最後に、3のケースであるが、これは、内観実践上は特殊なケースである。この人の場合は、親や、親に準じる依存の対象に対して、普通とは逆の偏りを形成している。
すなわち、普通は、してもらっていることの多さ、して返したことの少なさ、迷惑をかけたことの多さを十分に認識しないために、それを調べていけばいいのであるが、このケースにおいては、逆に、①してもらっていないことも、してもらっていると考えたり、②して返していることがあっても、過小評価していたり、③迷惑をかけていない場合も、迷惑をかけていると思いこむといった場合がある。
これは、通常のケースでは、自己中心的な意識が働くところ、3のケースは、相手が、自己の存在意義になっているために、その相手を中心とした意識が働いてしまい、相手に偏った見方をしているからである。
よって、私の見解としては、通常とは逆の方向性で内観をする必要がある。
5.内観で培う健全な親への認識と悟りの関係
さて、内観によって、両親をはじめとする人々に対して、感謝や尊重といった、健全で肯定的な心を培うことは、仏教の悟りを得る上で非常に重要である。
というのは、大乗仏教の教えの核心は、全ての衆生を愛する四無量心であり、それに関連して、全ての衆生に仏性があると説くことにある。
そして、全ての衆生を愛する四無量心を培う上で、いにしえの聖者方は、弟子たちに、自分の両親が自分をいかに愛してくれたかを思い出させ、全ての衆生が自分の過去世の母や父であったことを瞑想させてきた。
また、大乗仏教には、この宇宙が全ての衆生を育む仏陀の母胎の中であると考え、その仏に合一する教えがある。宇宙を自分の母であり、仏であると見ているのであるが、この思想を理解する上でも、今生の自分を生み育てた母親や父親に対する感情がバランスの取れたものであることは重要である。
また、全ての衆生に仏性があるという教えは、全ての生き物は、本質的には、慈悲という仏陀の心を有しているという意味であって、どんな悪人でも、例えば我が子を育もうとする瞬間には、慈悲・利他の心を現すといった事実が指摘される。
簡単に言えば、仏教の教えとは、全ての人、全ての生き物に価値を認め、それを愛することであるから、自分を生み出した、自分が今生初めて接した人間である親を愛することは、非常に重要な課題となる。
ところが、現代では親子関係が歪んでおり、親を尊敬していない子供が多くなっている。よって、この親子の問題を乗り越えなければ、仏教の教えの根幹が損なわれる。
一方、オウム真理教は、この問題を解決せずに、この問題を逆手にとった宗教であると思われる。すなわち、末法の世には悪業多き魂が多いとして、教団を肯定しない親は強く否定し、出家制度によって子供を親から隔絶し、教祖のもとに集中させることで、子供が救われるとし、親をはじめとする社会と敵対し、戦って勝利することを教義とした。
よって、この問題を乗り越えることは、現代における仏教の学習実践の困難を克服することであるとともに、オウム真理教を乗り越えることとも深く関連している。
そこで内観の実践の重要性が出てくる。確かに昔に比べて親の問題が増えているのだろうと思う。しかし、昔も相対的に不徳な親は多くいたはずであり、そういった場合は子供がどのような眼差しで親を見るかで、親への感情が大きく変わるはずである。そこに、内観の重要性がある。
また、悪化しているのは親だけでなく、子供の友人、学校の教師、マスコミの情報を含めた、子供を取り巻く社会全体であろうから、それによって、子供側が親を見る目が歪んでいることもあるはずである。
そして、内観では、客観的に、親に受けた恩恵や親に迷惑をかけたことを調べていく。そうすることによって、現代の親でも、依然として我が子を思う気持ちは決して少なくない、という事実が浮かび上がってくるのではないかと私は思う。
もちろん、人によっては、例えば、浮気、離婚、酒癖、女癖、暴言、暴力と、親の問題がいろいろあるだろうが、それであっても、親が子供になす自己犠牲の奉仕は膨大であるという事実もあるはずである。それらをありのままに認識し、親に合格点を与えられないものであろうか。
また、親に捨てられた子供の場合も、捨てたくて捨てたのではない親の苦しみに気づいたり、親代わりになってくれた人への感謝を深めたりすることで、自分の心を癒して浄化し、他者への愛というかけがえのない心の働きを深めることで、悟りの土台ができるのではないだろうか。