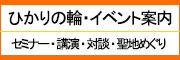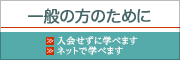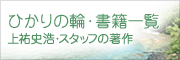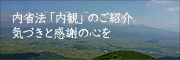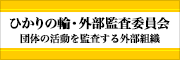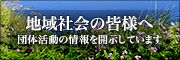新着情報 <ヨーガ・気功>
- 2025/04/09
- 「ヨーガの体操と呼吸法と瞑想の科学」(2025年3月15日横浜 52min)
- 2023/08/21
- 『3つの主な瞑想法とクンダリニーヨーガの瞑想』(2023年6月11日 大阪 43min)
- 2022/05/12
- 『心の健康の3つのコツ:筋肉・呼吸・姿勢と何でもQ&A』(2022年3月25日YouTubeライブ 85min)
- 2016/03/01
- 【動画】「ヨーガ基礎編」
- 2015/12/18
- 気功とは?
- 2015/12/18
- ベーシック・ヨーガの意義
- 2015/12/17
- クンダリニー症候群について
- 2015/12/17
- 気・クンダリニー・チャクラ
- 2015/12/17
- ヨーガとは?
- 2011/05/16
- 【動画】「エンライトメント・ヨーガ」
- 2011/02/06
- 「エンライトメント・ヨーガ」動画・実践編の内容テキスト
- 2011/01/19
- マインドフルネス・ヨーガとは
- 2008/03/14
- エンライトメント・ヨーガの効果
- 2008/02/23
- 3 丹田呼吸
- 2008/02/23
- 2 呼吸の重要性
- 2008/02/23
- 1 ブリージング・ヨーガとは
- 2008/02/10
- ナチュラル・ヨーガとは
- 2008/01/23
- 初心者向けのアーサナとその効果のご紹介
このコーナーについて
多様なヨーガや気功をご紹介しています。
ひかりの輪では、その方の状態に合わせた指導による、ヨーガや気功のコースを行っています。
ヨーガは、
「エンライトメント・ヨーガ(サマディと悟りのヨーガ)」
「ナチュラル・ヨーガ(大自然と一体となるヨーガ)」
「ベーシック・ヨーガ(基本的なヨーガ)」
「マインドフルネス・ヨーガ(心理療法のヨーガ)」
「ブリージング・ヨーガ(呼吸のヨーガ)」があります。
各種ヨーガは、心身に優しく働きかけ、心身の癒し、瞑想に導く効果があります。
どんな方でも無理なく行うことができます。気功は、「流体循環気功」と名付けた、ひかりの輪オリジナルの気功を行っています。
まずは、ヨーガ・気功コースの動画(エンライトメント・ヨーガ)/流体循環気功)で、お部屋で試していただければ、その効果を実感できるかと思います。ご関心のある方は、ご見学・無料体験もできますので、お気軽に全国の各教室にお問い合わせください。また、各種DVDも販売しています。
(ひかりの輪では、昔オウム真理教で問題となったような、心身に負担となるほど偏ったヨーガのやり方ではなく、心身のバランスと癒しをもたらすような、緩やかな行法実践を行っています。)
ヨーガ講義の予定とテーマ
「『ヨーガ・瞑想』講義のカリキュラム」 のお知らせ
ひかりの輪では、発足以来、ヨーガ・瞑想の探究と講義・実践を行ってきましたが、これまで行ってきたヨーガ・瞑想関連の講座を厳選して約1年間ですべて学べるヨーガ・瞑想の講義のカリキュラムを作りました。
カリキュラムは、ヨーガの基本から始まり、ヨーガの歴史と全体系の解説、そして、代表的なヨーガの行法と瞑想の理論と実践を含む充実したものとなっています。
以下に、カリキュラムと2025年末までの日程をお知らせいたします(なお、日程は変更の可能性がありますので、随時こちらのページをご確認ください。また2026年以降の日程は決まり次第、こちらのページに掲示いたします)。
※なお、このヨーガ・瞑想の講義は、東京教室での勉強会(約2時間)の中の一部の時間を使って、約30分~1時間程度行われるものです。よって、この勉強会においては、上記のヨーガ・瞑想の講義のほか、仏教・心理学講義、読経瞑想、質疑応答などのヨーガ講義以外のプログラムも含まれることをご了承ください。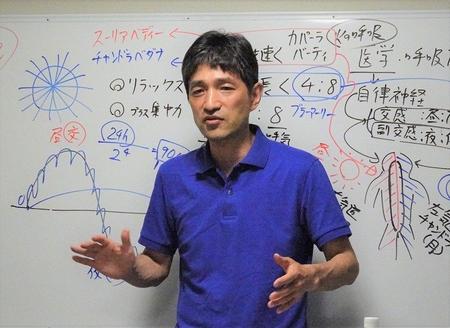
具体的なカリキュラムの内容と講義日程につきましては、こちらのページをご覧ください。