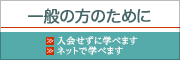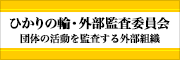仏教・ヨーガなどの専門用語の解説集
【ア行】
●アーサナ
アーサナはヨーガの中の身体技法。柔軟体操と似ているが、大きく違う点は呼吸と動作を合わせて行う点である。弛緩と緊張のバランスをとり、動作と呼吸をコントロールすることで、神経・ホルモン分泌・免疫系の働きが正常化し、身体の調和を取り戻し、各機能が整えられ、健康・美容にも良いとされる。
●アートマン
インド哲学においては、真実の自己をアートマンと言い、これは、永久不変の存在とされる。このアートマンは個人の本体であり、宇宙の根本原理であるブラフマンと究極的には一体であると説かれる。一方、仏教では永久不変のアートマンという存在は認めておらず、それを無我という。
●一元論(いちげんろん)
世界の諸現象をただ一つの原理から把握しようというもの。それに対して、2つないし複数の原理で把握しようというものを二元論・多元論という。
●宇宙意識(うちゅういしき)
一部のヨーガ修行者が用いる言葉で、意識が宇宙大に拡大した状態であるとされる。私たちの心は、通常は、肉体などの自我にとらわれているが、その本質は、広大で無辺である。煩悩を静め、慈愛の実践をし、ヨーガ修行で肉体から離脱するサマディに入ることで、宇宙意識を体験することができるという。仏教においても、似たような高次元の意識状態を規定している。
●縁起(えんぎ)
「因縁生起」(いんねんしょうき)の略。縁起は「縁って起こる」こと。因縁については、双方を区別せず、原因・条件を意味する時代もあったが、後に「因」は直接原因、「縁」は間接原因・条件を意味するようになった。
よって、縁起ないし因縁生起とは、一切の事物・現象は、直接ないし間接の原因条件によって生じているにすぎないという意味となる。すなわち、何ものも、それ自体で他と独立して生じ、存在することはなく、他と関わりあって生じ滅しているということである。
そのもの自体で独立して存在しておらず、さまざまな原因・条件によっているため、その原因・条件が生じる前は存在せず、その原因・条件が滅すれば、また滅することになり、一切の現象は無常であるという結論が導きだされる。
言い換えれば、縁起の意味は、すべての現象は、他との関係の中で生起しているということであり、仏典の言葉では、「此(これ)があれば彼があり、此がなければ彼がない。此が生ずれば彼が生じ、此が滅すれば、彼が滅す」と説かれる。「此」と「彼」とが、お互いに相互依存しているのであり、それぞれ、それ単独で個別に存在するものではないことを説いているのである。
特に大乗仏教では、縁起と連動して無自性、そして空という概念が強調され、すべての事物・現象は縁起しており、無自性であり空であると説く。
無自性とは自性がないという意味で、自性とは、縁起とは逆に、そのものだけで独立・孤立して存在する実体である。すなわち、無自性とは、そのものだけで独立して存在する実体がないという意味になる。空とは、サンスクリット語でシューニヤで、仏教用語としては、固定した実体がない、実体性を欠いていることを意味する。
この大乗仏教における、縁起の法に基づく空の思想は、ナーガールジュナなどによって確立されたといわれる。
さて、縁起の法には、チベット仏教ゲールク派などによれば、三つのレベルがある。まず、第一のレベルは十二縁起の法と呼ばれるものである。これは人間が苦しみの生存にいたる原因・条件について、十二の段階に分けて分析したものである。
第二のレベルの縁起の法は、全体と部分という概念について、全体が部分に、部分が全体に依存して(互いを条件として)存在しているという教えである。第三のレベルの縁起の法は、すべての認識の対象となる事物が、言葉による概念化に依存して(条件として)生じているというものである。
【カ行】
●神
神という場合は、ヒンドゥー教が説くような絶対神・最高神といった神と、仏教が説くように、それより低位だが、人間より上位の存在としての神がある。後者の方には、人々に害をもたらす悪神、魔神も含まれる。
日本では、神道と仏教が融合する神仏習合の文化の中で、仏と神が一体化していき、いわゆる神仏という言葉が生まれるにいたった。大乗仏教においては、ヒンドゥー教の神々を取り入れて、仏の下に位置づけたり、仏と一体と位置づけた。チベット仏教の守護神なども、この一例ということができる。
●カルマ、カルマの法則(=因果の法則)
「カルマ」は、「業」と訳される。原語のサンスクリット語は、カルマンで、その基本的な意味は、なすこと、なすもの、なす力などで、作用、行為、祭祀を表す言葉としてインド思想一般で広く用いられた。
その中で、輪廻転生の思想と結びついて、輪廻転生をもたらす一種の力として、ある行為の結果として生じて働く、潜在的な行為の余力を示す言葉になった。なお、釈迦牟尼は輪廻を絶対視しなかったと言われるが、その後にできた大乗仏教は、ヒンドゥー教の思想も影響も受けて、輪廻が中心教義の一つとなった。業は身体にかかわる行為を身業、言葉に関わる業を口業、意識に関わる業を意業といって、これを三業という。
より具体的に説明すると、私たちは生きているかぎり、心を動かし、言葉を話し、身においてさまざまな動きをしているが、これらの心の行為・口の行為・身の行為はそれが為されたら終わりではなくて、私たちの深い意識にその残存、形跡(痕跡)を残す。
そして、その形跡はある条件が成立すると現象として現われる潜在的な形成力を有している。この形跡を種(「原因」)と考えると、種が発芽するためには、土や水、光という「条件」が必要であるが、そういった条件が整ったときに芽(「現象」)が生じる。
こうして、自分に起きる現象というものは、自分がかつて為した行為の残存物が現象化したものだということになる。そして、善き残存は善きこと、幸福・喜びを産みだし、悪しき残存は悪しきこと、不幸・苦しみを生みだす。
これが、「カルマの法則」といわれるもので、これに従えば、自分が過去に為した行為の結果が、現在から未来において自分に返ってくるということになる。自分が為したことはすべて、将来において何らかの結果を生み出す原因となるということである。そして、この業は、輪廻転生の要因にもなり、業に応じて転生する世界が決まるとされる。
なお、カルマの法則は、因果(いんが)の法則ともいわれる。因果とは原因と結果のことで、結果を生みだすものを因といい、その因によって生じたものが果である。よってすべての現象は原因があって結果があるというのが因果の法則である。
特に善い行為(善因)には善い結果としての報い(善果)、悪い行為(悪因)には悪い結果としての報い(悪果)が、因果の法則によって生じることを因果応報といい、そのため、自分が過去になした行為の業の結果を自分自身が未来に経験することを自業自得という。
なお、この思想は仏教独自のものではなく、仏教以前に紀元前8世紀ごろ、既にインドに定着しており、それを仏教が取り入れたものである。
●カルマ・ヨーガ
すべての人を神の現れと見て奉仕するヨーガにおける実践。
●観音菩薩(かんのんぼさつ)
慈悲や智慧を象徴し、衆生済度を志す菩薩とされ、古くから日本でも広く信仰されてきた。「阿弥陀如来」の化身・弟子として知られるとともに「観音菩薩」独自でも広く信仰されている。観音菩薩は「観世音菩薩」、ないし「観自在菩薩」などともいわれる。
いろいろな姿形があり、33の化身を持ち、さまざまな姿・方法で救済を行うといわれている。仏像などで有名である、十一面観音、千手観音などは、多くの顔や手を持つことで、多くの人をもれなく救おうという意思を現わしているとされる。最もオーソドックスな原型は、聖観音菩薩像とされる。また、如意輪観音、不空羂索観音など、他にもさまざまな形の観音菩薩の仏像がある。釈迦が悟る前の王子時代を象徴するものともいわれ、そのため、釈迦と一体と解釈する場合もある。
●帰依(きえ)
仏教用語としての帰依は、三宝とされる仏・法・僧に対して信奉することをいう。
●空(くう)→中観派の項を参照
●功徳(くどく)
善を実践することによってその人に備わった徳性のこと。具体的に何が善であるかを一言で表現するのは難しいが、仏教においては、悟りを妨げる根本的な三つの煩悩として、貪欲(貪り)、瞋恚(怒り)、愚痴(無智)を規定し、それを三毒と呼び、三不善(根)と規定しており、それを滅することを三善(根)という。
大乗仏教では、六波羅蜜といわれる修行体系において、布施、持戒、忍辱、精進といった功徳を積むプロセスがある。また一般に仏陀、菩薩、神々などに対する供養も功徳になるとされる。
功徳は、それを積むことによって解脱へ進むと考えられており、すなわち悟り・解脱にいたるための条件である。そして、仏は無量の功徳を備えているとされる。また、幸福・幸運も、仏教的には偶然ではなく、その人の功徳によって必然的に生じたものだと解釈される。
●供養(くよう)
サンスクリット語の原語はプジャで、尊敬を持ってねんごろにもてなすことが原意で、宗教的偉人などに敬意を持って供儀や供物を捧げることをいう。
仏教では、仏・法・僧の三宝に対する供養がよく説かれ、父母・師長・亡者に対する供養もある。捧げるものは多種多様であるが、香、華、灯明、飲食物、資財などがある。
●クンダリニー
ヨーガが説く霊的なエネルギーのこと。通常は人の尾?骨付近のチャクラに眠っているが、ヨーガ等の実践で活性化し、身体の中を上昇し、最終的には頭頂に至るとされる。ヨーガでは、クンダリニーの上昇にともない、チャクラが開かれるとされる。また、性エネルギーを昇華させたものがクンダリニーのエネルギーとなるため、梵行(性的な事柄を避ける)修行が必要とされる。
このクンダリニーヨーガを実践する場合は、適切な指導を受けずに、不適切なやり方をすると、心身を痛めたる可能性がある。また、これによって、神秘体験をしたり、超能力が身についたかのような体験をすることがあるが、そのために慢心を抱くと、魔境、誇大妄想に陥り、真の悟りへの道を逸脱するとされる。
●原始仏教(げんしぶっきょう)
釈迦が生きていた時代を含み、釈迦の死後およそ100年から200年までの間の最初期の仏教をいう。最近は初期仏教とも言われる。主な教えは一番初めに説かれた四諦・八正道や縁起、五蘊の無常・苦・無我(非我)の説など。
●五蘊(ごうん)
蘊は、サンスクリットの原語はスカンダで、集まりが原意。五蘊とは人間の肉体や精神を五つの集まりに分けて示したものであり、色(しき)・受(じゅ)・想(そう)・行(ぎょう)・識(しき)という5つである。
仏教では、この五蘊が仮に集合されたものが人間であるとして、「五蘊仮和合」(ごうんけわごう)と説く。これによって人間という存在に実体がないこと(=無我)を現わした。
五蘊のうち「色蘊」は、初めは人間の肉体を意味したが、後には、すべての物質も含んでいわれるようになった。受以降は、すべて精神的な要素であるが、受は、感受作用、想は、表象作用(いわゆるイメージ)、行は、意思作用、識は、認識作用などと説明される。ただし、特に行・識にはさまざまな解釈があるので注意されたい。
【サ行】
●サマディ
瞑想などにより煩悩を止滅していくと、サマディと呼ばれる超越的な瞑想状態に入るという。
サマディには段階や種類があるが、その中には仮死状態に近く、肉体の機能が停止するものがあり、呼吸は停止し心臓の鼓動もほとんど止まるといわれる。
精神的には生命愛著も超えた状態であるとされ、呼吸や心臓の鼓動といった普段は無意識に行っており制御できない行為も、深い部分の意識・煩悩に起因しているという証明ともされる。
サマディの中で無分別サマディと呼ばれるものは「見るもの」と「見られるもの」、つまり主体と客体の区別はなくなり、主客未分の直感的な意識状態になるものもあるという。
●三グナ
ヨーガで説かれる心を構成する三つの要素であり、ラジャス・タマス・サットヴァという。ラジャスは、情熱、活動、動性を表し、タマスは不活発、鈍さ、暗性を表し、サットヴァは純粋、光、喜び、善性を表す。心の3つの性質であり、常に誰にでも存在しているという。
この3つの要素のどれが一番強く現われるかによって、その人の心の傾向が決まる面があり、心の発する波動は3つのグナから発生し、三グナのバランスが重要であるとされる。
[ラジャス]ラジャスは、情熱、活動、動性を表す。このラジャスの要素が多くなると、落ち
着きの無さ、イライラ、せっかち、焦り、怒りっぽさ、せかせかする傾向が強くなるという。なお、ピンガラ気道(右気道)に、エネルギーが優位になると、ラジャス傾向になるという。
[タマス]タマスは、不活発、鈍さ、暗性を表す。このタマスの要素が増えると、物事を遅ら
せる、怠惰、曖昧、愚鈍、遅い、鈍い、うつ状態などになるという。また、イダー気道(左気道)にエネルギーが優位な時は、タマス優位になるという。
[サットヴァ]サットヴァは、純粋、光、喜び、善性を現わす。サットヴァの心は、常に静寂
で確固としており、喜びは内面にある。また、人が、サットヴァ優位なときは、その行動の特質として、はっきりしており、すみやかで勤勉であり、落ち着きがあり、動作が機敏というものがあげられるという。中央気道であるスシュムナー気道にエネルギーが入るとサットヴァになるとされる。
●三苦(さんく)
苦苦(くく)、壊苦(えく)、行苦(ぎょうく)をさす。
苦苦は、直接的な苦しみであり、肉体的な苦(身苦)と精神的な苦しみ(心苦、憂)に分けられることもある。
壊苦は、直接的な苦(苦苦)ではなく、楽が壊れるときの苦であり、行苦は、一切の存在が無常であり、生滅変化を免れないことによる苦である(行の原語のサンスカーラには移り変わること、という意味がある)。
三苦はすべては苦である(一切皆苦)ことを示している。直接的な苦だけが苦なのではなく、楽であるものも必ず壊れて苦になり、また不苦不楽(苦でも楽でもない)の状態も、無常に移り変わるので苦しみに帰結する。
本質的には、苦苦も壊苦も、無常を根本として起こる苦であるから、行苦を根本として起こってくるといえるし、また行苦とは、人間生存が無常であるという事実の中に感ずる苦であるから、生存苦、すなわち生きること自身が苦であることを示したものということもできる。
●三身(さんじん)
大乗仏教で説かれる、仏陀の三つの身体で、法身〔ほっしん〕・報身〔ほうじん〕・応身〔おうじん〕のこと。
この身体の解釈には,さまざまなものがあるが、一般に法身はサンスクリットの原語はダルマカーヤであり、永遠不変の真理、絶対的真理そのものを意味し、永遠不滅であり、人格性をもたないものとされる。詳しくは法身の項を参照のこと。
また、応身は、原語はニルマナカーヤであり、さまざまな衆生の救済のために、それらに応じて、この世に現われる仏陀の身体であり、人格性を持つが、同時に無常なものである。応身は別に変化身と呼ばれる場合もある。
そして報身は仏陀となるための因としての行を積み、その報いとしての完全な功徳を備えた仏陀の身体とされる。一説では法身と応身の両者を統合した身体とも位置づけられる。
チベット仏教などでは、法身は人の心が完全に浄化されたものであり、報身は、言葉が浄化されたものであり、応身は身体が完全に浄化されたものなどと説かれている。
●三世(さんぜ)
過去・現在・未来のこと。
●三宝(さんぼう)
三宝とはサンスクリット原語ではブッダ・ダルマ・サンガであり、仏、法、僧と訳される。
ブッダ(仏陀)の原意は、目覚めた人であり、古くは、優れた修行者や聖者に対する呼称であったが、仏教で多く用いられ、釈迦を尊んで呼ぶ言葉となった。その後、大乗仏教において、釈迦に加えて多くのブッダを規定するが、さらには華厳経などのように、大宇宙そのものを仏の現われと見るといった教義も展開された。
ダルマ(法)は、仏陀の説いた教えであり、それを一言でいうことは不可能であるが、釈迦の説いた中核の教えとしては縁起の法などがあり、さらに仏教の教えの特徴を表すものとして三法印(諸行無常、諸法無我、涅槃寂静)などがある。
サンガ(僧、僧伽)は、原意は集い、群れ、団体、組織などであり、仏教においては、仏教の教団(仏陀の教えを奉じる集団)のことを意味する。僧が滅すれば、この世においては仏教も滅びるのであり、その意味で極めて重要である。
サンガは狭義には出家僧のことであるが、大乗の教団では、在家・出家の区別が不明瞭となる。悟った聖者の集団を聖者僧といい、これが三宝における僧であるという見解もある。一方、一般の僧を世俗僧・凡夫僧ともいう。
なお、大乗仏教においては、三宝はすべて真如から生じた一体のものとの見方があり、それを一体三宝という。チベット仏教においては、仏陀=心、ダルマ=言葉、僧=出家教団=身体と見る考えもある。住持三宝と呼ばれるのは仏像、経典、出家の僧のことである。
●三法印(さんぼういん)
仏教の教えの特徴をあらわす三つのしるし。「諸行無常(しょぎょうむじょう)」「諸法無我(しょほうむが)」「涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)」の三つ。
まず「諸行無常」とは、すべての物事は常に変化しつづけているという事実を表している。
次に「諸法無我」とは、すべての事物は永久不変の本質を有しないという意味である。逆にいえば、すべてのものはそのもの自体で独立して存在するのではなく、直接的・間接的にさまざまな原因(=因縁)が働くことによって生じているにすぎず(これを縁起の法という)、それらの原因が失われれば直ちに滅し無常であり、そこには何ら実体的なものはない(これを諸行無常ともいう)。
なお、ここにおける法とは教えという意味ではなく、事物とか認識の対象といった意味であり、これは原語のダルマが多義語であり、主に教えという意味と事物という二つの意味があるからであるが、注意を要する。また、ここにおける我の原語はアートマンであり、これはインド哲学思想において、常住=永久不変の本質といった意味を持つ。
最後に「涅槃寂静」とは、迷妄の消えた悟りの境地は静かな安らぎの状態であるということ。
これに「一切皆苦(いっさいかいく)」を加えて四法印とすることもある。
●持戒(じかい)
仏教に帰依する者が守るべき戒を保持して守ること。一般に、戒律の保持(持戒)は仏教修行の基礎とされ、仏教の基本的な修行の項目である戒・定・慧(三学)の第一に数えられ、また大乗仏教における六つの実践課題である六波羅蜜の修行では、その第二が持戒波羅蜜(持戒の完成)である。戒にはさまざまな種類があるが、大乗仏教の主たる戒律としては、十善戒というものがあり、具体的には、
①不殺生(生き物を殺さない)
②不偸盗(盗みをしない)
③不邪淫(邪淫をしない)
④不妄語(嘘をつかない)
⑤不綺語(必要のないおしゃべりをしない)
⑥不悪口(悪口をいわない)
⑦不両舌(人を仲たがいさせることを言わない)
⑧無貪〈または不慳貪〉(貪らない)
⑨無瞋〈または不瞋恚〉(怒らない)
⑩無痴〈または不邪見〉(痴=無智を持たない)
となっている。
なお不邪淫は出家と在家において異なり、出家者に対しては原則として、いかなる性行為も禁止される一方で、在家においては他人の夫や妻と交わるなど、邪な性行為が否定される。
なお戒律は、身・口・意の三つの側面から分類され、上記の①から③までを身体の戒律、④から⑦までを言葉・口の戒律、⑧~⑩が意識の戒律ということになる。
●自我執着(じがしゅうちゃく)
自分に対する執着。仏教的な教義においては、人は本来は実体のない自己に対して強くとらわれるがゆえに苦しんでいると説き、この自我に対する執着を超えることが重要な修行になる。
●色界(しきかい)
色は、サンスクリット原語は、ルーパであり、色〔いろ〕・形のあるもののことで、物質的存在の総称をも意味する。
そして、色界とは、欲望は超越したが、色、すなわち物質的な条件にとらわれた生物が住んでいるとされる世界のことであり、より詳しくは、精妙な物質でできた、色・形のある世界であり、色界に住む天人は、食欲と性欲を断じ、男女の区別がなく、光明を食するともいう。
●四苦八苦(しくはっく)
根本的な苦しみを生(生まれること)・老(老いること)・病(病むこと)・死(死ぬこと)の四苦とする。
この四苦に加え、怨憎会苦(おんぞうえく、憎んでいる対象に出会う苦しみ)、愛別離苦(あいべつりく、愛するものと別れなければならない苦しみ)求不得苦(ぐふとくく、欲しいものが得られない苦しみ)、五蘊盛苦(ごうんじょうく、とらわれの五つの集まりを持つことは苦しみ)の四つを加えて八苦という。
なお、四苦で、生まれることを苦とするのは、人生が苦しみであるといった意味だけでなく、出産の際の胎児の苦しみそのものを意味すると考えることができる。
●四諦(したい)
四諦とは、[苦諦]・[集諦]・[滅諦]・[道諦]という四つの真理のことである。釈迦が悟りをひらいた後、最初の説法(初転法輪)において説いたとされる仏教の根本教説であり、初期仏教の中心的教えのひとつである。
[苦諦]とは、この迷いの生存は苦であるという真理である。具体的な苦の内容としては、生老病死をはじめとする、いわゆる四苦八苦などが挙げられる。
[集諦]とは、苦が生起する原因についての真理で、それは、欲望、執着、渇愛に苦の因があると説くものである。
[滅諦]とは、苦の止滅についての真理で、それは、欲望のなくなった状態が、苦が滅した理想の境地であると説くものである。
[道諦]とは、苦の止滅に至る道(方法)についての真理であり、それは、八つの正しい修行方法(八正道)であると説くものである。
●四念処(しねんじょ)
①身体、②感覚、③心、④諸々の事物の四つについて、正しく観察し、それらに対する執着を滅する瞑想修行である。
①身体が、清浄(浄)であり、②感覚(受)は楽をもたらし、③心は常(不変)であり、④諸々の事物に永久不変の本質(我)がある、という四つの間違った考え(四顛倒)を打破するためのもので、それぞれ、身念処、受念処、心念処、法念処と言う。
具体的には、
①身念処:観身不浄:身体の不浄性を観察する、
②受念処:観受是苦:受=感覚が苦しみであることを観察する、
③心念処:観心無常:心が無常であること観察する、
④法念処:観法無我:全ての事物には、永久不変の本質(我)はなく、そのものだけでは独立して存在してはおらず、様々な原因・条件によって生じているにすぎないことを観察する。
●四無量心(しむりょうしん)
[慈]・[悲]・[喜]・[捨]という四つの広大無辺な(利他の)心のこと。
[慈]とは、生けるものに楽を与える心。他の幸福を望む心。
[悲]とは、苦を取り除くこと。 他の苦しみを悲しみ、苦しみから抜け出すことを望む心。
[喜]とは、他をねたまないこと。他の幸福を(ともに)喜び賞賛する心。
[捨]とは、好き嫌いによって差別しないこと。自我のとらわれを捨て、他を平等に見る心。
●釈迦牟尼仏・シャカムニ
仏教の開祖、ゴータマ・シッダルータのこと。インドで悟りを開いて、その教えを布教した。釈迦牟尼とは、シャーキャ族出身の聖者という意味で、釈迦牟尼仏とは、釈迦族出身の聖者たる仏陀という意味である(牟尼とは聖者という意味)。なお、釈迦は、ゴータマ・シッダルータが属していた種族の名前で、サンスクリット語やパーリ語の原語は、シャカというより、サキャに近い。
インドとネパールの国境付近のカピラヴァストゥという小国の王子として生まれ、生病老死の四苦を感じて、(一説によれば)29歳のときに出家したとされ、悟りを開いた後に、80歳で入滅するまで、インド各地(ガンジス河中流域中心)を布教して歩いたとされる。
なお、釈尊は、日本・中国における釈迦牟尼仏の尊称であるが、おそらくは釈迦牟尼世尊の語を略したものであると思われる。
●精進(しょうじん)
精魂を込めて、ひたすら勤め励むこと。六波羅蜜の4つ目であり、出家した者がひたすら宗教生活を一途に生きることである。その後、肉食をしない生活をする意味も持つようになった(精進料理)。
●十二縁起(じゅうにえんぎ)
人間の苦しみの原因・条件を順に分析したもので、12に分類して系列化したもの。仏教の基本的な教えの一つ。漢訳された仏教用語で表現すると、①無明、②行、③識、④名色、⑤六処、⑥触、⑦受、⑧愛、⑨取、⑩有、⑪生、⑫老死 の十二となる。
●修験道(しゅげんどう)
山を神として敬う古来日本の山岳信仰と神道、仏教、道教、陰陽道などが習合して確立した日本独特の宗教である。奈良時代に成立したとされる。開祖は役行者〔えんのぎょうじゃ/役小角 えんのおずぬ〕とされる。平安時代ごろから盛んに信仰されるようになった。
●衆生(しゅじょう)
すべての生きとし生けるもの、一切の生き物。
●ジュニアーナ・ヨーガ
哲学的なヨーガ、思索のヨーガといわれる。
●神仏習合
日本本来の神信仰(神道)が、新たに伝来した仏教と接触することによって生じた、思想・儀礼・習俗面などでの融合現象のこと。神社に付設して寺が建てられたり、仏像をご神体にしたりした。中でも、神とは、仏・菩薩が仮の姿をとって、この世に出現したものであるとする本地垂迹説(ほんじすいじゃく)という教えがあり、たとえば、天照大神(あまてらすおおみかみ)の本地仏は、十一面観音あるいは大日如来などとされた。
●神仏分離
明治新政府がとった、神道と仏教を分離する政策。神道の国教化と神孫としての天皇の権威確立のため1868年に下された。それによって、神社に付属する寺の僧が還俗させられたり、仏像をご神体とすることの禁止などが行われた。
この神仏分離令は、廃仏毀釈(仏教・釈迦を廃する)の嵐を巻き起こし、多数の文化財が破壊され、膨大な廃寺が生じた。神仏分離の結果として、神道と仏教とは異なる宗教であるという観念が定着することになった。
●禅定(ぜんじょう)
サンスクリット語のディアーナの音写である「禅」と、サマディの漢訳語「定」の複合語であり、心静かに心を統一して瞑想し、真理を観察すること。またそれによって心身ともに動揺することがなくなり、安定した状態。大乗仏教で菩薩が修習すべき実践徳目である六波羅蜜の第五に配される(禅定波羅蜜)。
【タ行】
●大乗仏教(だいじょうぶっきょう)
大乗仏教とは、仏教史の研究においては、西暦紀元前後からインドに興った仏教の革新運動と位置づけられる。
ゴータマ・ブッダ(釈尊)の入滅後まもなく、出家教団は、多くの学派に分れたため、部派仏教の時代と呼ばれているが、出家の仏教者たちは、遍歴をやめ、僧院に定住し、王族や豪商たちの経済的援助のもとに学問と瞑想に専心し、僧院に住む声聞(しょうもん、仏弟子の意)と、1人で山野に修行する独覚(縁覚ともいう)があったが、ともに阿羅漢という聖者になることを最高の理想としていた。
これに対し、仏教の革新運動の信者たちは、仏陀となることを理想とし、自らを菩薩(ボーディサットヴァ=仏陀のさとりを求める有情〔うじょう〕)と呼んた。そして、紀元後1世紀に成立した八千頌般若経の中で、みずからを大乗と称し、従来の部派仏教を小乗とおとしめて呼んだ。
小乗仏教と大乗仏教の違いは、小乗が自利にのみ走り一般の在家信者を顧みない傾向が強かったのに対し、大乗仏教の菩薩たちは、みずからが仏陀となることとともに、あるいはそれ以上に、あらゆる人々を悟らせ救済しようとする慈悲を強調したことで、そのために大乗という。
また、小乗教徒は、遠い未来に弥勒が成仏するまでの間は仏陀は存在しないと考えていたが、大乗教徒は、現在にも十方の世界に無数の仏陀が存在することを信じ、様々な仏陀の信仰を生み出したことも、教義の大きな違いになった。また、ヒンドゥー教やゾロアスター教の有神論の影響をも受け、他教の神々を自らの教義の中に取り込んだ。
さらに、独創的な空の思想をも展開し、紀元後1世紀以降に、般若経・維摩経・法華経・華厳経・無量寿経等といった大乗経典が編集された(第1期ないし初期大乗経典)。
3世紀には、ナーガールジュナが、『中論』等を著して、空の思想体系化に努め、4世紀には、勝鬘経・涅槃経など、如来蔵を説いた経典、および解深密教・大乗阿毘達磨経の阿頼耶識〔あらやしき〕を説いた経典が編集された(第2期ないし中期大乗経典)。
5世紀には無着・世親によって瑜伽行派が生まれ、中観派と対立したが、経典としては、如来蔵と阿頼耶識との統合をはかった楞伽経や大乗密厳経が編集された(第3期ないし後期大乗経典)。
6世紀ごろからは、密教化が進んだ。7世紀には、大日経・金剛頂経などが作られ、金剛乗が成立したが、金剛乗は、自らを大乗と区別する意識をも持っていたので、小乗、大乗、金剛乗と三つの仏教を分けて呼ぶ傾向もある。
一部繰り返しになるが、大乗仏教の教理は、仏教の中で、自身の悟りを求めるにあたって、まず苦の中にある全ての生き物を救いたいという心(菩提心)を発こすことを条件とし、この利他行の精神として、仏になる修行=菩薩行を実践することを最重視する考えに基づいた教えであり、自分一人だけでなく、多くの人を乗せて彼岸(悟り)に渡る船という意味で大乗と称する。
また、一切のものは、常に変化し、相互依存して、固定的実体がない(他からの影響なくそれ単独で存在するものはない)という空の思想が、大乗仏教の中心思想であり、これについては、ナーガールジュナが理論的に大成したといわれる。
●智慧(ちえ)
サンスクリット語の原語は定まらないが、その一つはプラジュニャーであり、これは、仏教の真理を洞察する強靱な認識の力を意味する。事物・現象の真理・実態をありのままに正しく認識する力であるから、例えば、縁起、空、無常、無我といった教えを理解し、体得していることと言いかえることもできるだろう。
大乗仏教の六つの実践徳目である六波羅蜜においては、その最後、6番目に数えられ、その前の5つの実践は全て、この智慧の完成のためであるともされる。
通常人は、無智に覆われ、智慧が完成していないことから、事物・現象をありのままに見ることができない。そのため、万物は変化し、固定した実体を持たず、相互に依存し合い、独立した実体はないところ、そのように見ることができず、苦しんでいるが、智慧の完成によって、この苦しみを越えることができる。
●チベット仏教
仏教がインドからチベットに伝わる中で生まれた仏教の教えで、さまざまな宗派がある。その最大宗派であるゲールク派の長は、ダライ・ラマ法王と称し、同時に政治的にもチベット民族の最高指導者である。
チベット仏教は、インドでは事実上滅びた仏教について、とりわけその後期の大乗仏教を最も純粋に継承するという主張もあるが、法王サイドの見解においても、チベット仏教はチベットのオリジナル仏教とも言うことができるような独特の教義体系を形成している面もある。
さまざまな宗派・修行体系があるので一概には説明できないが、大乗仏教的な精神に則って、菩提心(他者を利するために悟りを求める心)と智慧(空性を理解する智慧)を獲得することを重要な柱としていると言うことはできると思われる。
その中では、さまざまな経典の教えを整理して、仏教全体の教えを順を追って説いた「道次第(ラムリム)」の教えや、菩薩としての生を説く「心の修行(ロジョン)」なども説かれている。また、基本的には、その教義は、ナーガールジュナの中観を中心にしている、という解釈もある。宗派は、ゲールク派に加えて、カギュ派、ニンマ派、サキャ派などがある。
●チャクラ
サンスクリット語の原意は、車輪を意味する。それから転じて、ヨーガにおいて、ナーディの寄り集まったエネルギー・センターのことを意味する。蓮の花のような花弁で象徴的に表されることもある。
主要なチャクラは以下の通り7つあって、人体の各神経叢やホルモン分泌器官と関係しており、チャクラに働きかければ、ホルモン活動のバランスが保たれるという。さらに、チャクラが浄化され、開くと、さまざまな能力が開発されるともいう。
1.サハスラーラ・チャクラ
頭頂に位置するチャクラ。色は紫色で解脱の門といわれる。
2.アージュニャー・チャクラ
眉間に位置するチャクラで、色は藍色、脳の下部にある脳下垂体につながっており、脳下垂体は多くの体内ホルモンの活動に指示を与えるとされる。このチャクラを開発するとインスピレーションが働くようになり、現実世界での成功が得られるともされる。なお、チャクラについては、別項を参照のこと。
3.ヴィシュッダ・チャクラ
位置はのど、色は青色。言葉・声・音と関係し、ホルモンでは甲状腺に関係しているとされる。また、権力・地位と関連しているとされ
4.アナハタ・チャクラ
胸の中央に位置するチャクラで、色は緑色で、呼吸と関連し、胸腺とつながっているとされ、胸腺は免疫系の機能に不可欠な細胞を作り出すとされる。名誉、高貴さ、プライドと関連しているとされる。チャクラについては別項を参照。
5.マニプーラ・チャクラ
位置はほぼヘソのあたりで、太陽神経叢に関係し、色は黄色とされる。また、浄化することで、学問などの才能が開花するという。
6.スワディシュターナ・チャクラ
位置は性器の付け根あたり。色はオレンジ。水の元素で体液と関連し、性ホルモンを分泌する卵巣・精巣とつながっており、情緒・詩情と関係しているとされる。また、このチャクラを浄化することによって、禁欲修行をするのに大きな助けとなり、性欲を超えられるともされる。
7.ムーラダーラ・チャクラ
人体の一番下部にあるチャクラで、尾?骨の位置にある。色は赤。地の元素で、筋肉・骨などと関係があり、副腎とつながっていているとされる。このチャクラを強化すれば、疲労回復および健康体を得ることができるともいう。
●中観派(ちゅうがんは)
ナーガールジュナが説いた空の思想を基とする大乗仏教の一学派である。すべてのものは、原因と条件によって生起しており(縁起)、何の因も縁もなくそれ独自で生じることはなく(無自性)、固定した実体はない(空)と説く。
●中道(ちゅうどう)
釈迦牟尼は出家前は、王子として豪奢で安楽な生活をし、出家後は厳しい苦行の生活を送ったが、悟りは得られず、苦と楽の両極端を捨て、心身を整え、禅定によって悟りを開いたとされる。中道とは、このように、両極端に偏らない、中庸を得た道のことを言い、中道の修行の指針として、八正道がある。さらに、これから転じて、修行における中道だけではなく、物事の捉え方、見方を含めて、さまざまな分野において使われるようになった。
【ナ行】
●ナーディ
ヨーガにおいて、体全体に張り巡らされているエネルギー(気)の通り道(管)のことを言う。中国・仙道が説く経絡と同じものと考えてよいと思われる。
さまざまな解釈があるが、ナーディ(管)の中でも代表的なものは、3つあり、具体的には、
①動的で男性的な性質のピンガラー管、②静的で女性的性質のイダー管、③身体の中央を貫いており、調和をもたらすスシュムナー管の三つである。
この三管は、三グナに対応していると思われ、具体的には、ピンガラーがラジャス、イダーがタマス、スシュムナーがサットヴァに対応する。
通常、ナーディは、煩悩的な心の働きによって詰まりが生じており、エネルギーの流れが滞っている。しかし、修行によって、その詰まりを取り除いて、エネルギーの通りをよくすると、心身は軽快になる。そして、最終的には、中央の管をエネルギーが上昇して、頭頂まで抜けることによって、解脱に至るとされる。
●二元論(にげんろん)
世界の諸現象を二つの原理から把握しようとするもの。一方、ただ一つの原理から把握しようというものを一元論と言い、また、二元論を含めて、複数の原理から想定するものを多元論と言う。
二元論にはさまざまな種類があり、存在論的二元論としては、精神と物質を別のものと区別するもの、価値論的な二元論は、善と悪を区別するもの、また、認識論的二元論としては、主観と客観を区別するものなどがある。
現代社会に広がる近代哲学思想・科学思想は、精神と物質、人間と世界を別のものだと区別する傾向が強いが、仏教では、その相互に関連性がある(縁起の法)とする一元論的な立場を取る。
ただし、仏教の中でも、小乗仏教と大乗仏教では、大乗仏教の方が一元論的な傾向が強く、その中では、小乗仏教が区別している、煩悩と菩提心、仏陀と凡夫、輪廻の世界と仏陀の浄土が、本質的には一体である(不二である)という教えまで展開された(煩悩即菩提、凡夫即仏など)。
また、バラモン教、ヒンドゥー教に関連するインド哲学においては、サーンキャ二元論と呼ばれる哲学があり、それは、全ての現象は、精神的原理の真我(プルシャ)と、物質的原理のプラクリティ(自性=三グナの源)の二つから生じていると説く(サーンキャ二元論)。しかし、インドの主流の哲学思想は、ヴェーダーンタの一元論であり、それは、全ては宇宙の根本原理であるブラフマンの展開したものとされる。
ヴェーダーンタの哲学は、この宇宙の全ては大日如来の現れであると説く一部の大乗・密教の思想とよく似ている面がある。
二元論的な世界観において、主要な区別の対象となるものは、自分と他人、精神と物質、人間と世界、主体(観察者)と客体(観察される対象)、善と悪、聖と邪(仏と凡夫、神と悪魔)、楽と苦などである。
●如来(にょらい)
サンスクリット原語はタターガタで、修行を完成した者の名称。仏教だけの用語ではなく、諸宗教で用いられたが、後にもっぱら釈迦牟尼の尊称となり、大乗仏教では諸仏の呼称ともなった。
なお、原語の意味は確定しておらず、おそらく仏教者の作った言葉ではなく、同時期の他宗派(ジャイナ教)の経典にも出てきてqいる。初期の仏典では、その言葉の意味が解説されていないが、タターが「如実に」、アーガタが「来た」という意味なので、如来と漢訳するようになった。
●如来蔵(にょらいぞう)
すべての衆生に具わっているとされる悟りの可能性。仏性に同じ。サンスクリット語は如来(=仏)と胎との複合語で、「一切の衆生は如来を胎に宿している」と経典にある。
●ニルヴァーナ
煩悩の火が吹き消された状態の安らぎ、悟りの境地をいう。三毒を止滅した状態。「すべての束縛から解脱することを涅槃という」と経典にある。涅槃と漢訳される。
六波羅蜜(別項)の第3項目である忍辱波羅蜜のことで、耐え忍ぶこと。菩薩の修行徳目である六波羅蜜の3つ目である。特に、他から誹謗・中傷、あらゆる侮辱や迫害に耐え忍んで怒りの心を起こさないこととされる。また、物質的な不足に耐える、誹謗中傷に耐える、仏教の法が説く驚くべき真実に耐えることとも解釈される
●涅槃(ねはん)→ ニルヴァーナの項参照
【ハ行】
●バクティ・ヨーガ
一般には、神々に対する信愛のヨーガと言われ、熱烈に神を信じることを言い、インドのヒンドゥー教において説かれている。なお、これから転じて、神々に対する供養や奉仕、神々の意思の実現を行なう、ということも意味する場合がある。
●八正道(はっしょうどう)
釈迦が最初の説法(初転法輪)で説いた、仏教の根本教理である四諦の教えの一部である。「四諦」の中には、苦を止滅する道の教え(道諦)が説かれたが、その具体的な実践項目として説かれたのが、八正道である。
①正見(正しい見解)
②正思(正しい思惟)
③正語(正しい言葉)
④正業(正しい行い)
⑤正命(正しい生活)
⑥正精進(正しい努力)
⑦正念(正しい思念)
⑧正定(正しい精神統一)
この八正道は、欲楽(左道)でもなく、苦行(右道)でもなく、この二つの極端を離れた中道の修行の具体的な実践方法としても、説かれる。
●布施(ふせ)
出家修行者、仏教教団、貧窮者などに財物その他を施し与えること。三つの布施(三施)という考え方があり、①金銭や衣食などの物資を与える(財施)、②仏の教えを説き与える(法施)、③他の怖れを取り除く、安心を与える(無畏施〔むいせ〕ないし安心施)である。
なお、大乗仏教では、菩薩が行うべき六つの実践徳目を六波羅蜜と言うが、その一番目のものであり、布施波羅蜜と呼ばれている。また、この財施、法施、無畏施(安心施)の三つは、仏教が説く三つの根本的な煩悩である、貪り(貪欲)、怒り(瞋恚)、無智(愚痴)を取り除くとも考えられる。
●仏陀・ブッダ
「悟りを開いた人」「目覚めた人」のことで、固有の存在をさす言葉ではないが、釈迦牟尼のことをさす場合もある。釈迦と同じ意識のレベルに達した者や存在を仏陀と呼ぶ。如来と同義語。阿弥陀如来、大日如来などはよく知られている。
●仏性(ぶっしょう)
サンスクリット語ではブッダ・ダーツで、衆生が本来有しているところの、仏陀となる可能性。如来蔵と同じ。あるいは、仏陀の種子、仏陀の性質。慈悲そのものの心性。大乗仏教においては、すべての魂には仏性が宿っているという思想がある。
●法界(ほっかい)
サンスクリット語ではダルマ・ダーツ。原意は、意識の対象、考えられるもの、存在するものの意(変化するものも、永久不変のもの双方を含む)だが、さらには、事物の根源、存在の基体という意味を表し、しばしば真理そのものと同じ意味だとされる。
この用語は、宗派によってさまざまな定義があり、日本仏教においては、華厳宗では、真理そのものの現れとして現実の世界を法界といい、真言宗では、全世界・全宇宙のことを法界という。
一方、チベット仏教などでは、法界は、仏陀の三身のうちの法身と結びついて用いられるが、その法身とは、真理そのものとしての仏陀の本体で、色も形もない真実そのものの身体であるとか、一切の思考、一切の現れを越えた、空性の心の状態、平安この上ない状態などと説明される。
●法身(ほっしん)
サンスクリット語ではダルマカーヤ。原語の意味は、真理(法)の身体、真理(法)を身体としているもの。
部派仏教の時代など初期には、仏陀の肉体に対して、仏陀の説いた正法や功徳を法身と呼んだとされるが、大乗仏教では絶対的な真理を法身というようになり、法身、報身、応身という仏陀の三身の一つとされ、真理そのものとしての仏陀の本体、色も形もない真実そのものを示し、それは永遠不滅であり、人格性をもたない。
●ブラフマン
古代インド哲学において、宇宙の究極的原理、根本原理とされるもので、ヴェーダ聖典に説かれている。
そして、インド哲学が説く解脱とは、この宇宙の根本原理のブラフマン(梵)と、個々の生命体の究極的な原理であるアートマン(我)との合一であり、両者が一体であることを悟ることであるとされる(梵我一如)。
このように、本来は人格神の名前ではなく、男性神でも女性神でもなく、中性の哲学的な原理であったが、その後、男性化されてブラフマー(梵天)となることもあったが、宇宙の根本原理のブラフマンと、神の一種としてのブラフマーは区別して考える必要がある。
●プラーナ
生命エネルギー、気。ヨーガ的な人間観では、私たちはこのプラーナによって生きているといわれるが、このプラーナを効率よく体内に取り入れる方法として、プラーナーヤーマ(調気法)という行法がある。
●プラーナーヤーマ
ヨーガ技法のひとつ。調気法と訳される。大気中にあるプラーナと呼ばれる気を効率よく取り入れ、整える技法であり、さまざまな種類の技法があるが、一般には、吸って、止めて、吐くという呼吸を一定の秒数で行うもので、わかりやすく呼吸法と呼ばれることもある。多くの種類があり、効果も少しずつ異なっている。
●法具(ほうぐ)
仏教の伝統的な宗派において、仏陀の象徴物とされ、儀式や瞑想時に伝統的に法具が用いられてきた。さまざまな種類があり、効果もさまざまであるとされる。
●菩薩(ぼさつ)
サンスクリット語でボーディサットヴァ。仏陀・如来には至っていないが、苦しみに迷う生き物すべてを利するために悟りを求め、他を救うことを行いながら如来に至る修行を行っている存在のこと。観音菩薩、弥勒菩薩、地蔵菩薩などがよく知られている。
●発菩提心(ほつぼだいしん)
菩提心(サンスクリット語ではボーディチッタ)は、仏教において、悟りを求める心、悟りを得たいと願う心のことである。特に、一切衆生(すべての生き物)を苦しみから脱却させるために、仏陀の境地(悟り)を得たいと願う心のことである。
菩提心を起こすことを発菩提心(ほつぼだいしん)という。この修行の中においては、覚醒(=仏陀の境地)は、輪廻に迷う生き物すべてを利するために求められる。輪廻に迷うものを救うには、彼らの中で眠っている仏性を目覚めさせる必要があり、このことを知って、自分もすぐれた覚醒を目指そうとするのである。
●梵我一如(ぼんがいちにょ)
インド古代哲学の思想の中で、宇宙の根本原理ブラフマン(梵)と、個人存在の本体のアートマン(我)は同じものであるということ、または、同じものであるという悟りのこと。
ただし、仏教においては、通常、ブラフマンやアートマンという概念は用いないし、特に、個人存在の本体としてのアートマンという概念は否定し、個人存在にはどこまでも本体はなく、実体がない(空である)と説く。
●煩悩(ぼんのう)
身心を乱し悩ませ、正しい判断を妨げる心の働きをいう。仏教においては、三つの根本的な煩悩として、いわゆる三毒が説かれ、それは、貪(貪欲、貪り)、瞋(瞋恚、怒り)、癡(愚痴、無智)である。
その中の特に、癡(無智)、すなわち物事の正しい道理を知らないこと、物事をありのままに見ることができないことが、もっとも根本的な煩悩であるとされ、十二縁起の中では、それを無明と呼んでいる。
煩悩は、自己中心的な考えと、それに基づく事物への執着をともなうもので、この煩悩を滅尽していくことが、仏教の修行ではひとつの目的である。
【マ行】
●曼荼羅・マンダラ
仏教(特に密教)において聖域、仏の悟りの境地、世界観などを仏像、シンボル、文字などを用いて視覚的・象徴的に表わしたもの。古代インドに起源をもち、中央アジア、中国、朝鮮半島、日本へと伝わった。
mandalaの意味については、多くの場合、次のように説明されている。mandaは「本質、真髄、エッセンス」などの意味を表わし、laは「もつ」の意であって、mandalaとは「本質をもつもの」の意だとする
また、mandalaには形容詞で「丸い」という意味があり、円は完全・円満などの意味がある。
「マンダラ」という語は、英語ではヒンドゥー教やその他の宗教のコスモロジー(宇宙観)も含め、かなり広義に解釈されているが、日本語では通常、仏教の世界観を表現した絵画等のことを指す。
●マントラ
日本語では「真言」と訳され、比較的短いフレーズの言葉で仏陀・菩薩・神々などを称える内容などによって成り立っている。なお、よく聞く「南無阿弥陀仏」「南無妙法蓮華経」などもマントラであり、マントラの種類は何種類もある。
●密教(みっきょう)
一般の大乗仏教(顕教)が民衆に向かい広く教義を言葉や文字で説くのに対し、密教は極めて神秘主義的・象徴主義的な教義を師資相承によって伝える点に特徴がある。
初期密教は、呪術的な要素が仏教に取り入れられた段階であり、各仏尊の真言(マントラ)を唱えることで現世利益を心願成就するものであった。やがて、密教が普及してくると仏教としての理論体系化が試みられた。
実在した釈迦牟尼にかわって、新たに密教の教主である大日如来を中心とした五仏を主軸に、曼荼羅に示される多様な仏尊の階層化・体系化が実施された。後期密教では仏性の原理の追求が図られた。法身普賢や金剛薩?といった本初仏が尊崇された。また、ヒンドゥー教やイスラム教の隆盛に対抗するため、憤怒相の護法尊が数多く登場した。
●弥勒菩薩(みろくぼさつ)
弥勒とは、サンスクリット語でマイトレーヤで、慈愛の師という意味である。釈迦牟尼が入滅してから56億7千万年後の未来に姿をあらわすという未来仏の名前であり、現在は、兜率天で修行しているとされる。また、唯識瑜伽行派〔ゆいしきゆがぎょうは〕といわれる唯識の教えをアサンガに降ろしたといわれている。
●貪り(むさぼり)
仏教では「貪り」「怒り」「無智」が私たちの苦しみの元である根本煩悩であり、「三毒」という言い方をする。好ましいと感じる対象に対する強い執着、激しい欲求のこと。
●無色界(むしきかい)
三界(欲界・色界・無色界)の最上層で、欲望も物質的な条件も超越した精神的な条件のみを有する生物の世界。住人は、四無色定という四つの禅定の境地にある。
●無常(むじょう)
すべての物、現象は変化してやまない、一時も留まることなく転変するということ。生じたものは必ず滅するということ。仏教では、諸行無常(全ての現象は無常である)などと説いて、一切のものは変化し移り変わるという事実をその教えの根幹においている。
●無智(むち)
仏教の教え、ものの真実のありよう(縁起、無常、無我)を理解せず、現象は不変で実体があると思い込み、それにとらわれる状態。
【ヤ行】
●唯識瑜伽行派(ゆいしきゆがぎょうは)〔または、瑜伽行唯識派、唯識派、瑜伽行派など〕
唯識とは、あらゆる存在は、ただ識、すなわち心にすぎないとする見解であり、唯識派とは、外界の事物はみな空であり、あらゆる存在は心(識)の現れにすぎないと見る教えを説く学派のことをいう。
般若経の空の思想を受け継ぎながら、しかも少なくともまず識は存在するという立場に立って、自己の心のあり方をヨーガの実践を通して変革することによって悟りに到達しようとする教えである。こうして、ヨーガの実践を通して唯識を観ずるところから、瑜伽行唯識学派〔ゆがぎょうゆいしきがくは〕、あるいは瑜伽行派〔ゆがぎょうは〕(瑜伽とはヨーガのこと)と呼ばれる。
唯識の原語には、知らしめるという意味が含まれているが、これは、唯識が、自己と自己を取り巻く自然界の全存在は、自己の根底の心である阿頼耶識〔あらやしき〕が知らしめたもの、変現したものという意味である。ただし、西洋における唯心論との違いは、心の存在もまた幻の如き存在(空である)として、究極的にはその存在性も否定される。
唯識思想の特徴として、ヨーガの実践に加えて、眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識の六つのほかに、末那識〔まなしき〕、阿頼耶識という2つの意識を合わせて、8種類の意識(八識)を立てたことがある。
この最後の2つは、現代心理学でいう、いわゆる無意識層にあたると思われるが、これは、ヨーガの実践により表層意識を静めた結果、無意識層を体感した結果とも思われる。この阿頼耶識は、よくユング心理学の説く集合的無意識との類似性を指摘される。
唯識に、一水四見という言葉がある。これは同じ水を見ても、人間は水と見、餓鬼は血膿と見、魚は棲み処と見、天の住人は甘露と見るというもの。これは、カルマ(心の働き)に応じてものの見え方(捉え方)が違うということを表していて、唯識思想を端的に表現している。
この唯識派の開祖は、弥勒(マイトレーヤ)とされるが、実際の人物であったかはさだかではない。その後、アサンガ(無着)、ヴァスバンドゥ(世親)の兄弟によって組織体系化された。日本において唯識は、広く仏教の基礎学問として学ばれてきた。
●ヨーガ
ヨーガとは、さまざまな意味において用いられているが、初めてヨーガという言葉を明確に定義したのは、この言葉が自己の名前となったインドの六派哲学の一派であるヨーガ派であり、その開祖パタンジャリによって、紀元5世紀頃までにまとめられたヨーガの最も権威ある経典『ヨーガ・スートラ』においては、「ヨーガとは心の作用を止減することである」と定義されている。
そして、ヨーガ派は、三昧に至るまでの八つの段階の実践法などを体系化し、これは、他学派の実践手段としても採用された。そして、バラモン教・ヒンドゥー教に限らず、仏教にも影響を与え、基本的な修行法として尊重され、仏教では、禅(ディアーナ)、定(サマディ)という言葉で言及されることが多い。
この意味で、ヨーガとは、解脱ないし悟りに向けての正しい見方をえるための瞑想、心のコントロール・統一の実習とみなすことができるが、ヨーガ(yoga)という語の語源は、<つなぐ><結合><結び付ける>という意味を持っていた。
古代インド哲学の文献の中から、ヨーガの定義について見てみると、ヨーガという行法体系が、明確に現れてくるのは、紀元前600年から300年頃で、その頃の文献である『カタ・ウパニシャッド』には、「感覚が浄まり、心が平静で、知性が乱れないとき、ヨーガの最高の状態に達したということができる。このように心を自由自在にコントロールすることができれば、迷いから解放されることができる」とある。
このように、本来、ヨーガ技法の本質は、外界の刺激に反応して一時もとどまることなく散漫に移りかわっていく心の働きを、精神を集中することによってコントロールし、心のより深い本質(アートマン・真我)に到達し、真我と宇宙の根本原理であるブラフマンが同一であることを体験することにある。
●ヨーガの八段階
パタンジャリの著したヨーガの根本経典である『ヨーガスートラ』にある、ヨーガを段階的に進めていくための階梯。
①禁戒(ヤマ)・・・非暴力、正直、不盗、不淫、不貪
②勧戒(ニヤマ)・・・心身の浄化、満足を知る、苦行、自在神を祈念する
③体位法(アーサナ)・・・安定した快適な座位の確保
④調気法(プラーナーヤーマ)・・・呼吸の正しいあり方とそのコントロール。
⑤制感(プラティヤーハラ)・・・感覚の統御された状態
⑥凝念(ダーラナ)・・・一つの対象に心を結びつける、精神集中
⑦静慮(ディアーナ)・・・集中の度合いが高まり、拡がっていく状態
⑧三昧(サマディ)・・・主体と客体の区別の消え失せた意識状態
●欲界(よっかい)
欲望にとらわれた生き物が住む世界。仏教の世界観で、欲界・色界・無色界からなる三界の最下層の領域をさす。私たちが住んでいるこの現象の世界は欲界である。
【ラ行】
●輪廻転生(りんねてんしょう)
インドでは、仏教以前から輪廻思想が広く信じられていた。仏教においても、地獄・動物・餓鬼・人間・阿修羅・天という六つの世界(六道)を、私たちは車輪が廻るようにカルマに応じて繰り返し生まれ変わっているといわれている。そして、この輪廻の世界は苦しみの世界であり、そこから脱却することが幸福への道であると説かれ、そのための方法がさまざまな修行法として確立されている。
●六識
①眼識(視覚)、②耳識(聴覚)、③鼻識(嗅覚)、④舌識(味覚)、⑤身識(触覚)、⑥意識の6つの「識」のこと。
識とは、サンスクリット語でヴィジュニアーナで、(区別して)知るもののことをいい、分別や判断などの認識作用、または、それを行う認識主体としての心をいうが、一般には後者の認識主体の意味で使われることが多い。一部の仏教宗派では、識を、心(チッタ)、意(マナス)と同じ意味であるとした。
そして、上記の6つの識は、六根(五感と意識の6つの感覚器官)と、六境(6つの感覚器官の対象となるもの)の接触によって生じる6つの認識作用のことを意味する。
●六根(ろっこん)
根の原語は、能力を意味し、その能力を有する感官のことをいうが、六根とは、仏教用語で、眼〔げん〕・耳〔に〕・鼻〔び〕・舌〔ぜつ〕・身〔しん〕・意〔い〕といわれる6つの根のことであり、それぞれ、①視覚器官(視覚能力)、②聴覚器官(聴覚能力)、③嗅覚器官(嗅覚能力)、④味覚器官(味覚能力)、⑤触覚器官(触覚能力)、⑥知覚器官(知覚能力)のことである。
●六境(ろっきょう)
境は、認識の対象、対象領域などといった意味で、六境とは、上記の六根(6つの感覚器官)の対象となるもので、仏教用語で、色〔しき〕・声〔しょう〕・香〔こう〕・味〔み〕・触〔そく〕・法〔ほう〕といわれる。なお、ここでの法は、認識の対象、事物のことであり、教え、真理という意味ではない。
●六波羅蜜(ろっぱらみつ)
大乗仏教において、菩薩に課せられた、六種の実践徳目のことで、布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧の六つ。菩薩は、この6つの徳目を得て涅槃の彼岸に到るという。
波羅蜜とは、P?ramit? (パーラミター)の音写で、p?ram (彼岸に)+ita(到った)と分けて、「彼岸(覚り)に到る行」と解する。また、「p?rami」(<parama 最高の)+「t?」(状態)と分解して、「究極最高であること」「完成態」とも解釈する。よって、六波羅蜜とは、六つの悟りに至る行および6つの完成態という意味となる。
なお、布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧のそれぞれについては、各項目を参照のこと。