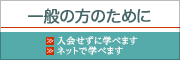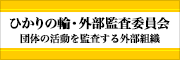『最新心理学が裏付ける仏教の悟りの思想と、始まる悟りの大衆化』(2024年5月1日 東京 前半74min 後半96min)
これは、2024年5月1日のGWセミナーでの上祐の講義の一部です。
この講義では、上祐が、最新心理学が裏付ける仏教の悟りの思想と、始まる悟りの大衆化について語っています。具体的には、「ひかりの輪の2024年GWセミナー特別教本『悟りの心理学:人類の心理的進化の可能性 脳科学が説く新たな幸福の価値観』」の第1章を読み上げながら、その詳しい解説を加える形で行いました。
同教本第1章の全文は、動画の画面の下の箇所をご参照ください。
また、その内容の概要は、以下の同教本第1章の目次をご参照ください。
・第1章の目次
----------------------------------------------------------------------------------
第1章 仏教・ヨーガの悟りの心理学とは?
1.悟りとは何か
2.悟りとは高度な心理学であること
3.人が苦しみを感じる原因の心理的な分析
4.仏教・ヨーガが説く悟りの心理学の根幹:無我
5.心とは一体何か?
6.意識の不思議と根元性
7.仏教・ヨーガの無我・真我の思想
8.心が自分ではないという思想の意味=自他の区別の超越
9.自動思考・自動感情:最新心理学が発見した驚くべき無我の事実
10.仏教ヨーガと最新科学が否定する自と他の区別
11.無我の教えと連動する縁起の教え(万物相互依存)
12.万物が一体=無我の思想が悟りに導く
13.自と他を区別せずに広がった悟りの心理状態とその恩恵
14.怒りを解消する自他の区別を超えた悟り
15.悟りの境地と利他の実践のセット
16.自と他の区別を超えた利他の心を培う瞑想と悟りの道程
17.心の主になるという視点
以下のテキストは、「2024年GWセミナー特別教本『悟りの心理学:人類の心理的進化の可能性 脳科学が説く新たな幸福の価値観』」第1章として収録されているものです。教本全体にご関心のある方はこちらをご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------------------
第1章 仏教・ヨーガの悟りの心理学とは?
1.悟りとは何か
「悟り」とは、抽象的な言葉だが、それは、さまざまな精神的な苦しみ・ストレス・生きづらさ・行き詰まりに悩む現代人にとっても、その根本的な突破口となる究極的な幸福、苦悩からの解放である。
悟りを一言でいえば、それは、意識の自我からの解放である。または、意識の拡大である(究極的に世界・宇宙全体への拡大であるため、宇宙意識ともいわれる)。それは、人の心理が体験しうる、最も安定した、最も豊かな幸福である。それは、究極的には、あらゆる苦しみを根絶するものであり、苦しみの根本的な治療法である。
言い換えると、悟っていない通常の意識は、「自分」という狭い存在の中に閉じ込められている。その中で心は、常に一喜一憂し不安定であり、狭く広がりがない。悟りは、自分という小さな精神的な牢獄から解放された意識の状態であり、それゆえに、それは意識の拡大であり、解放された心の状態である。
悟りの境地は、自と他の区別を超えた意識状態である。通常の意識は、自と他を比較して、他に優っては喜び、劣っては苦しみながら、十分には自分の思い通りにならず、完全な充足は得られず、不満・不安・怒り・抑(よく)うつがあるが、悟りの境地は、こうした一切の苦しみから解放されて、完全な充足をもたらすものであり、それは、「本当の最高の幸福を得た」という実感をもたらす。
なお、悟りの境地は、仏教の専門用語では、「涅槃(ねはん)」と呼ばれることがあり、このサンスクリット原語は、「ニルヴァーナ」である(ニルヴァーナの音訳が涅槃であり、原語が訛った結果である)。このニルヴァーナの原意は、(煩悩の)炎が吹き消された状態といったほどの意味となるが、それは、真に平安な状態であるため、このことを仏教の専門用語では、「涅槃寂静(じゃくじょう)」(悟りの境地は静かで平安である)という教えがある。
2.悟りとは高度な心理学であること
悟りとは、苦しみを乗り越える高度な心理学・実践哲学ともいうべきものであって、特定の何者か、神仏・経典・その他を絶対として崇拝するという意味での宗教とは異なると考える。それは、現代の心理学の裏付けもある合理的なものである。
そもそもが、仏教やヨーガは、東洋の伝統の心理学ともいうべきものであり、東洋における心に関する深い学問・探究は、西洋の心理学よりもはるかに早く始まったと考えられる。例えば、人が、通常は自覚しない深層心理の存在を説き始めたのは、仏教の唯識(ゆいしき)思想が、西洋の心理学よりも一千年以上早いと思われる(唯識思想の経典である解(げ)深(じん)密(みっ)経(きょう)は、遅くとも西暦4世紀頃までには成立していたと推定されている)。
3.人が苦しみを感じる原因の心理的な分析
悟りの思想を学ぶための土台となるのは、「人は、なぜ苦しむのか」という根本的なテーマである。そこで、このテーマに関して、苦しみが生じる原因・構造に関する仏教の伝統的な心理分析を、現代的に表現し直して考えることにする。
人は、「今よりもっと、他人よりもっと」と、財物・名誉・地位・異性・その他を求める心の働きがある。これを仏教では、煩悩、我欲という。ポイントは、この欲求が、自分達の予想と異なって、実際には、結果としてはさまざまな苦しみをもたらし、本当の幸福に至るものではないということだ。すなわち、人の通常の心の働きは、自分を本当の意味で幸福にするものではないということである。
それをなるべくわかりやすくいうならば、そのように求めて、以前より他人より得られた一時は喜びを感じるが、その喜びは長続きせずに、「もっと欲しい」という欲求が生じる。こうして欲求には際限がないため、人は、何かしら求めても得られない欲求不満を抱えながら生き、得られない時の失意の苦しみを経験する。よって、得ても得ても満足できず、本当の充足が得られないために、一般的にいえば、恵まれている人の中にさえ、「本当には幸福になれない」と感じ、虚しさ・空虚感を抱える人も現代には少なくない。
一方、以前より他人より何かを得ると、その喜びは長続きしないのに、いったんそれを得ると、それを失うことには苦しみを感じる。言い換えれば、それなしではいられない状態、とらわれ、一種の依存状態が生じるのである。そのため、得たものを失う不安、奪われる不安、ついには失った時の苦しみを感じる。
そして、この失う苦しみに関していえば、人生において得たものは、老い病み死ぬ中で、自分の財物・地位名誉・人間関係はおろか、自分自身の体・生命さえ、いずれは失うものであり、その意味で、得て失わないものは何一つない。
さらに、皆が「今よりもっと、他人よりもっと」と求める限り、他者は、自分と幸福を奪い合う存在となり、自分の幸福の障害となる面が多くなる。自分より恵まれていると見える他者への妬みや、他者に劣っている自分に関する卑屈・自己嫌悪といった苦しみが生じる。また、不当に自分の幸福を妨げる、または奪うと見える他人に対する怒り・憎しみ・恨みが生じる。
現代の先進国社会では、人間関係が最大の苦しみになっているが、その苦しみの根底には、絶えず自と他を比較するために、自分では気づかないうちに、他者との関係が協調的なものではなく、敵対的なものとなっているということがあると思われる。この自分の内側の要因を見逃して、人間関係の苦しみを、もっぱら他者のせいにしても、苦しみを真に解消・解決することはできない。他人を批判・攻撃して、人間関係が破壊されるか、人間関係を放棄して引きこもることになる。
さらに、「今よりもっと、他人よりもっと」と求めても、加齢とともに、それを得て喜びを感じることは難しくなることが多い。加齢とともに、たいていは、得られるものは、前より少なく、若い他人より少なくなってしまう。そして、老い病み死ぬ中で、一切を失う結果となる。これは、人生の幸福は、尻すぼみ、尻下がりということであり、高齢者が「若い人はいいよね」という背景となる。
さらに、悟りによる苦しみの超越と関連付けるならば、人によるだろうが、人の最大の苦しみとして、老い病み死ぬことが挙げられるかもしれない。自分は自分自身に執着し、それが消滅すると感じられる死を恐れ、また、死後の世界があるならば、それが今より不幸なものとなることを恐れる。しかし、悟りの境地が深まると、こうした老い病み死ぬことに対する不安・恐怖も、ついには薄らいでいく。
こうして、「今よりもっと、他人よりもっと」と、自分(だけ)のために、財物・名誉・地位・異性・人間関係その他を求めると、さまざまな苦しみが生じることがわかる。これを多少簡略化して表現してしまえば、求めて得られぬ「不満足」、老い病み死ぬことを含めて、得てとらわれたものを失う「不安定」、幸福を奪い合う他者との敵対関係の「不調和」などと表現できるかもしれない。こうして、人は絶えず、不満足、不安定、不調和に悩みながら、老い病み死んで全てを失う不幸を経験して人生が終わることになる。
これに対して、悟りとは、真の充足(満足)、真の心の平安、他者との調和を実現し、加齢とともに、ますます幸福になる尻上がりの人生を実現するものである。その典型的な先駆者が、悟りの道を説いた仏教開祖の釈迦牟尼であったと考える。
4.仏教・ヨーガが説く悟りの心理学の根幹:無我
では、早速、仏教・ヨーガが説く悟りの心理学の根幹を解説する。その前提として、その心理学は、現代の最新の心理学とよく合致しているが、しかし、その最新の心理学の思想は未だ十分普及しておらず、現在の一般の常識とは異なる面があることをあらかじめ指摘しておきたい。言い換えるならば、21世紀に住む我々の常識の中には、依然として非科学的な思い込み、認識不足がある。また、これは人類の歴史の常であって、例えば400年前のガリレオの地動説のように、特に、革命的で科学的な発見・理論が一般の常識になるまでには、時間を要するものである。
第一に、仏教の思想には、私・私のもの・私の本質ではない、という意味を持つ無我(ないし非我)という教えがある。そして、諸法無我(一切の物事は私ではない)と説かれるように、心や体を含めた一切の物事を、自分・自分のものと見ないのである。というよりも、自分・自分のものではなく、そう見るべきではないにもかかわらず、誤ってそう見てしまうがために、人は苦しんでいると説いている。
そして、ここで一番重要なことは、悟っていない人全てが「自分である」と思っている(自分の)心さえも、「自分ではない(無我)」としている点である。そして、これを理解するためには、まず、心とは何かについて考えなければならない。そもそも、我々は、心という言葉を頻繁に使っているが、「心とは何か」ということをほとんど考えたことがない。言い換えれば、心とは何かを定義したことがない。
5.心とは一体何か?
ウィキペディアでは、「心(こころ)は、非常に多義的・抽象的な概念であり文脈に応じて多様な意味をもつ言葉であり、人間(や生き物)の精神的な作用や、それのもとになるものなどを指し、感情、意志、知識、思いやり、情などを含みつつ指している。」とし、広辞苑を引用して、以下のようなものを挙げている。「人間の精神作用のもとになるもの。人間の精神の作用。知識・感情・意思の総体。おもわく。気持ち。思いやり、情け。他に 趣き、趣向、意味、物の中心、等。」。デジタル大辞泉では「人間の理性・知識・感情・意志などの働きのもとになるもの。また、働きそのものをひっくるめていう。精神。心情。」などとしている。
いずれも曖昧であるので、科学の専門家の定義を紹介すると、脳科学者の松本元(げん)氏によれば、心は、「感情、知覚、意志、記憶と学習、意識、無意識」の5つから成るとしている(『脳・心・コンピュータ』日本物理学会/松本元、丸善出版)。幸福学の研究で知られる前野隆司慶大教授は、心理学の深層心理(無意識)の理論を取り入れて、「知(知覚)、情(感情)、意(意志)、記憶と学習、意識、無意識」を挙げている(『脳はなぜ「心」を作ったのか』前野隆司、ちくま文庫)。そして、ここで最も重要なものが「意識」である。
6.意識の不思議と根元性
脳科学・心理学が目覚ましく発展する中で、この意識だけは依然として、ほとんど未解明である。第2章に述べるように、例えば感情に関しては、さまざまなホルモンの働きと結びつけて解明されてきている。しかし、意識に関しては、それがいったい何者なのか、何でできているのか、どこにあるのか、仮に脳にあるのであれば、脳の一部に局在するのか、全体に遍在するのか(ヨーガでは必ずしも脳にあるとはしない)、ということが、全く解明されていないのである。
しかし、意識というものがなかったら、我々は他の全ての存在を認識することができない。心や体や他者・外界を含めて、何かが存在するという認識・概念は、意識があってこそ成立するものだ。意識を失うと何も経験しないように、仮に、この宇宙に意識を持つ生命体が存在しなければ、何かが存在するという認識・概念自体も生じないだろう。その意味で、意識は、全ての存在と一体不可分のものだ。
7.仏教・ヨーガの無我・真我の思想
さて、仏教・ヨーガでは、心は無我(私ではない)とするが、それは、思考や感情といった心の働きは私ではないという意味であって、意識を含めて私ではないと説くものではない。特に、ヨーガは、思考や感情が静まった純粋な意識だけの状態を真(しん)我(が)と呼び、それを真実の私・私の本質(アートマン)と定義する。
これを理解するためには、経験する主体と客体という概念が役に立つ。何かを経験する時、経験する側と経験される側がある。例えば、我々が何かを見る時には、見る側の人間の目・視覚機能を含めた脳があって、見られる側の対象物がある。それと同じように、思考や感情などの心の働きに関して、その思考や感情を経験している主体は意識であって、思考や感情は、意識に経験される側=客体であると考えることができる。その意味で、ヨーガの思想では、意識は、主体の中の主体、主観の中の主観である。一切を経験する主体である。
そして、ヨーガでは、思考や感情を静め、真我だけの状態に至ることを解脱とする。よって、解脱は、真我独存位(真我が他と交わらずに独りだけ存在する状態)とも呼ばれる。そして、真我(独存位)とは、永久不変の平安(の意識)であると説く。そして、そもそも、「ヨーガ」という言葉の意味が、心の働きを止滅することという意味である。なぜそうかというと、意識以外の心の働き、思考や感情などを(瞑想によって)止めることによって、普段は思考や感情と一体化している真我が、本来の真我だけの状態に戻る(=解脱する)ことができるからである。
すなわち、ヨーガの思想では、普通は(悟り・解脱していない人の場合は)、意識が、自分(=意識)と(本来は自分ではない)思考や感情を混同し、思考や感情を「自分だ」と錯覚しており、そのために、意識(真我)が、苦しみの思考や感情などと共に(本来は不必要に)苦しんでいるが、意識(真我)が、その混同・錯覚から解放されるならば、苦しみの思考や感情からも解放されて、不変の平安に至ることができるというのである。
なお、仏教には、明確には真我という思想はない。宗教学者によると、開祖の釈迦牟尼は、真我の存在・思想を否定も肯定もしなかったようだが、釈迦以降の仏教徒は、仏教が無我の教えを強調する中で、ヨーガが説く真我を含めて一切は自分ではないと解釈した。ただし、実際に悟り・解脱を目指す上では、この両者の違いは重要ではないと思われる。
重要なことは、思考や感情といった心の働きを、自分ではないと考えて、その働きを静める瞑想(禅定)によって悟り・解脱を目指す点において、両者には違いがないからである。すなわち、悟り・解脱に至るためには、「思考や感情などの心の働きは、自分ではない」と教えれば足りると考える仏教に対して、ヨーガは、「本当の自分は真我であるから、真我ではない思考や感情などの心の働きは、自分ではない」と強調するのがヨーガであり、両者の教えの説き方の違いではないかと思われる。
8.心が自分ではないという思想の意味=自他の区別の超越
思考や感情などの心の働きさえ、自分ではないとする無我の思想は、結果として、さまざまな心の働きを静め、さらには、自己中心的な意識を解消することになる。すなわち、静まって安定した、広がった意識状態を与える。まず、なぜ無我の瞑想が、思考や感情などの心の働きを静めるかというと、それらを客観視するからである。そして、これは鬱病などの治療に用いられているマインドフルネス認知療法の経験で確認されている。マインドフルネスは、今やGAFAなどの大企業でもストレスリダクションや仕事の能率を上げるために採用されているというが、これは禅の瞑想から米国の医師が宗教色を抜いて作った心理療法である。
マインドフルネス瞑想は、自己客観視の瞑想ともいわれ、自分の思考や感情を含めて、ものごとを冷静に客観視するものだ。その訓練を通して、自分の思考や感情を客観的に見ている意識を「メタ認知」「超越的自我」などと呼ぶ。これはヨーガの真我の思想とよく似ている。そして、思考や感情を客観視するということは、自分(=自分の意識=メタ認知・超越的自我)と、自分の思考・感情の間に、一歩距離を置くことであり、マインドフルネス認知療法の見解では、これを「自分と、自分の思考と感情の脱同一化」と呼んでいる。
そして、重要なことは、脱同一化が起こる際に、鬱病などが治癒されていく(苦しみが解消する)ということが報告されている。この点は非常に重要であり、意識が、自分の思考や感情を自分と混同し、苦しみの思考や感情と共に苦しんでいる限りは、苦しみを感じるが、混同をやめて両者の脱同一化をするならば、感じる苦しみが和らぐということである。こうして、マインドフルネス認知療法の臨床研究は、まさに仏教・ヨーガが説く、無我の教えによって、苦しみを解消する悟り・解脱の思想と完全に一致している。
そして、意識が、思考や感情に対して一歩距離を置くと、その感じる苦しみが減るということは、(苦しみの)思考や感情自体も静まっていくことを意味する。これは言わば、意識が、ネガティブな思考や感情に思い入れをして一体化していると、その思考や感情は延々と続くことになるが、距離を置いて関心を薄めると、エネルギーを失ったかのように、思考や感情が静まるかのようである。そして、ヨーガの真我の思想も、これと同様であり、真我が、心などの働きを構成する根本的なエネルギーであるプラクリティと接触すると、接触前までは平衡状態にあって静止していたプラクリティが活動を始めると説く。
9.自動思考・自動感情:最新心理学が発見した驚くべき無我の事実
さらに、マインドフルネス認知療法の見解では、そもそもが、抑うつ感情などのネガティブな思考や感情は、(過去の経験・習慣などから)自動的に生じているという(自動思考・自動感情)。この自動思考・自動感情というものは、非常に重要なポイントである。自動的に生じているというのは、言い換えれば、無意識的・習慣的なものであるということであり、その時の自分の意識が、自分の明瞭な意志によって生じさせたものではなくて、無意識の脳活動が、言わば勝手に(今までの習慣などから)作り出している思考・感情であるということである。だとすれば、それは、自分の(意識の)思考や感情ではない、すなわち、無我であるともいうことができるではないだろうか。
そして、目覚ましく発展している認知心理学の最新の研究結果に基づく主流派の見解は、鬱病の人のネガティブな思考や感情だけではなく、人の思考や感情全般に関して、その全てでなければほとんどは、自分の意志によって生じているのではなく、外界や体の状態などの影響を絶えず受ける無意識の脳活動によって生じており、本人がそれを「自分の思考や感情だ」と錯覚しているという驚くべきものである。これは言い換えれば、人は、実際には、個々人が、他から独立した個人の自由な意志によって行動してはいないということであり、我々の現在の常識とは大きく異なる。しかし、これもまた、最新科学の発見と大衆の常識の食い違いであって、この点については、参考資料で詳しく紹介する。
10.仏教ヨーガと最新科学が否定する自と他の区別
さて、先ほど、思考や感情といった心の働きを、「自分ではない」と見る瞑想訓練などによって、①心が静まるとともに、②自己中心的な意識が解消すると述べたが、この②の自己中心的な意識の解消に関して、次に述べることにする。
これはある意味では当然のことである。というのは、心や体を含めた一切は、自分ではなく、自分(意識)が見ている対象である、という認識が深まるならば、自分の心身も、他人や外界の環境も、全ては自分ではないものとして同列となっていく。つまり、自分の心や体を「自分だ」と認識してこそ、それ以外の存在(他人や外界の環境)を「自分ではない」と認識するのであって、心や体を「自分だ」と認識しないならば、その延長上として、自分や他人や外界の環境の一切を、客観的な視点から見ている意識が生じるのである。多少誤解を招く面もあるが、あえて例えていうならば、自分の少し外から、自分や他人や環境を見ているような意識と表現できるかもしれない。というのは、こうした感覚が、ヨーガでは、悟り・解脱の意識状態(に近いもの)であると説かれることがある。
しかし、普通に考えれば、私たちの意識は、私たちの体の外からではなく、私たちの体の中から、全てを経験している。よって、別のたとえをするならば、人々は、実際には自分ではない何者かが作った三次元立体映画の中にいて、その三次元立体映画の多数の登場人物のそれぞれの脳の中に、それぞれの意識が、その映画を見る観客席があって、そこから映画を見ている単なる観客なのだが、自分の観客席がある登場人物に感情移入して一体化してしまい、自分の観客席がある登場人物と、映画のほかの登場人物をひどく区別する錯覚を起こしているということになる。
仮に、その錯覚がなくなれば、人は、自分の観客席がある登場人物のことばかりを愛するのではなく、全ての登場人物・映画全体を楽しむ(愛する)映画の観客の心理状態に至る(戻る)ことができる可能性が出てくる。これが、仏陀(悟った者)が持つ万人・万物への平等な愛(大慈悲・平等心)であり、神の万物への愛=博愛に通じる。
また、もう少し例えを変えるならば、自分は単なるその映画の観客ではなくて、観客兼俳優のようなものである。そして、その映画の中のある登場人物の役割を演じる上で、その役割・シナリオは、自分ではない何者かが作ったものであるにもかかわらず、「自分が作って自分で演じている」と錯覚している。そして、他の登場人物のところに観客席がある他者の意識も、自分と同じ錯覚をしている。そのため、特定の他者に過剰に執着したり、過剰に憎んだりしながら、ほとんどの登場人物には、自分は無関係であり、無関心(冷淡)である。
そして、その映画を作っている自分ではない何者かとは、心理学的に言えば、おそらくは世界全体である。それぞれの人間の思考・感情・行動は、自分の意識・意志によらず、その無意識の脳活動によって生じていると述べたが、その無意識の脳活動は、それがおさまる体の状態と影響を与え合い、さらに、その脳と体の状態は、それを取り巻く外界の環境や他者と影響を与え合う。その結果、人々(生き物)は、皆で皆の思考・感情・行動を作り合っており、その意味で、実際には、一体不可分、連動する中で、行動している。なお、ここで「皆で皆を作り合っている」と言っても、作り合っているのは、皆の意識ではなくて、皆の思考・感情・行動であって、皆のそれぞれの意識は、自分の観客席がある登場人物の思考・感情・行動を、誤って自分が作った自分のものと錯覚している。
そして、この一体的な世界に関して、深層心理学の巨匠であるカール・ユングは、人の持つ無意識の中には、個々人の無意識もあるが、全ての人々が共有する無意識があるとして、それを集合無意識と呼んだ。さらに、その集合無意識の中心として「セルフ(自己)」なる概念があると提唱した。このセルフの概念は、宗教が説く神の概念に近い。また、米国に定住してヨーガを広めた先駆者であるインド人のヨーギーであるパラマハンサ・ヨーガナンダも、この世界は、映画監督である神のシナリオによる三次元立体映画であって、人々(の意識=真我)は、その映画の中の観客兼俳優(に過ぎないもの)であると述べている。そして、要点は、観客兼俳優という本来の自分の立場を見失って、その登場人物の役柄に感情移入し同化してしまっているから、その本来の立場を改めて自覚することが、解脱であるということになる。
11.無我の教えと連動する縁起の教え(万物相互依存)
さて、無我という思想は、私・私のもの・私のものではない、という意味であると述べたが、他には、永久不変の本質がない、といった意味がある。それは、仏教の中核の思想である「縁起」や「空」の教えと本質的には同じ意味を持つ。
「縁起」とは、縁で起こると書くが、縁とは条件という意味であり、縁起とは、物事が条件によって生起するという意味である。言い換えれば、無条件に生じるものではなく、条件によって生じ、条件が変わって滅することを意味する。この条件によって生じるということは、言い換えれば、自分の力だけで生じるのではなく、他者に依存して生じるという意味を持つ。
そして、仏教には、「空」という教えがあるが、この空という概念も、物事に(他から独立した)固定した実体がないという意味であり、そのため、永久不変の本質がないという意味を持つ無我や、他に依存して生じるという縁起と本質的に同じ意味を持つ。また、物事が生じては滅して移り変わることを説く仏教の「無常」の教えにも通じることがわかるだろう。
そして、釈迦以降の仏教の教学の中で、縁起の法は、万物が縁起である、すなわち、万物が相互に依存しあって存在していると解釈されるようになった(仏教専門用語では相依(そうえ)性(しょう)縁起(えんぎ)という)。同じように、諸行無常(万物は移り変わり無常である)、一切皆空(一切は他から独立した固定した実体がない)、諸法無我(万物は無我である)と説かれる。こうして、仏教の基本的な世界観は、万物は相互に依存しあって存在しており(すなわち、一体として存在し)、何かが変われば他者も変わるから万物は無常・空である、同じ真理を異なる表現で説いたものということもできる。
12.万物が一体=無我の思想が悟りに導く
そして、この点が重要なのであるが、この世界の万物が、相互に依存しあって一体として存在しているのであれば、他から独立した存在としての私・我、他とは別の存在としての私・我は、存在しないことになる。ところが、人が、「私」と「他者」という言葉を使って思考すると、その脳裏には、あたかも他とは全く別の私、他から独立した私、他から独立した完全な自由意志を持って行動する私が存在するように感じられてしまう。
なお、これは、言葉による思考の一種の欠点である、「私」と「他者」などのように、二つの異なる言葉を使うと、その両者に違いがあるというだけではなく、両者が全く別のもの、完全に独立したもの、その間には何のつながりがないものという錯覚を起こしてしまう。例えば、「山」と「平地」という言葉があるが、山と平地の明解な境界線がないことは、よく考えればわかる。全てでなければほとんどの言葉に関して、物事の差異を教えてくれる利点と、全く別のものという錯覚を生じさせる欠点の双方があることに注意するならば、悟り・解脱が近づくことになる。
こうして、思考や感情といった心の働きは、私(意識)ではないという認識(無我)とともに、(意識以外の)万物は一体である、という認識が、悟りを深めることになる。すなわち、我々の常識では、自分の思考や感情・行動と、他人の思考や感情・行動は、別物であるが、最新の科学・心理学と、仏教・ヨーガの東洋の伝統の心理学を見るならば、それらは実は密接不可分に関係し、別物として区別することはできず一体であり、むしろそれらと区別できるのは、それらを体験しているそれぞれの人の意識なのである。
ところが、それぞれの意識が錯覚を起こして、自分の思考や感情・行動を、「自分(の意志)によるものだ」と錯覚して、他の思考や感情・行動と区別するために、それによって例えば、過剰な怒り・憎しみ・敵対感情が生じることになる。それに気づいて、皆が皆を作り合っている一体の世界を体験していることに気づくならば(悟るならば)、万物を一体として愛する静まった意識(すなわち、ブッダの大慈悲に相当する意識)を得るステップとなる。
さて、本稿では、具体的な悟りの思想・哲学・心理学の根幹について述べたが、実際にそれを体得する方法に関しては、詳しくは述べなかった。その方法は、仏教開祖釈迦牟尼が説いた直説の教え(四諦(したい)八正道、戒(かい)・定(じょう)・慧(え)の三学(さんがく)など)から大乗仏教・密教の教え、またヨーガでいえば、古典ヨーガの八階梯の教えなどさまざまなものがあり、とても一冊の本で書ききれるものではないので、関連するひかりの輪の他の特別教本を参照していただいたり、このGWセミナーの中の実習を参考にしていただきたい。
13.自と他を区別せずに広がった悟りの心理状態とその恩恵
さて、ひかりの輪で実習する仏教・ヨーガの身体行法を行うと、思考や感情が静まってくる。具体的には、ヨーガの伝統に基づく体操法・姿勢法・呼吸法やシンボル瞑想(マントラ瞑想)である。これらは、正しく実践すれば、徐々に思考や感情を静める効果がある。
これに成功するならば、意識は鮮明なままに、思考や感情が静まった状態を経験することができる。その時の意識は、思考や感情が静まっているため、自と他を強くは区別していない状態である。ただ、鮮明な意識があり、静かな平安な意識である。これは無我の境地ということもできる。
この意識状態は、自分と他人を区別していないから、普段と比較すれば、意識が広がったように感じられるものとなる。静まった広がった鮮明な意識である。これが、仏教が説く瞑想状態(禅定)の本質の一つだと思う。
この意識状態は、まず、安定しており、苦しみがなく、平安である。日常の心は、さまざまな欲求や興奮とともに、不安・恐怖・怒り・いらだち・嫌悪などの苦しみがあり、絶えず動いており、不安定であるが、それらが静まって、苦しみがなく、平安である。また、大きく広がった解放感や温かさ、場合によっては、至福感などが体験される。
この心身の状態は、健康にも良く、体は安定し、無駄なエネルギーの消費はない(その意味で休息している)。日常のさまざまなネガティブな思考・感情・ストレスが、いろいろな意味で心身の健康を害することはよく知られているが、その意味で、禅定の状態は、健康長寿をもたらすと思われる。それを示唆するさまざまな医学的調査研究の結果もある。
また、この意識状態は、雑念がなく、意識は鮮明であるから、何かの物事に取り組もうとするならば、それに深く集中することができ、そのため、知能などの心身のパフォーマンスの向上をもたらす。そのため、禅定・瞑想状態は、「心の安定と集中」と表現されることもある。パソコンに例えれば、雑多なタスクから解放され、重要なタスクに全能力を集中できる状態と表現できるかもしれない。なお、近年、ストレス解消や仕事の能率を上げるものとされて普及しているマインドフルネスは、禅の瞑想から宗教色を抜いてできた心理療法である。
こうして、禅定の状態は、集中力・知能などを高めるが、それにとどまらず、その本質的な恩恵は、物事をありのままに見る力、仏教で「智慧」と呼ばれる高度な認識力の土台となることである。ここでいう物事をありのままに見る力・智慧とは、一般的な意味での観察眼とか、知能という意味ではない。前に述べたように、悟り=真の幸福に導く世界の道理を理解する力であり、常識的な世界観の中にあるさまざまな錯覚を乗り越えるものである。
14.怒りを解消する自他の区別を超えた悟り
ここでは、自他の区別を超えた心理状態が、他者に対する怒りの感情を取り除くことについて述べたい。まず、怒りの感情による苦しみは、それを相手にぶつけて相手を破壊するならば晴れるように思われるが、相手に報復を受ける恐れがあってできない場合もあるし、自分の怒りが自分勝手なものであって、客観的には相手には非がない場合は大きな問題となるし、相手に非があっても、自分の報復が行き過ぎれば、自分の方が悪者になってしまうこともある。
そもそも、怒りの感情にとらわれている時は、客観的で合理的な判断ができないため、非が自分にあるのか相手にあるのかという判断を含めて、正しくできない場合が少なくなく、感情にまかせて行動するうちに、後で後悔するような衝動的な言動に陥ってしまう場合もある。よって、相手に非がある場合であっても、自分の中の怒りの感情を制御した上で、落ち着いて相手に対応することが望まれる。
そして、この怒りの状態を取り除く根本的な法則が、本章で述べた、自と他の区別を超える智慧である。まず、怒りの感情の背景には、自分に不快な他者の存在・行動が、理不尽に見えることがある。すなわち、例えば、「なぜあいつは、こんなことをするのか」という感情である。
そして、重要なことは、この言葉の通りに、自分は、相手がなぜそうなのか、そういうことをするのかという理由・原因がわかっていないのである。よって、「あんな奴はあり得ない」などと感じ、その存在が許容できない(許せない)心理状態に陥っているのである。
一方、ここで、仮にその理由・原因が、本質的な点までわかったとすれば、怒りの感情はだいぶ落ち着くことになる。というのは、その場合は、「仮に自分に相手と同じ理由・原因があったならば、自分も同じことをするだろう」という理解が働くからである。すなわち、これは、相手と自分を区別する意識が和らいでいることを示す。言い換えれば、「ありえない」という感情は、「自分の場合にはありえない」という感情なのである。
さて、これらの事実を踏まえた上で、仏教の自と他の区別を超えた智慧・世界観を説明するならば、それは、自分の存在や思考・感情・行動も、他人の存在や思考・感情・行動も、独立しておらず、相互に依存しあって存在しており、つながっているということである。これは、「縁起の法」として説かれる仏教の思想であり、万物は相互に依存してあって存在し、独立していないというものだ。
そして、前に述べたように、最近のさまざまな科学的研究においても、我々の常識的な世界観と矛盾して、個々人の思考・感情・言動は、他者・環境から独立しておらず、個人には、他から完全に独立した自分だけで形成した思考・感情・言動はない、という見解が強まっている。
自分の思考や感情は、そのすべてか、そのほとんどが、自分の意志によって生じるのではなく、自分の中のもう一人の他人ともいうべき無意識の脳活動によって生じており、自分の意識はそれを後から体験しながら、それを自分の思考・感情・言動であると思い込んでいる関係にあることが、さまざまな心理学的・脳科学的な実験から確認されている。
そして、その無意識の脳活動は、脳が体の一部である以上、体の状態の変化、さらには体を取り巻く環境の変化によって、その状態が左右され、その結果生じる思考・感情・言動も変化する。もちろん、自分が見聞きして学ぶ、他人の言動や発言を含めた他人からの情報の影響を受ける。そもそもが、思考の土台である言語・言葉自体、自分で作ったものではなく、親や他人から学んだものであり、同じ言語でもその使い方は人によってさまざまであり、それにも自分の感情・言動は影響を受ける。
また、心理学や脳科学に限らず、遺伝学の視点からいっても、人の心理的・性格的な傾向は、肉体的な傾向と同様に、遺伝の影響がある。遺伝が5割で後天的なものが5割だといわれるが、後天的なものである親を含めた生い立ちの環境についても、本人の自由にはならず、本人が作ったものでもなく、本人に責任はない。そして、そのような人格形成の結果として、自分の怒りの対象となる相手の今日の言動がある。
こうして見ると、人は、皆で皆を作り合っているのであって、万物は万物を作り合っているのであり、皆が皆のあり方に大なり小なり関係があるということが、科学的な視点から見た、自分と他人の関係であり、仏教的な法則に基づいた、自分と他人というものの一体的な関係性である。
そして、怒りとは、相手の問題が相手にこそあるという場合には強まるが、その原因が相手に限らず、その他の存在、そして全体にあると認識される場合には弱まる。わかりやすくいえば、自分も相手のように生まれ、相手のような生い立ちを経て、相手のような環境にいるならば、同じようなことになったであろうという認識である。
そして、こうした世界観・人間観を体得した心理状態は、自分と相手の区別が和らいだ状態であり、自分と他人を区別する意識が根底にある怒りの感情は弱まることになる。
15.悟りの境地と利他の実践のセット
自他の区別を超え、静まって広がった意識状態と連動して、仏教が説くのが、利他による幸福、共栄型の幸福である。これは、他を利することによる幸福である。
一方、「今よりもっと、他人よりもっと」と、財物・地位・名誉他を求める現代主流の幸福観を競合型の幸福と呼ぶならば、それは、他に勝って、他に優って得る幸福であり、他と自分のいずれかのみが幸福になるものである。しかし、このような生き方が強いと、自と他の区別を超えた悟りの心理状態に至ることは難しい。日常で自他の激しい区別の習慣を形成しながら、瞑想の時だけいきなり自他の区別を超えようとしても、果たせないことは自明であろうが、体験してみればさらによくわかる。
これに対して、この共栄型の幸福は、他を幸福にして自分が幸福になる、他と共に幸福になる、他と苦楽を分かち合うことで幸福になるものである。そして、これは、自と他の区別を超えて広がった悟りの意識状態を得ることを妨げずに助け、その逆に、瞑想を通じて、自他の区別を超えて広がった意識状態を体験すれば、それが日常生活での利他の実践の助けになる。
仏教では、この利他の幸福こそが、自分のためにも真の幸福の道であり、利他の心と行為こそが、賢明な利己の行為であると説く。すなわち、自分の幸福と他者の幸福は、本当は一体のものであり、両者が別物だというのは、錯覚・無智であるということである。
競合型の幸福の際限なき追求は、その錯覚・無智があるがためになされるが、そのためにさまざまな苦しみを招く。よって、人生の幸福の指針としては、際限なく求めがちとなる競合型の幸福の追求は、健やかに生きることができる程度までに留めて(足るを知り)、共栄型の幸福、利他・慈悲を心がけながら生きることである。
16.自と他の区別を超えた利他の心を培う瞑想と悟りの道程
さて、最後に、こうして自と他の幸福を区別する無智を理解し、自と他の幸福を一体と見て利他に励む智慧を身につけるためには、どのような実践をするべきであるのかについて述べる。
第一に、前にも述べたが、自と他の区別・自我執着を弱める瞑想は、有効である。それは、意識が、自分の心を「自分だ」と錯覚・混同して一体化した状態ではなく、自分の心や体に対して一歩距離をとって、心や体を客観視する状態である。
そして、意識が自分の心や体を客観視するということは、他者・万物に対するのと同じ視点から、自分の心や体を見る状態になり、自分と他者・万物が、実際には別物ではなく、つながった一体のものである真実を認識し、意識が拡大することを助ける。最終的には、一体である自分と他者を含めた万物を俯(ふ)瞰(かん)する視点を持った、大きな意識状態に至ることを目指す。それは、安定して広がった意識である。
具体的な瞑想としては、冒頭に紹介した①「四(し)法(ほう)印(いん)」に加えて、②心を含めた万物が、実際には自分ではないことなどを悟る「四(し)念(ねん)処(じょ)」の瞑想や、③自分と他者万物を区別せずに平等に愛する「四(し)無(む)量(りょう)心(しん)」の瞑想などを行うといいだろう。これについては機会を改めて詳述したい。
第二に、これらの瞑想に加えて、仏教の思想・哲学・世界観をよく学び、検討して、納得する必要がある。すなわち、私たちの常識の中の錯覚・思い込みとは異なり、いかに実際には、自分と他者・万物が相互に依存しあってつながり、一体として存在しているかや、前に述べたように、いかに自分の幸福と他人の幸福が一体であるか(利他が利己となるか)などについて、思い込むのではなく、経典・教本を学んだ上で、自分でもよく検討・吟味して、深く納得しておくことが重要である。
第三に、意識状態とそれと連動する脳神経の状態は、体の状態と深く関係しているため、自他の区別を超えた意識・認識に至りやすい身体の状態を作る。そのために、仏教やヨーガでは、姿勢法・体操法・呼吸法といった身体行法や、真言を唱える瞑想、読経という形の瞑想、歩行の形をとる瞑想(歩行禅)などがある。これを日常の習慣にすることは大きな助けになる。
そして、呼吸法の形の瞑想、真言瞑想、読経瞑想、歩行瞑想のいずれもが、繰り返し述べているように、思考や感情が静まって安定し、自他の区別を超えて広がった鮮明な意識の状態を最終的には目指している。よって、瞑想の形態は異なるが、目的とするところに違いはなく、同じ目的のための異なる手段であって、例えるならば、同じ一つの山の山頂に至るための複数の道のようなものである。
第四に、日常の利他行である。日常の行動において、自と他の(幸福の)区別が強くならず、逆に、自と他の幸福を一体と見る心の働きが強まるように、なるべく他を害さず、他を利する利他の実践を行う。その際に、なるべく感謝をもって行う。なぜならば、利他の行為は、本質的に利己の行為だからである。いわゆる「情けは人のためならず」ということである。
自分が他人に「何かをしてやっている」という偉そうな意識、上から目線の意識、慢心、支配欲などが強まると、自と他の区別を逆に強めてしまい、結果として、他のためにならないことがあるので、これには十分に気を付ける必要がある。日常の行為も、瞑想の行為と本質的に異なることはなく、繰り返し行われる中で、自分の意識のあり方、心の働きの習慣を形成する。よって、日常において、他を害する言行などがあれば、それは、瞑想の効果を相殺してしまうことになる。日常の言動も瞑想も、自と他を一体と見る視点をもって、行うべきである。
17.心の主(あるじ)になるという視点
こうして、仏教やヨーガの訓練は、心(と体)の制御の道の側面がある。そもそも、仏教の禅定(ぜんじょう)とは、「心の安定と集中」という意味である。そして、心の制御を説き、心を私ではない(無我)とした仏陀は、「心を制御する『心の主』となること」を弟子に説いたという説がある。
逆にいえば、悟っていない普通の人は、真の幸福には至らない愚かさを含んだ心の働きに翻弄されており、その「心の奴隷」になっている状態であるというニュアンスを含んでいると思われる。
しかし、この心の働きであるさまざまな煩悩的な欲求は、さまざまな苦しみをもたらし、真我を苦しめるものであり、真の幸福に導くものではないから、心を、我ではないと気づいて(無我)、心を制御し(ヨーガ・禅定)、心の主となることを説くのである。
------------------------------------------------------------------------------
《参考資料》
仏教・ヨーガの思想を裏付ける最新の認知心理学の詳細
(2019年~2020年 年末年始セミナー特別教本『最新科学が裏付ける仏教・ヨーガの悟りの思想 2』第2章より)
1.はじめに
本章では、あらためて仏教・ヨーガの思想を裏付ける最新の認知心理学の詳細についてご紹介したいと思う。まず、認知心理学と、それが連動する脳科学の最近数十年間の発展は、非常に目覚ましいものであるばかりではなく、その結果は、研究当事者にとってさえ驚くべきものだったようだ。
下條信輔氏(カリフォルニア工科大学教授)によれば、その結果として、認知心理学が発見した人間の意識・心の働き・脳などの実際の在り方は、我々の常識と大きく乖離したものになっている。それは、認知心理学者をあたかも現代のガリレオのような立場に置きかねないほどのもので、今後は最新の科学的な知見と常識の矛盾の対立をどのように乗り越えていくかの智恵が必要だと考えているほどなのである。
2.心を自分とみなさない仏教・ヨーガ・心理学の一致点
認知心理学は、「行動主義心理学」と呼ばれる心理学の流れの中にある。行動主義心理学とは、他の心理学に比較して実験を重視する心理学で、その意味では、心理現象という目に見えないものを扱うがために一般的な科学的な普遍性を保ちにくい一面もある、心理学の世界の中では最も科学的な心理学の分野ということができるだろう。
この行動主義心理学の中で、「認知行動療法」というものが生まれた。認知行動療法とは、人の精神的な苦悩は、その人の認知=物の見方・考え方によるものであるという視点に基づいている。すなわち、うつ病やストレスの多い人は、その人の考え方・ものの見方に極端に否定的な傾向があって、それに自ら気づいて、自分の認知と、認知に基づく行動を変えていくことによって苦悩を和らげることができるというものである。
そして、この認知行動療法の流れの中で、「マインドフルネス認知療法」というものが現れた。マインドフルネスとは、仏教の「念」(サティ)の英訳であり、仏教の禅の瞑想を学んだ医学者が、その中から作り出した体や心の痛みを和らげる心の持ち方・瞑想の仕方のことをいう。本来の念とは、「記憶して忘れないこと」などが原意であり、それから転じて仏陀の教えを絶えず思うことなどと解釈される。
しかし、心理療法としてのマインドフルネスは、「今ここ」の自分の心身などに関して、是非の判断を入れずに、すなわち冷静に客観的な視点から注意を向けることである。そして、心の中の思考や感情に対しても、このマインドフルネスの瞑想を行うと、結果として、「自分と(自分の)思考や感情が別のものだ」という感覚に至り、そうなると苦しみが和らぐということが臨床的に確認されている。これを「思考と感情の脱同一化」という。そして、自分の思考や感情を見ている自分の意識を、「超越的自我」ないしは「メタ認知」などと呼んでいる。自分を見ている自分という意味である。
ここまで書けば、すでに理解いただける方も多いと思うが、これは、仏教やヨーガが説く「心の働きは真実の私ではない」という思想とよく通じている。仏教では、心は無我であるとされている。この無我とは、私ではない、私のものではない、私の本質ではない、といったほどの意味である。この場合の無我は、「私がない」という意味ではなく、「私ではない(私に非ず)」という意味であり、非我ともいわれることがある。この瞑想によって、心に起因する苦しみが解消するとされる。
3.ヨーガの真我の思想と心理学の深い一致点
また、ヨーガは、「真我」というものを説くが、この真我の思想が、上記の心理学の見解とさらによく一致しているのである。
まず、真我とは何かを説明しよう。真我は、ヨーガにおいて、真の自己・真の自我などとされている。別に、「純粋観照者」とも呼ばれる。そして、真我は、単にただ対象を見るものであり、いかなる作業もせず、永久不変である。それは「見る」という能力からなる純粋精神である。ここで見るといっても、真我が、自分の意思で見るという働きをなすというのではなく、それはただ真我の本来の在り方にすぎないとされる。よって、見るというよりも「照らす」といった方がよい面があり、光が無心にものを照らすように、真我は意思しないで自然に対象を照らすものであるとされる。
そして、ヨーガにおいては、真の自己である真我が、心を自分自身と錯覚・混同することが、苦悩の原因だとしている。すなわち、真の自己である真我は、本来は心ではないのであるが、心を自分と錯覚することで、(心と共に)苦しんでいるというのである。この苦しみを解消するためには、真我が、心を自分とは別のものであることを認識する必要がある(弁別智を得ること)。
そして、その方法が「ヨーガ」なのである。というのは、本来ヨーガとは、「心の働きを止滅すること」と定義されたものであり、心の働きを止滅することで、通常は、心と結合・一体化し、心と共に様々な苦しみを感じていた真我が、心から離れて自己本来の姿・あり方に戻ることができ、それにともない苦しみが消滅するのである。
なお、これを真我の独存の状態といい、さらには解脱ともいう。そして、本来の真我の姿は、自立独存の絶対者であって、時間と空間の制約を受けず、永久不変であり、絶えず平安と光明に満ちた存在であるとされる。
こうして、真我が(思考や感情といった)心の働きと自分を、別のものと認識することで苦悩が消滅するというヨーガの思想は、自分と思考や感情の脱同一化をはかり、自分を見ている自分=超越的自我・メタ認知を得ることで、苦しみが和らぐとするマインドフルネス認知療法の見解と、非常によく似ていることに気づくだろう。そもそもマインドフルネス認知療法自体が、仏教の念・禅・瞑想に由来するものであるから、仏教と深い共通性を持つヨーガの思想とよく合致することは、必然的であるかもしれない。
4.仏教の「無我の思想」とヨーガの「真我の思想」は本質的に矛盾しない
なお、仏教では真我の概念は説かない。それは例えば、仏教には「一切は無常」という思想があるから、永久不変なものとされる真我という概念になじまない。しかし、これは、解脱に至る上で何に力点を置くかの違いであって、両者に本質的な矛盾があるわけではないと考えることができる。ヨーガも仏教も、私たちが「心」と呼んでいる思考や感情などは真実の私ではないと悟って、それに執着しないことで苦しみが解消されると説く点において、全く一致している。
そして、そのために、単に「心は私ではない」と説いて、心に対する執着を脱し、真実の私に関してはあえて論じないのが、仏教(少なくとも開祖のゴータマ・シッダッタ)の姿勢である。一方、真我の存在を強調し、心が真我とは全く別のものであるとして、心に対する執着を脱しようとするのが、ヨーガの姿勢である。その意味で初期仏教は、努めて心理学的であり、それに対してヨーガも同様に、極めて心理学的な思想ではあるが、科学的に検証不能な真我という概念を立てるところにおいて、仏教と比較するとわずかに、より哲学的・形而上学的・宗教的な色彩があるということができる。
5.最新の認知心理学は様々な意味で心の働きは自分ではないことを明らかにしつつある
最新の認知心理学は、様々な意味で、心の働きは自分ではないことを明らかにしつつある。デイヴィッド・イーグルマン准教授(スタンフォード大学精神医学科)は、「意識は傍観者である」とし、様々な心の働きは、無意識的な脳活動が司っており、「意識は遠いはずれから脳の活動を傍観しているにすぎず」「私たちの行動をコントロールしているのは私たちの意識ではない」とし、さらに、にもかかわらず意識は、無意識の脳活動が形成する心の働きを、自分がしたことのように錯覚を起こすと述べている。
前野隆司教授(慶応大学システムデザイン・マネジメント研究科)も同じように、知覚・感情・意志といった心の働きは、無意識の脳活動が形成しており、意識は、その結果を単に受動的に経験しているだけであるが、意識は、それを「自分のものである」と錯覚しているという。
しかし、意識が心の働きを制御していないとすれば、その心の働きと連動してなされる行為が、(私たちの意識の)自由意志によってなされたかどうかに疑問が生じる。この点に関しても、下條信輔教授(カリフォルニア工科大学)などは、「人は自分でわかり言葉にできる心の働きよりもむしろ、自分で気づかない無意識的な心の働きに強く依存している」とし、「人は自分の自由意志によって行為し、当然その責任も全て当人にある」というのが近代民主主義社会の根底にある考え方に近いだろうが、「最前線の人間科学は、人間の自由意志の尊厳とそれにのっとった社会の諸々の約束事を根底から覆しかねない」とまで述べている。
こうして、私達の自覚する「意識」と、その意識が経験している五感・心の中のイメージ・思考・感情・意志・欲求といった様々な「心の働き」と、「脳」の活動の実際の関係は、私たちの日常の感覚・常識がとらえている在り方と大きく異なり、それはむしろ、仏教やヨーガの心理学が2500年頃前から説いてきた在り方に非常に近いことがわかってきたのである。
6.思考は物理的な要素に支えられている
デイヴィッド・イーグルマン准教授が言う通り、私たちが「自分の思考」と呼んでいるものも、純粋に自分の意識が作ったものではなく、自分の脳や体や自分の体以外の様々な物理的な要素に支えられている。その意味で、客観的・合理的な視点から言えば、それが本当に「自分」の思考であるとは言い難い。単に浮かび上がってくる思考を「自分の思考だと考える習慣」があるだけである。
実際に脳が変化すれば、人が考えることの種類が変わる。深い眠りでは思考は生じず、脳が夢を見る睡眠の状態に移ると、思いがけない突飛な思考が生じる。日中でも、アルコールや麻薬、たばこ、コーヒー、または運動を加えることで、脳と思考は変化する。脳という物質の状態が、思考の状態を左右する。脳に打撃を受ければ、様々な精神活動ができなくなる(最悪は植物人間の状態)。
こうして、私たちは、思考は物理的な土台をもたない風に乗る羽毛のようなものだと直感的には思いがちであるが、実は、脳の状態に直接左右されているものだ。
7.私たちの思考・感じることは、意識の支配下にはない
そして、同教授によれば、最新の科学的な研究の結果としてわかることは、「私たちの行動・思考・感じることの大半は、私たちの意識の支配下にはない」ということである。脳のニューロンの広大なジャングルは、私たちの意識が知らないところで、独自のプログラムを実行しており、脳は独自に事を仕切っており、その営みの大部分に「意識」はアクセス権を持っていないのである。言い換えれば、無意識的な脳活動が、私たちの様々な心理作用を形成しているのである。
しかし、私たちの意識は、その脳の膨大な働きを認めずに、それを全て自分の力でやっていると思い込んでいる。実際には、脳はたいてい自動操縦で動いていて、意識はその脳の膨大な活動にほとんど近づけない。この事実の証明として、例えば、衝突の危険をはっきりと意識が認識する前に、足は車のブレーキを踏むという事実がある。また、パーティなどで聞いているつもりもなかった隣のグループの会話に自分の名前が出てくると突然気づくという事実がある(カクテルパーティ効果)。この時に意識に隣のグループの会話を気づかせるのは、無意識の脳活動の結果である。
膨大な無意識的な脳活動が行っている中で、意識が経験すること(できること)は、その「要約」のようなものである。例えるならば、社会の出来事を要約して伝える新聞の見出しのようなものだ。そこには社会の全ての情報などは到底存在し得ないし、その本当にごく一部にすぎない。仮にそれ以上を与えられたとしても、意識には受け取れる容量はないだろう。しかし、私たちの意識は、新聞の見出しを読んでいるだけなのにもかかわらず、それを最初に思い付いたのは自分であるかのように錯覚する。実際には、その情報が生じる前には、意識の知らないところで、脳が膨大な活動をしていたのである。
8.様々な科学的な発見や芸術活動を生み出す無意識の脳活動
イーグルマン教授によれば、電磁気の法則を発見したマックスウェルは、死の床で、その有名な方程式を発見したのは自分の中の何かであって、自分ではないと告白した。アイディアがただ降りてきたというのだ。ウィリアム・ブレイクも、名高い長篇詩「ミルトン」を「あらかじめ何も考えず、むしろ自分の意思に逆らって、いきなり(何者かが)口述して書き上げた」と言っている。ゲーテは、名著「若きウェルテルの悩み」を、意識的に考えを投入することなく、ひとりでに動くペンを持っているかのように書いたと言っている。
そして、無意識・深層心理学を展開した偉大な心理学者カール・ユングは「私たち一人ひとりの中に、私たちが知らない別の人がいる」と言った。ピンク・フロイドも「僕の頭の中に誰かがいるが、それは僕じゃない」と言ったそうだ。こうして、私たちの心に起こることの大半は、私たちの意識の支配下にはない。
こうして、意識は、たいていの意思決定に関わっておらず、傍観しているだけであるが、それによって私たちは上手く行動できている。例えば、意識がそのプロセスに関与すると、行動が遅くなりすぎてしまい、間に合わないことが度々ある。先ほど述べた急ブレーキを踏むときもそうだが、プロの球技のスポーツ選手などもそうである。目がボールをとらえて意識が認識するまでには0.5秒かかるが、それだけの時間をかけていては遅すぎて、たいていボールを打ち返せないのである。意識に関与させずに、神経系・脳・筋肉が直接的に活動しなければならない。
9.自分の意識は、自分の精神活動の中心にいない
こうした考察の結果は、私たちの意識は、私たちの心の働き・精神活動の「中心ではない」ということである。その活動の主体は、膨大な無意識の脳活動が行っており、私たちの意識は、実際には、その中心から遠くはずれた周辺から、その結果を傍観しているにもかかわらず、その中心にいると錯覚しているのである。
こうして、人間の日常的・直感的な感覚と最新の科学的な発見が、正反対となって鋭く対立することは、人類の歴史において時々起こっている。その典型が、400年ほど前のガリレオを巡る地動説と天動説の対立である。その当時の人間でなくて、21世紀の我々であっても、科学の学習を受けることがなかったら、日々太陽が自分たちの住む大地に対して昇っては降りるのを見ながら、「太陽が地球の周りを回っている」としか思わないだろう。
しかし、ガリレオは、地球の外に出て宇宙から地球と太陽の関係を客観的に見ることなく、地球の中にいながら、地球と太陽の関係を客観的に、すなわち科学的に見ることができたという点で偉大な人物である。
このガリレオの地動説と天動説の教訓からわかることは、要するに、人は、気づかないうちに自己中心的な視点・価値観を有しているということだ。自分がいる地球から見るから、全ては地球を中心に回っているように見える。そして自分の意識が心の働きその他すべてを体験するから、意識が心の働きの主体・中心であるかのように見える。
これを言い換えると、自分の中から、自分を客観的に見ることは難しいということだろう。地球の中ではなく、仮に、地球の外=宇宙から太陽と地球を見ることができたならば、容易に両者の関係を正しく見ることができただろう。同じように、自分の属している家族・集団・組織・民族・国家などの性質も、その外側の存在である他の家族・集団・組織・民族・国家と客観的に比較するならば、より正しく理解することができるだろう。
極めつけに、自分の目を自分では見ることはできない(鏡に映った自分の目の姿は見ることはできるが)。そして、目の中の盲点(網膜の中で光線の受容体の細胞のない部分)の存在を発見した科学者も、自分の目の観察から盲点を発見したのではなく、他人の目を覗き見ているうちに盲点を発見した。
なお、この盲点の話には、もう一つ重要なポイントがある。それは、人間が自分の目の経験から盲点の存在に気づかなかったのは、意識に立ち上る視覚の映像は、意識の知らない無意識の脳活動が、盲点の周りの映像で盲点の部分を埋め合わせた映像を作った上で、意識に見せるようにできているためである。すなわち、視覚の映像の体験においても、私たちの意識は、無意識の脳活動がなしていること(いわゆる視覚に関する編集作業)を知らないのである。