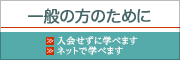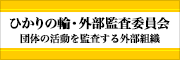『釈迦の教え=初期仏教の本質は宗教ではなく高度な心理学!』(2024年8月10日 東京 55min)
これは、2024年8月10日の夏期セミナーでの上祐の講義の一部です。
この講義では、上祐が、釈迦の教え=初期仏教の本質は、宗教ではなく高度な心理学であることについて語っています。具体的には、ひかりの輪の「2024年夏期セミナー特別教本『仏教の変質の歴史と初期仏教の創造的再生 21世紀の新しい仏教的な生き方』」の第1章を読み上げながら、その詳しい解説を加える形で行いました。
同教本第1章の全文は、動画の画面の下の箇所をご参照ください。
また、その内容の概要は、以下の同教本第1章の目次をご参照ください。
・第1章の目次
---------------------------------------------------------------
第1章 釈迦の教え、初期仏教について
1.はじめに
2.「仏教」・「宗教」という言葉自体が本来のものではない
3.釈迦は、自身を神と位置づけず、自身への崇拝を禁じた
4.絶対神(God)という信仰概念
5.聖書の唯一絶対神の誕生のプロセス
6.釈迦は原則として非暴力・不殺生(反戦争)
7.カースト制度を否定した、平等主義の強い思想
8.輪廻転生より現世で悟ることを強調した
9.初期仏教は、宗教ではなく、高度な心理学・心理療法の性質を持つ
10.医師としての釈迦、治療法としての仏法、高度で心理的な発達の智恵
11.信じることと、悟る=気づくことの違い
以下のテキストは、「2024年夏期セミナー特別教本『仏教の変質の歴史と初期仏教の創造的再生 21世紀の新しい仏教的な生き方』」第1章として収録されているものです。教本全体にご関心のある方はこちらをご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------------------
第1章 釈迦の教え、初期仏教について
1.はじめに
ここでは、仏教の開祖である釈迦自身が説いた仏教の教え、すなわち初期仏教の特徴について、釈迦後に変質していった仏教(特に大乗仏教)や、その仏教の変質に影響を与えた他の宗教と比較して述べる。これは仏教に限らず、宗教と人類社会の関係において非常に重要な視点であり、今後の人類社会を助けるための思想を考える上でも極めて重要である。
ただし、それについて述べる前に、まずは、初期仏教とは何かについて、なるべく正確に把握しておく必要がある。初期仏教とは、仏教開祖釈迦自身が説いた教えのことである。そして、初期仏教と、それ以降の仏教をしっかりと分ける必要がある理由は、他宗教の影響などを受けて、仏教が、後に大きく変質したからである。さらに、特に大きく変質したのは、日本に伝来した北伝仏教とも呼ばれる大乗仏教であり、日本人の多くは、初期仏教には馴染みがなく、開祖の釈迦が説いた本来の仏教をよく知らない面がある。
さらに、これに関連して、「仏教」や「宗教」という言葉自体が、明治時代にできた英語の和訳の日本語であるということを知っておくことも重要である。それ以前は、仏教ではなく、「仏道・仏法(ダルマ)」といわれていた。「仏教」というと、「宗教」と同じように、仏を絶対者として信じる教えというイメージがあると思う。しかし、釈迦の説いた仏道・仏法とは、釈迦を絶対者として崇拝する宗教ではなく、ブッダとは目覚めた人・悟った人という意味であって、決して絶対者ではなく、仏道・仏法とは、悟った人間になる道・法であって、端的にいえば悟りの道である。
2.「仏教」・「宗教」という言葉自体が本来のものではない
一方で「宗教」という言葉も、明治以前には日本にはなく、代わりに「宗(しゅう)」ないし「道(どう)」という言葉が使われた。宗とは、道理・真理といった意味であるから、宗も道も、正しく生きる道・道理といったほどの意味となる。これは、日本の民族宗教を「神教」といわずに「神道」といい、同様に日本の国産宗教である「修験道」などの例があることを思い出せば、理解しやすいだろう。
一方、宗教は、英語のreligionのことであり、欧米キリスト教文化の中では、キリスト教をはじめとする聖書の教えのことになる。そして、religionの原意は、絶対神(God)との再融合といったほどの意味である(『イスラーム化する世界と孤立する日本の宗教』関口義人 彩流社 2022)。すなわち、悪魔の虜となって絶対神から離れてしまった人間が(イエスなどの預言者・神の代弁者への信仰を通して)、絶対神の御許(おんもと)に戻ることを意味している。よって、宗教とは、その原語の英語から見ても、絶対者を信じて救われる教えである。よって、宗教と、日本古来の「道」や「宗」は、その本質的な意味において大きく異なることになる。
問題は、現代の日本人にとって、宗教といえば、仏教も含めて、仏を絶対者として崇拝するかのようなイメージがあることである。そして、その原因としては、仏教が、仏祖釈迦牟尼の死後に、徐々に他の宗教などに影響を受けて絶対神崇拝の思想に変質し、そのタイプの仏教(大乗仏教)が日本に伝来した、という歴史的な経緯にも原因がある。これについては、また後で詳しく述べたいと思う。そして、こうした宗教・仏教という言葉の使い方自体が、釈迦とその思想(初期仏教)の性格を正しく理解することを阻んでいる面がある。
3.釈迦は、自身を神と位置づけず、自身への崇拝を禁じた
釈迦は、自分を神と崇めてはならないとし、また自分への崇敬の念によって自分の教えを信じてはならないとしたとされる。教えに対しては、その確からしさをよく吟味し、納得した上で修習(しゅじゅう)するように述べたとされる。
また、絶対神の存在を説いたこともなく、それゆえに自分を、その化身であるとか、神の子であるとしたこともない。彼は、自身を「ブッダ(仏陀・仏)」と位置づけたが、ブッダとは目覚めた人(悟った人)という意味であり、そもそも釈迦だけを指した言葉ではなく、聖者といったほどの意味の普通名詞であった。よって、ブッダとは、神のことではなく、人間として悟りを得た者という意味である。
また、彼の教えの目的は、他の人々を、彼と同様の悟りに導くものであって、その意味で、悟ることができるのは自分だけである、とするものでもない。これを土台として、後世の仏教には、全ての人々が未来に仏陀となる可能性(仏性)を有するという思想も現れるに至った。
4.絶対神(God)という信仰概念
ここで、釈迦は自分を神と崇めてはならないと説いたと述べたが、「神」という概念自体が、西洋・聖書系の思想と、東洋の思想では異なる。西洋のGodは、絶対神・唯一神などと言われる。これは、人間や人間の住む世界を超越している存在であり、そのため「超越者」と呼ばれる。Godは、世界や人間を創造した創造主であり、悪魔さえもGodによって創造された。そして、Godは絶対神であるから全知全能であり、死後の世界を含めて一切を知り、一切を司る。
そして、絶対神は唯一神であり、すなわち唯一絶対の神であるから、その言葉は、人類全体に適用される。すなわち、実際には、いろいろな民族がいろいろな神を信じているのが人類社会である以上、人類社会は多神教の世界ともいうことができるが、唯一絶対神を信じている民族・信者の集団にとっては、それは全知全能の存在であって、間違いが一切なく、それと矛盾するものは、邪神・邪教・邪教の信者ということになる。
唯一絶対神という概念は、それを信じる民族を、自己絶対化する側面がある。例えば絶対神が、特定の地域を統べるために選んだ民族を選民(たとえばユダヤ・イスラエル民族)という概念があるが、自分たちが信じる全知全能の絶対神の言葉は絶対の善であり、そのため、時には暴力・戦争で他民族を排除しても、それは神の名において正当化され、聖戦ということになる。
そもそも、絶対神は、全知全能で、この世を創造したものであり、人間を創造したものであり、死んだ者も復活させる力があるため、人間を殺す権利、生殺与奪(せいさつよだつ)の権能があると解釈される。これは、他の神を信じる他の民族から見れば全くの傲慢に見えるが、唯一絶対神という概念は、それを信じる民族を絶対化し、それを信じる民族と信じない民族を善と悪、神側と悪魔側に二分化する排他的な性質を持ち、聖戦という名で暴力も正当化する一面がある。
5.聖書の唯一絶対神の誕生のプロセス
ユダヤ民族のための神である旧約聖書の神こそが、唯一絶対神の典型であるが、じつはユダヤ民族が最初に信じていた神は、多神教の中の最高神であって、唯一絶対神ではなかったとされる(こうした信仰を拝(はい)一神教(いつしんきょう)などという)。しかし、新バビロニアの王・ネブカドネザル2世により、ユダヤ人たちが、バビロンをはじめとしたバビロニア地方へ捕虜として連行・移住させられると(バビロン捕囚)、ユダヤ人たちは、バビロニアの圧倒的な社会や宗教に囲まれる葛藤の中で、それまでの民族の宗教のあり方を徹底的に再考させられることになり、自分達の中での宗教的なつながり・連帯を強め、律法を心のよりどころとし、ユダヤ教を確立した。
そして、この時期に、神ヤハウェの再理解が行われ、神ヤハウェはユダヤ民族の神であるだけでなく、この世界を創造した神であり唯一神である、と理解されるようになったという。バビロニアの神話に対抗するため、旧約聖書の天地創造などの物語も記述されていった。後のローマ帝国以降のディアスポラ(ユダヤ民族の離散)の中でも失われなかったイスラエル民族のアイデンティティは、こうしてバビロン捕囚をきっかけとして確立されている。それはある意味で民族の存亡をかけたものだったのかもしれない。
この聖書の絶対神は、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教を通じた神となった。そして、先ほど述べたような性質もあって、ゾロアスター教を起源とする終末思想が聖書でも説かれることになった。それは、世界は基本的に善と悪の戦いであるという善悪二元論の思想であり、神側・救世主側と悪魔側の最終戦争があり、最後の審判で皆が裁かれ、正しい信仰を持った聖徒は神の国に入り、そうでない者は地獄に落ちるという、神による裁きを説くものである。
いっぽう初期仏教では、釈迦は、絶対神の存在も、それによる世界の創造や、最終戦争や最後の審判といった終末の思想も説くことがなかった。そのため、前に述べたように、自らを絶対神と結びつけて、その化身であるとか、唯一の(絶対)神の子などとも説くことがなかった。ところが、釈迦の後の仏教は、絶対神を信じる他宗教の影響などを受けて徐々に変質していったと思われることは、後に詳しく述べることにする。
6.釈迦は原則として非暴力・不殺生(反戦争)
釈迦は、戒律として、非暴力・不殺生を説くとともに、他の宗教と異なり、宗教的に正当化される暴力・殺生・戦争・聖戦・最終戦争などの類(たぐい)は説いたことはない。
また、釈迦は、クシャトリヤ=武士階級の一員として、釈迦族の王子として生まれたが、王・武士として、他国との戦争・支配権の争奪・政治に関わる将来を、出家によって捨てて、人間の苦しみを取り除く悟りを得る修行の道を選び、悟った後は、その教えによる衆生済度にあたる道を選んだ。
そして、自分の出身部族である釈迦族が、コーサラ国の王(ヴィドゥーダバ)に滅ぼされようとした時も、繰り返し王を制止はしたが、実力をもって阻止することはせず、ついに釈迦族は滅ぼされるに至っている。詳しくは以下の通りである。
ヴィドゥーダバが8歳になった頃、母親の実家である釈迦族の地へ行って、弓術(きゅうじゅつ)などの修練に励んで来るように王に命じられ、釈迦族の子弟と共に弓術を学んだ。ちょうどその頃、城の中に新たな講堂が完成し、神々や王族などのみが登ることができる神聖な獅子の座に、ヴィドゥーダバが昇り座ったのを釈迦族の人びとが見て、「お前は下女の産んだ子だ。それなのにまだ諸天さえ昇っていないのに座った」と、怒って太子の肘を捕らえて門外に追い出し鞭を打って地面に叩きつけた。ヴィドゥーダバは「我が後に王位についた時、このことを忘れてはいけない」と恨みを懐(いだ)くようになった。(中略)
ヴィドゥーダバは成長すると、波斯(はし)匿(のく)王(おう)の留守中を狙って王位を奪った。ヴィドゥーダバ王は、釈迦族殲滅(せんめつ)を企て進撃するが、それを知った釈尊は、一本の枯れ木の下で座って待っていたといわれる。進軍してきたヴィドゥーダバ王は、釈尊を見かけると「世尊よ、ほかに青々と茂った木があるのに、なぜ枯れ木の下に座っているか?」と問うた。釈尊は「王よ、親族の陰は涼しいものである。」と静かに答えた。しかし、釈尊は、これを三度繰り返し(ヴィドゥーダバを制止し)つつも、その宿縁の止め難きを知り、四度目に(ヴィドゥーダバは)とうとう釈迦族のいるカピラ城へ攻め込んだ。「仏の顔も三度まで」ということわざはこの出来事に由来していると言われている(ウィキペディア「毘(び)瑠璃(るり)王(おう)」より)。
7.カースト制度を否定した、平等主義の強い思想
また、釈迦は、釈迦族という小さな部族の王子(釈迦族は近くの強国のコーサラ国の属国だったという)であったが、バラモン教において、神の代理人として祭祀を行うバラモン階級ではなく、その下のクシャトリヤ階級(武士階級)の出身である。そして、釈迦はカーストを否定し、皆が平等であるとして、弟子の序列も、出家の順や、修行の頑張り具合などで決めたという。また、釈迦の教団は、当時から男尊女卑が強い地域にあって、初めて女性の出家を認め、男女平等においても革新的であったとされる。
この平等主義は、世界を善悪・聖邪で二分化して善が悪と戦う聖戦という思想を生みにくいものである。あとにも述べるとおり、人が戦争という組織的な大量殺害を行うことは、本来的には大きな罪であるところ、それを全くの善として正当化するのが、聖戦という概念であるが、その場合、全くと言ってよいほど、戦い滅ぼす相手は悪と位置付けられる。さもなければ聖戦にはならないからである。それゆえ、人々を平等に扱う思想は、暴力を正当化しにくいものである。
なお、この釈迦によるカースト制度の否定は、釈迦の死後も、バラモン教およびバラモン教から発展したヒンドゥー教との対立軸となった。これは、インド仏教が中世においてイスラム教勢力の侵入によって滅びる直前に成立した、インド仏教最後の経典とされる時輪経典の内容にも反映されているし、さらには、第二次世界大戦後にインドで仏教が復興した際には(仏教復興運動・新インド仏教)、反カースト運動の一環として復興したものであった。この仏教復興運動では、釈迦は、(カースト制度を正当化する思想である)輪廻転生とカルマの法則を説かなかったとまで解釈している。
8.輪廻転生より現世で悟ることを強調した
日本人には、輪廻転生は仏教オリジナルの思想だと思われがちである。しかし、実際には、釈迦が生まれる前から、インドはバラモン教が支配する世界であり、そのバラモン教が説いたのが、輪廻転生とカルマの法則である。
そして、この教えは、当時のインド社会では政治的に重要な意味を持っていた。というのは、カルマの法則と輪廻転生の思想が、カーストと呼ばれる階級制度の正当性を支えるものとなっていたのである。カースト制度では、バラモン(司祭階級)と呼ばれる特権階級の人達が、他の階級の人々(クシャトリヤ=武士階級、ヴァイシャ=商人階級、シュードラ=奴隷階級、パンチャマ=不可触民)を支配する。
そして、輪廻転生とカルマの法則に基づいて、階級制度の存在は不当な差別ではなく、人は、前世の業の報いにより、今生その身分のもとに生まれるのであり、生涯その身分の元での役目を全うすることによって、来世の福が保証されるとしたのである。
一方、そうした中で教えを説いた釈迦の教えは、学術的な調査によれば、当時の人々にとって、絶対的な常識となっていた輪廻転生(とカルマの法則)をはなから否定することはせず、来世の幸福のための教えを説くこともあったが、その教えの力点は、現世で善行を積み、現世で悟ること(涅(ね)槃(はん)に至ること)であったという。
なお、先ほど述べた第二次世界大戦後にインドで起こった反カースト運動の一環として起こった仏教復興運動では、カースト制度とバラモン教以来の輪廻転生の深いつながりを踏まえて、釈迦は(カースト制度を正当化する思想である)輪廻転生とカルマの法則は説かなかったという独自の解釈をしている。
9.初期仏教は、宗教ではなく、高度な心理学・心理療法の性質を持つ
釈迦の教えの目的の中核は、端的に言えば、その最初の説法とされる四諦(したい)八正道に説かれる通りに、人間のさまざまな苦しみを取り除くことであり、取り除いた状態である悟りの境地に至ることである。その苦しみの原因は煩悩であり、煩悩の根本は、心理的な無智であり(漢訳仏教用語では痴(ち)・愚痴(ぐち)・無明(むみょう)などと表現される)、それを取り除くための手段が、八正道ないし、戒律・禅定・智慧などと呼ばれる修行法であり、それによって生じる智慧が、苦しみの根本原因の心理的な無智を取り除いて、苦しみを取り除くとする。
前に述べたように、これは、釈迦を神(絶対神の化身)として崇めることを否定するばかりか、人々が釈迦に続いて、悟りという高度な心理的発達をなした人間となることに導くものである。つまり、唯一絶対神の唯一の神の子とされるイエスなどを信じて救われる教えではなく、釈迦自身を特別な存在とはせず、教えによって悟りを得ることができる人間の一人であると位置づけるものである。
なお、大阪大学名誉教授の故佐保田鶴治氏は、イエス・ムハンマド・モーゼのように、唯一(ないしは少なくとも最高)の神の代弁者(預言者)を信じる宗教を「預言者的な宗教」とし、仏教やヨーガのように、人々が修行によって神に近づいていく宗教を「神秘主義的な宗教」として、宗教を二つに区分したが、佐保田鶴治氏は、それと同時に、釈迦牟尼を偉大な心理学者であるとも表現した(佐保田鶴治著『ヨーガ根本経典』平河出版社)。
これはなぜかというと、釈迦の教えの中核は、主に人間の精神的な苦しみを取り除く智恵であり、苦しみをもたらす心の働きと、それを乗り越える実践法を説いたものであるから、一般の人を、煩悩という心の病を抱えた患者とみなし、その病を治す治療法を説いたとみなすことができる。実際に、煩悩の根源は、漢訳仏教用語では、痴・愚痴などと表現され、この漢字は、悟っていない普通の人は物事をありのままに見ることができない心理的な問題、物事の認知における病を抱えている、という仏教の思想を反映している。
そして、その教えは極めて合理的、論理的であり、人の心の働きや言動に対する客観的な観察に基づいている。その教えを理解する上で、自分の理性による疑問・批判を捨てて、はなから信じなければならないことはない。これは、現代的に表現すれば、東洋の伝統的な心理学に基づく心理療法に近いともいうことができる。
もちろん、その教えは、日常の行動規範(戒律)、呼吸法や座法を組んだ瞑想といった一定の身体行法が含まれている。すなわち、教えの学習・思索・瞑想といった心理的な作業だけではない。しかし、この点に関しては、現代の医療・心理療法でも、その中で、心身の健康に悪い日常の生活習慣の改善や一定の運動といった健康指導をなされることは多いから、医療ないし医療を補完するものとしては、自然なことである。
実際に、厚生労働省のHPにおいても、仏教の修行と身体行法や瞑想法などを共有するヨーガをいわゆる「統合医療」の一環として記載している(統合医療とは、近代西洋医学と、相補(補完)・代替療法や伝統医学等とを組み合わせて行う療法であり、多種多様なものがある)。
10.医師としての釈迦、治療法としての仏法、高度で心理的な発達の智恵
そのため、釈迦は、「応病(おうびょう)与(よ)薬(やく)(病気に応じて薬を与える)の人」ともいわれ、医師に例えられることがある。これは、前に述べたが、煩悩という心の病に応じて、それを治癒する方法(仏法・ダルマ)という薬を与えた、という意味である。さらに、この釈迦とその思想の性格は、後世の大乗仏教における、「医薬の仏」といわれる「薬師如来」という尊格に通じると解釈できる。
もちろん、現代でいう精神科の医師とは、健常者ではなく、精神疾患を患う者を治す者である一方で、釈迦の思想は、健常者を含めた、悟っていない全ての人々を、煩悩という心の病を患った者とみなすものと解釈される点において違いがある。さらに、煩悩を心の病のように見なしながらも、釈迦が説いた悟りという修行の最終目的は、人間としてのさまざまな苦しみを一掃したごとくの状態をもたらすものだから、単なる心理療法の一種ではなく、常人を超えた高度な心理的発達を実現するものである点も、違いである。
しかしながら、現代にいたってもなお、人間が、その煩悩・我欲によって、日常において、さまざまな他者との対立的な関係によるストレスを抱え、民族・国家としては、依然として戦争という愚行をなし、核兵器の誕生とともに絶滅の危機もいわれるようになったことを考えるならば、人間の間では健常者とされるものであっても、人は全て、心の病を患っていると解釈するのは、非合理的とはいえないのではないだろうか。そもそも、病人とは、健常者との対比で認識される概念であるから、どんなにひどい病気であっても、全ての人がそれに罹っているとしたら、それは病気とは認識されないのである。
11.信じることと、悟る=気づくことの違い
また前に述べたように、釈迦は自己を神と崇めることを禁じ、自分への崇敬の念からのみ自分の教えを信じるのではなく、教えの確からしさを、疑いさえもって、よく吟味するように説いたという。これは、すなわち、絶対神やそれを信じることではなく、真の幸福の道を悟る=気づくこと=智恵(智慧)の獲得を目的としたものであるということができる。
絶対神とその救いを信じることと、真の幸福の道理を悟る智恵を得ることは、心理的な作業として、全く異なるものである。後者は、現代的にいえば、宗教というよりも、心の科学・心理学に相当するものであり、東洋の伝統的な心理学・心理的な医療であり、悟りという常人を超えた高度な心理的発達を得る智恵、ということができるだろう。そうしたこともあり、佐保田鶴次氏と同じように、インドを植民地支配した英国の宗教学者は、仏教を見て、それは彼らがいう宗教ではなく、幸福になるための実践哲学であると考えたという。