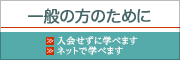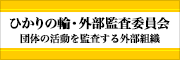仏教・宗教の歴史の総括とこれからの思想
目 次
釈迦の教えと釈迦後の変質
第1.釈迦の教え(初期仏教)の特徴(釈迦後の大乗仏教や他宗教と比較して)
第2.釈迦後の仏教の変質:仏陀の神格化・殺生の一部肯定・他の宗教の影響・
大乗仏教の発生
付記1:仏教経典の予見と現代社会の動向から探る未来の仏教の復興の可能性
付記2:麻原・オウムが説いた時輪経典・シャンバラの教義と伝統仏教の教義
の大きな相違点・矛盾
付記3:カーラチャクラ経典とシャンバラに関して
付記4:阿閦如来に関して
---------------------------------------------------------------------------------
釈迦の教えと釈迦後の変質
第1.釈迦の教え(初期仏教)の特徴(釈迦後の大乗仏教や他宗教と比較して)
まず、釈迦が生前に説いた釈迦自身の教え(初期仏教)の特徴について、釈迦の入滅以降に誕生した大乗仏教や他の宗教と比較して述べたいと思う。
1.自身を神と位置づけず、自身への崇拝・絶対視を禁じた
釈迦は自分を神と崇めてはならないとし、また自分への崇敬の念によって自分の教えを信じてはならないとしたとされる。教えに対しては、その確からしさをよく吟味し、納得した上で修習するように述べたとされる。また、絶対神の存在を説いたこともなく、それゆえに自分をその化身であるとか、神の子であるとしたこともない。彼は自身をブッダ(仏陀・仏)と位置づけたが、ブッダとは目覚めた人(悟った人)という意味であり、あくまでも、神ではなく、人間として悟りを得た者という意味である。また、彼の教えの目的は、他の人々を、彼と同様の悟りに導くものであり、その意味で、悟ることができるのは自分だけであるとするものでもない。これを土台として、後世の仏教には、全ての人々が未来に仏陀となる可能性(仏性)を有するという思想も現れるに至った。
2.輪廻転生より現世で悟ることを強調した
釈迦が生まれる前から、インドはバラモン教が支配する世界であった。バラモン教は、輪廻転生とカルマの法則を説き、それが、バラモン(祭祀階級)が特権階級として他の階級の人々を支配する階級制度(カースト)の正当性を支えるものとなっていた。階級制度は不当な差別ではなく、前生の行い(カルマ)に応じたものであるということである。
そうした中で教えを説いた釈迦の教えは、学術的な調査によれば、人々にとって絶対的な常識となっていた輪廻転生(とカルマの法則)をはなから否定することなく、それを説くこともあったが、その教えの力点は、現世で善行を積み、現世で悟ること(涅槃に至ること)であったという。
3.カースト制度を否定し平等主義の強い思想
また、釈迦は、釈迦族という小さな部族の王子(釈迦族は近くの強国のコーサラ国の属国だったという)であったが、バラモン教において、神の代理人として祭祀を行うバラモン階級ではなく、その下のクシャトリヤ階級(武士階級)の出身である。そして、釈迦はカーストを否定し、皆が平等であるとして、弟子の序列も、出家の順や、修行の頑張り具合などで決めたという。また、釈迦の教団は、当時から男尊女卑が強い地域にあって、初めて女性の出家を認め、男女平等においても革新的であったとされる。
なお、この釈迦によるカースト制度の否定は、釈迦の死後も、バラモン教およびバラモン教から発展したヒンドゥー教との対立軸となった。これは、インド仏教が中世においてイスラム教勢力の侵入によって滅びる直前に成立したインド仏教最後の経典とされる時輪経典の内容にも反映されているし、さらには、第二次世界大戦後にインドで仏教が復興した際には(仏教復興運動・新インド仏教)、反カースト運動の一環として復興したものであった。この仏教復興運動では、釈迦は、(カースト制度を正当化する思想である)輪廻転生とカルマの法則を説かなかったとまで解釈している。
4.非暴力・不殺生(反戦争)
釈迦は、戒律として、非暴力・不殺生を説くとともに、他の宗教と異なり、宗教的に正当化される暴力・殺生・戦争(聖戦)を説いたことはない。また、釈迦は、クシャトリヤ=武士階級の一員として、釈迦族の王子として生まれたが、王・武士として、他国との戦争・支配権の争奪・政治に関わる将来を出家によって捨てて、人間の苦しみを取り除く悟りを得る修行の道を選び、悟った後は、その教えによる衆生済度にあたる道を選んだ。そして、自分の出身部族である釈迦族が、コーサラ国の王(ヴィドゥーダバ)に滅ぼされようとした時も、繰り返し王を制止はしたが、実力をもって阻止することはせず、ついに釈迦族は滅ぼされるに至っている。詳しくは以下の通りである。
ヴィドゥーダバが8歳になった頃、母親の実家である釈迦族の地へ行って、弓術などの修練に励んで来るように王に命じられ、釈迦族の子弟と共に弓術を学んだ。ちょうどその頃、城の中に新たな講堂が完成し、神々や王族などのみが登ることができる神聖な獅子の座に、ヴィドゥーダバが昇り座ったのを釈迦族の人びとが見て、「お前は下女の産んだ子だ。それなのにまだ諸天さえ昇っていないのに座った」と、怒って太子の肘を捕らえて門外に追い出し鞭を打って地面に叩きつけた。ヴィドゥーダバは「我が後に王位についた時、このことを忘れてはいけない」と恨みを懐くようになった。(中略)
ヴィドゥーダバは成長すると、波斯匿王の留守中を狙って王位を奪った。 ヴィドゥーダバ王は、釈迦族殲滅を企て進撃するが、それを知った釈尊は、一本の枯れ木の下で座って待っていたといわれる。進軍してきたヴィドゥーダバ王は、釈尊を見かけると「世尊よ、ほかに青々と茂った木があるのに、なぜ枯れ木の下に座っているか?」と問うた。釈尊は「王よ、親族の陰は涼しいものである。」と静かに答えた。しかし、釈尊は、これを三度繰り返し(ヴィドゥーダバを制止し)つつも、その宿縁の止め難きを知り、四度目に(ヴィドゥーダバは)とうとう釈迦族のいるカピラ城へ攻め込んだ。 「仏の顔も三度まで」ということわざはこの出来事に由来していると言われている。(ウィキペディア「毘瑠璃王」より)
5.現代社会の宗教のイメージから見ると、宗教ではなく、実践哲学・高度な心理療法である教え
前に述べた通り、釈迦の教えは、自己を神として崇めることを否定し、自分の教えの確からしさを吟味せずに信じることを否定し、絶対神を説かず、自分をその化身・預言者・代理人ともせず、その天地創造や世界の終末も説くことがなかった。そうしたことから、インドを支配するに至った大英帝国の学者が釈迦の教えを調査した際には、宗教ではないと分別されたという。また、ヨーガと共に初期仏教誕生当時の東インドの思想に詳しい故佐保田鶴治博士(元大阪大学名誉教授)も、「釈迦は偉大な心理学者」であったとしている(『ヨーガ根本経典』平河出版社)。
釈迦の思想の要点は、①悟りを得ていない普通の人は、物事の見方の根本的な過ち・無智(無明・痴)を根本原因として、貪りや怒りといった煩悩的な欲求(我欲)が、実際には幸福ではなく、さまざまな苦しみを招くことが理解できずに苦しむという一種の心の病にかかっており、②その無智と無智による煩悩を滅する智慧を体得する(=悟る)方法として、各種の修行法を説いた。
そのため、釈迦は、応病与薬(病気に応じて薬を与える)の人ともいわれ、煩悩という心の病に応じて、それを治癒する方法(仏法・ダルマ)という薬を与えた。すなわち、現代社会の一般的なイメージとしては、宗教とは、幸福になるために神仏を信じよという教えであろうが、釈迦は、そのようなことは説いていない。釈迦が説いた仏=仏陀とは、目覚めた人・悟った人という意味であって、あくまでも人間である。
その意味で、釈迦の思想(初期仏教)は、苦しみを取り除く実践哲学・心理学であり、釈迦は、医者(治療家・心理療法士)といった性格が強い。この釈迦とその思想の性格は、後世の大乗仏教における、医薬の仏である「薬師如来」という尊格に通じると解釈できる。
◎参考資料
上記の問題は、宗教や仏教という言葉自体にさかのぼる。
「仏教」は、明治以来の言葉であり、それ以前は仏道または仏法と称された。すなわち、仏道=仏になる道=覚道ということである。しかし、仏教というと、一般の人には、人間が仏陀を神のように信じる教えというイメージになる。
同じく「宗教」も、明治時代の欧米化の際に、英語の religion を和訳してできた言葉である。religionの原意は、絶対神から離反した人間が再び絶対神と融合するといったほどの意味であるという(『イスラーム化する世界と孤立する日本の宗教』関口義人・彩流社)。それ以前の日本の宗教は、道や宗と呼ばれることが多かった。日本の民族宗教は神道と呼ばれ、神教とはいわないし、同様に国産宗教である修験道などがある。この宗は、道と同様に、道理・真理などといったほどの意味であり、religion(絶対神との再融合)とは、意味において大きな違いがある。
こうした宗教・仏教という言葉の使い方自体も、釈迦とその思想(初期仏教)の性格を正しく理解することを阻んでいると思われるが、それに加えて、以下に述べるように、釈迦の死後に仏教が大きく変質し、それが日本に伝わったことがある。
第2.釈迦後の仏教の変質:仏陀の神格化・殺生の一部肯定・他の宗教の影響・大乗仏教の発生
1.仏教全体の歴史
そこでまず、およそ2500年前に起こった初期仏教(釈迦の思想)が、インドからチベット・中国・朝鮮に渡り、日本に6世紀頃に伝来し、今日に至るまでの全体的な歴史の概略を述べる。というのは、日本人が一般に馴染んでいる仏教である「南無阿弥陀仏」の阿弥陀念仏(浄土宗・浄土真宗など)や「南無妙法蓮華経」の日蓮宗系の教えは、鎌倉時代にできた日本オリジナル仏教ともいうべき性格のものであり(鎌倉新仏教といわれる)、檀家数では浄土教系が 6 割を占めているために、日本の仏教の中枢をなしているものの、仏教の歴史全体から見ればかなり特殊な教えであり、日本人が仏教を全体的に知るためには、仏祖の釈迦牟尼の思想と、その死後にインドで展開した仏教の変化の歴史を知ることが重要である。
まず、仏教の開祖は、 ゴータマ・シッダッタ(パーリ語)を本名とし、現在のネパールにて生誕し、釈迦族という小さな民族・小国の王子であった。存命年代は、紀元前 7 世紀~紀元前 5 世紀など諸説がある。出身部族はシャーキヤ族であり、その領国はシャーキヤ国であり、釈迦は、シャーキヤを音写したもの。釈迦牟尼=シャーキヤムニは、サンスクリット語で「シャーキヤ族の聖者」という意味の尊称であり、これを音写したのが釈迦牟尼(釈迦牟尼仏)、略して「釈迦」と呼ばれる。
なお、ブッダは梵語で「目覚めた人」という意味で、もともとインドの宗教一般において、すぐれた修行者や聖者に対する呼称であったが、仏教で用いられ、釈迦の尊称となった。これを音写して漢字で仏陀と書き、仏陀の略称が仏であり、「仏教」や「仏像」という言葉の元になった。釈迦について同時代の一次史料は乏しく、人種さえ不明であり、釈迦の死後に成立した経典が伝える釈迦の生涯いわゆる仏伝が史実を伝えているかは疑問が持たれている。
釈迦族の王族として生まれた釈迦は、あとつぎの男子をもうけたあと、29 歳で王族の地位を捨て出家し、林間で修行し、35 歳で悟りを開き、布教の旅に出て、遊行の身のまま世を去った。シャーキャの都カピラヴァストゥにて育てられ、王子としての期待を一身に集めて育てられるが、その後、老い病み死ぬ人生の無常や苦を感じて、29 歳で出家した。その後、さまざまな宗教思想家の教えを受けたが、それに満足せず、その後 6 年の間にさまざまな苦行を行ったが、過度の快楽と同様に、極端な苦行も悟りの道ではないと考えて苦行をやめ、樹下に坐して瞑想に入り、悟りに達して仏陀となったとされる(35 歳)。これを成道という。そのあと、自分が悟った真理は世間の常識に逆行し、法を説いても徒労に終わるとも考えることがあったが、その後、サールナートにおいて、五人の沙門(出家者)に、中道、四諦と八正道の教えを説いた(釈迦の最初の説法=初転法輪)。
その後、マガダ国の国王も帰依し、竹林精舎を寄進、後の高弟が改宗して教団に加わり、マガダ国の人々や、バラモンやジャイナ教の信者が帰依し、教団は増大し、規律維持の戒律が設けられた。その後、故国のカピラヴァストゥを訪問し、釈迦族の王子や子弟が弟子となり、コーサラ国やガンジス河を遡って西方地域へも足を延ばし、祇園精舎も設けられた。
釈迦が死去(涅槃)する前に、コーサラ国の王子のヴィドゥーダバは、父親から王位を簒奪すると、かねてから釈迦族に恨みを抱いていたため、何度か釈迦が制止するも、最後には釈迦族を滅ぼし、自らも戦勝の宴の最中に洪水または落雷によって死んだとされる。
釈迦は多くの弟子を従え、ラージャグリハから最後の旅に出て、各村々でそれぞれの教えを説いた(「四念処」・「自灯明・法灯明」・「戒定慧」の三学など)。最後は、クシナガラに行き、その近くの川のほとりで死去した(80 歳没)。仏教では釈迦の死を入滅、仏滅などという。釈迦の死後、その遺骸は火葬され、釈迦の遺骨(仏舎利と呼ばれる)は八分され、弟子たちは釈迦の残した教えと戒律に従って跡を歩もうとし、何度か結集して、釈迦の教法と律とを阿含経典群にまとめた。
釈迦の死後の 100 年頃になると、仏教教団は分裂した。最初の分裂は、上座部と大衆部(だいしゅぶ) の分裂であり(根本分裂)、その後に 20 余に再分裂した。この時代を部派仏教の時代という。上座部の流れは、スリランカを経て、タイなど東南アジアに現在も残っている。
その後に、アショーカ王が現れ、紀元前 3 世紀に第 3 回仏典結集が行われ、この際に初めて仏陀の教えは、口伝ではなく、経典にまとめられたという(言語はサンスクリット(梵)語、パーリ語)。このアショーカ王時代に、仏教はインド全域に広がり、その後に中央アジア、そして紀元1C 頃に中国に達した。
そして、紀元前後に、大乗仏教が発生した。大乗仏教の教えと経典は、学術的に見れば、釈迦の死後に説かれた教えであるが、その中には、釈迦に由来すると主張するものもある。その主旨は、一切智の仏となり、一切衆生を済度することを強調するものが多い。中国を経て、朝鮮には 4世紀ごろに伝えられ、その後、日本などに広がった。
その後、7 世紀ごろに、ヒンドゥー教神秘主義のタントラと深い関係を持つ密教が発生した。これは、仏教のヒンドゥー化ともいわれるが、インドから、チベット、ブータンへと伝わる。その教義は、秘密の儀式で仏になる(即身成仏)というもので、中国・ベトナム・朝鮮にも伝わり、日本にも、弘法大師などによって伝えられた。
チベットは8世紀ごろに国をあげ仏教(密教)を導入し、チベット仏教として今日に知られる。こうして、仏教の教義は極めて多様であるが、その受け入れ方は、国・宗派によって、多種多様である。
現代の状況としては、仏教が国教ないし国教的であるのは、タイ・スリランカ・カンボジア・ラオス・ブータンなどである。これは、歴史の中で大部分の仏教国は滅亡したことを示している(チベット仏教は独立を失っている)。仏教の宗教人口は、ヒンドゥー教より少ないが、その発祥地であるインドにおいて、ヒンドゥー・イスラムとの争いで一度滅亡している。20世紀になって、インドでの仏教復興運動が、反カースト制度運動と共に起こり、仏教徒への改宗が行われ、現在はインドの人口の 1%弱(900 万人弱)が仏教徒であるとされる(一部の調査では2000万人とも)。仏教の宗教人口は世界全体では5 億人強とされ、そのうち上座部が 1.5 億、大乗系が 3.6 億などである。
こうして、仏教は、インドからチベット、中国、韓国、日本や、スリランカ、東南アジア諸国に広がり、キリスト教・イスラム教と共に 3 つの世界宗教の 1 つとされるが、その教義の解釈は多様であり、異端に厳しいキリスト教やイスラム教に比較して、宗派が非常に多い。
その思想は、三宝とされる仏陀(ブッダ)、法(ダルマ)、僧(サンガ)に対する帰依、三学と呼ばれる戒律と禅定と智慧の実践が説かれる。その主たる目的は、悟り、輪廻からの解脱、衆生済度などであるが、念仏による極楽浄土への往生を目的とするなど、宗派によって大きく異なる。
2.仏教の変質:他の宗教・土着の文化・時代状況の影響
この仏教の歴史の中で、釈迦の思想(初期仏教)の本質的な部分が、その死後に、他の宗教・文化などの影響を受けて、大きく変質していったことがある。まず第一に影響を与えたものは、インド土着の文化であり、仏教以前からインドを支配していたバラモン教である。バラモン教は、釈迦の時代に仏教の興隆を受けて衰退したため、仏教の思想の一部やインド土着の文化を取り入れて、自己改革して勢力を盛り返した。この第二次のバラモン教が、現在ヒンドゥー教と呼ばれるものである。
それ以来、インドにおいて仏教とヒンドゥー教はライバル関係にあったが、お互いにお互いの教義を取り入れることとなった。その中で、仏教は、ヒンドゥー教の神を降伏し、仏教に改宗させた者として位置づけることがあった。こうして、ヒンドゥー教の影響を受けながらも、単純にヒンドゥー教の神をそのまま取り入れることにはならなかった背景の一つとして、釈迦の死後も、仏教は、バラモン・ヒンドゥー教の説くカースト制度を否定し続けたことがある。この対立軸は、前に述べたように現在までも残り、インドにおける反カースト運動としての仏教復興運動につながっている。
また、紀元前後にインドで発生した大乗仏教は、時期的に見て、その一部は、キリスト教などの聖書系の宗教の影響を受けたという学術的な説がある。特に、日本にも広がった阿弥陀信仰(阿弥陀念仏)は、「阿弥陀キリスト教」といわれるほどに、両者の信仰構造はよく似ている。すなわち、唯一の神の子イエスを信じて「最後の審判」や死後に救われることを目的とするように、阿弥陀如来を信じて、その念仏を唱えて来世極楽浄土に転生しようと信じる点である。
その中で、先ほど言及した医者としての釈迦と、それに通じる大乗仏教の尊格である薬師如来は、阿弥陀如来と対極的な性格としてよく位置づけられる。阿弥陀如来は、その浄土が、西方にあり(西方極楽浄土)、来世幸福が中心の御利益である。一方、薬師如来は東方にあって、病気癒し・戦争・飢饉・天災を鎮める現世幸福が中心の御利益である。これは、インドから西方の中東・キリスト教圏(来世を説く)と、東方の中国等の現世的な思想(来世を説かない)が反映されたものだという見解がある。
その経緯を説明するならば、6世紀ごろに日本に伝来した仏教は、当初は阿弥陀信仰は盛んではなかった。仏教が導入された飛鳥時代に建立された日本初の寺院である飛鳥寺のご本尊は釈迦如来であり、聖徳太子建立の法隆寺は薬師如来、その後の奈良時代に聖武天皇が全国に建立した国分寺のご本尊も薬師如来、仏法を鎮護国家に用いた弘法大師も、密教では大日如来、顕教では薬師如来を中心に据えた。特に、為政者は、国を戦・飢饉・疫病なく、無事・平穏に治めるために、その御利益があるとされる薬師如来を重視したと思われる。
しかし、平安時代ごろから、天災・飢饉・疫病などの広がりのために、キリスト教の終末思想に似た「末法思想」が広がりをみせる。本来の末法思想は、釈迦の死後から時を経て、悟る者がなく仏法の効力がなくなる時代を意味するものであるが、それとは異なり、キリスト教の終末思想のように世界の終わりを思わせる解釈がなされた。なお、末法思想自体が、釈迦の思想ではなく、紀元後5~6世紀に生まれたものだとされる。
そして、終末思想的な末法思想のために、来世の極楽浄土への往生を求める浄土教系の教えが広がり始め、特に、鎌倉時代に浄土宗・浄土真宗が発生し爆発的に広がった。それ以来、日本の仏教はこの浄土系が主流であり、江戸時代に導入された檀家制度を経て、仏教の信者の6割は浄土系ともいわれる。
ここで、キリスト教の影響を考える上で重要なのは、キリスト教を含めた聖書系の特徴として、ゾロアスター教までさかのぼるとされる善悪二元論の終末思想があることである。世界には終末があり、その前に「最後の審判」に先だって、善と悪(救世主と悪魔の勢力)の闘い=最終戦争があり、最終戦争で救世主側に滅ぼされる者と、救世主と共に戦い、戦争後のキリスト千年王国に入る者の区別があり、さらにその後に訪れる「最後の審判」で、天に召される者と地獄に落ちる者を分けるとする思想である。
これは救世主と聖徒(善業多き魂)による(悪魔とその支配下の悪業多き魂に対する)最終戦争の概念を説いているから、宗教的な戦争=聖戦を正当化する。また、現世とは(間もなく)終末がやってくるものと位置付けられ、現世の価値が相対化されて、死後の世界の価値が重視される。そして、聖戦に参加して自分が死ぬことがあるとしても、それは、死後ないし「最後の審判」に神の国に召される殉教となるとして美化・奨励されるのである。こうして、聖戦と殉教と来世の幸福は、信者が戦争に向かう心理的な障害を取り除いてしまう。
なお、人々が戦争に向かうことを宗教が心理的に可能にするという構造は、人類の歴史において、戦争が始まった時までさかのぼるという見解がある。日本では、戦争がなかったとされる縄文時代には、自然万物を神と見るアニミズム的な信仰(精霊信仰)が中心であったが、その後に戦争が始まったとされる弥生時代において、自分達の群れ・民族は特別であると位置づけて、他の群れ・民族に対する戦争を正当化、讃美する思想が生まれた痕跡があるというのである。
さて、時代を中世から近代に戻すならば、この聖戦・殉教の思想は、キリスト教に限ったことではないが、欧州のキリスト教国による武力手段をともなうキリスト教の布教である植民地侵略として、世界規模の影響を与えることになった。アフリカ・アジア・アメリカの大陸における植民地支配や開拓と自称したアメリカ合衆国の建国などである。
また、日本においては、先ほど述べたキリスト教の影響を受けたと思われる阿弥陀信仰の集団である一向宗門徒・石山本願寺が、戦国時代において、織田信長などと激しい(宗教)戦争を行ったことはよく知られている。浄土系の信者による戦争では、「厭離穢土・欣求浄土」と言って、汚れた現世よりも清らかに浄土に往生することを願って、死を恐れずに戦争に向かっていくことが説かれたという(なお、厭離穢土・欣求浄土には、戦争のない平和な世界を作って現世を浄土にするという解釈もあり、これが、浄土宗の家系であった徳川家康が、戦国の世に立ち向かった動機の一つとなったという説もある)。
また、織田信長との戦いにおいて、進めば(戦死しても)浄土、(戦いから逃げて)退けば地獄、として、信者を心理的に戦争に駆り立てる流れもあったという。こうして、宗教による聖戦と殉教・来世の幸福の概念は、強い戦争遂行の動機となったのである。
3.仏教の一部が、仏を神格化し、殺生を肯定するように変質し始めた経緯
非暴力・不殺生・反戦の思想であった釈迦の死後、仏教の一部において、釈迦を神格化したり、釈迦を超える絶対神的な仏を生み出し、殺生を肯定したりするという変質が生じたことが知られている。
その一部としては、前にも述べた通り、キリスト教の影響を受けた大乗仏教が考えられる。キリスト教では、ゾロアスター教の影響を受けて、善悪二元論の世界観・終末思想と神と悪魔(善と悪)の最終戦争、すなわち聖戦が説かれており、これは、イスラム教を含めて聖書系の宗教に共通する性格でもある(この影響は、仏教に限らず、ヒンドゥー教にも及んだであろう)。
これに加えて、仏教が、インドの中でライバル関係にあったヒンドゥー教への対抗に迫られるがあまり、①釈迦牟尼をいたずらに神格化したり、②殺生を行っていた人々を仏教徒として取り込むために迎合したりしたため、殺生肯定の「仏説」が形成されたことが研究者によって指摘されている。
以下に、その詳細を『ブッダが考えたこと』(宮元啓一著・春秋社)p99-105より抜粋して紹介する。
しかし、ゴータマ・ブッダが入滅してのち、仏教徒たちはゴータマ・ブッダを神格化する方向に大きく傾いていった。その傾向は、仏教やジャイナ教という新しい宗教に地盤を奪われたバラモンたち(古来のヴェーダの宗教を主宰することによって生活の糧を得てきた特権階級)が、失地回復のために多数派工作に走り、救済主義色に全面的に染められた新しい民衆宗教としてのヒンドゥー教を形成し、それが民衆の人気を広く博して隆盛に向かうのに比例して強まっていった。
ヒンドゥー教の最高神(とくにヴィシュヌ神)は、全知全能と讃えられ、かつ一方、最高神に無条件に帰依すれば、最高神は無条件にその帰依者に絶大な恩寵を授けるとされた。仏教徒たちは、この新しく魅力的で民衆宗教として成功を収めつつあるヒンドゥー教と競り合うようになった。
そこで、仏教徒たちは、すでにあったゴータマ・ブッダの全知者性の「全知」をむくむくと肥大化させ、片や、やはりすでにゴータマ・ブッダが説いていた「慈悲」(正確には「慈と悲」であるが、これについてはあとで触れる)を、仏の一大特性としてむくむくと肥大化させ、その両者を結び合わせるようになっていった。
そして、両者が完全に結び合ったさまをわれわれが見ることのできる最初の文献は、西暦紀元前二世紀の半ばに、ギリシア系のバクトリア王国の国王メナンドロス(インド訛りでミリンダ)が、仏教の学匠ナーガセーナ長老と対論を交わしたという歴史的な事実をもとに作成された『ミリンダ王の問い』(ミリンダ・パンハ)という仏典である。
この『ミリンダ王の問い』では、①釈迦が(ヒンドゥーの絶対神のように)全知全能であるなら、その弟子のデーヴァダッタは、出家すればサンガを分裂させる(破僧伽)という大罪を犯して地獄に落ちることを予知していたのにもかかわらず、その出家を認めた残酷な人物であることになり、②逆に残酷な人物でないならば全知者ではないことになるという矛盾に関する問答である。そして、これに対するミリンダ王への回答の内容を紹介しながら、宮元啓一氏は、これは「オウム真理教の「ポア思想」なる殺人肯定理論の原型」ともいうべきものであるとしている。
「大王よ、それと同様に、如来は人々の利益のために(かれらを)打ち、人々の利益のために(かれらを)落とし、人々の利益のために(かれらを)殺すこともするのです。大王よ、如来は人々を打ったのちにもかれらに利益を付与し、落としたのちにも人々に利益を付与し、殺したのちにも利益を付与するのです」(同、五ページ)
そしてナーガセーナ長老は、結論へと向かってつぎのようにいう。
「大王よ、もしもデーヴァダッタが出家しなかったならば、在家の身分のままで地獄(の果)を招く多くの悪業をなして、幾百兆劫もの間、地獄から地獄へ、破滅の所から破滅の所へと行きつつ、多くの苦しみをうけるでありましょう。尊き師はそのことを知りつつ慈悲をたれて、デーヴァダッタを出家させたのです。『わが教えに従って出家したならば、(かれの)苦しみは終りをつげるであろう』と(言って)慈悲をたれて、重い苦しみを軽くしたのです」(同、五~六ページ)
賢明な読者諸氏はもう気がつかれたであろう。ナーガセーナ長老がいっていることは、二千年以上の時を超えて、オウム真理教という大量殺人教団がいってきたことと、まったく同じ理屈なのである。それはもう恐ろしいほどである。念のために、右のナーガセーナ長老のことばを、ほんの少し変えてみよう。
「信者諸君、もしも地下鉄の乗客たちがサリンで殺されて転生(ポア)しなかったならば、今の状態のままで地獄という果を招く多くの悪業をなして、幾百兆劫もの間、地獄から地獄へ、破滅の所から破滅の所へと行きつつ、多くの苦しみを受けるでありましょう。尊き師(麻原彰晃)はそのことを知りつつ慈悲をたれて、地下鉄の乗客たちをサリンで殺して転生させたのです。『わが願いによってサリンで殺されたならば、地下鉄の乗客たちの苦しみは終わりを告げるであろう』といって慈悲をたれて、重い苦しみを軽くしたのです」
地下鉄サリン事件をはじめとする、オウム真理教による一連の恐るべき殺人事件は、まさに、ナーガセーナ長老の仏教によって正当化されるのである。このように、肥大化した「全知」と肥大化した「慈悲」とが合体すると、何もかもが正当化される。残虐な連続大量殺人も正当化される。
これは、じつは、ナーガセーナ長老の仏教だけのことではなく、大乗仏教、密教にも共通する根本思想である。心を清澄にするための苦行系の修行のひとつであったという本来のありかたから切り離された「慈悲」を、「全知者」がたれるという図式は、右のようなことまでも完全に正当化してしまうのである。
わたくしは、一九九七年刊行の拙著『インド死者の書』(鈴木出版)の最後の付章において、ヒンドゥー教や仏教を引き合いに出しつつ、救済主義思想と自己責任思想とを対比させ、救済主義思想を付帯的なものとし、自己責任思想を中心に据える知恵が、今こそ、つまり二度と再び地下鉄サリン事件を引き起こす宗教団体を出現させないために必要となるのではないかと論じた。
オウム真理教は仏教ではないという僧侶や仏教学者が多いようであるが、それは間違いである。オウム真理教は、(ナーガセーナの)仏教の、そしてもちろん大乗仏教、密教の、鬼子ではあるとはいえ、れっきとした子供なのである。こう見てくればくるほど、慈悲や全知者の問題だけにかぎっても、最初期の仏教、ゴータマ・ブッダの仏教が何であったのかを、できるだけ正確に理解する必要性が、ますます増してくるのである。
こうして、仏教勢力が、全知全能の神を打ち出して民衆の人気を集めていたヒンドゥー教に対抗するために、いたずらに釈迦牟尼を神格化したり、殺生を行っていた民衆に迎合したりしていった結果として、釈迦牟尼の本来の不殺生の教えが無視され、殺生を肯定する「仏説」が新たに作り出されていったことが考えられる。
これを踏まえれば、麻原・オウム真理教の思想の反省・総括とともに、他宗教その他の影響を受けて変質した仏教の歴史をよく認識して、戦争の撲滅が叫ばれる現代人類社会の潮流にも合わせて、あらためて仏教を浄化し、その本来の釈迦の思想、非暴力・不殺生に立ち戻ることが重要であると思われる。
なお、このような変質が起こった最初の時期としては、このミリンダ王が紀元前2世紀後半にアフガニスタン・インド北部を支配したギリシャ人であるインド・グリーク朝の王であることから、釈迦よりも4世紀ほど後以降であると推察できる(なお、この『ミリンダ王の問い』という経典は、タイ・スリランカ系の経典には収録されていない(外典扱い)。ミャンマー(ビルマ)系には収録されている)。
4.後期密教の時代にも、仏教の一部が殺生を肯定するように変質した経緯
さらに、この後に成立した経典においても、ヒンドゥー教に対抗して仏教の一部が殺生を肯定するものがある。その一つは、インドの後期密教に分類される経典である。その背景としては、インドの下層階級を仏教の信者に取り込もうとする中で、彼らの呪詛などの殺生肯定の文化の影響を受けたというものである。
そして、インド後期密教の中には、麻原・オウム真理教が利用した「秘密集会タントラ」などに収められている「五仏の法則」の「アクショーブヤの法則」がある。この点に関して、仏教学者の松長有慶氏は、その著書『秘密集会タントラ和訳』(法蔵館)において、その法則を経典から引用して「虚空界の中央に、仏曼荼羅を観想すべし。阿閦金剛を観想して、その手に金剛杵をもつと思え。(中略)これら秘密金剛によって、一切衆生を殺すべし。〔殺された〕このような者たちは、かの阿閦の仏国土において仏子となるであろう。」と紹介した上で、以下のように述べている。
(秘密集会タントラは)さらにまたインドのカースト制度の中では最も下賤な者と見做されたスードラ階級の人たちこそ、解脱するのに最も適わしい人と規定し、インド人社会の伝統的な階級制度に真っ向から反撃を加える。
このような既成の秩序に対する挑戦的な姿勢は、仏教の伝統的な戒律に対する全面的な否認としてもあらわれている。出家者として、あるいは仏教徒として守るべき五戒、十善もことごとく弊履のごとく捨て去られる。それらにかわって、殺、淫、盗などの行為が、解脱への早道として、行者に勧められているのである。
仏教やジャイナ教において、不殺生の戒は厳重である。ところがタントラ聖典において、殺生に対する肯定の思想が顕著に認められる。『秘密集会タントラ』においても例外ではない。とくにその後半部の忿怒尊に関連した観法において、殺生の禁の容認というよりも、それを奨励する記述が目につく。
それらはもともとインド古代社会において民衆の間で行われていた習俗的な攘災作法とか、行者が執行していた呪法を、そのまま仏教の中にもちこんだものである。古くから人々はわが身にふりかかる天災、病気、横死などの不幸は、精霊や鬼神のもたらすものと信じていた。それらの怨霊や悪鬼を除去し、また消滅させるための呪法は、ヴェーダの時代から広く行われ、仏教教団や信者の中に次第にそれらが取り入れられた。
「秘密集会タントラ」においても、これら攘災の呪法は大幅に摂取されている。そしてこれらの呪法は、忿怒尊およびそれらを統括する阿閦如来の所轄事項と見做されることになった。ただし原始的な呪法を、仏教タントラに採用したとき、それらをもともとの呪法のまま利用する場合と、それらの呪法に思想的な意味づけを行い、呪法を仏教化ないし内面化する場合とがある。
『秘密集会タントラ』においても、たとえば人を呪い殺す原始的な呪詛法に仏教的な意味を付加することがある。その場合、いかなる方法によっても仏教に信を向けない人を、一旦殺害することによって阿閦の仏国土に往生させ、仏教の信者とするといった会通も行われている(第九分第6偈)。(中略)
『秘密集会タントラ」が、殺や性といった近代社会の倫理からはタブー視され、また仏教の戒律によって厳しく禁じられている行為をあえて真正面から取り上げたのには理由がある。バラモンの権威を痛烈に否認していることからも知られるように、社会の底辺にいる人々を、仏教信者に取りこむために、かれらが日常的に行っている生活習慣や儀礼あるいは呪法を摂取して、それらに仏教的な意味づけを施す目的があった。タントラ聖典が対象とする人たちは、知的水準の高い上層階級ではなかった。タントラ聖典に用いられている言語が古典サンスクリット語を逸脱し、その中に俗語が多く含まれているのも、このような担い手の文化水準を反映したものといえる。
中島尚志氏(四天王寺国際仏教大学教授・元裁判官〉も、その著書『オウムはなぜ消滅しないのか』(グッドブックス)において、以下のように述べている(p154-155より抜粋)。
『秘密集会タントラ』のうち、少なくとも殺人を容認し、その実行を勧めている箇所は、誤りであると断定する必要がある。なぜなら、殺人が「いかり」という根本煩悩の一態様であるとしても、このタントラの教えは、殺人を人間の根本的な働きである「生き抜こうとする力」、「生きる」という働きよりも上位に置こうとしているからである。特に、同経典が仏教を強制する手段として殺人という方法を提言していることは、反仏教的でさえある。(中略) 現実に、この経典がインドでどの程度、修行者たちによって受け入れられたのか、その研究がなされている。その研究によれば、殺人と窃盗は、宗教的な儀礼がほとんど描かれておらず、現実には、修行者たちに受け入れられ、実行されていた報告はない。宗教的な儀礼の痕跡も発見できていないのである(高島淳ほかの論文)。
なお、ここで中島尚志氏が、殺人を怒りと結びつけている点は、重要である。密教経典では、殺人肯定の教えは「アクショーブヤ(阿閦如来)の法則」と呼ばれていることは前に述べた通りであるが、本来のアクショーブヤ仏(阿閦如来)の本質的な特徴としてよく知られていることは、同仏が別名として不瞋恚仏ともいわれるように、瞋恚=怒りを根絶した仏であることだ。
仏教では、怒りの延長上に殺生があるととらえるが、本来の阿閦如来の位置づけとは、怒りと殺生の対極的な存在であったのである。その意味で殺生を肯定する思想は、中島氏が言う通り、反仏教的=反釈迦の思想であるとともに、本来の阿閦如来の思想にも反したものである。
そして、この阿閦如来は、秘密集会タントラ(梵語ではグヒャサマジャタントラ)に加えて、それに続いて発生した主な後期密教経典であるヘーヴァジュラ・タントラ(呼金剛タントラ・喜金剛タントラ)や、後に述べるカーラチャクラタントラ(時輪タントラ)においても、その経典の主尊・中尊は、阿閦如来の化身とされており、すなわち、後期密教においては、仏の中の最上位の尊格(本初仏)の地位にあるため、この仏の解釈に関して生じた変質には特に注意する必要があり、その解釈を再浄化し、本来の解釈に立ち戻る必要がある。
なお、これらの後期密教の思想を継承しているチベット密教の伝統においては、例えば、以下のダライ・ラマ14世のように、「アクショーブヤの法則」について、殺生を肯定するものとして文字通り解釈することを厳に否定している(ダライ・ラマ十四世著『宇宙のダルマ』より)
また大乗仏教を含む、仏教のさまざまな哲学学派の多様な説明を全体的に考察するには、様々な経典が、それぞれ了義(直接に真理を説いている経典)なのか、未了義(さらに解釈を必要とする経典)なのか、区別することが必要だということも分かってきます。(中略)ですから、結局は、論理に基づいて、その経典が了義か未了義か、自分で判断しなくてはなりません。このように、大乗仏教においては、論理が聖典より大事なのです。
ある特定の表現や経典が、未了義であるかどうかは、どのようにして決めればよいのでしょうか? 未了義の経典には、様々なタイプがあります。たとえば、ある経典には、自分の親を殺さなくてはならないと書かれています。このような経典の言葉を、文字通り、額面通りに理解するわけにはいきません。さらなる解釈が必要です。この場合、親とは、汚された(有漏の)行いと執着のことです。それらの結果として、輪廻の中に再生する、それ故、そのような汚された行為と執着を断て、という意味なのです。
同じような表現は、「秘密集会タントラ」のような密教経典の中にも見いだせます。そこでブッダは、「仏を殺せ、仏を殺せば、最高の悟りに到達できるだろう」と言っています。もちろん、このような教えを文字通りに受け取るわけにはいきません!
また、他にも、その伝統の中では、人の殺生は、死んだ者を生き返らせることができる者でなければ、やってはならないという表現をもって、死んだ者を生き返らせることができる人間など実際にいないため、禁じているものもあるという。
5.インド最後の仏教経典の時輪タントラに見られる聖戦・最終戦争思想
さて、インドで仏教が滅ぼされる直前に成立したインド仏教(後期密教)の最後の経典として、「時輪タントラ」があり、キリスト教(のヨハネ黙示録など)の最終戦争に似通った最終戦争の予言が説かれている。そして、ヨハネ黙示録とセットで、最終戦争を行うキリストを自任した麻原・オウム真理教によって利用された。
これもまた、時輪タントラに先立って成立した上記の後期密教経典の殺生肯定の思想が基盤となって形成されている可能性があるだろうが、それに加えて、何といっても、イスラム勢力によって仏教が滅ぼされる可能性が出てきた時代背景が反映されていると思われる。実際に時輪経典が予言した通り、経典成立後に、イスラム勢力によってインド仏教は滅びることになった。
そして、時輪経典は、一度滅ぼされた仏教が、将来において、シャンバラという仏教の理想郷の王がやってきて、仏敵を滅ぼす最終戦争を行い、仏教を復興させるという予言を説いているのである。キリスト教のヨハネ黙示録と同じように、弾圧されたキリスト教徒が反撃して、理想の世界を作るというものである(一種のリベンジ・ルサンチマン(復讐)の思想と解釈する識者もいる)。
しかし、時輪経典の正式な解釈書である『ヴィマラプラバー』(シャンバラのカルキ・プンダリーカ王の著作とされる「時輪タントラ」の大註釈)においては、下記の通り、きちんと殺生・戦争を否定する解釈がなされている(以下、『超密教時輪タントラ』(田中公明著・東方出版)p86より抜粋)
そして最終戦争に関しても『ヴィマラプラバー』の後半部分では、異教徒とは実は煩悩のことであり、戦争で異教徒を滅ぼすというのは、煩悩を退治することであるなどと、宗教的に昇華された解釈が好んで示されるようになる。
なお、田中公明氏によれば、経典が説く(煩悩との戦いと解釈すべき)最終戦争の時期とは、経典から正しく計算するならば、麻原が説いた20世紀末ではなく、25世紀初頭であるという(以下、『超密教時輪タントラ』(田中公明著・東方出版)p81より抜粋)
ラウドラ・チャクリン王が即位するのは二三二七年、最終戦争が開始されるのは王の治世の末年すなわち二五世紀初頭ということになる。そして、ラウドラ・チャクリンが復興した仏教は、以後千八百年に亙って行われる。
また、そもそも、聖戦を行い、仏敵を滅ぼすという転輪聖王という概念自体が、初期の仏教経典とは全く反するものである。というのは、転輪聖王を説く初期仏教経典、すなわち、パーリ仏典の『転輪聖王獅子吼経』や『大善見王経』や、梵語の阿含経典の『長阿含経』(大正蔵1)の第6経「転輪聖王修行経」、『中阿含経』(大正蔵26)の第70経「転輪王経」では、転輪聖王は(軍隊を有しているという記載はあるが)、武力を用いずに統治することが、その大きな特徴とされている。
転輪聖王は、古代インドの伝記上の理想的帝王のこと。この王が世に現れるときには、天の車輪が出現し,王は、その先導のもとに、武力を用いずに全世界を平定するとされるところから,この名がある。サンスクリットのチャクラバルティンCakravartin、またはチャクラバルティラージャCakravartirājaの訳。実際,釈尊がその誕生のときに,出家すれば仏となり,俗世にあれば転輪聖王となるであろうとの予言を受けたというのは,よく知られた伝説である。(平凡社「改訂新版 世界大百科事典」)
統治の輪を転がす王の意。インドのジャイナ教徒,ヒンドゥー教徒,仏教徒の間で考えられていた武器を用いず正義だけで世界を統治する全世界の理想的帝王である。(ブリタニカ国際大百科事典)
また、転輪聖王が現れる時代についても、それは戦争がすでになくなった非常に良い時代であるとしている。大まかに言えば、以下の通り、大きな戦争があった後に、人類が反省して寿命が徐々に延びた後に、転輪聖王が現れるという。
釈迦は比丘たちに(中略)いにしえの転輪王たちの時代について話を始める。かつて法輪をはじめとする七宝を伴って天下を治めていたダルハネーミという名の転輪王、彼から代を経るごとに、善法は徐々に失われ、それに伴って人々の寿命も8万歳から10歳へと短くなり、人々は愚かになっていった。そして7日間にわたって大戦争が起こり、世界は破滅する。
しかし、暴力を拒み、森林や洞窟に隠れていた人々は生き残り、復興を始める。五戒を守り、三毒や非礼・不敬を抑え、善法を復興していくことで、この流れを戻していくことが可能になる。そして、寿命が8万歳に戻った時、地上の人間界であるジャンブディパ(閻浮提)は栄え、ヴァーラーナシーはケートゥマティと呼ばれて都となり、その王城にはサンカと呼ばれる転輪王が現れ、彼が治める時代には、マイトレーヤ(弥勒)という名の如来が現れ、無上の梵行が成就される。(ウィキペディア「転輪聖王獅子吼経」)
その後、人間の徳は回復し、再び8万年の寿命がある繁栄の時代を迎える。転輪聖王が出るのはこの繁栄の時代であり、彼は前世における善行の結果転輪聖王として現れる。仏陀と同じ32の瑞相を持ち、4つの海に至るまでの大地を、武力を用いる事無く、法の力を以って統治する。(ウィキペディア「転輪聖王」)
こうして見ると、時輪経典の聖戦・最終戦争を行う転輪聖王の概念は、すでに述べたとおり、釈迦の死後に生じたヒンドゥー教に対抗するための仏教の変質や、キリスト教からの影響を受けたことによる変質、さらには、イスラム勢力の攻撃を受け始めていた時輪経典の成立時の逼迫した時代背景によって変質したものだと思われる。よって、時輪経典による仏教思想の変質にもよく注意し、それを再浄化して、本来の釈迦の思想に立ち戻ることが重要である。
その一方で、時輪経典のシャンバラと仏教復興の予言と、現実の人類社会の動きが重なる点もある。それはカースト制度を否定する平等主義に関してである。時輪経典では、仏教の復興をもたらすシャンバラにおいては、その王によってカーストが統一・解消されていると説かれている。
そして、実際に、インドが1947年に独立した後に、時輪経典が予言する通り、インドで仏教が復興するに至ったが、それは、カースト制度に反対する最下層の不可触民などが、開祖釈迦牟尼以来、カーストを否定した仏教に集団改宗したことによるものであった。
そのリーダーは、不可触民でインド独立と共に法務大臣となり、インドの独立憲法の草案者としてインド憲法の父とされるアンベードカル。信教の自由・封建遺制の禁止・被差別カーストへの支援を規定し、女性の地位向上にも努め、カースト解消に不徹底なガンディーやイスラム教の風習にも批判的であった。
彼は、1950年の世界仏教徒連盟の創立総会への参加をきっかけに、以前から興味のあった仏教への関心を深め、1954年にインド仏教徒協会を創設、1956年に仏教徒となると、続いて50万人もの不可触民が仏教へ改宗し、新仏教運動へのきっかけとなった。1953年には「アジアは西洋よりもすでに重要性を増しつつあるが、仏教の精神が広まらなければ、アジアにおいても西欧と同じ争いが繰り返されるだろう。」と発言して、反カースト・平等主義の仏教の精神が、争い・戦争の回避に必要と主張した。そして、このインド仏教復興運動は、現在、日本人の佐々井秀嶺氏が主導者となっている。
-----------------------------------------------------------------------------
付記1:仏教経典の予見と現代社会の動向から探る未来の仏教の復興の可能性
仏教経典の予見と現代社会の動向をあわせて未来の仏教の復興の可能性について考えてみたい。
第一に、人類の「長寿」化に伴う仏教思想の復興である。これは、転輪聖王獅子吼経の予言である。一般的に言っても、長寿を通していろいろな経験をするほど、際限のない煩悩・我欲の追求がむしろ苦しみをもたらし、空しいものであるという釈迦の思想は、体験的に理解しやすくなるだろう。そして、実際に、近年の長寿先進国社会の超高齢者に「老年的超越」という仏教的な悟りの境地と極めて似通った心理状態が高齢者人口の数パーセント(広く見れば2割)に現れ始めている事実がある。よって、転輪聖王獅子吼経の予見は実現しつつあるともいうことができるかもしれない。
また、仏教的なライフスタイルは健康長寿をもたらすから、長寿時代には、それがより求められる可能性があるのではないだろうか。実際に仏教僧が長生きであることは、学術的にも確認されており、奈良から明治までの仏教僧と公家・大名のそれぞれ数千人の平均寿命を調べた調査では、仏教僧が20歳も上回っていたという(仏教僧約70歳、公家・大名約50歳)。
なお、現代的な解釈においては、転輪聖王の時代とは、現代の民主国家では、王=政権・行政等であり、例えば、絶対者を信じる宗教という形ではなく、心理療法や自己開発という形態をとった仏法が医療や教育に導入されて広まる時代と解釈できるかもしれない。
第二に、心理学の発達にともなう仏教思想の復興である。これに関する現在の現象としては、例えば、うつ病の治療やストレスリダクション等の手段として、禅瞑想に由来するマインドフルネス瞑想が、大企業などでも採用されるなど、非常によく知られるようになった(マインドフルネスは仏教の「念」(梵語のサティ)の英訳)。マインドフルネスは米国の医師(ジョン・ガバット・ジン)によるものだが、欧米の心理学者・医学者が仏教・ヨーガの思想に傾倒するのは、稀代の心理学者カール・ユングの事例がよく知られている。また、心理学の4大潮流といわれる中で最も新しいトランス・パーソナル心理学に関しては、ケン・ウィルバーなど、禅やチベット密教の瞑想に傾倒した者を始め、仏教・ヨーガなどの東洋の自我超越の思想の影響を深く受けている。
これは、釈迦とその教えの本来の性質が、煩悩をさまざまな苦しみをもたらす心の病とし、仏教の教え=ダルマをその病を治す治療法・薬とし、釈迦が病気に応じて薬を与える応病予薬の医師・心理療法士であったことを確認する現象であろう。仏教と心理学・医学の融合である。なお、この釈迦の医師としての性質が反映された大乗仏教の尊格が、医薬の仏とされる薬師如来であると思われる。この点を強調して表現すれば、仏教は、絶対者を崇拝する宗教ではなく、煩悩という心の病に対する医療であるということだ。
さらに、時輪経典も、仏教の復興は、仏教の理想郷のシャンバラが人類社会と邂逅する形で生じると説くが、そのシャンバラでは、心理学等の科学が悟りを助けているとされていることにも通じるものだ。
第三に、平等主義・反差別・民主主義の広がりにともなう仏教の復興である。現代の人類社会は、平等主義・反差別の強い国際的な潮流があり、人種・階級・性・民族などのさまざまな差別が批判されている。そして、インドでは、釈迦がバラモン教のカースト制度を否定したことに端を発し、仏教とヒンドゥー教の間で、その釈迦の評価、シャンバラとそのカルキ王の解釈などに関する大きな相違点にもつながった。
そうした中で、現実に1930年以降、インドにおいて、アンべードカルなどの反カースト運動として(中世に滅亡した)仏教がインドで復興するに至った。このインドでの仏教の復興は、中世のインドでイスラム勢力の侵入を受けて仏教が滅亡する前に、その滅亡と将来の復興を予言した時輪経典の予言の一部が、すでに成就したとも解釈できるかもしれない。
今後の見通しとしても、インドが近代化・経済発展するにつれて海外との交流は深まり、内外から差別解消・人権意識の要求が強まり、すでに国内外から批判されているインドのカースト制度は緩和されていくのではないか。そして、この流れは、インドでの反カースト運動の旗手である新インド仏教(インド仏教復興運動)に追い風となるのではないだろうか。現在、インド仏教は、人口の0.8%とか、900万人程度とされているが、一説には2000万人という説もあり、現在のインド仏教復興運動の指導者である佐々井秀嶺氏(日本人・真言宗智山派)は1億人と主張している。
また、今後仮に中国が民主化されることがあれば、今でさえすでに同国は世界最大の仏教人口を有するので、インドと共に、仏教復興の流れが生まれるかもしれない。その際は、インドの仏教復興運動を、今日本人僧侶の佐々井氏が主導しているように、中国の仏教の復興を日本が助力する可能性もあるかもしれない。佐々井氏が所属する真言宗の開祖・弘法大師空海が、中国で真言宗を学んだ際の師の恵果は「私の教えは東の国で広まる」と話したという。
そして現に、近年の中国では、仏教ブームが起きつつある。かつて仏教は、共産党によって弾圧されていたが、近年、激しい経済競争の中で疲弊した人々の救いになっており、若者やエリート層の中で、仏教を信仰したり、寺院めぐりを行ったりする人が増えているという。そのことは、日本のNHKが報道しているばかりでなく、中国の人民日報までもが報じている。
共産党政府は、行き過ぎた経済競争や拝金主義で荒廃する民心を安定させるために、体制に影響のない範囲内で、「安定と調和」をもたらす仏教(ならびに儒教などの)古来の宗教・思想を部分的に容認、奨励しつつある模様である(なお、共産党政府が、仏教だけでなく、かつて弾圧した儒教の復興を後押ししていることもNHKによって報じられている。「他人を思いやる」「利得にとらわれない」ことを重要視する儒教にこそ、中国人の心の原点があるとしている)。
最後に、仏教の復興とシンクロする他のキーワードを検討すると、「水」や「東」が出てくるように思う。まず、これまでの仏教復興とシンクロする現象と思われる①人類の長寿化、②科学の発展、③平等主義(反差別)というトレンドは、現代社会の特徴ではあるが、同時に占星学が説く人類の未来の黄金時代である「水瓶座の新時代」(アクエリアン・ニューエージ)の性質と共通している。というのは、占星学においては、水瓶座の支配星である土星の特徴が、寿命・科学・大衆・民主主義・平等主義を含むからである。なお、水瓶座の時代の思想においても、水瓶座の水に注目して、水は、例えば「水平」などというように、平等という概念と関連性があると主張されることがある。
また、水瓶といえば、転輪聖王獅子吼経が説く、長寿の人類社会に現れる弥勒如来の象徴法具が、偶然にも水瓶である。また、弥勒菩薩は、地蔵菩薩と共に、阿閦如来の弟子・脇侍とされるが、その阿閦如来は、五智如来の中の一尊であって、五智如来に対応する地・水・火・風・空の五大(元素)の中では、水をシンボルとする仏とされる。
次に「東」に関していえば、これまで述べた「薬師如来」や「阿閦如来」は共に、東方に仏国土を持つとされる。一般的にも、今後の人類社会は、欧米の西洋から、経済発展等が著しい東洋・アジアに力点が移るといわれている。
そして、村山節(みさお)氏(歴史学者)が提唱した文明法則史観によれば、世界史の研究の結果として、800年ごとに人類文明は、東洋と西洋が入れ替わる形で興隆するという。そして21世紀からの800年は、東洋が興隆するサイクルとなり、これまでの800年は西洋が興隆した時代であり、欧米キリスト教国中心の時代であったという。
これと符合するかのように、約800年前の13世紀初頭に、インド仏教がイスラム教の侵入で滅びたとされる一方で、日本においては、鎌倉時代と共に鎌倉新仏教が始まったが、その中では、キリスト教の影響を受けた仏教と考えられる阿弥陀念仏の信仰が爆発的に広まった。これが、仏をキリスト教の絶対神のように位置づけ、それを信じて来世の幸福を願う信仰であることは、すでに述べた通りである。
話を21世紀の東洋地域の興隆に戻すと、今後、一般的な意味で、人類社会の中の東洋諸国の地位が高まるにともない、仏教・ヒンドゥー教・儒教・道教といった東洋の思想への注目が高まる可能性があるのではないかと思われる。欧米諸国のキリスト教がかつてそうだったように、どのような時代も、経済的・社会的に発展した国や地域の宗教・文化は、世界の関心を集めると思われる。
その中で、特に、仏教・ヒンドゥー教の発祥地のインドは、今年の状況では、世界で最も経済成長している地域とされており、2050年までには米国をGDPで追い抜き、ゆくゆく世界最大の経済大国となることが一般にも予想されている。そして、欧米で初めてヴェーダーンタの教えを広めたインド人のヨーガ指導者であるヴィヴェーカーナンダは、インドの精神的な復興に先立って、その社会的な復興が起こると予見した。
さらに、近年著しい経済成長を遂げており、間もなく米国をGDPで追い抜くともいわれる中国では、仏教ブームが始まっている。こうして、インドと中国が、遠くない将来に、米国を抜いた世界第一位と第二位の経済大国になり、さらに、上座部仏教を国教とする東南アジア諸国も高い経済成長を続けている。仏教・ヒンドゥー教・ヨーガの思想を持つ東洋地域が、世界経済の中心となる日が遠くない現実がある。
そして、インド、中国、東南アジアについて述べてきたが、長寿・科学・平等・水・東洋・東方といったキーワードを追っていくと出てくるのが、意外かもしれないが、我が国日本である。
まず、長寿・科学・平等性というキーワードに関しても、日本は、まさに、①世界最高長寿国(の一つ)であり(女性の平均寿命は世界一)、②アジアの中で最も先に科学が発達した国であって、③縄文時代から平等性の高い文化を持つ。
その平等性の高い文化は、古く縄文時代の環状列石・環状集落から、十七条憲法の第10条の「耳の環(輪)」の譬えに至るまで、輪という言葉で象徴されてきた。この平等主義的な人間観は、優劣の差別、善悪二元論の世界観が正当化しやすい暴力・殺生・戦争行為を否定する土台となり、十七条憲法の第1条における「和をもって貴しとなす」という教えにつながる。
そして、この和とは、平和・和議・講和といわれるように、戦争をやめる・しないという意味である。すなわち、暴力・戦争の否定である。また、和には、二つのものを一つに調和させるという意味もある。この日本の和の文化は、宗教において、民族宗教の神道と外来宗教の仏教を融合し、神仏習合という文化を育む結果となった。
人間の歴史では、前に述べたように、その民族を特別視する宗教が戦争を可能にする(引き起こす)面があり、宗教の相違・対立が戦争の原因となることが少なくない中で、神仏習合の日本の文化は、人類の戦争からの脱却のための貴重な先例となる文化ではないか。二つの宗教を融合することに成功した民族は、他の民族には類を見ず、日本の大きな財産と思われる。
そして、実際に日本列島では、縄文時代の1万数千年の間、さらに、近世の江戸時代の260年の間、他の地域・他の民族に見られないほど長きに渡る戦争のない時代を実現した。さらには、日本の王室は、他のいかなる民族とも異なり、少なくとも千数百年の長きにわたって同じ皇室・王室(天皇家)を維持している。中国などは、政体が変わるたびに、前体制の王室は滅ぼされているし、イギリスの王室も数百年の歴史しかない。
これは、日本の天皇の氏族が、権力を独占・独裁せずに、自らは宗教的な権威にとどまって、政治権力は、時の実力者(貴族や武士)に割譲してきたことなどが背景にあるといわれる。平等性の高い統治が戦争を回避する一例であろう。このように見るならば、我が国は、まさにその国名である「大和=大いなる和」の名の通りであるということができないだろうか。名は体を表すである。
さらに、水や東のキーワードから見ても、日本は、東の端にある極東の国であると認識されている。仏教も、インドから東へ広がって、その東端が日本であった。また、日本は、水に囲まれた海洋国家・島国である。また、一般に、龍神は水の神とされるが、日本は、その地形から、「極東の龍」と呼ばれることもある。
そして、先ほど紹介した村山節氏の文明法則史観の研究をさらに進めた千賀一生氏は、800年周期で東西の間で交代する文明の興隆と衰退にともない、世界の中心となる都市も交代するが、世界中心都市が位置する経度を調べてみると、800年周期で、かなり規則的な動きを持って変化していることを発見したという。
その規則から推測すると、過去800年間は大英帝国の首都のロンドン(およびそれに準ずるのがアメリカ合衆国のニューヨーク)であったが、今後の800年間は、日本列島を通る経度の位置に世界の文明の中心が生じるという計算になるという。具体的には、日本の明石・淡路島(やオーストラリアなど)を通る東経135度線上(日本時間の設定地点)に来るという。ただし、同じく研究者の中矢伸一氏によると、過去の各時代の世界中心都市の位置を厳密に調べてみると、千賀氏が発見した規則性には、経度において数度の誤差があり、厳密に135度線ではなく、西日本全体に及ぶ経度の範囲となる可能性があるという。
一般には、少子高齢化・人口減少・経済の低成長の日本は、他の東洋諸国に比較しても、老いた国であり、衰退傾向であると思われることがある。しかし、この傾向は、長期的に見れば、世界全体の人口がほどなくピークに至るとされるなど、日本に限らぬ世界全体の傾向であり、世界の日本化(ジャパニフィケーション)が生じるという指摘もある。
その中で、昨年あたりから、不透明感を増す中国ではなく、安定した日本の株式市場に世界の投資資金が入り出している。さらに、新型コロナ後において、世界の中で日本が観光したい国の筆頭になるという調査結果が出ており、来日する観光客が急速に増えている状況があり、欧米からの観光客を中心に、日本の伝統宗教文化の地を観光する人達が増えているが、その中に高野山や出羽山などで、体験修行をする外国人も増えているという。こうして、今後の日本が持つ、ユニークな経済的・社会的・文化的・宗教的な可能性については、あらためて論じたいと思う。
-----------------------------------------------------------------------------
付記2:麻原・オウムが説いた時輪経典・シャンバラの教義と伝統仏教の教義の大きな相違点・矛盾
シャンバラは、『時輪タントラ』に説かれる伝説上の仏教王国であり、同タントラではシャンバラの位置はシーター河の北岸とされ、シーター河が何を指すかについては諸説あるが、中央アジアのどこかと想定される。シャンバラ伝説は『時輪タントラ』とともにチベットに伝わり、モンゴルなど内陸アジアのチベット仏教圏に広く伝播した。
ところが、シャンバラは、元はインドのヒンドゥー教のプラーナ文献に登場する理想郷(ユートピア)であった。ヒンドゥー教のヴィシュヌ派は、釈迦をヴィシュヌ神の化身の1つとするが、釈迦のカースト制度批判によって揺らいでしまった社会秩序を正し、カースト制度を立て直すために10番目のアヴァターラとしてカルキが出現すると説いた。シャンバラとは、カルキの治める国の名であった。
しかしながら、その後、時輪経典で説かれた仏教のシャンバラ伝説は、このヒンドゥー教のシャンバラ解釈とは真逆のものとなった。『時輪タントラ』とその註釈書『ヴィマラプラバー』(無垢光)は、シャンバラ王カルキは人民を仏教に教化して「金剛のカースト」という1つのカーストに統一し、カースト制度を解消させると説いたのである。すなわち、『時輪タントラ』は、ヒンドゥー教のカルキ説をシャンバラの王の名前としては取り入れつつも、これを批判してヒンドゥー教と真逆に、カーストを解消する存在と位置づけたのである。
そして、この仏教とヒンドゥー教におけるカーストにおける対立点などが、時輪経典の主尊である阿閦如来(阿閦金剛)と同体と見なされる降三世明王(ごうざんぜみょうおう=密教の五大明王の一尊)や、阿閦如来の化身とされる時輪金剛や妙喜金剛(へーヴァジュラ)といった仏が、シヴァ神を踏みつける姿で描かれている背景につながる。
この点に関して多少詳しく説明すると、日本の仏教(主に真言宗と天台宗)では、五智如来の化身とされる五大明王があり、その中の東方に位置する「降三世明王」を阿閦如来の化身とするが、この降三世明王の「降三世」は、サンスクリット語でトライローキャ・ヴィジャヤ(三界の勝利者 Trailokyavijaya)という意味で、正確には「三千世界の支配者シヴァを倒した勝利者」という意味がある。
その起源の伝説としては、シヴァは妻のパールヴァティーと共に「過去・現在・未来の三つの世界を治める神」としてヒンドゥー教の最高神として崇拝されていたが、大日如来はヒンドゥー教世界を救うためにシヴァの改宗を求めるべく、配下の降三世明王を派遣し(あるいは大日如来自らが降三世明王に変化して直接出向いたとも伝えられる)、頑強難化のシヴァとパールヴァティーを遂に超力によって降伏し、仏教へと改宗させたというものである。すなわち、降三世明王の名は「三つの世界を治めたシヴァを下した明王」という意味なのであり、降三世明王の姿は、その両足で地に倒れた大自在天(シヴァ)と妻烏摩妃(パールヴァティー)を踏みつけているのが最大の特徴である。
なお、大黒天にも、以前解説したように、シヴァが改心した姿であるという解釈があるが、阿閦如来の化身の降三世明王は、シヴァを降伏して仏教へ改宗させたという伝説が、その名前自体の由来になっているほどに、明確・明瞭な存在である。こうして、インド後期密教の世界の中では、シヴァを改心させたのが阿閦如来の化身の降三世明王であり、降伏されて改宗したのが大黒天であるということである。
そして、この改宗を求める背景として、先ほど述べた通り、仏教とバラモン・ヒンドゥー教において、釈迦の時代から時輪経典の後期密教の時代まで一貫して続いた対立軸であるカーストの是非があることが理解できるだろう。
以上の点を踏まえるならば、麻原が説いた時輪経典およびシャンバラに関する教えは、その伝統的な仏教の教義を大きく歪め、内部矛盾の多いものになっていることがわかる。
その背景としては、カーストやシャンバラの解釈において、釈迦・時輪経典などの仏教と、ヒンドゥー教の教義の間には、実際には大きな対立があるにもかかわらず、麻原は、ヒンドゥー教の最高神であるシヴァ神をシヴァ大神として絶対神・最高神とし、釈迦や他の仏教の尊格をその下に置きながら、仏教の時輪経典やシャンバラに関する教えを説いたという矛盾がある。そのため、本来の仏教の教義とは異なって、対立する仏教とヒンドゥー教を混ぜ合わせ、ヒンドゥー教シヴァ派の立場の時輪経典・シャンバラの教えともいうべき独自の教義を説いているのである。
実際には、シャンバラの主尊の時輪金剛の本地である阿閦金剛の化身とされる降三世明王は、シヴァを降伏して仏教に改宗させた存在とされ、そのため、時輪金剛の歓喜仏などの仏画では、その足がシヴァやウマーパールヴァティーを踏みつけた姿が描かれている。よって、時輪経典や時輪経典が描くシャンバラは、シヴァを最高神とした世界では全くなく、シヴァを最高神とするヒンドゥー教の思想とは相いれないものである。
なお、麻原は、シャンバラの王をルドラ・チャクリンと呼んでいるが、この呼び名自体は一般的なものであって、麻原独自のものではないが、ヒンドゥー教においては、ルドラ神がシヴァ神と一体視されている面があるため、シャンバラの王がシヴァ神と関係するかのような誤解を呼ぶことになる。ルドラ・チャクリンは和訳すれば転輪聖王であり、梵語ではチャクラ・ヴァルティンであるので、本稿ではこちらを用いた。
また、麻原は、インドで仏教がイスラム教に滅ぼされた時に、仏教はヒンドゥー教の中に守られて、いわば「シヴァ仏教」として残されたと主張しているが、確かに仏教とヒンドゥー教の中にはライバル関係の中で混合していった部分はあるとしても、時輪経典にも見られるように、仏教はヒンドゥー教の最高神であるシヴァは明確に否定し、改宗させるべき対象としている。この点を見ても、シヴァ仏教なるものは現実にはありえないものであり、実際に、ヒンドゥー教のシヴァ(派)と仏教が融合した教義を説く仏教宗派は存在しないと思われる。
また、同じように、麻原はヒンドゥー教の教えに従って、聖戦を行うカルキを解釈しているが、ヒンドゥー教が説く釈迦のカースト否定による世の中の乱れをカースト制度を立て直して回復するとされる存在であり、仏教の時輪経典に登場するシャンバラの王のカルキは、名前は同じであっても、ヒンドゥー教のカルキとは真逆に、カースト制度を解消する存在である。
さらに、麻原は、真理の国を作るための聖戦を行うシャンバラの王のルドラ・チャクリンという解釈をしたが、前に述べた通り、仏教の正統な時輪経典の解釈としては、その聖戦は、実際の現実世界の戦争を予言したものではなく、煩悩との戦いを示すための比喩的な表現とする平和主義的な解釈であるという点も重要である。仏教の正統な時輪経典は、反戦・平和主義である(また、同じく前に述べた通り、経典が予言するその戦争の時期を計算するならば、時期も25世紀ごろの話であり、麻原が予言した20世紀末ではない)。
加えて、麻原は、時輪経典・シャンバラの主尊の阿閦金剛の仏国土である妙喜世界から転生してきたとされる維摩経の主人公である維摩居士を強く否定している。具体的には、維摩居士が、釈迦の出家した高弟達を法話において論破する点などに言及して、維摩を魔境であると強く否定しているのである。また、維摩経を重視して、それを講釈した聖徳太子に関しても、自分よりも下の存在だと位置づけている。そして、阿閦如来を自ら創建した高野山金剛峯寺の総本堂の金堂の本尊としたと伝承される弘法大師空海に関しても強く否定している。こうして、麻原の仏教指導者の解釈も伝統仏教と矛盾するものである。
----------------------------------------------------------------------------
付記3:カーラチャクラ経典とシャンバラに関して
『時輪タントラ』(カーラチャクラ・タントラ)は、インド仏教・後期密教の最後の教典である。無上瑜伽タントラの一つ。インド仏教を壊滅させたイスラム勢力の脅威に対抗するものとして11世紀に編纂された。釈迦の晩年の口伝を編纂したものという形式をとる。"Kāla"は「時間」を、"Cakra"は「輪」を意味し、「時輪」と漢訳している。修行法、暦学、天文学、インド仏教の衰退と復興の予言が説かれている。
修行法は、12種類の風(ルン、気)が説かれており、無上瑜伽の代表的な教典の一つである。六支瑜伽と呼ばれる六段階の修行法から成り、具体的には、抑制、禅定、止息、總持、憶念、三摩地から成る。本尊は、時輪金剛の歓喜仏(ヤブユム)。阿閦如来を本地とした守護尊(イダム)の「時輪金剛」が、『時輪タントラ』の本尊として男尊と女尊が抱き合った歓喜仏の姿で曼荼羅にも描かれる。
そして、その足下に、シヴァとその妃のウマー・パールヴァティーを踏みつけている。これは、時輪金剛の本地(本体)である阿閦如来の化身とされる降三世明王が、シヴァを降伏して仏教に改宗させる存在とされていることに通じるものである。これは、時輪経典が、当時仏教を滅ぼそうとしていたイスラム教と共に、仏教の教義が、ヒンドゥー教の教義とは、カースト制度を否定する点等を含めて異なることを明確にする意図があったと思われる。
末法時代の予言として、経典成立当時の政治社会情勢からイスラム勢力の侵攻によるインド仏教の崩壊が予見されていたため、時輪経典には、①イスラムの隆盛とインド仏教の崩壊、②インド仏教復興までの期間(末法時代)は密教によってのみ往来が可能とされる秘密の仏教国土・理想郷シャンバラの概念、③シャンバラの第32代の王となる転輪聖王(梵語でチャクラヴァルディン)、④転輪聖王による侵略者(イスラム教徒)への反撃、転輪聖王が最終戦争で悪の王とその支持者を破壊する予言、未来におけるインド仏教の復興、地上における秩序の回復、世界の調和と平和の到来、等が説かれた。また、暦法・天文学に関連して、"Kāla"は時間の意味であり、暦法や天文学も説かれている。チベット暦に影響を与えた。
なお、時輪経典の成立・出自についての伝統的な説としては、ダライ・ラマ14世によると、時輪タントラを含む四種のタントラは、業と感覚が純化され神秘的な状態に達した人々に、秘法という形で与えられたものであって、歴史上の釈迦が説いたかどうかは、さほど重要な問題ではないという。
そして、チベット仏教の信仰上の位置づけでは、シャンバラの王スチャンドラが、シャンバラ内の96の国々の民の利益のため、インドを訪れ、釈迦から授けられた教えとされる。時輪タントラの教えは、以降の7人の王、22人のカルキ王を介して受け継がれてきたという。ブッダによって開始された時輪タントラの根本タントラを受け取った後、スチャンドラは時輪タントラの最初の注釈を書き上げた。一代目のカルキ王マンジュシュリー・キールティは要約したタントラを作り、彼の息子であり二代目カルキ王であるプンダリーカもまた解説書『無垢光(ヴィマラプラバー)』を著し、時輪タントラはシャンバラから広まることになった。
一方、インド人のカギュ派の祖師の一人ティローパは、時輪タントラを求めて、シャンバラを目指していたところ、文殊菩薩の化身が現れ、彼に時輪タントラの秘伝、経典、解説書、口伝を授けたという。カギュ派はその後、チベット人のマルパによって継承され、インドでは仏教が滅びたこともあって、時輪タントラの教えはチベットで広まることになった。
なお、シャンバラ王国の様子の描写としては、18世紀のゲルク派の学匠ロントゥル・ラマの『本初仏吉祥時輪の由来と名目』の説明によると、シャンバラには9億6千万の町があり、96の小王国がある。小王たちの上に立つシャンバラ王は王宮カラーパに住んでおり、そこから南の方角には立体型の大きな時輪曼荼羅がある。そしてシャンバラの人たちは寛容な法の下で健やかに暮らし、善行に勤しんでいるという。
そして、シャンバラは、阿閦如来の変化身である忿怒尊ヘーヴァジュラ仏(呼金剛仏、喜金剛仏)を本尊とするカーラ・チャクラで満ちているとされ、無上不動の信仰・智慧を得ることが説かれている。これに加えて、そもそもシャンバラは、阿閦如来が主尊の時輪経典が説く世界であることからも、シャンバラは、阿閦如来の世界ということになる。
なお、シャンバラは近代には西洋の神秘思想家らの関心を引き、欧米でも有名になった。H・P・ブラヴァツキーをはじめとする神智学者らは、シャンバラはゴビ砂漠にあったと主張した。神智学協会と関係していた平和運動家・画家のニコライ・リョーリフは、チベット国境に至るモンゴル遠征の体験記のなかでシャンバラについての自分の考えを発表し、欧米のシャンバラ解釈に影響を与えた。
なお、一つ特筆すべきは、現代においても、ダライ・ラマ14世によって、極めて多くの人々に対して、シャンバラを説く同経典のイニシエーションが行われていることである。ダライ・ラマ14世によると、これは今後未来において、人類社会がシャンバラと邂逅する時に備えるためだという。かつてインドでイスラム勢力に滅ぼされた仏教であるが、今現在チベットも、中国によるチベット侵攻以来、独立を失っており、危機に瀕している。その中で、仏教が衰退後に復興すると予言する時輪経典の布教に力を入れるのは、民族の期待が現れているのかもしれない。
しかしながら、時輪タントラが、解釈によっては、武力をもって仏教の悪しき敵対勢力を滅ぼすとも解釈できる点においては、その正統な解釈において、修正が加えられている。すなわち、その悪しき敵対勢力との戦いとは、現実世界での戦いを意味するのではなく、人の心の中の悪魔・煩悩との戦いであるとの解釈である。
そして、この点においては、ヨハネ黙示録の描く終末戦争とは、実際に未来に起こる救世主側と悪魔側の人類の最終戦争とは解釈しない今日の伝統キリスト教会の姿勢に通じるものがある。それは、終末戦争は、人の心の中の悪魔との戦いであるという解釈や、キリスト教会が弾圧を克服し、ローマ帝国の国教になった時点で、すでに終了した戦いであるといった解釈である。
-----------------------------------------------------------------------------
付記4:阿閦如来に関して
阿閦如来(あしゅくにょらい、梵: Akṣobhya, アクショーブヤ)は、大乗仏教の如来の一尊である。梵名のアクショーブヤとは、「揺れ動かない者」という意味で、意訳としては、無動(無動如来)、無瞋恚(不瞋恚仏)、無怒、不動などと訳される。同じ不動と訳される不動明王(アチャラナーター)は、揺ぎ無き守護者の意味があり、共通点がある。
阿閦如来は、後期密教において、無上瑜伽タントラの各経典の主尊と同一視されながら、曼荼羅において、中尊(中心の仏・尊格)とされて、阿閦金剛(あしゅくこんごう、梵: Akṣobhyavajra, アクショーブヤ・ヴァジュラ)の名で呼ばれる。なお、ヴァジュラは、この如来の悟りの境地が、金剛(ダイヤモンド)のように堅固であることを示す。
三昧耶形(象徴物)は、五鈷金剛杵(ヴァジュラ)である。これは、ひかりの輪で最も用いる法具である。種字はウーン(हूं [hūṃ]フーム)。真言は、オン・アキシュビヤ・ウン(オーム・アクショーブヤ・フーム)。密号は不動金。印相は、右手を手の甲を外側に向けて下げ、指先で地に触れる「触地印」(そくちいん、「降魔印:ごうまいん」とも)を結ぶ。これは、釈迦が悟りを求めて修行中に悪魔の誘惑を受けたが、これを退けたという伝説に由来するもので、煩悩に屈しない堅固な決意を示す。
阿閦如来の起源としては、東方の阿比羅提(あびらだい、アビラティ、妙喜・善快と訳す)という国に現れた大目(広目とも)如来のところで、無瞋恚・無婬欲の願を発し修行して、東方世界で成仏したといわれる。阿閦仏は、その国土で説法中であるとされ、東方に仏国土を持つ現在仏である。
阿閦金剛は、性タントラを導入した後期密教の始まりの経典であるグヒャサマジャタントラ(秘密集会経典)の主尊であり、青色の歓喜仏(ヤブユム)の姿で、タンカなどの美術品に描かれることが多い。そして、グヒャサマジャタントラの後も、へーヴァジラタントラ、カーラチャクラタントラといった代表的な後期密教経典の主尊と位置づけられた。
その憤怒系の変化身が、へーヴァジュラ(妙喜金剛)であり、後期密教の代表的な経典であるへーヴァジラタントラ(妙喜金剛経典)の主尊である。さらに阿閦金剛は、インド後期密教最後の経典であるカーラチャクラタントラ(時輪経典)の主尊でもあり、時輪経典では、時輪金剛(カーラチャクラヴァジュラ)といわれ、その男女が抱き合った姿(歓喜仏・ヤブユム)が知られている。
また、五大明王の一つの降三世明王も、阿閦如来の化身とされるが、この降三世明王とは、三界の支配者であるシヴァとその妃のウマー・パールヴァティーを降伏して、仏教に改宗させたという意味であり、シヴァを踏みつけた姿をしている。これは、時輪金剛も同様であり、仏教経典として、ヒンドゥー教に対する姿勢を示している。
日本と異なり、インド後期密教の流れを受け継ぐチベット仏教やネパールの仏教では、阿閦如来は単独で広く信仰され、造像例も多い。これは、前に述べたように、インド仏教の後期に主流となった後期密教では、忿怒形の護法尊が多数信仰されるようになり、最高位の仏(本初仏、勝初仏)が、大日如来から、法身普賢、金剛薩埵、持金剛仏等へと変化していったが、その中で、阿閦如来は、阿閦金剛として、無上瑜伽タントラの各経典の主尊と同一視されつつ、曼荼羅の中尊を担うようになったことが、その背景にある。
最後に、阿閦如来に関する仏教の解釈において、修正・浄化が必要と思われる点は、本稿ですでに論じたように、誤って解釈するならば殺生を肯定する思想とも解釈される「アクショーブヤの法則」である。この法則は、①専門家の研究によれば、釈迦後の仏教が、ヒンドゥー教などとの教勢拡大の中で、呪詛等の文化のあった下層民衆を取り込むために、不殺生を説いた釈迦の思想を歪めたものであり、その意味で破棄して本来の仏教の思想に立ち戻るべきであるし、②また、ダライ・ラマが論じるように、その教えの言葉を文字通りに受け取って解釈するべきものではなく(未了義)、正統な教えの比喩的な表現と解釈して、殺生を肯定する思想ではないと解釈すべきものであり、③理論的に言えば、宗教において、神が人間に対する生殺与奪の権能があるとされるのは、殺しても生き返らせることができる生殺与奪の能力があるからであって、「アクショーブヤの法則」に関しても、チベット密教の伝統的な解釈の中で、生き返らせる能力がある者でなければ行ってはならないなどと表現して、人による実行を禁じているように、これは、人間が行うことは許されないと解釈するべきである。
また、先ほど述べたように、阿閦如来は、無瞋恚・無婬欲の願を発して(=怒りと性欲を滅する発願をして)修行して成仏したとされ、別名不瞋恚・不動ともいわれるが、仏教では一般に瞋恚(怒り)が殺生の原因と解釈されることを見ても、瞋恚を滅した阿閦如来は、瞋恚と殺生を否定するものと解釈するべきである。
さらに、阿閦如来の浄土は東方妙喜世界とされるので、同じく東方の仏国土を有する東方浄瑠璃世界の教主である薬師瑠璃光如来(薬師如来)と同一視される場合があるが、この薬師如来は、健康長寿に加え、戦争などを鎮める仏とされており、この視点からも、阿閦如来は、本来殺生・戦争を否定する仏として解釈すべきである。
-----------------------------------------------------------------------------
※なお、以上の記事の内容を補足するものとして、以下の関連記事もご参照ください。
・【2】オウムの密教的な教えの総括と今後の思想・実践
・【3】オウム真理教のヨーガ行法の総括と今後の方針・実践
・【5】オウム真理教型ヨーガ行法・密教瞑想の問題・危険とその解決・改善(※2024年6月追記)