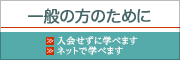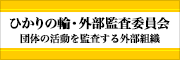四無量心の教え:基礎編
以下のテキストは、2016~17年年末年始特別教本『総合解説 四無量心と六つの完成』第1章として収録されているものです。
教本全体にご関心のある方はこちらをご覧ください。
1.四無量心とは何か
「四無量心」とは、仏陀や菩薩の心の在り方及び実践である。その意味で、仏教の思想と実践の最も重要なものの一つであり、仏道修行の基本であって、なおかつ究極の目的ということもできる。
まず、『岩波仏教辞典』(第二版、岩波書店)が解説する四無量心の意味を見て、その概略を理解しよう。
「四つのはかりしれない利他の心、慈、悲、喜、捨の四つをいい、これらの心を無量に
おこして、無量の人々を悟りに導くこと。」
2.四無量心の「無量」とは何か
こうして、四無量心とは、四つの無量の(=はかりしれない)利他の心である。では、「無量」とは、具体的にはどういう意味だろうか。
『分(ふん)別(べつ)論(ろん)註(ちゅう)』という仏教の経典解釈書によれば、
「無量とは、『対象となる衆生が無数であること』あるいは『対象とする個々の有情
(著者注:生き物)について(慈悲の心で)余すことなく完全に満たす』という遍満
無量の観点から、このように称する。」
とされている。(ウィキペディア「四無量心」より)
こうして、無量とは、利他の心の広さと深さに関係する。広さに関しては、その利他の心は、この世界・宇宙のすべての生き物=無数に広がっている。よく「すべての衆生(生き物)」と表現されるが、すべての生き物に及ぶ、広大無辺な利他の心である。
次に、深さに関しては、その利他の心は、個々の生き物を完全に幸福にするという意味を持つ。そして、大乗仏教の「菩薩道」という思想においては、これは、究極的には、すべての生き物を最高の幸福の境地である「仏陀の境地」に導くことを意味する。すなわち、すべての生き物を、ついには仏陀の状態にすることが、四無量心の利他の心の究極である。
3.慈・悲・喜・捨とは何か
それでは、慈・悲・喜・捨とは何か。その原語を含め、いつくかの文献から引用する。
「「慈」とは生けるものに楽を与えること、
「悲」とは苦を抜くこと、
「喜」とは他者の楽をねたまないこと、
「捨」とは好き嫌いによって差別しないことである。」
(『岩波仏教辞典』(第二版・岩波書店)より)
「慈無量心(サンスクリット語:マイトリー, パーリ語:メッター)
-「慈しみ」、相手の幸福を望む心。
悲無量心(サンスクリット,パーリ語: カルナー)
-「憐れみ」、苦しみを除いてあげたいと思う心。
喜無量心(サンスクリット,パーリ語: ムディター)
-「喜び」、相手の幸福を共に喜ぶ心。
捨無量心(サンスクリット語: ウペクシャー パーリ語: ウペッカー)
-「平静」、相手に対する平静で落ち着いた心。動揺しない落ち着いた心を指す。」
(ウィキペディア「四無量心」より)
それでは、次に慈・悲・喜・捨のそれぞれに関して、より具体的に解説をする。
4.慈・悲・喜・捨の、より具体的な解説
「慈(マイトリー)」とは、他の幸福を願う心であり、他に楽を与える行為である。こうして、四無量心とは、心の持ち方と、行為・実践の双方を含んでいる。
「悲(カルナー)」とは、他の苦しみを悲しむ心であり、他の苦しみを取り除く行為である。「悲」といっても、自分の苦しみを悲しむのではなく、他の苦しみを悲しむ意味である。
「喜(ムディター)」とは、他の幸福をねたまずに、共に喜ぶことである。そして、行為としては、他の幸福の源である他の善行を称賛する、見習うことなどが含まれる。
「捨(ウペクシャー)」の意味としては、いろいろな表現があるが、まとめれば、「平静で平等な心」ということができる。「平静」とは、苦楽に一喜一憂せず、心の沈みと心の浮つきの双方を離れた、落ち着いた平らかな心の状態を意味する。また、「平等な心」とは、他者に対して、好き嫌い・差別を超えて、皆を等しく利する心である。
なお、「捨」には、無関心という意味もある。これは、自分の苦しみや自分を苦しめる他の悪行(あくぎょう)に、無関心・怒らないという意味である。自分の苦楽に一喜一憂しない、平静な心の中核として、自分の苦しみや、それをもたらす他の悪行に無関心・怒らないという心の状態があるということである。
よって、これは、他の苦しみに対して、無関心・無頓着という意味ではない。仮にそうであれば、他の苦しみを悲しむ「悲」の心と矛盾する。他の苦しみに対する無関心を含めた、単なる無関心は「無智捨」と呼び、「捨無量心」とは似て非なるものとする経典もある。
こうして見ると、「喜」が、他の善行を称賛することである一方で、「捨」は、他の悪行を怒らないことである。よって、四無量心の一つの解釈として、四無量心とは、他に楽を与え、他の苦を取り除き、他の善行を称賛し、他の悪行に怒らないことと解釈することもできる。実際に、同じインドで発祥し、仏教の母胎となったヨーガの経典は、そのように表現している。
5.仏教の伝統における四無量心の位置づけ
説明の言葉が多少難しくなるが、伝統の仏教の教義では、四無量心は、「四(し)梵(ぼん)住(じゅう)」とか、「四(し)梵(ぼん)行(ぎょう)」ともいわれる。これは、四無量心を修行する者は、大梵天界という高い天界に生まれ変わるとされているからである。
また、四無量心は、上座部仏教が説く、「サマタ瞑想(止)」に入る際の40種類ある瞑想対象である「四十業処(しじゅうぎょうしょ)」の一部である。ここで上座部仏教とは、テーラワーダ仏教ともいわれ、釈迦牟尼の直説である初期仏教の教えに忠実な仏教宗派であり、後にインドからスリランカ・東南アジアに広がった。
そして、この初期仏教の時代から、仏教瞑想の基本的な教義として、「止観(しかん)」というものがある。そして、「止(サンスクリット語でサマタ)」は、心を静める(止める)瞑想である。「観(ヴィパッサナー)」は、物事をありのままに見る瞑想である。心を静めると、物事をありのままに見ることができ、物事をありのままに見ると、心が静まる。この「止の瞑想」の一部として、四無量心があるのである。
これを簡略化したものが、現代において広く行われている「慈悲の瞑想」である。慈悲の瞑想は、現代において「ヴィパッサナー瞑想」として広がっている瞑想においては、その準備段階として、セットにして行われる。これは、仏教の精神を最もよく表現した瞑想法として、きわめて重視されている。
慈悲に関して最も有名な経典の一つである『慈悲経』(パーリ仏典小部小誦経9番)には、慈悲の瞑想の要点として、「生きとし生けるものが幸せでありますように」と願うことが説かれている。さらに、慈しみを修習する上で、毎日の生活で従うべき態度、精神的姿勢、行動等などが説かれている。
例えば、「自分の独り子を命がけで守るのと同じ態度で、一切の生類への慈しみを増大させるように」など。この慈悲の瞑想は、パーリ仏典では非常に重要視されており、長部、中部、相応部、増支部等のたくさんの経典に出てくる。
そして、慈悲の瞑想をすることで得られる成果については、釈迦牟尼は、息子のラーフラに、以下のように説いている。
「ラーフラ、慈の瞑想を深めなさい。というのも、慈の瞑想を深めれば、ラーフラ、どんな瞋恚(しんに)(怒りの心)も消えてしまうからです。ラーフラ、悲の瞑想を深めなさい。というのも、悲の瞑想を深めれば、ラーフラ、どんな残虐性も消えてしまうからです。ラーフラ、喜の瞑想を深めなさい。というのも、喜の瞑想を深めれば、ラーフラ、どんな不満も消えてしまうからです。ラーフラ、捨の瞑想を深めなさい。というのも、捨の瞑想を深めれば、ラーフラ、どんな怒りも消えてしまうからです。」
(『大ラーフラ教誡経』パーリ仏典中部62番)
6.四無量心が静める様々な煩悩
上記の経典が説くように、四無量心は、利他の心ではあるが、同時に、それを実践する者の煩悩を和らげ、心を静め、悟りに近づけるものである。すなわち、「利他」を目的としながら、それが「利己」の結果をももたらす。そこで、慈・悲・喜・捨のそれぞれについて、どのような煩悩を静める効果があるかを詳しく述べることにする。
7.「慈」が静める煩悩:貪りと怒り
釈迦牟尼は、ラーフラに対して、「慈」の瞑想と実践によって、瞋恚(怒りの心)が消えると説いている。確かに、慈しみの心と怒りの心は対極であるから、慈の瞑想によって、怒りの心が静まることは納得がいくだろう。
しかし、これには、より深い意味合いがあるのである。それは何かというと、怒りの根底には、貪り・執着があるということである。そして、慈の瞑想は、この貪り・執着を和らげ、怒りの心を和らげるのである。
人は、自分のものを際限なく求めて、とらわれる心=貪り・執着がある。その究極が独占欲である。これがあると、それを妨げる者に対する怒りが生じる。貪り・執着が全くない状態であれば、怒りも生じない。
そして、この貪り・執着を和らげるのが、他の幸福を願い、他に楽を与えることである。自分のものを際限なく求めるのではなく、足るを知ることがなければ、他に与えることはできないからである。
この意味で、慈は、貪り・執着を和らげ、その結果、怒りを和らげることになる。
8.「悲」が静める煩悩:冷たさ・残虐性
釈迦牟尼が説いているように、他の苦しみを悲しみ取り除く「悲」の瞑想と実践によって、残虐性を和らげることができる。これをもう少し広く表現すれば、冷たさ・冷たい心を和らげるということができるだろう。残虐さといえば、他の苦しみを喜ぶ、他を苦しめようとする心というニュアンスがあるが、冷たい心は、そこまではいかないが、他の苦しみに無関心という状態である。
他の苦しみに無関心ということは、その根底に、「他の苦しみは、自分とは無関係である」という意識がある。例えば、他の苦しみに対して「自分には責任がない」とか、「今、他人が経験している苦しみは、自分の過去や未来の苦しみではない」といった、いわゆる「他人事」という意識である。これは、自と他の幸不幸を区別する意識であり、煩悩としては「無智」という根本的な煩悩の範疇に入る。
そして、「慈」が和らげる貪りの煩悩と、「悲」が和らげる冷酷な心は、不離一体である。というのは、貪りが強ければ、他から幸福を奪い、他を苦しめることになるが、他の苦しみに無関心だからこそ、貪りを続けるからである。
その意味で、慈悲の実践は一体である。他に楽を与える「慈」の実践は、他の苦しみを取り除く「悲」の実践に自ずと繋がり、同じように、他の苦しみを取り除く「悲」の実践は、自ずと他に楽を与える「慈」の実践に繋がってくる。
そして、これは、自分が煩悩的な喜びを得ている時に、その裏側では、他者が苦しんでいるという重要な事実を示している。すなわち、自分の煩悩の喜びの裏側には、他の苦しみがあり、他の煩悩の喜びの裏側に、自分の苦しみがあるということである。
9.煩悩的な喜びは、自と他の間で奪い合うもの
煩悩的な喜びをよく観察してみると、財物・異性・食べ物・名誉・地位・権力といったものは、いずれも際限なく求めれば、他との奪い合いになる。
例えば、お金持ちであるという喜びも、貧乏であるという苦しみも、他との比較・競争で決まっている。日本人は途上国からは、皆が王侯貴族に見えるほど金持ちだと見えるそうだが、日本人の中では、経済苦を原因として年間数千人が自殺するし、自分が貧しいというコンプレックスで悩んでいる人がいる。
異性も、三角関係を含めて同性への妬みなど、他との奪い合いの側面は否めない。食べ物の喜びの裏には、食べ物になる死んだ生き物の苦しみがある。名誉・地位・権力は、少数の人しか得られないからこそ成り立つものであり、得る人の喜びに裏には、得られない人の苦しみがあることは明白である。
10.慈悲は、奪い合いを超えて、分かち合いを深める
こうしてみると、煩悩的な喜びは、自他の間で奪い合うものである。その結果、わかりやすくいえば、人は、他と楽を奪い合い、互いに苦しみを押し付けあう傾向がある。
そして、その反対が慈悲の実践であり、他に楽を与え、他の苦しみを取り除く。これを言い換えれば、他と苦楽を分かちあう実践である。こうして、「奪い合い」を控えて、苦楽の「分かち合い」を深めることが、慈悲の実践の要点である。
11.「喜」が静める煩悩:妬み
他の幸福を喜ぶ心は、妬みを和らげる。妬みは、「喜」とはまさに逆の心の働きで、他の幸福を憎む心である。この妬みの心の背景には、「自分が他に優位になることで幸福になる」と考える錯覚がある。これに対して、喜の心は、「他の幸福を喜ぶ広い心が、真の幸福の道である」という気づきに基づいている。
さらに深く考察すれば、人は、自と他の幸福を区別し、「幸福は自他の間で奪い合うもの」と錯覚しがちである。そうして、自分のものを「今よりもっと、他人よりももっと」と際限なく求める。しかし、この際限のない欲求がある限り、満たされることはなく、求めても得られなかったり、得たものさえ失ったり、自分より得ている他人への妬みや不満がある。
一方、自と他の幸福を一つと見て、他の幸福を自分の幸福とする広い心を培い、それが本当の幸福であることに気づくならば、不満が根本的に解消する。そして、「喜無量心」ともいわれるが、世界のすべての人々・生き物の幸福を自分の幸福とも見て、共に喜ぶ心には、無量の喜びが宿り、完全に満たされる。よって、釈迦牟尼は、「喜の瞑想によって、不満がなくなる」と説いているのである。
12.「捨」が静める煩悩:怒り
釈迦牟尼は、「捨」は、「慈」と同様に、怒りの心を静めると説いている。捨は、前に述べたように、苦楽に傾かず、一喜一憂しない「平静な心」、好き嫌い・差別を超えた「平等な心」、そして、自分の苦しみや、それをもたらす他の悪行に「無関心・怒らない」という意味がある。その意味で、捨の実践が、怒りの心を静めることは自明である。
しかし、捨が怒りを静めるという教えは、実は非常に深い内容を含んでいる。それについては別の章で述べることにする。
【※この教本の目次・購入は、こちらから】