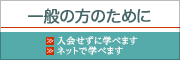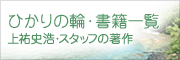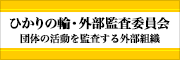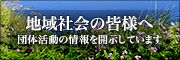2021~22年 年末年始セミナー特別教本「最先端の脳科学が説く幸福の道 脳科学と宗教思想」
(2025年4月28日)
2021~22年 年末年始セミナー特別教本「最先端の脳科学が説く幸福の道 脳科学と宗教思想」
第1章 最先端の脳科学が示すこれからの幸福の道
1.はじめに
脳科学は、この30年間ほどで目覚ましく発展した分野だとされる。しかし、同時に、片手で持てる大きさで、重さも1300グラム程度しかない脳という器官は、宇宙とともに、未だ解明されていないことから、未知のフロンティアともいわれる。
具体的には、1990年代に、脳の状態をリアルタイムで観察することができるファンクショナルMRIという機器が導入され、脳の各部位にどんな働き・機能があるかなどの研究が進む助けとなった。
また、脳の内部構造に関しては、1つの脳に1000億個ほどのニューロンとよばれる神経細胞や、それを助けるグリアと呼ばれる細胞があるとされるが、1996年には、人が他者に共感する能力を支える共鳴細胞(ミラー・ニューロン)が発見され、これは脳科学上の大発見だといわれる。
また、現在「脳トレ」といった脳の訓練が流行っているが、その背景となった大発見として、1997~8年に、脳の神経細胞は成人後は新たに生まれないという、それまでの脳科学の常識を覆して、成人後にも新生することが発見された。ただし、新しい細胞は、刺激・訓練がないとすぐに死んでしまうので、成人後も筋肉と同じように、脳を鍛える意味と必要の双方があるということになったのである。
さらに、人にとっても、科学にとっても、ある意味で最も重要な目的が「幸福になること」であろうが、これに直接的に関係する人の感情、すなわち、幸福感、喜び、怒り、不安・恐怖といった感情に関係する神経伝達物質というものの研究が、飛躍的に進んだ。例えば、ドーパミン、アドレナリン、セロトニン、オキシトシン、エンドルフィンといった言葉が、いっそうよく聞かれるようになった。
2.脳科学から見た幸福と仏教思想
最先端の脳科学が示す、これからの幸福になる生き方を学ぶと、それが仏教的な思想における幸福感と重なる点が多い。第一の共通点は、自分だけの利己的な幸福を求めるのではなく、自他双方の幸福、利他的な幸福を求めることの重要性である。
これをさらに言い換えると、脳科学から見て、他を利する気持ちや行動は、自分を利するものであることが確認された。具体的には、その人に幸福感を与えるとともに、心に限らず、身体の健康、記憶力・集中力などの知性、人間関係を改善するのである。
例えば、強い痛みがある時に加えて、他に感謝したり、感謝されたりする場合に分泌されるエンドルフィンは、モルヒネの6.5倍の鎮痛効果があるとされ、痛み・苦しみを和らげるため、癒しのホルモンとも呼ばれる。加えて、免疫力を高め、NK活性と呼ばれる抗癌効果もあり、細胞の再生を助け、若返り・アンチエイジング効果もある。さらに、脳の中の海馬という部位が司る記憶力や集中力を高める効果もあり、知能を高める効果もある。
また、他者への愛や慈しみや慈悲を持つときに分泌されるというオキシトシンについては、第2章で詳しく述べることにするが、エンドルフィンとともに、ストレスを減少させ、幸福感を与え、免疫力・記憶力を高めることに加えて、血圧などを下げるなどして心臓・脳・血管を健康に保ち、不安をもたらす脳の扁桃体という部位の興奮を静めて安心をもたらし、副交感神経を活性化してリラクセーションをもたらすという。エンドルフィンやオキシトシンなど、幸福感をもたらす脳内神経伝達物質は、脳内快感物質、脳内麻薬などといわれることもある。
3.仏教思想の菩薩道との関係:自他の幸福が一体
ここで仏教思想との関連を見るならば、感謝と慈悲は、仏教で最高の生き方とされる菩薩道の重要な要素である。菩薩道とは、すべての衆生を(今の自分を育んだ)恩人と見て感謝し、その恩に報いるために、様々に苦しむ衆生すべてに対して、慈悲の心を持って済度するという生き方であり、感謝と慈悲が、重要な実践上の柱となっている。脳科学的に言えば、これは、救済される衆生に加え、菩薩道を行う者自身が幸福になる生き方であるということになる。
ここで重要なことは、最先端の脳科学に基づく幸福観と、仏教思想の幸福観の共通点として、利他は真の利己という視点があることである。利他の心や行為は、他を利するとともに、それを実践する本人こそを利するということである。これは、自と他の幸福は一体であり、自他双方の幸福を求めることこそが真の幸福の道であるという考え方に結び付く。
フランスのマクロン大統領の生みの親ともいわれるヨーロッパ有数の識者であるジャック・アタリ氏などが、「利他こそ最も賢明な利己である」という思想を提唱しているが、仏教を含む伝統的な宗教思想に加えて、脳科学という最先端の科学が、それを裏付ける時代となった。
4.現代社会の主流の幸福観:幸福は他との奪い合い
利他こそ利己だという思想は、「情けは人の為ならず」「人を呪わば穴二つ」などといった格言でも、よくいわれてきた。しかし、私たちの日常の感覚では、その逆に、「正直者は馬鹿を見る」「善人は損をする」といった話もよく聞く。
特に現代の競争社会においては、勝ち組・負け組とか、貧富の格差などがよくいわれ、他に勝つことによって幸福になるという価値観が強い。他に勝利することで幸福になるのであれば、自分の勝利の幸福は、他の敗北とセットであり、幸福は、自他の間での奪い合いということになる。
ここで、競争の勝利が幸福であるというと、少し概念が狭くなりすぎるので、これを「他との比較」という言葉で言い換えたい。心理学者によれば、現代社会の人の主な幸福とは「自己愛の充足」によるものであり、わかりやすく言い換えれば、他との比較において、他に優位になることによる幸福感である。
例えば、お金・財力、名誉・地位、学歴、容姿など、現代社会において人々が幸福の指標とする事柄は、結局は、他との比較の中で意味を持つものが多い。自分がお金持ち・リッチであるという喜び・満足感も、多くの場合、友人・知人との財力の比較によって決まる。言い換えると、いくら以上の年収ならばお金持ちであるという絶対的な基準はない。もしあるとすれば、途上国の人から見れば、経済大国の日本人は、皆がある意味でお金持ちであって、その国で、経済苦を理由としての自殺が年間で数千人にのぼる理由は説明できないだろう。
他と比較して自分が優位であれば幸福であるということは、自分の幸福は、自分よりも劣っている他者がいてこそ成立することになる。そのため、この幸福観・価値観では、幸福は、他と奪い合うものだということになる。
5.他者との闘争という人間の本能とアドレナリン
人類の歴史を見れば、闘争は生き残るために必要不可欠なものだった。そもそも、人間は動物の1つであり、動物は弱肉強食といわれる生存競争、まさに闘争的な環境の中で生きている。自分が他の生き物を捕獲して殺して食べて生き残るか、捕獲できず殺せず食べられずに死ぬか。
生命体が、生命体である以上は、生きること、生き残る(生存)こそが、最優先の欲求であり、その実現こそが最優先の幸福であろう。そうでない生命体は容易に死んでしまう。そして、弱肉強食の世界では、闘争の勝者が生き残り、その意味で幸福となり、敗者は生き残れず、その意味で不幸となる。
今の私たちである現生人類(ホモ・サピエンス・サピエンス)は、今の学説では、20万年ほど前にアフリカで生まれたのではないかといわれているが、サバンナの中での原始的な生活で生き残るためには、自分の身に対する脅威を把握して、自分を守る行動をとることは、生き残るために非常に重要なものであった。
こうした中で、人間には、自分の身を守るための神経伝達物質として、ノルアドレナリンやアドレナリンというものがある。これは「怒りのホルモン」ともいわれ、自分に対する脅威=敵に対して、逃げて身を守るか、それとも戦って(相手を撃破して)身を守るかの選択と行動を促すとされる。よって、怒り・恐怖・不安といった感情と結びつく。
アドレナリン・ノルアドレナリンは、体を戦闘態勢に入らせるために、血圧を上げ、血液を体中に行きわたらせ、血糖値を上げて、すぐに筋肉を使えるようにする。このように、生物として生き残るために最も重要なことの1つである、敵と戦って勝つ(ないしは敵から逃げ切ることで勝つ)ための物質である。
6.現代人のアドレナリンの過剰分泌
ところが、原始的には身を守って生き残るために最も重要な神経伝達物質ともいえるアドレナリンやノルアドレナリンが、現代人においては、それが過剰に分泌されるがゆえに、逆に自分の身を危うくしている面がある。
というのは、アドレナリン・ノルアドレナリンは、外敵が現れた時に合わせて、一時的に、体を戦闘態勢に持っていくためには必要不可欠であるが、それが不必要な時にも出るなどして、出過ぎてしまうと、体を不要に酷使することになる。
前に述べたように、血圧・血糖値を上げる働きがあるため、高血圧・高血糖(糖尿病)・脳出血・心臓・血管の障害をもたらす。これは脳にとっても体にとっても危険な状態である。そもそもが、ノルアドレナリンは、本来、数ミリグラムをラットの腹腔に注射するだけでラットが死んでしまうというほど、強い毒性を持つという。
では、なぜ、アドレナリンが不必要に出過ぎるようなことが起こるのだろうか。結論からいえば、それは、生存のために必要不可欠な闘争の場合に限らず、他者を自分の幸福の「敵」と見なし、アドレナリン・ノルアドレナリンが分泌される場合が少なくないからだと思われる。
例えば、戦争・闘争などにおける文字通りの敵(自分の生命の脅威)ではなくて、客観的に見るならば、単なる何かしらの競争の相手、自分との比較の対象にすぎない相手であっても、自分の幸福に対する脅威と感じられてしまう(ある意味では錯覚する)ことが起こるのである。そして、それを攻撃して勝利し、脅威を排除したいと思う(ないしは勝てない相手であれば、その競争から逃げたいと思う)のである。
7.人の根源的な欲求:生存欲求の実態とは
人を含めたあらゆる生命体の根源的な欲求は、生存欲求だろう。そもそも、生命体とは、何もしないで静止している非生物と異なり、生存のために何らかの活動をしているものである。生存欲求があるから生存のための活動をしているのか、生存のための活動をしているから生命欲求があると見なされているかは、複雑な問題になる。しかし、それはともかくとして、生存欲求・生存のための活動がないものは、進化論に基づく適者生存・自然淘汰から見ても、すぐに消滅してしまい、生き残ることはないだろう。
次に、生存欲求は、分類によっては、二つの種類がある。一つ目は、自分個人、自分という個体の生存欲求であり、普通の意味の生存欲求である。二つ目は、自分の子供を産んで、自分の子孫(遺伝子)を残すという繁殖の欲求である。この双方ともないと、その人ないし、その人の遺伝子は、生き残ることはないのは自明だろう。
言い換えれば、現在生きている私たち人間を含めた生命体は、過去において、生存と繁殖の欲求を持ち、なおかつ、実際にそれに成功した者たちだと考えられる。それは、進化論の適者生存の理論に基づくならば、これまでの各歴史の段階で、その環境に適応して生存と繁殖による生き残りに成功し続けたということだ。
環境に適応して生き残ったということは、弱肉強食である地球の生命圏の実態や、無数の闘争を含んだ人類の歴史に基づいて考えるならば、大変な競争(環境の中)の勝利者であるということも意味するだろう。
地球の39億年の生命の歴史、現生人類の20万年の生命の歴史の中で、歴史の中の様々な種の間の生存競争と個体の間での生存と繁殖の競争に勝ち抜いた子孫なのであり、我々現代に生きる人類はすべて、すでに途方もない勝ち組(の子孫)なのかもしれない。
こうした我々は、客観的に見ても、大変な生存競争に生き残るに必要な生存と繁殖の欲求と能力を祖先から引き継いだ存在と考えるのが合理的だろう。そして、その欲求と能力の一部として、自分の生命の脅威に対して対処するアドレナリン・ノルアドレナリンの神経伝達物質・神経回路が発達しているのである。
8.生存欲求から派生する様々な欲求:進化心理学の理論より
生存欲求が人の根源的な、最優先の欲求であったとしても、人には、その他の様々な欲求がある。ところが、一見して生存欲求とは異なる欲求に関しても、その背景にあるのが生存欲求であると見る考えが、これまでに発展してきた心理学・脳科学などには見られる。例えば、進化心理学等がそうである。
これは、ダーウィンの進化論の視点から、人間の心の働き・欲求を理解する学問で、進化で形成された心理メカニズムを研究する。その要点は、今生き残っている人類の心の性質は、長い進化の歴史の中で、その時々の環境に適応して生き残る上で有利であったものの結果であるという視点である。
まず、環境に適応した体形や行動形態を持つ者が生き残り、その遺伝子がその子孫に伝え続けられ、そうでない者の遺伝子と子孫は消滅し、適応した者に淘汰されていくというのが、進化論の自然淘汰の理論である。そして、進化心理学は、この理論を体形や行動形態に限らず、心の傾向にも適用したものである。
というのは、人の心理的な要素、例えば、感情なども、遺伝子に組み込まれている(ただし、その人がどんな感情・性格・人格の持ち主になるかは、遺伝子だけではなく、生まれた後の環境や訓練に左右されるので、この点は誤解しないようにされたい)。よって、生き残るに有利な心の傾向とその遺伝子を持った者が生き残ってきたというのが、進化心理学の視点となる。そして、その視点から見ると、以下のような心の働き、心理的なメカニズムが、人類の生存を助けたことが推察される。
9.恐怖や不安に関する脳の感情システムと、現代社会での誤作動
まず、恐怖・不安の感情である。これは、先ほど述べたアドレナリン・ノルアドレナリンに関係する。熱帯雨林が消えた後にサバンナが広がった地上では、用心深くいち早く危険を敏感に察知し、すばやく身を守る者が生き残ったと推察される。
それに役立ったのが、恐怖の感情(アドレナリン神経回路)であろう。ちょっとしたことでも敏感に(場合によっては過剰に)反応し、逃げるか戦うかの機敏な行動ができるように、アドレナリンを分泌して心拍を上げ、血流を全身に送ることが生存に必要・有利だったのである。さらに、身を守るために、道具を使うことを促すことになった。
ところが、前に述べたように、現代の人間、特に野獣の脅威も内戦もない先進国に住む人間は、原始時代とはかなり異なる環境に住んでいる。そして、その環境においては、この恐怖・不安の感情(=アドレナリン神経回路の働き)が強すぎて過剰に働き、自分の身を守るのではなく、逆に、心身の健康や人間関係を損ねて、マイナスに働く場合が多くあるのではないか、ということがある。
猛獣がいるサバンナでは、脅威に過剰に反応することは必要だったが、環境の異なる現代で、生命に危険等がない場合にも、脅威・恐怖を感じ「逃走か闘争」の態勢が発動してしまう。例えば、原始時代ならば、10頭の野生動物がいて、その中の9頭は草食動物でも、1頭の猛獣がいれば、その猛獣に恐怖を持って意識を集中しなければ、生き延びることはできなかった。
しかし、そうした環境に適応してきた脳のシステムが、現代では過剰に働いている。例えば、自分の仕事に対して、会社の同僚の10人のうち、9人が肯定的な評価をしたのに、1人が否定的な評価をしたために、その1つの否定的な評価に意識が集中して、日夜思い悩み、頭から離れないなど。また、「みんなに良く思われたい」という気持ちが強く、誰にも嫌われたくなく(誰にも嫌われるのが怖く)、葛藤しながら風見鶏・優柔不断的な言動に陥ってストレスをため込むなどである(この場合、皆に信頼されなくなる可能性は少なくない)。
これは、現代社会に、これまでの歴史の中で形成されてきた脳が、ミスマッチしているということになる。そして、これと同じように、暗闇恐怖、高所恐怖、閉所恐怖症なども説明できるという。つまり、現代社会では、先祖の環境のような暗闇や高所などが生命の危機になる状況は、ほとんどないにもかかわらず、これらに恐怖を感じる人が多い。
これがひどい場合は、恐怖症になってしまうが、過剰な不安・恐怖に基づく精神的な問題として、不安神経症、脅迫観念症、被害妄想などの様々な精神疾患が広がっているのは、ご存じのとおりである。
10.集団行動・共同作業の欲求、所属欲求・承認欲求の形成
次に、集団行動・共同作業(の欲求)がある。集団で協力することで、猛獣と戦い、生き延びる確率が高くなり、集団で狩りを行うことで、獲物を捕る確率が高くなった。さらに、本格的な農耕という組織的な共同作業によって、より飢えずに豊かに、大勢で生きていくことができるようになった。
集団作業を行わず、分け前だけを得ようとする者がいれば、集団から追い出されるが、それは死(の可能性が高くなること)を意味するから、集団から拒絶されることを強く嫌がった。嫌がる人が追い出されないように努力して生き残った。
こうした歴史の結果として、現代の私たちも、社会・集団から拒絶されることを嫌がり、孤独を嫌がり、居場所を求め(所属欲求)、居場所を確保するためにも集団の他者からの承認を求める(承認欲求)ようになったというのである。そして、実際に、今の社会の中で、居場所が欲しいが得られない、承認欲求が満たされない、愛されたいのに愛されないという悩みを抱える人は非常に多い。
なお、心理学者のマズローが提唱した人間性心理学においては、人の欲求は、①生存欲求 ②安全欲求 ③所属欲求 ④承認欲求 ⑤自己実現欲求 などに分類されている。ただし、進化心理学に基づけば、所属欲求や承認欲求の発生の原因は、生存欲求・安全欲求に関係し、すべては生存欲求に根っこがある。
ところが、恐怖と不安の感情と同様に、この所属と承認の欲求に関しても、その欲求が形成された昔の人類社会と、現在の人類社会では、大きく環境が異なっているという問題がある。そのために、結果として、所属欲求・承認欲求が過剰であり、それが、自分の生存を助けるのではなく、逆に、心身の健康や人間関係にマイナスに働く面があるとも思われる。
例えば、「自分には居場所がない」、「自分は認められていない」と悩み、生き甲斐を見失い、うつになり、自死を選ぶ人が少なくない。人間関係が苦手で他人との交流がなくなって、大都会に住んでも、精神的な意味で孤独となり、孤独死する人も少なくない。
11.所属・承認欲求や孤独に関する脳の感情システムの誤作動
その人たちは、「生きていても全く楽しくない」と感じていることは重要な事実であるが、昔の人類から見れば、少なくとも物理的な意味で、生きる希望が断たれるという意味での孤独状態ではない。これは、恐怖の感情のシステムに関して、脳が現代社会の環境にミスマッチ・誤作動を起こしている可能性と類似しているように思える。
小さな集団で生活していた祖先は、集団から離れて生きることはできなかった。集団から離れることは、死を意味した。集団に受け入れられることは、死活問題だった。そのため、集団内での自分の評価を気にするという、心理メカニズムが形成された。それが、もはや死活問題でないにもかかわらず、人からの評価を非常に気にするということが、現代の私たちの脳にも起こっているのである。
特に、基本的な人権と社会福祉制度を持つ民主主義の先進国社会では、生まれた時点で無条件で、国家の一員として承認され、野獣もいなければ戦争もなく、物理的には原始時代とは比較にならない規模の人口を有する都市社会に住んで、物理的な意味での孤独はなく、身体などに障害があっても、健康で文化的な生活が最低限できる社会福祉制度があるなど、生存や安全に必要な所属欲求・生存欲求は、自動的に満たされているともいうことができる。
そのような社会の中で、実際に現代の人々が、満たされないと悩む所属や承認の欲求は、客観的に見れば、昔の人類の生存や安全への欲求とは次元が異なる。その背景には、自と他を比較して、他よりも居場所が乏しい、他人よりも承認されていないというコンプレックスを背景とした、生き甲斐のなさがあるかもしれない。だとすれば、これもまた、恐怖や不安の感情とともに、進化の結果できた脳のシステムが、現代社会において、なにかしらのミスマッチを起こしているとも考えられるかもしれない。
なお、蛇足ではあるが、進化心理学が説く現代社会における脳の誤作動の可能性の1つとして、甘いものや脂っこいものを好む心理メカニズムがある。食糧事情の不安定な祖先の環境では、生存のためには役立ってきた。そういう心理メカニズムの持ち主の方が、生き延びてきた。しかし、現代においてこの心理メカニズムは役に立つだろうか。現代において、栄養不良は存在しない。にもかかわらず、甘いもの、脂っこいスナックはあふれている。そして、肥満、生活習慣病を誘発している。
12.社会脳の発達(仮説)
なお、所属や承認の欲求に関係して、人間の脳が飛躍的に進化したのは、協力関係の強い集団の他者に対応する=社会的な課題に取り組むようになったからであるとする「社会脳仮説」を、多くの学者が支持している。集団内での他者への対処は、モノを操ることより複雑であることが、脳の進化を進めたというのである。
共同作業を行うには、他者が何を考え、何を欲求しているかを知る能力が備わっていることが必要であり、この能力が、自分を自分でどう感じるかに関係する感情(自己意識的感情)、例えば、自尊心、罪悪感、恥といった感情も発達させたという。集団にプラスの行動をとったときに自尊心を抱き、集団に害を及ぼすマイナスの行動をとったときに罪悪感を抱き、集団内で自己の価値を下げる場合は、恥を感じる。
こうした罪悪感や恥がなければ、欲求をコントロールすることが難しくなり、他者を害することを行い、集団から追放されることになる可能性が高く、集団からの追放は死を意味したから、そうならないようにする自己意識的感情は、生存のために大切な感情となったのである。
また、この社会脳の働きと連動するのが、前に述べた共感細胞とも呼ばれるミラーニューロンであり、幸福の神経伝達物質であるエンドルフィンやオキシトシンであると思われる。ミラー(鏡)ニューロンによって、人は、他者の気持ち、喜び・苦しみを鏡のように自分にも映して感じ取り共感する。そして、互いに感謝し、慈しみ、同情し、助け合うことで、エンドルフィンやオキシトシンといった幸福の神経伝達物質が出て、幸福感を感じるとともに、健康や知性が向上する。
こうして人間の脳は、他者と助け合うことによって、生き残る確率が高くなることを知っており、それに合わせて、他者に対する肯定的な感情・行動で幸福を感じるようにできている。
13.集団の他者に配慮する心理の注意点
ただし、集団・社会に対する心の働きに関しては、注意をしなければならないことも多い。例えば、他者すべてから良く思われたいと思いすぎ、風見鶏・優柔不断となって、ストレスをため込んで苦しむこともある。
また、所属する集団全体が間違ったことをしている場合に、それに異を唱えることが難しい場合がある。その場合は、自分の身近な、自分が所属する集団組織と、その外にある社会全体のどちらを優先するかという問題になる。これは自分が配慮する集団の範囲が、家族までか、仕事や宗教などで所属する集団組織までか、社会・国家全体か、さらには人類社会全体かといった、その人の配慮する範囲の広さの問題であるという心理学的な見解もある。その見解では、一般に、より配慮範囲が広い人の方が、その意味で公正無私である方が、長期的には幸福な人生になるという心理学的な研究がある(京都大学の藤井教授による認知的焦点化理論など)。
それから、その集団になじみがなく、集団が心地よく思わないような新しい方向性・考え方・生き方がなかなかできずに、自分を見失ってしまうといったことも起こり得る。これは集団と個人のバランスの問題である。日本社会によく指摘される、いわゆる村社会的な社会心理構造に基づく過剰な同一化圧力の弊害である。
この問題に関しては、自分が他者との支え合いで生きている以上は、自分のことばかり考えていてもダメであるが(自分が望む生き方が成功するわけではないだろうが)、逆に他のことを優先するあまり、自分を殺してばかりいても幸福にはなれないであろうから、その間のバランスの問題ではないかと思う。
その意味で、社会脳の働きは、助け合ってこそ、生きる可能性を大きく向上させた人間にとって、その幸福に必要不可欠な機能であるが、一方で、その行き過ぎや間違いにも気をつけなければならないシステムだと思う。
14.繁殖(生殖)のために形成された心のメカニズム
ここでは、個体の生存欲求に加えて、もう一つの大きな要因である繁殖欲求に関連して形成された人の欲求の傾向を見ていく。
進化心理学の視点から見ると、男女それぞれは、どのような異性に魅力を感じるようになったのだろうか。言い換えれば、どのような男性に魅力を感じる女性が、その子孫を残すことに、より成功しただろうか。進化心理学の見解によれば、女性が、男性を選ぶ要素は、子孫を残すことが目的であるから、子供を産んで子供を養い育てる能力があるかが重要な基準になり、そのためには、健康(栄養)の状態が良いこと、子供を産んだ場合も、子供も健康(栄養)状態が良いこと、運動能力が高いこと、知力が高いことなどがあるとする。
一方、男性が、女性を選ぶ基準は、高い繁殖力である。それは、若さと豊満な乳房・骨盤である。すなわち、多くの男性が若くていわゆるグラマーな女性を好むというのは、進化心理学や認知心理学では、そうした女性の方が繁殖能力が高いことを、無意識的に理解しているからであるという。
もちろん、これは、グラマーであることが、男性が女性を好む唯一の条件だと主張するものではなく、女性が好む男性の場合と同様に、他にも、様々な要素があるだろう。また、先祖からの遺伝子が、好みの異性に関する一定の性格的な傾向を形成しても、生後の環境・教育・経験が、人の心理の形成に影響を与える。
また、遺伝子による先天的な条件と環境・経験による後天的な条件の双方が、人の性格・人格の形成に働くというのが、心理学の通説である。そのためもあって、グラマーな女性を、逆に不快に感じる男性もいるのである。
15.自と他を比較する心の働きの形成
次に、進化心理学では、繁殖が一つの要因となって、人は、自と他の比較をするようになったと考える。自分の子孫を残すためには、異性を獲得することが必要であるが、そのためには、他の同性と比べて、相対的に魅力があることが重要となる。その集団の自分の身近な同性と自分を比較し、どちらが異性を引きつける能力が高いかを比べることが、大きな意味を持つ。
そして、この比較は、その次に、他の同性よりも、自分がより魅力的になろうとする努力につながっただろう。その意味で、異性・配偶者を得て繁殖するということも、人類の進化の歴史の中では、同性の間での(激しい)競争ということができるかもしれない。そして、後にも述べるが、その後、この他者との比較というメカニズムは、異性を獲得するという場面でなくても、働きだしたという。
こういうと、この教本の読者の方の中には、「私は、そもそも結婚して子供を産みたいとは思わないから、その意味では、他の同性と自分を比較する必要もないが、自他の比較は強くて悩んでいる」という方もいるだろう。
しかし、心理学では、先祖からの遺伝的な要素と、生後の環境などの後天的な要素の双方が、その人の心理的な傾向を形成するとする。よって、その人の遺伝子の中には、繁殖のためには他より優れている必要があると理解し、自と他をよく比較して、他者より優れた存在になろうと努力して、繁殖に成功したという先祖の性格の遺伝子が伝わっていても、現代社会に生まれた後に、未婚率の大幅な増大を見る社会環境の中で、結婚して子供を産むことが幸福の条件とは必ずしも思わない性格が、後天的に形成されることはあり得るということになる。
だとすれば、自分の意識は、子供を産みたいとは思っていないが、無意識的に働く脳が形成する感情のシステムは、現代社会の環境から形成された自分の意識に追いついていないのかもしれない。その結果、無意識に働く脳の感情のシステムは、自分は子供を産まないのだから、他と比較・競争する必要はないと理解しておらず、惰性的に、自と他の比較を続けているのかもしれない。
16.意識と無意識の分裂
深層心理学的にいえば、その人が自覚する表面の意識(顕在意識)では、「子供を産みたくない」と思っていても、自覚しない意識(無意識・潜在意識)では、「産みたい」という気持ちが依然として残っている可能性もある。ユングなどが説く、意識と無意識の分裂である。
この、人間の心理が多重構造をなしているという理論は、人において、頭では価値がないとわかっていても、感情的にはなかなかやめられないことがあることを説明する。また、自分には不都合な欲求を、表面の意識では抹殺して、無意識領域に抑圧するということもあるとされる。
例えば、「本当は、結婚・出産もできればしたいが、現実的にはできそうにないから、したくないと思っておこう(そう思っていれば悔しくないし)」と考えているうちに、自覚する意識では、本当に結婚したくないと思っている(と錯覚する)状態になる可能性もあるということである。そうした場合、ある時に、何かをきっかけに、抑圧していた欲求が表面化すると「自分の本当の気持ちに気づいた!」となる(なお、気づいたのではなく、気持ちがわかったと思う人もいるかもしれないが)。
なお、仏教・ヨーガの瞑想は、自分の無意識(潜在心理)まで深く到達して探求し、望ましくない潜在意識の認識・欲求を修正して、意識と無意識の統合を図る機能がある。これは、自分の心全体を知り、心全体を制御することになる。特に感情は、無意識の脳活動で形成されている。
我々が自覚する意識(表層意識)では、自分の感情は直感的なもので、理由がないように思われる。好きなものは好きで、理由はないということである。しかし、感情を形成する無意識(の脳活動)には、生存欲求などを背景として、きちんとその感情の理由があると見るのが、最近の心理学や脳科学の見解には多いのである。
その意味では、釈尊が説いた仏教の思想や瞑想は、2500年前に東洋に生まれた、日常的な規範と瞑想などを手段とした、深層心理学的な心(煩悩)の制御の知恵ということができると思う。
17.他との戦争・競争・優劣の比較に関して
もちろん、前に述べたように、他との競争に勝つことを望むこと、それに関連して他と自分を比較して、他より優位になることを望むことは、繁殖ばかりと関係しているのではない。
人類の歴史を俯瞰(ふかん)すれば、人類の最大の「敵」は、原野の野獣ではなく、人間自身であり、最大の「競争相手」も、同じく人類である(なお、ここではあえて「敵」と「競争相手」を区別して表現したが、その意味は後で述べる)。
人間の間の戦争では、人と野獣の戦いと同様に、勝者こそが生き残るのだから、生存を最重視する価値観からは、勝利こそ絶対であり、敗北は死であり無価値である。より客観的にいえば、勝利する人がどんなに悪い人でも、敗北する人がどんなに良い人でも、勝利した人の遺伝子が、その子孫に伝わって残るのであるから、今の私たちに伝わっているのは、良い人の遺伝子だったかどうかはわからないが、少なくとも、勝率の高い先祖の遺伝子であった可能性が高い。そして残った者の子孫は、自分達の祖先を、悪として(邪悪な侵略戦争をやった者として)否定することは滅多にない。
そして、現代の考古学・歴史学では、人類にとって、戦争、すなわち個人の暴力行為ではなく、集団による組織的な他者への暴力の行使は、その本能ではなく、そのため、いつの時代のいつの地域にもあったものではないという見解がある(日本の縄文時代には戦争の明白な痕跡が見られない)。
そして、本格的な農耕が始まった頃に、戦争が始まったという見解がある。例えば、原始的な農耕時代において、水田稲作の導入により、収穫物と共に人口が爆発的に増える中で、不作の年に飢えに怯えた集落同士が、自らの生存を賭けて、戦争を始めたのではないかという見方もある。その意味では、性急な結論は控えるべきだが、その場合の戦争は、生き残るためには必要だったのかもしれない。
18.生き残るために必要ではない戦争の原因は
しかし、その後はむしろ、より豊かで高い戦闘力を持つ民族が、他の民族を侵略して、より豊かになる戦争が始まった。いわゆる侵略戦争である。
侵略戦争は、人類の歴史全体を見るならば、わずか80年前の第二次世界大戦の後にようやく下火になった欧米の植民地侵略の時代まで人類の主流の活動だった。極めて最近まで侵略戦争の時代だった。では、人間は、生き残るために必要がないのに、なぜアドレナリンを出して戦闘モードに入って、他を殺してまで、豊かになろうとしてきたのであろうか。
それは、覇権国家といった言葉があるように、人は、他の人々や領土を支配するなどして、自分がいろいろな意味で、他者よりも優位な立場を得ること自体に、強い欲求・快感・幸福を感じるからかもしれない。ただし、その背景にも、戦争によってか合法的な経済競争によってかの区別なく、財力・名誉・地位・権力その他において、他に対して優位になることが、よりよく生き残る可能性を高めるという思いがあるからかもしれない。
例えば、現在の米国では、黒人奴隷解放の南北戦争から200年近くたっても、依然として、黒人等への差別による社会の分断が指摘されている。白人層と黒人層の間の貧富格差や社会的地位の格差は、依然として顕著であり、それと連動して、医療サービスの受給、健康状態、寿命における顕著な格差が指摘されている。実際に、新型コロナの死亡率も、白人層と黒人層では大きな違いがある。
戦争がなく平和で、米国のような人種差別も少なく、一定の社会福祉制度も整っている現在の日本社会でも、他よりも豊かな方が、より幸福に、より長く生きることができると人々が考える事情はある。少し前にも、老後には数千万円の貯蓄が必要だという話が物議をかもして、政治問題になった。
また、バブルが崩壊してデフレに陥った後、新聞に「今自分たちの国がこんなに大変なのに、なぜ途上国に多額の援助をし続けているのか」という読者の不満の投稿が掲載された。途上国は飢餓にあえぎ、国民の年間所得は日本の100分の1で、日本の途上国への援助は日本のGNPの1%程度だ。数字だけでいえば、毎月30万円の給料の人が、毎月3000円の給料の人に、毎月3000円ほど援助してきたが、自分の給料が上がる見通しが乏しくなったという大変な事態が発生したのだから、3000円の支援を減らすべきだと主張していることになる。
現代の日本でさえこうなのだから、植民地侵略の時代では、勝者である欧米諸国の国民は、敗者からの収奪によって得る膨大な富・利益に歓喜したともいう。それは、彼らが、より幸福に、より長く生きるためにも役に立つと思われ、二つの世界大戦で植民地支配が難しくなるまでは、なかなか手放しがたいものだったのだろう。
19.喜び・歓喜の神経伝達物質「ドーパミン」とその問題点
さて、エンドルフィンやオキシトシンとともに、喜び・幸福感を与える神経伝達物質がドーパミンである。これについては、第2章で改めて詳しく述べるが、中枢神経系に存在し、先ほど述べた怒りのホルモンのアドレナリン、ノルアドレナリンの前駆体でもあるとされる。
そして、これは、何かを獲得・達成したときの喜び・快感を与え、それに基づく意欲を生み出す。ただし、感謝によって出るエンドルフィン、愛情・慈しみによって出るオキシトシンの明るい温かい気持ちをもたらす幸福感と異なって、興奮を伴う喜び・歓喜という特徴があると思われる。
原始的な状況でいえば、例えば、その日に生き残るための獲物を苦労して獲得したときに生じる喜び・歓喜の感情である。この状況では、アドレナリンも出ている。小動物や草食動物が狩猟の対象である場合は、それは直ちに自分の身の脅威にはならないが、生き残るために動物を捕食することを迫られているわけだから、生き残りのための戦い(生存競争)の中にいるわけで、体はアドレナリンが分泌されて戦闘モードに入るわけである。
こうして、他者へのポジティブな気持ちの際に出るエンドルフィンやオキシトシンと異なって、ドーパミンは、他者に勝利した際の歓喜のためにも分泌されるということである。獲物を獲得するとは、自分には幸福だが、獲物側には死・不幸を意味するし、戦争による自己の勝利と生き残りは、他人の敗北と死を意味するものである。
さて、ドーパミンの話に戻すと、ドーパミンは、獲得・達成したときに快感を与えるだけでなく、その先に獲得する可能性があるときも、分泌されて快感を与える。それが獲得・達成しようとする意欲を形成する。よって獲得に加えて、様々な事柄に関する意欲の形成に関する神経伝達物質である。
ところが、ドーパミンには、一つ重要な特性がある。それは、同じものが苦労なく平然と獲得されるような状況が続くと、すなわち同じ刺激が続くと、徐々に分泌されにくくなり、喜びを感じられなくなるということである。そのため、ドーパミンが出て喜びを感じるためには、より強い新しい刺激が必要となる。すなわち、以前よりもっと多く、もっと良いものを獲得しなければ、ドーパミンが出ないのである。
これが、人の欲求は際限がないという事実の背景の1つではないかと思われる。何かを新たに得た場合はうれしいが、それがそのまま続くならば、それは当然のものと感じられて喜びではなくなり、それ以上を求めるようになる。その一方で、得たものに関しては、それにとらわれてしまい、それを失うと苦しみを感じる。
例えれば、給料が15万円から20万円に増えた時はうれしいが、その時の喜びは長くは続かず、もっと欲しいと思うが、そのままずっと20万円であれば、自分は頭打ちであると苦しむ。さらに、仮に20万円が15万円に下がれば大変苦しむ。20万円に上がる前は、15万円でもそれなりにやっていたにもかかわらずである。
20.ドーパミンがもたらす「とらわれ」「のめり込み」「依存症」
こうして、ドーパミンは一種のとらわれ、それなしではいられない中毒症状的な状態を作り出す面がある。実際に、薬物を摂取して感じる快感は、回を重ねるごとに減少し、摂取する量を増やす誘惑にかられるのも、このドーパミン神経回路の特性である。
そして、過剰な飲酒・過食・買い物・ギャンブルに対して、足るを知らずにのめり込んでいくのも同様である。その意味でドーパミンは、時に人が何かに過剰にのめり込む状況をもたらす面がある。
そして、もっと求めたとしても、かなわない場合が多い一つの背景には、自分だけではなく、皆がもっと求めるために、奪い合いが生じるからにほかならない。よって、もっと得ることはおろか、逆に他人に奪われて、前よりも減る場合さえある。この場合、他へのやっかみ・妬み・憎しみ・恨み・怒りが生じて、苦しむことになる。それが場合によっては、互いの生死をかけた闘争・戦争の原因にもなる。
このドーパミンによる際限ない欲求の拡大は、他人との闘争・競争の勝利、名誉・地位・権力・支配の欲求にも当てはまり、それらの追求を、際限のないものにする可能性がある。よって、このドーパミン神経回路の働きは、ある程度制御しなければならないという面があるが、これについては、また後で述べることにする。
21.過剰な勝利・優位の欲求の大きな弊害
ところが、他との競争で勝利しようとする欲求、他と比較して優位になりたいという欲求は、それが行きすぎると、特に現代の社会においては、幸福よりも、逆に不幸をもたらす面が目立ってきたという重要な事実が、脳科学の視点から指摘されている。それに関わってくるのは、先ほど述べたアドレナリンや、ストレスホルモンといわれるコルチゾールである。
ただし、前もって結論をいうならば、これは、優れたスポーツ選手がそうであるように、競争の相手を自分の幸福を奪う「敵」とは見ずに、切磋琢磨して互いに成長し合う「友」と見る場合には、当てはまらない。その場合は、人は、競争の勝利を絶対としてはおらず、勝ったり負けたりしながら、切磋琢磨して皆で成長するシステムだと考え、競争相手を自分の助力者・友と見る。
勝利を絶対だと考えると、強い競争相手は、自分の幸福を妨害する敵であり、悪魔のように見えて、憎しみ、妬みの対象となる。しかし、(共に)成長することが目的の場合は、競争相手は強力な方がよく、自分の成長=幸福の大きな助力者、恩人、教師・導き手(神・仏)と見えるだろう。
前者の勝利絶対の場合は、様々な心身の問題・人間関係の問題が生じる。競争の勝利を絶対として、自分と他人を比較して他に優位に立つことを強く望み、劣っていることを強く嫌がる場合は、現代人にも非常に多い。いや、競争社会の現代社会こそが、他の時代に比較しても、自と他の優劣の比較に、より深く陥っているのではないかとも思わせる。
結果として、自己嫌悪・コンプレックス・妬みや、他者の自分の扱いへの不満・怒りなどが、相当に現代人の心には渦巻いている。勝てないからあらゆる競争には参加せず、他人と交流するとコンプレックスを感じるため交流せず、社会から引きこもる(これを心理学では「劣等コンプレックス」の心理状態などということがある)。そして、孤独に苦しむ。他人より劣っているばかりの自分は、生きていてもちっとも楽しくないし、生きる価値を感じないと思い、生きがいを喪失する。うつなどの精神疾患に至る。自死ないしは孤独死に至る。
また、自分が劣っているというコンプレックスに対して、引きこもるのではなく、それを紛らわすために、自分に実力がないという現実を受け入れずに、自分に対する他者・社会の扱いが不当・不合理だと思い込む。そして、他者に攻撃的で、独善的、被害妄想的な意識・言動に陥る(これを心理学では「優越コンプレックス」という)。ことさら他人の悪口を言って貶めて、自分以下の存在と見ようとする。問題が起こる度に、他に責任転換をする。時には独善的な視点から、他人には有難迷惑なことをする。不正を行ってまで、競争で他者に自分が勝ったように見せかける。そして、昨今大きな問題となった電車などでの無差別大量殺人も、このタイプの、社会全体や勝ち組への不満・怒り(逆恨み)に起因するとされる。
22.ネガティブな感情がもたらす心身への弊害と不幸
さて、話を元に戻して、他者が本当に自分の脅威であるならば、それに対してアドレナリン・ノルアドレナリンが分泌されて、戦闘モードに入り、戦うか逃げるかの行動をとることは必要である。
しかし、実際にはそうではないのに、勝利ばかりを絶対とする競争や、他との過剰な優劣の比較などによって、いろいろな他人を、自分の幸福を妨害する敵とばかり見るようになり、敵意・悪意・怒り・妬み・憎しみ・恐怖・不安・自己嫌悪・コンプレックスといったネガティブな感情を抱くならば、それは心身に逆効果になる。
まず、アドレナリンは前に述べたように、体を酷使することになり、高血圧・高血糖(糖尿病)・脳血管・心臓などの疾患のリスクを高める。例えば、高齢者が、瞬間湯沸かし器のように怒った後に、脳血管障害で死亡するリスクが高いことは、よく知られている。
なお、アドレナリンが本当の危機に対して一時的に出ることには、人間の体は耐えられるという。頻繁に出る、絶えず出ることになると、人間の体は耐えられない。わかりやすく言い直すと、人間の体は、一時的には強いストレスには耐えやすいが、持続的なストレスには耐えにくいという。
そして、ネガティブな感情が継続的になると、ストレスホルモンのコルチゾールの分泌が過剰となる。こうなると、免疫力が低下し、記憶を司る脳の海馬が萎縮して、知能が低下する。うつ病などの精神疾患のリスクも増大する(うつ病の人はコルチゾールの値が高いという)。また、慢性疾患のリスクの増大ももたらすという。
加えて、自律神経の交感神経が過剰に優位となる。すると、緊張・不安などによって、不眠症や、それによる生活習慣病のリスクが増大する。また、免疫力・細胞の再生力が低下して病弱になる。精神的には、リラクセーションができず、十分に休息できなくなる。
よって、他を敵視する怒り・恐怖・不安といった感情は、必要な場合に制御し、自分の心身の健康・知能・人間関係が不要に損なわれないようにする必要があるということができるだろう。