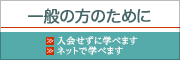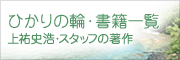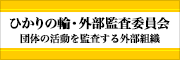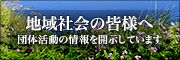2023年 夏期セミナー特別教本「21世紀のための仏教の幸福哲学 縄文以来の宗教と政治・瞑想解説実践編」
(2025年4月28日)
2023年 夏期セミナー特別教本「21世紀のための仏教の幸福哲学 縄文以来の宗教と政治・瞑想解説実践編」
第1章 21世紀のための仏教の幸福哲学
1.絶対神を信じる宗教(religion)と仏教の悟りの道
宗教とは、religionの和訳であり、もとから日本にあった言葉ではないという。religionの原意は、「絶対神との再融合」といったほどの意味である。すなわち、かつては、絶対神と共に楽園に存在した人類が、罪(原罪)を犯してそれを失い、いわば悪魔の虜となった今現在の状態から、再び(救い主であるイエスの信仰などによって)絶対神の御許(おんもと)に戻るといった意味だろう。
これに対して日本には、そもそも宗教という言葉はなく、「宗」とか、「道」という言葉・概念があった。宗とは、道理・真理などという意味で、天台宗・真言宗・浄土宗・日蓮宗・禅宗などといった使われ方をした。道には、人の従い守るべき正しい教え・道徳・道理といった意味があるが、より具体的には、仏道(仏の教え・悟りの教え・八正道など)・神道・道教の道(タオ)から、修験道・剣道・柔道・茶道・芸道・王道・邪道・求道などと使われてきた。
また、絶対神=Godも、日本語の神とは意味が異なり、超越者、創造主ともいわれ、人間や自然を含めた世界を超越した絶対者(超越者)であり、世界が創造される前から存在し、世界を創造した存在である。これに対して、日本語の神とは、場合によっては、人間の中で特別に優れた人をいう場合もあれば、八百万(やおよろず)の神というように、世界万物を神と解釈する場合もある。
そして、仏教開祖の釈迦牟尼(釈迦族の聖者という意味)が説いた教え(初期仏教)は、ブッダ(仏陀)を説くが、これは、人や世界を超越したGodという絶対存在ではなく、人間の中で悟った人(覚った人・目覚めた人)のことを意味するものであった。ただし、それが釈迦の入滅(死後)に、一部の仏教宗派において、人ではなく、徐々にGodと似た絶対者・絶対神的な要素を帯びていった経緯はある。
さらに、釈迦牟尼が直接説いた教え(初期仏教の思想)は、ダルマ(dharma)といわれ、これは、仏陀の教え・仏法という意味であるが、その趣旨は、生きた人間が悟りを得る道であって、悟って苦しみを超越することに主眼があった。よって、これは、絶対神のような絶対存在である仏様を信じることで、その御許に戻って幸福になるという趣旨ではない。
そして、この悟り(覚り)とは、我々の日常用語としても、気づくとか、目覚める、という意味があるように、普通の人が気づいていない、見逃している真理・道理に気づく、目覚めるという意味がある。
そして、ここでの要点をわかりやすく言えば、religionと呼ばれる欧米の絶対神信仰は、基本的に、人間の知性・理性によって、科学の法則のようには、その存在を確認することができない絶対神や絶対神による救いというものを「信じる」思想であるが、(初期)仏教の思想は、普通の人が、一種の愚かさのために、まだ悟っていない=気づいていない真理・道理を「悟る」「気づく」道であって、修行に励んだ人が、その理性・知性を高めることで、ついには気づく(覚る)ことができる真実・真の幸福の道であると、私は理解している。すなわち、人の能力では「悟る」「気づく」ことができず、信じるか信じないかの選択を迫られるreligionとは、異なる性格のものだと思う。
実際に、欧米のキリスト教徒がインドを植民地支配するようになって、その宗教学者が仏教を研究した結果、これは宗教(religion)ではなく人生哲学であると解釈したという。彼らから見れば、仏教は、絶対神・創造主も、それによる世界の創造も、世界の終末も全く説いていない思想であり、信じる=信仰の対象には思えなかったことは想像に難くないのではないだろうか。
よって、現在の日本語においては、同じ「宗教」という言葉・概念の中に含められてはいるが、その中には、religionという「信じる宗教」と、(初期)仏教の「悟りの道」といった異なる概念が混在していると私は思う。そして、本稿で解説しようとしているのは、後者の「悟りの道」の思想である。
2.仏陀の最初の教え:四諦(したい)が説く一切皆苦
まず、仏陀が最初の説法(初転(しょてん)法輪(ぼうりん))で説いた、四諦の教えにこそ、その世界観・幸福観がよく表れている。四諦とは、四つの真理というもので、①この世界は苦しみである(苦(く)諦(たい))、②苦しみの原因は煩悩である(集諦(じったい))、③煩悩を滅すれば苦しみを滅することができる(滅諦(めったい))、④苦しみを滅する道は八正道である(道諦(どうたい))、というものである。
ここで重要なことは、第一に、最初の「この世界は苦しみである」という教えの意味を正しく理解することである。まず、「この世界は苦しみである」というのは、まだ煩悩を有する普通の人(凡夫)に当てはまることであり、この世界自体が、本質的に絶対的に苦しみであるという意味ではない。
煩悩を有する普通の人には、この世界は苦しみと感じられるものである、というほどの意味であり、③の滅諦が説くように、煩悩を滅した悟った人にとっては、この世界は苦しみと感じられるものではなくなるのである。すなわち、人の苦しみ(と喜び)は、人の内側の心理状態によって生じる(面がある)という思想を表している。
第二に重要なことは、この教えにおいて、「苦しみ」という漢訳の仏教用語の元になった言葉は、パーリ語で「dukkha」、サンスクリット語で「duḥkha」であるが、これは多義語であって、単に苦痛という意味だけではなく、それに加えて、不安定、不満足、不完全といった意味があることだ。
そして、この教えにおいては、この後者である「不安定、不満足、不完全」という意味が重要になる。実際に、煩悩を有する普通の人にも、この世界は、苦しみ・苦痛ばかりではなく、喜び・快楽もあると感じられるわけだから、dukkhaが単に苦痛という意味しかないのであれば、この教えを合理的に納得することは難しいだろう。
3.苦楽表裏・無常・一切皆苦の教え
これを言い換えるならば、dukkhaという言葉は、喜びと苦しみの二つがある中で、その中の苦しみの方を意味する言葉では必ずしもないのである。それは、なぜかというと、仏教の思想では、「苦楽表裏」などといって、苦しみと喜びは、じつは表裏一体であって、別々のものではないという思想があるからだ。より具体的に言えば、例えば、人の感じる喜びは、不安定なことに、それ自体が、さまざまな苦しみの原因を作って、苦しみに変わっていくと説くのである。
これは、仏教が重視する「無常」の教えの一環でもある。喜びを感じることがあっても、その心理を客観的に長期的によく見ると、それは一時的な現象であって、その喜び自体が原因となって、さまざまな苦しみが生じるというのである。喜びは、苦しみに変わっていく無常なものであるというのである。
よって、「この世界は苦しみである」という苦諦の教えは、「一切皆苦」とも表現されることがある。一切皆苦も、この世界の一切は苦痛であるという意味ではなく、煩悩を滅して悟りを得ていない人には、この世界の中の喜びは、ことごとく苦しみに変わっていく、不安定なもの(dukkha)であるという意味がある。言い換えれば、煩悩を滅して悟りを得ていない人には、この世界には、安定的で満足できる完全な喜びは例外なく一切ない、といった意味である。
それでは次に、なぜこのように言うことができるかを理解するために、人が喜びや苦しみを感じる心理のメカニズムを見ることにしたい。
4.人が幸福・不幸を感じる心理の中核に優劣の比較がある
人の主な幸福・不幸は、自分では気づかないうちに行う、前の自分や、友人・知人などの他人との比較によって生じる。前の自分や友人・知人などの他者と比較して、(今の)自分が優っていれば、喜び(優越感・達成感)を感じ、劣っていれば、苦しみ(劣等感・喪失感)を感じるのである。そのため、人には「今よりもっと、他人よりもっと」と求める欲求がある。
そして、心理学的な研究によれば、飢え・渇きや戦争といった、絶対的な苦痛がなくなった現代の先進国社会では、自と他の優劣の比較による幸福・不幸が、大きなウェートを占めるといわれる(心理学的に言えば、現代人の幸福・不幸は、自己愛の充足の有無で生じると表現することがある)。
なお、ここで少し脱線するかもしれないが、仏教の教えによれば、この比較に基づいた際限のない欲求は、人間社会に広がった心の癖のようなものである。それは、仏道の修行によって取り除くことが可能なものであって、人間にとって絶対的に避けられない欲求ではない。
では、話を元に戻して、この人間の喜びを感じる心の仕組みを具体的な事例で考えてみよう。例えば、月給が、20万円の人が、30万円に上がるならば、喜びを感じるだろうし、15万円に下がれば苦しみを感じる。また、自分の月給が30万円で、他人が20万円であれば、喜びを感じ、その逆であれば苦しみを感じる。
5.得た喜びがすぐに消えていく心のしくみ
そして、20万円の給料が30万円に上がった後、それがしばらく続くと、上がった時に感じた喜びは消えて、「もっと欲しい」という欲求不満が生じる。これは、給料が30万円に上がった時は、その30万円と、それ以前の20万円を比較して、喜びを感じたが、その後、30万円の給料が続いて、それが当然のものとなれば、比較の対象が20万円ではなくて、30万円になるからである。
そのため、30万円より多くを得ないと喜びを感じなくなり、より多くを求めることになる。これが、「人の欲求には際限がない」とよく言われる背景にある心の仕組みである。
6.際限なく求める心理状態に関する脳科学の知見
なお、この点を脳科学的に説明すると、生きるために有益な何かを獲得することによって喜びを感じるのは、その際にドーパミンという神経伝達物質が分泌されるからである。このドーパミンは、「獲得と意欲のホルモン」などといわれる。
すなわち、①人が何かを求めて獲得した時に、喜びを感じさせるとともに、②獲得の前に、獲得しようとしている時にも分泌されて、獲得の意欲を形成するのである。例えば、古代人であれば、その日を生きる糧を得るために狩猟などをする際に、狩猟に成功した時の喜びと、狩猟しようとする意欲を形成するのである。
ところが、このドーパミンは、何度も同じ刺激を受けていると出なくなるという性質がある。すなわち、先ほどの生きる糧の食べ物の例でいえば、現代人は毎日、1日3食がさしたる苦労もなく当たり前のように差し出される。そのために苦闘と空腹の果てに、獲物を獲得した古代人のような喜びは経験できない。
よって、ドーパミンが分泌されて喜びを感じるためには、以前より、より強い刺激、より多くの刺激が必要になる。すなわち、先ほどの月給の話でいえば、月給が20万円から30万円に上がっても、30万円が続いて当然のものとなれば、40万円、50万円と「もっともっと」と際限なく求める欲求が生じることになる。
こうして、脳科学的な視点から見ても、人の心理は、なかなか満足することがなく、際限のない欲求を抱く傾向があるのである。ただし、こうした人の心理も、仏教の教えから見れば、その性質を人がよく自覚して、それを制御しようと努めるならば、徐々に弱まっていくものである。これを言い換えるならば、人の脳神経ネットワークの働きは、努力によって、変更・調整が可能な面があるということである。
7.得た喜びは消えて、得られない苦しみが生じる
ところが、当然のこととして、どんなに恵まれた人であっても、望むものすべてが得られることはない。むしろ「求めても得られないことが多い」と感じるのが、人間の常ではなかろうか。人によっては、「自分の望みはなかなかかなわず、自分は(他人と比較して)恵まれていない」と感じる人も多い。
なぜそうなのか? その原因の一つは、客観的に見れば、当然のことである。すなわち、自分だけではなく、皆が同じように、より多くを求め、多くの人々の間に、激しい競争、すなわち、幸福の奪い合いが生じるからである。その結果、求めて得られない場合は、前に述べた通り、苦しみを感じる。
そして、「今よりもっと、他人よりもっと」と求めて幸福になろうとすることは、自分が幸福を感じる時は、その裏側に、自分に負けて不幸を感じる人が必ず存在することになり、幸福を奪い合い、苦しみは押し付け合うという、人と人との間の関係が生じることになる。
これは、際限なく求めて幸福になろうとする限りは、自分の幸福の裏に他人の不幸が、他人の幸福の裏に自分の不幸があることになり、すべての人が幸福になることは、原理的に不可能ということになる。
そして、「勝ち組・負け組」という言葉が、社会に広がっているが、これは、他人よりもっと得て幸福を感じる勝ち組と、他人ほどには得られずに不幸を感じる負け組に分かれていると感じることを表しているのだろう。このため、飢餓や戦争がなくなった現在の日本社会でも、依然として多くの人が満足を感じていないのではないか。
8.絶えず不満を抱え、満ち足りることが乏しい人の心
さてここまでの検討をまとめてみると、「今よりもっと、他人よりもっと」と求める限りは、①得られなければ、最初から苦しみが生じるが、②得られて喜ぶ場合も、それは一時的なもので、それに永久に満足することなく、すぐに喜びは消えていき、より多くを求めるが、③求めても得られないことは多いため、得られない苦しみ・不満を絶えず感じる心理状態になることがわかる。
この心理状態の流れを客観的に長期的に見るならば、得て感じた喜びは、ほどなく消えていき、より多くを求めても得られない苦しみ・不満に変わっていくということもできるだろう。これは、冒頭に述べた、喜びの裏側に苦しみがある(苦楽表裏)、喜びは一時的で、それが苦しみに変わっていく(無常)を示す事例の一つにほかならない。
こうして、人は、絶えず欲求不満を抱える傾向があって、そのために、充足した状態、満ち足りた心理状態には、なかなかなりにくい。現代社会で頻繁にいわれる精神的な「ストレス」も、客観的に見るならば、じつは、この絶え間ない欲求と不満が背景にあると思われる。多くの人が、気づかないうちに、絶えずさまざまな「不満」を抱えていて、今のこの時に十分に充足した心の状態には、なかなかならない。
例えば、皆さんは、人生において、これまでに「満ち足りた心境」というものを経験したことがあるだろうか? もしあれば、それは、いつのことだろうか? 何年前? 何カ月前? 何日前? 今日は一時でもあっただろうか。
9.得たものを失う不安・苦しみ
次に、何かを得て喜ぶと、それと同時に、それを失う不安・苦しみが生じ、それを守ろう、失うまいというストレス・苦しみが生じる。しかし、長期的に見れば、後で詳しく述べるように、老い・病み・死ぬ中では、すべてのものを失っていくのが人生である。また、より多くを得れば得るほど、失う不安、守る苦しみ、失う時の苦しみも大きくなる。
しかも、得た時の喜びは、先ほど述べたように、しばらくするとそれに慣れてしまう形で消えていき、より多くを求める欲求不満になるにもかかわらず、得たものを失う不安、守る苦しみ、失ったときに苦しむことは続くのである。月給20万円が30万円になった後に、30万円が当然のものとなって喜びを感じなくなっても、30万円から20万円に減るならば、苦しみを感じることになる。
これは不合理のように思えるが、現実であることは間違いない。この原因は、最初に述べたように、比較によって幸福・不幸が生じるが、時々によって比較の対象が変化するためである。すなわち、以前よりも多くを得た時に、それが続くと、増えた状態と比較して、より多く得ないと幸福を感じなくなる一方で、増えた状態と比較して、より少なくなってしまえば不幸を感じるからである。
10.得ることで、とらわれが増えると、精神的な不自由も増える
この状態を客観的に見るならば、前より多くを得ることで、比較の対象が変わった結果、苦しみに弱くなってしまったという見方もできる。たとえば、月給が20万円であった時は、それでそれなりにやっていけていたのに、30万円に上がったために、30万円にとらわれて、30万円なしではいられなくなってしまい、20万円に落ちると苦しみを感じるということだからである。
つまり、より多くを得て喜ぶと、幸福・不幸を決める比較の基準が上がり、その結果、苦しみなく生きることができる(月給の)範囲が狭くなるということである。苦しみなく生きていくことができることを、その人の(精神的な)自由・幸福であると考えるとすれば、その意味での幸福や自由は、逆に、減ってしまったことになる。ある意味で、精神的には弱みが増えたようなものである。
これは、30万円という月給に対して「とらわれ」が生じた状態であるとも表現できるだろう。30万円になった時に、再び20万円に戻る不安を抱いて、戻らないように、30万円を守ろうとして気をもみ、ストレスを感じるのである。すなわち、20万円から30万円に月給が増えたが、その結果として、とらわれ=精神的な不自由も増えたということである。
これもまた、冒頭に述べた、喜びの裏に苦しみがある、苦楽表裏の現象の一つである。例えて言うならば、木は高く登れば気持ちが良いが、高く登れば登るほど、落ちる不安や落ちた時の痛みも大きくなるということである。
そして、ある心理学的な見解では、20から30に上がった時の喜びより、30から20に下がった時の苦しみの方が大きく感じるという見解もある(喜びの大きさと苦しみの大きさを同じ尺度で科学的に計量することはできないため、あくまでも主観的・心理的な印象に基づく見解であるが)。これは、「欲しい」と思う気持ちよりも、それを得た後に、「失いたくない」「失うのが嫌だ」と思う気持ちがより大きい(場合の)ことを示しているのではないだろうか。
しかしながら、仏教の教え・修行においては、より多くを得たとしても、それに対する(精神的な)とらわれを生じさせない工夫をすることで、その裏側に失う不安や苦しみが生じることを予防することができる。それについては後に詳しく述べる。
11.自分の幸福を妨げる者、奪い合いによる怒り・憎しみ・妬み
さらに、「今よりもっと、他人よりもっと」と、皆が求める社会の中では、当然奪い合いが生じる。より多くを求めるのは自分だけではないのである。すると、自分の幸福を妨げる、奪う他者に対する怒り、憎しみ、妬みが生じることになる。
しかも、これは、より多くを得れば得るほど強くなる。なぜなら財物や地位や名誉も、より大きなものほど、得ることができる人は少なく、競争・奪い合いは激しいからである。すなわち、ピラミッド構造になっており、上に行くほど、小さく狭くなっているのである。
前と同じ木登りの喩えでいえば、木は上に行けば行くほど、細くなっており、より少ない人しか登ることはできない。すると、怒り・憎しみを抱いて、蹴落とし合うことが多くなり、自分より上の他者を、憎む、妬むことになるのである。
12.怒り・憎しみの対象=「敵対者」を作り出す自分の心
ここで注意しなければならないのは、人は、自分の幸福を奪う、損なう、妨げる者を「敵」とみなして、怒り・憎しみ・妬みを抱くが、自分の欲求が強ければ強いほど、他人を敵と感じやすくなる一面があるということである。すなわち、他人ばかりが悪いわけではなく、他人の在り方と、自分の心の在り方の双方が、自分の中に「誰かが敵だ」という認識を作り出すのである。
よって、自分でも気づかないうちに、多くの欲求・欲望を持っている人ほど、欲求の少ない人に比べて、より多くの他人を「自分の敵」と認識する心理状態に陥ることになる(しかし、本人はそれを自覚していない場合が多い)。仏教では、この点に注目し、自分が敵対者と見なす者に対して、自分の内省を含め、深い考察をすることの重要性を説く。そして「敵は教師」という教えもある。イエスが説いた「汝の敵を愛せ」という教えにも通じるのではないかと思う。
13.怒り・憎しみがもたらす不幸:人間関係の悪化
先ほど述べたように、「他人よりもっと」と際限なく求める心が強ければ強いほど、いろいろな意味で、自分の幸福を妨げると感じる他者、怒りや憎しみを感じる他者は、増えることになる。
ところが、その心の働きと言動は、敵対視した他人から自分の幸福を守る結果ばかりにはならず、逆に、自分の幸福を損なう結果を招くことが多い。これは、「人を呪わば、穴二つ」「情けは人の為ならず」などと昔からいわれてきた普遍的な道理・道徳ではある。しかし、現代社会に至っても、これは十分には根付いていないと思うので、よく検討してみたいと思う。
まず、例えば、他に怒り・憎しみを抱いて、何かしらの苦痛や攻撃を加えれば、苦しめられた他人からは当然、同じ怒り・憎しみが返ってくる当然の道理がある。例えば、他人の悪口をことさら言う人がいるが、こうした人は当然嫌われ、不幸になることになる(なお、他人に具体的な問題がある場合、それを論理的に指摘することは悪口ではないだろう。また、相手の成長を願ってのものであれば、利他・愛の行為でもあるだろう)。
14.心理学が示す、怒り・憎しみ・攻撃性が招く不幸
しかし、精神科医の樺(かば)沢(さわ)紫(し)苑(おん)氏によれば、現在、自分の中のコンプレックスを紛らわすために、絶え間なく悪口を言う悪習慣に陥っている人たちが少なくないという。同氏は、これを悪口依存症と表現しているが、負け組の人が、無理に勝ち組になろうとして、無理な悪口を言う状態であろう。自分の側に何かの問題が発覚した時には、他人から集中的に批判されて、擁護されることもないだろう。
また、現代心理学の一部では、人が幸福になるために必要な基本的な条件として、心の安定・健康・知性に加えて、良い人間関係を説く。この点に関連して、京都大学の藤井聡教授は、幸運の正体を解明するために、「幸福な人・幸運な人とは、どんな人なのか」に関する社会学的・心理学的な調査・研究を行った。
その結果として、配慮範囲が広くて長い人(より多くの他者に配慮し、より長期的に考える人)が、長期的には、自分の周辺に盤石な人脈・ネットワークを作ることができ、その人を幸福にしようとする多くの人に恵まれて、幸福になることが判明した。
一方、配慮範囲が狭くて短い人(自分のことばかり、目先のことばかり考える人)は、最初は効率よく幸福になるように見えるが、本人の主観的な幸福感は乏しく(欲望が大きいからと思われる)、長期的には、豊かな人脈は形成できないために、多くの損失を被る人生となることが判明した。
そして繰り返しになるが、現代心理学の一部も、人が幸福になるための基本的な条件(リソース)として、心の安定、健康、知性に加えて、良い人間関係の重要性を指摘している。
15.脳科学が示す怒り・攻撃性が招く不幸:心身の不健康
脳科学的に見ると、自分の勝利・優位を妨害する他の存在に対する怒り・憎しみ・攻撃性が強すぎると、アドレナリンやコルチゾールといったストレスホルモンの過剰な分泌を招き、心身の不健康や、知力の低下、寿命の短縮を招く。
これらのホルモンは、身の危険の脅威などがある時には、それと闘ったり、それから逃避したりして自分を守るために、必要不可欠なホルモンである。しかし、現代人の場合は、身の危険に限らず、しばしば自分の利益・価値を害するとみなして、他を敵視・恐怖・嫌悪する場合が少なくない。
こうして、ストレスホルモンの過剰分泌の状態になると、アドレナリンの場合は、高血圧・高血糖・動脈硬化・脳卒中や心筋梗塞などの心血管障害のリスクを高める。コルチゾールは、免疫の低下、高血圧・高血糖、糖尿病、肥満、癌、うつ病などのメンタル疾患のリスクを高め、不健康を招くことになる。
さらに、コルチゾールの分泌過剰は、記憶に関係する脳の海馬を委縮させてしまい、記憶力や目標達成力を損ない、不幸を招くことになる。まさに「人を呪わば穴二つ」ということである。先ほど述べた悪口依存症に関しては、悪口が多い人は、認知症になるリスクが2倍ほど高く、寿命が5年ほど短いといった欧州での統計的な研究結果もあるという。
逆に、他に対する感謝や慈しみは、幸福ホルモンといわれる、セロトニン・エンドルフィン・オキシトシンの分泌を促進させる。感謝の心は、エンドルフィンを分泌させる。このホルモンは、癒しのホルモンといわれ、鎮痛効果、免疫向上、細胞再生・新陳代謝、抗がん効果、若返り効果などがあるとされる。
オキシトシンは、他への慈しみの感情とともに分泌され、慈しみのホルモンといわれるが、幸福感、ストレス解消、不安の解消(脳の偏桃体の過剰な振動を鎮める)、副交感神経を活性化させてリラックス・安心・休息を促進、免疫力の向上、血圧等の低下による心臓・心血管障害の回避に役立つ。
さらに、エンドルフィンもオキシトシンも、コルチゾールとは反対に、記憶力・集中力・目標達成力を向上させる効果があるとされる。
こうして、脳科学と心理学の研究結果から、自分の目先の利益しか考えず、不満・怒り・憎しみが強い心や言動は、他人を苦しめるとともに、自分自身に、心身の不健康・知力の低下・人間関係の悪化といった、さまざまな不幸を招く。
逆に、感謝・慈しみの心や利他的な生き方は、他者を幸福にするとともに、本人自身を幸福にする。心身を健康にして、知力・集中力・目標達成力を高め、人間関係を改善し、幸福をもたらすのである。これは、まさに仏教が説く、利他こそが真の利己であり、自他の幸福は一体であるという思想を裏付けている。
16.人はなぜ、自ら不幸を招く生き方をするのか
こうしてみると、人は、自分の目先の利益ばかりにとらわれ、自ら不幸を招く生き方をする面があることがわかる。これはいったいなぜであろうか。仏教の教えによれば、それが、悟っていない人たち全てが抱える精神的な愚かさであり、漢訳仏教用語では、痴(無智)などと呼ばれる。
そして、この無智のために、自らに不幸を招く欲求である貪りや怒りといったさまざまな煩悩が生じるとされる。すなわち、煩悩を戒める仏教は、快楽を捨てろと説いているのではなく、刹那的には心地よくても、長期的に見れば、自分にさまざまな不幸をもたらす自滅的な欲求を戒めているのである。
よって、この無智とは、自分だけの自己中心的な、目先の刹那的な利益・快楽ばかりしか認識することができず、そのため、他人と共に得る自分の長期的な本当の幸福を損なうことが認識できない心理状態である。わかりやすく言えば、「今の自分さえよければいい」という未成熟な心理状態である。
実際には、今の刹那だけではなく、長期的な幸福を考えれば、自分と共に他人の幸福も図ることが必要であるが、仏教の教えから見れば、現代に至ってもなお、人間は、十分に無智を乗り越えてはいないのである。その意味で、仏教の思想は、人間が幸福になるためには、その理性・知性・知恵がいまだに不十分な段階であり、それを深めて進化するべきであると説く思想ということができると思う。