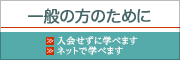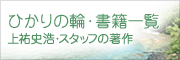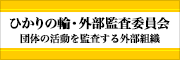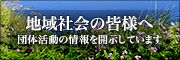2023年 GWセミナー特別教本「覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始」
(2025年4月28日)
2023年 GWセミナー特別教本「覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始」
第1章 仏教の悟りの幸福哲学
1.はじめに
ここでは、仏教の基本的な世界観・幸福観のエッセンスに関して述べたいと思う。これは仏教の瞑想を行う上でも、非常に重要である。というのは、仏教で最も重要な瞑想とは、智慧や慈悲といった、その教えのエッセンスを繰り返し修習して、心身に浸透させるものであるからだ。すなわち、教えの言葉を知っていても、その意味を深く理解していてこそ、効果的な瞑想を行うことができ、心の浄化、意識の改革を実現することができるからである。
2.仏陀の最初の教え:四諦(したい)が説く一切皆苦
まず、仏陀が最初の説法(初転(しょてん)法輪(ぼうりん))で説いた、四諦の教えにこそ、その世界観・幸福観がよく表れている。四諦とは、四つの真理というもので、①この世界は苦しみである(苦(く)諦(たい))、②苦しみの原因は煩悩である(集諦(じったい))、③煩悩を滅すれば苦しみを滅することができる(滅諦(めったい))、④苦しみを滅する道は八正道である(道諦(どうたい))、というものである。
そして、特にまず、最初の「この世界は苦しみである」という教えの意味をよく理解する必要がある。まず、「苦しみ」という漢訳仏教用語のサンスクリット原語「ドゥッカ」であり、それは単に苦痛という意味ではなく、不安定、不満足、不完全といった意味を持っている。つまり、単に喜びと苦しみの中の苦しみという意味ではない。これはなぜかというと、仏教では、苦楽表裏といって、苦しみと喜びは表裏一体で、別々のものではないという思想があるからだ。つまり、喜びであっても、不安定なことに、それがさまざまな苦しみに変わっていってしまうといった意味合いがあるのである。
次に、この苦諦は「一切皆苦」とも表現される。つまり、(煩悩を滅して悟りを得ない限りは)この世界のことごとくがドゥッカであるといったほどのニュアンスがあるのである。すなわち、ドゥッカではないもの、安定的で、満足できる、完全な喜びはなく、これは例外がないといった意味合いがある。
ではなぜ、このように言うことができるかを考えるために、人が喜びや苦しみを感じる心理のメカニズムを見ることにしたい。
3.人が幸福・不幸を感じる心理の中核に優劣の比較がある
人の主な幸福・不幸は、自分では気づかないうちに行う、前の自分や、友人・知人などの他人との比較によって生じる。前の自分や友人・知人などの他者と比較して、(今の)自分が優っていれば、喜び(優越感・達成感)を感じ、劣っていれば、苦しみ(劣等感・喪失感)を感じるのである。
これについて、心理学的には、幸福・不幸は自己愛の充足の有無で生じると表現することがある。特に、飢え・渇きや戦争といった、絶対的な苦痛がなくなった現代の先進国社会では、この比較による幸福・不幸が大きなウェートを占めるといわれる。
例えば、給料が20万円の人が、30万円に上がれば喜びを感じるが、それが続くと、当初感じた喜びは消えて、もっと欲しいという欲求不満が生じる(欲求に際限がない)。これは、最初は前の20と今の30を比較して喜びを感じたものが、時とともに前の30と今の30を比較するからである。
なお、脳科学的に説明すると、生きるために有益な何かを獲得することによって喜びを感じるのは、その際にドーパミンという神経伝達物質が分泌されるからであるが、これは何度も同じ刺激を受けていると出なくなる。よって、より強い刺激、より多くの刺激が必要になる。すなわち30ではなく40、そして50と、「もっともっと」と際限なく求める欲求が生じる。こうして、脳科学的な視点から見ても、人の心理は、なかなか満足することがなく、際限のない欲求を抱く。
ところが、より多くを求めても、得られるとは限らない。これは当たり前のことであるが、その原因の一つは、客観的に見れば、自分だけでなく、皆が同じように、より多くを求めて、人の間の競争・奪い合いが生じるからである。その結果、求めて得られない場合は、前に述べた通り、苦しみを感じる。
4.得た喜びが消えて、得られない苦しみ・不満を生み出すメカニズム
こうして、「今よりもっと、他人よりもっと」と求めて、①得られなければ苦しみが生じるが、②得られて喜んだとしても、長期的に見るならば、それに満足することなく、より多くを求めようとする欲求が生じ、それが得られないという苦しみ・不満を感じる結果となるのである。
これを長期的、大局的に見るならば、得て喜んでも、その喜びが消えて、より多くが得られない苦しみ・不満に変わっていくということができることがわかるだろう。
この心理は、現代社会では非常に多く、「欲求不満」・「ストレス」などと表現されることが多い。現代社会で多くの人が、絶えずなにかしらの「不満」に心がとらわれていて、今のこの時に、十分に充足していないのである。
わかりやすく言えば、満ち足りた心境にないということである。例えば、皆さんは、人生において満ち足りた心境を経験したことがあるだろうか? もしあれば、それはいつのことだろうか? 何年前? 何カ月前? 何日前? 今日は一時でもあっただろうか。
5.得たものを失う不安・苦しみ
次に、何かを得て喜ぶと、それと同時に、それを失う不安、守る苦しみが生じる。そして、ついに失う時には苦しみが生じる。そして、より多くを得れば得るほど、失う不安、守る苦しみ、失う時の苦しみも大きくなる。
しかも、得た時の喜びは、先ほど述べたように、しばらくするとそれに慣れてしまう形で消えていき、より多くを求める欲求不満になるにもかかわらず、得たものを失う不安、守る苦しみ、失ったときに苦しむことは、続くのである。すなわち、20が30になった後、30に喜びを感じなくなっても、30から20に減ると苦しみを感じるのである。
これは、30に対して「とらわれ」が生じている状態であるとも表現できるだろう。30になった時に、再び20に戻る不安を抱き、戻らないように、30を守ろうとして気をもみ、ストレスを感じることも多い。
また、ある心理学的な見解では、20から30に上がった時の喜びより、30から20に下がった時の苦しみの方が大きく感じるという見解もある(喜びの大きさと苦しみの大きさを同じ尺度で科学的に計量することはできないため、あくまでも主観的な心理的な印象に基づく見解であるが)。これは、「欲しい」と思う気持ちよりも、それを得た後に、「失いたくない」「失うのが嫌だ」と思う気持ちがより大きい(場合の)ことを示しているのではないだろうか。
こうして何かを得た場合、それと同時に、それを失う不安、失うまいとする苦しみ、実際に失った時の苦しみが存在する。例えて言えば、木は高く登れば気持ちが良いが、高く登るほど、落ちる不安や落ちた時の痛みは大きい。
6.自分の幸福を妨げる者、奪い合いによる怒り・憎しみ・妬み
さらに、「今よりもっと、他人よりもっと」と、皆が求める社会の中では、当然奪い合いが生じる。より多くを求めるのは自分だけではないのである。すると、自分の幸福を妨げる、奪う他者に対する怒り、憎しみ、妬みが生じることになる。
しかも、これは、より多くを得れば得るほど強くなる。なぜなら財物や地位や名誉も、より大きなものほど、得ることができる人は少なく、競争・奪い合いは激しいからである。すなわち、ピラミッド構造になっており、上に行くほど、小さく狭くなっているのである。
前と同じ木登りの喩えで言えば、木は上に行けば行くほど、細くなっているから、多くの人が登ることはできず、そのため、怒り・憎しみを持って蹴落とし合うことが多くなり、自分より上の他者を憎む、妬むことになるのである。
7.これ以上は幸福な人が増えない? 先進国社会の現状:意識調査から
こうして、私たちの幸福・不幸は、自分たちが気づかないうちに、前の自分や他人との優劣の比較に基づいているために、意識調査をするならば、次のような不合理で理不尽ともいうべき心理状態が生じることになる。
① 先進国では30年前と比較して、「自分は幸福だ」と感じる人の割合が増えていない。
これは、客観的には、人々の(平均的な)所得や利便性は増えているが、人々の間での、勝ち組と負け組の割合は決して変わらないためではないかと思われる。
② 日本では30年前と比較して、「幸福だ」と感じる人の割合が減った。日本でもお金や
利便性は増えているが、他国と比較すればデフレ・失われた30年となったし、市場原
理主義改革で貧富の格差が増え、富の集中が起こった。
③ 自分の給料が多くても、他の給料がさらに多ければ、自分の給料が少なくても、他の給料がさらに少ない場合の方が、幸福を感じる(次ページの図を参照)。例えば、自分の給料が25万であっても、他の給料が10万であるならば、自分の給料が50万で、他の給料が100万である場合より幸福を感じる。
④ 幸福を感じる割合が一番多いのは、年収が700万円前後の人で、年収がそれ以上になると逆に幸福を感じる人が減る。なお、ある調査では、年収が1万5千ドル(日本でいえば生活保護受給の水準)以上になると、それ以上のお金を得ても、幸福感は増えないというものもある。
⑤ かつて経済水準は低いのに国民の幸福感が先進国並みに高いことで「幸福の国」として有名になったブータンは、それまでの情報鎖国を解消すると、幸福感が大幅に落ちてしまった(より恵まれた他国の状況を知ったからだと思われる)。
以上をまとめてみると、途上国のような絶対的な飢餓・貧困といわれるものや戦争がなくなって、社会保障や医療制度などの社会制度が整い、一定の健康で文化的な生活ができる先進国社会に関して言えば、これ以上、お金や利便性が増えても、これ以上幸福になることはできない(幸福を感じる人の割合は増えない)状況に至っているということができないだろうか。
8.老いる中でますます苦しみが大きくなる。幸福が尻すぼみの人生
さらに、こうして、求めても得られない苦しみ・不満、得たものを失う不安や苦しみ、奪い合いの苦しみは、年をとるほどに大きくなる。なぜならば、老いるほど、たいてい、求めて得る力は衰え、いろいろな意味で失うことが増え、他者に奪い負けることが増えるからである。最後には、命も失い死ぬことになる。
そこで、仏教は、人の苦しみを分類した「四苦八苦」という教えがある。仏教用語としての四苦八苦は、非常に苦しいという意味である日常用語としての四苦八苦ではなく、人間が苦しむさまざまなパターンを示して、まとめたものである。
それは、①求めても得られない苦しみ、②愛着したものと別れる苦しみ、③憎しみの対象と出会う苦しみ、④一切の存在にとらわれることによる苦しみ、⑤生まれる(出産の)時の苦しみ、⑥老いの苦しみ、⑦病の苦しみ、⑧死の苦しみである。
こうして、人生全体を見渡してみると、人生後半の老いた時期の方が、求めても得られない、得たものを失う、奪い合いに負けることは多くなる。苦しみがより多くなるのである。よって、老人はよく「若い人はいいね」と言う。今や、長寿社会といわれるようになったが、その中でも、「苦しく長い老後は嫌だ」と思ったり、「苦しまずに楽に死にたい」と思ったりする人は多い。
言い換えれば、(「今よりもっと、他人よりもっと」と求める普通の人の)人生の幸福は、残念ながら「尻すぼみ」なのであり、言い換えれば、「苦しみが尻上がり」なのである。若いうちには、喜んだり苦しんだりするし、人生は楽があれば苦しみがあると考えるが、それがだんだん、時とともに、苦しみの方が喜びより多くなって、最後は、すべてを失う死という最大の苦しみが待っている。
これは当たり前のことで、全ての人に起きることだから、特に若いうちは考えることが少ないかもしれないが、人生全体を見渡す長期的な視点を持って見ると、普通の人の人生の幸福は、尻すぼみである。
9.一切皆苦をあらためて検討する
ここで先ほど述べた「一切皆苦」について検討してみよう。結論から言えば、「今よりもっと、他人よりもっと」と、際限なく求め、煩悩の欲求のままに生きる限りは、以下のような苦しみの現実があり、それを考えると、一切皆苦を説いた釈迦牟尼の人生観に納得ができるのではないだろうか。
①この世界で、この喜びを得たならば、一生の間ずっと満ち足りて飽きることなく、 「もっと欲しい」という欲求と不満が生じないものは、一つもない。そして、「今よりもっと、他人よりもっと」と求めて、欲しいものは何でも得ることができる人も、一人もいない。
②木に高く登れば登るほど、落ちる不安・落ちた時の痛みが大きいように、喜びを得ると、その裏に、失う不安・守る苦しみ・失ったときの苦しみが生じる。そして、この世界に、どんなに高く登っても、落ちた時の痛みがない木は、一本もない。
③木は、高く登れば登るほど細くなり、多くの人が登ることができないように、「もっ
ともっと」と、皆で求めて奪い合う中で、得れば得るほど、奪い合い・競争は激しくなり、怒り・憎しみ・妬みも強くなる。そして、この世界に、上に行くほど太くなる木は一本もない。
④これまでの①から③をまとめてみると、この世界のすべての喜びは、時とともに、なにかしらの不満・不安・失意・怒り・憎しみ・妬みの原因となり、その意味で、不安定で、不満足で、不完全なものである( → 一切はドゥッカ・一切皆苦である)。
⑤さらに、「今よりもっと、他人よりもっと」と求めたとしても、老いるほどに、求めても得られないこと、かつて得たものを失うこと、他人に奪い負けることが多くなり、最後は死んですべてを失う。そして、この世界に、老いない人、死なない人は一人もいない。
よって、そのように求めて生きても、不満・不安・失意・怒り・憎しみ・妬みといった苦しみは、時とともに増大していくのが人生である。
10.幸福な人の割合が増えることは、ますます難しくなる? 長寿高齢化の先進国社会
先ほど、この30年の間に、先進国社会では幸福を感じる人の割合が増えていないと述べた。ここでは、老いる(高齢期の)苦しみに関しても、(先進国)社会に当てはめて考えてみたい。
現在、特に日本をはじめとする先進国は、医療技術などの発展で寿命が延び、長寿社会ともいわれるようになった。これ自体は良いことのように思えるが、しかし、長寿社会の人生とは、若い時よりも不幸である高齢期が長い人生を送る社会である。
介護なく健康に生きることができる健康寿命は、平均寿命より10歳ほど短く、その意味で、人生の終盤は、健康で楽しく生き切ることができる人は少ない。以前は、若いうちは派手にやって、年を取ったら苦しまずにさっさと楽に「ピンころ」で死ぬことが理想とされる面もあったが、現代社会は、悪く言えば、医療技術のために(不健康なのに)簡単には死ねなくなった面もあるかもしれない。老いる苦しみとは、言い換えれば、若さや健康などを失う(失っていく)苦しみと言うこともできるだろう。
そして、そんな老後を不安に思う人が多く、数年前も老後のために数千万円の貯蓄が必要であるといった主張が物議をかもし、政治問題化したばかりである。
さらに、長寿社会の先進国は、同時に少子化の問題で悩み、若年層の人口の割合が減り、高齢者の割合が急速に増加する「高齢化社会」である。だとすると、ますます幸福を感じる人の割合が増えることが難しい社会になっていくという恐れがないだろうか。
11.諸行無常・諸法無我の教え:「四(し)法(ほう)印(いん)」
仏教を代表・象徴する四つの教えとして「四法印」がある。それは「諸(しょ)行(ぎょう)無(む)常(じょう)」「諸(しょ)法(ほう)無(む)我(が)」「一切(いっさい)皆(かい)苦(く)」「涅(ね)槃(はん)寂(じゃく)静(じょう)」という四つの教えである。
ここで、一切皆苦の意味合いは、四苦八苦の教えなどを通して、すでに説明したが、諸行無常や諸法無我の教えも、一切皆苦と本質的に通じるものであり、ある意味で、それを言い換えたものだと言うことができる。
まず、「諸行」と「諸法」は、細かく言えば多少の違いはあるが、大雑把には、すべての存在・現象・物事といった意味である。よって、一切皆苦の「一切」と同じである(実は「一切皆苦」の原語を忠実に訳すと「一切行苦」であり、すなわち「諸行苦」と同じである)。
そして、「無常」とは、移り変わる、生じては滅するという意味である。先ほど述べたように、あらゆる喜びは、それを得るとともにさまざまな苦しみの原因となって、時とともに苦しみに変わっていく。さらに、人は、この世に生を受けて、一時的に若さと健康の喜びを得ても、時とともに老い病み死んで、それを失い、苦しみが増えていく。
また、「諸行無常」の「無常」と「一切皆苦」の「苦」が、本質的に同じことを意味することも、苦の原語のドゥッカが、不安定、不満足、不完全という意味であることを考えれば、理解できるだろう。不安定とは、まさに無常ということである。あらゆる喜びが、時とともにさまざまな苦しみに変わっていくので、それは無常であり、不安定=ドゥッカなのである。
また、これは先ほども述べたが、仏教では、苦楽を別々のものではなく、表裏一体のものと見る(これを苦楽表裏という)。そして、苦楽表裏は「苦楽無常」と言い換えることができる。なぜならば、喜びが苦しみに、また逆に苦しみが喜びに転じていく道理があるからである。
また、「無我」というのは、私、私のもの、私の本質ではない、といったほどの意味である。これも「無常」とともに考えるとよく理解できる。人生全体を見渡す長期的な視点を持つなら、財物・地位・名誉はおろか、自分の体や若さ・健康さえ、一時的に得たにしても、時とともに失うのが定めである。
これを言い換えれば、それらは、本当の意味では(長期的な視点から見れば)、私のものではなく、しばらくしたら天に返すために、一時的に預かっているもの、預かりものである。私たちの体を構成する材料である分子も、財物や地位や名誉も、やってきては去っていき、無数の人々・生き物の間を巡り続けていく。自分のものではなく、皆で共有し、使いまわしているものだということができる。
なお、この「無我」の意味の解釈としては、上記の解釈(私・私のもの・私の本質ではない)に加えて「永久不変の本質がない」という意味もある(一つ目の解釈は、釈迦牟尼の直説に見られるもので、二つ目は釈迦の死後に生まれた解釈である)。この意味においては、それは無常(ならびに苦=ドゥッカ=不安定)と、非常によく似た意味となることがわかるだろう。
12.縁起や空の教えも、無常・無我・苦の教えと本質的には同じ
無常・無我・苦などの教えとともに、仏教の基本的な世界観を示すものが、縁起・空という教えである。縁起とは、条件・原因によって生じるという意味である(「縁」が条件・原因という意味)。
縁起の思想は、仏教の中核の思想といわれるほどに重要な教えである。釈迦が説いた縁起の教えは、苦しみが煩悩を条件・原因として生じるというものであり、仏教用語では「此(し)縁性(えんしょう)縁起(えんぎ)」といわれる。内容としては、先に述べた四諦の教えと本質的に同じであり、煩悩と苦しみの心理的な因果関係を説いたものだ。
なお、仏教では、煩悩の根本(根本煩悩)は、無智(痴・無明)とされ、無智を根本とした煩悩が、どのような段階を経て苦しみをもたらすかを説いた教えを「十二縁起」という。これはまた別の機会に解説する。
しかし、釈迦の死後、縁起の教えの意味は拡大されて、森羅万象が条件によって生じていることを意味するものとなった。つまり、森羅万象は、どれ一つとっても、他から独立して、そのものだけで存在するものはなく、他に依存して、他を条件として生じるというものである。この世界すべてがそうであるから、言い換えれば、すべては互いに依存しあって存在していると説く(相依(そうえ)性(しょう)縁起(えんぎ))。
そして、なぜこの縁起が、無常などと同じ意味であるかというと、無常であるということは、何かの条件によって生じて、その条件がなくなれば滅するということだからである。無常ではなく、永久不変であるものがあるならば、それを言い換えれば、生じることもなければ滅することもなく絶えず存在し、その意味で、他から独立して無条件に絶対的に存在するものである。よって、この世界のすべてが、相互に依存しあって存在する(この世界のすべてが縁起している)ために、この世界のすべては、無常(諸行無常)であるということになる。
また、幸福・不幸を感じる心理的なメカニズムに、この縁起の教えを当てはめて表現するならば、人の感じる幸福・不幸は、その人の心が、その優劣を比較する対象を条件として決まるということになる。20万円という給料が、喜びとなるか苦しみとなるかは、それと比較されるこれまでの給料や友人・知人の給料の額によって、決まるのである。
そして、この比較の対象は、不変ではなく無常である。先ほど述べたように、10万の給料の人が20万の給料を得た時は、10万と20万を比較するが、しばらくすると、20万と20万を比較するから喜びがなくなり、「30万が欲しい」と思うようになると、30万と20万を比較するから欲求不満が生じるというように、絶えず移り変わっていく。よって、人が感じる幸福・不幸は無常であり、その理由は、幸福・不幸が、比較の対象を条件として生じる=縁起しているからである。
次に、空の教えも、仏教では非常に有名な教えである。空とは、「むなしい」という主観的な感情のことではない。それは「固定した実体がない」といったほどの意味となる。よって、これも、縁起や無常と同じ本質を持つ概念である。森羅万象は、他から独立しておらず、相互に依存しあっており(縁起しているために)、無常であって、固定した実体がないのである(空なのである)。
この空の教えを、優劣を比較して幸福・不幸を感じる人間の心理に当てはめるならば、例えば、20万という給料に喜びを感じることがあったとしても、その喜びには固定した実体がないということになる。先ほど述べたように、時が経ち、条件が変わると、喜びが消え、苦しみに変わる。こうして、20万という給料には、喜びという実体はないということになる。
これは、人が、ある時に何かに感じる喜びや苦しみには、固定した実体はないということになる。固定した実体がない原因には、さまざまなものがあって、①すべての現象は無常であるから、喜びを感じた外界の現象自体が変化して(なくなって)しまうかもしれないし(上がった給料が再び下がって元に戻るなど)、②それを感じる人の心理が変化して(20万では喜べずにもっと欲しくなるなどして)、同じものに対して、前と同じ喜びを感じなくなるかもしれない。
こうして、仏教では、人がこの世界にあると思っているものや、この世界の何かに感じている幸福・不幸には一切、固定した実体がなく、一種の幻影のようなものであると説く。こう表現するならば、「空」という言葉の語感と一致するのではないか。
そしてこのことを「一切皆空」と言う。「一切皆苦」と「一切皆空」は、言葉の表現がよく似た教えだが、本質的には同じ道理・法則を異なる表現で表したということもできると思う。それは、諸行無常・諸法無我(さらには縁起)も同様である。
13.仏教の幸福観:幸福は外界にはなく、心が生み出すもの
こうした仏教の幸福観の特徴を端的に表すならば、「幸福・不幸は、実際には、外界には実在せず、人の時々の心が生み出すものである」ということになる。絶えず何かと優劣を比較する人の心が、時々に感じるものが、幸福・不幸であるということである。
しかし、普通の人は、「外界にこそ幸福がある」と錯覚し、それを得ようと求めて、例えば、財物・地位・名誉などを求める。ところが、実際には、時々の自分の心(脳神経ネットワーク)が、何かと優劣を比較することで、喜びや苦しみの感情を作り出しているから、そのため、客観的・長期的な視点で見れば、時を経て、以前は喜んだものを悲しんだり、逆に悲しんだものを喜んだりすることもある。
そして、問題は、この時々に優劣を比較する心は、自分の意志・理性・智恵によって制御されておらず、それまでの習慣によって無意識的に行われ、喜びや苦しみ(や喜びでも苦しみでもない)の感情が、自動的に湧き上がってくる。
これを心理学的・脳科学的に言えば、私たちが自覚しない無意識の脳活動が今までの習慣などから勝手に作り出した苦楽の感情を、私たちの意識がそのままに経験させられているということなのである。これは、無意識的であり、自動的であり、習慣的なものであって、意識的ではなく、自分の意志によらず、その時の状況に応じて熟慮された判断ではない。
14.自らの心を制御する「心の主」となる生き方が、仏道・ヨーガである
そして、最大の問題は、これが私たち(の意識)を人生全体にわたって幸福にしてくれる自動システム(=良い習慣)であるのならばよいのだが、残念ながらそうではないことだ。
例えば、他者と優劣を比較すれば、半分の人は負け組となって不幸を感じることになる。また、頻繁に苦楽の感情の波がやってきて、それに心身が翻弄・消耗されながら生きることになり、穏やかな安定した心からは遠ざかってしまう。さらには、徐々に年を取るにつれて、若い時よりも、苦しみが増えていくことになる。
こうして、我々を幸福に導く自動システム・良い習慣だとはいえないことに気づくならば、「悪い習慣のついた心の奴隷」である状態を脱却して、本当に幸福になるために、自分で心を制御する「心の主」となる生き方をすることが望ましいことになる。
そして、仏道・ヨーガの修行の目的とは、まさにこの「心の制御」であり、「心の主」になることだということができる。実際に、釈迦牟尼は、遺訓として、弟子たちに「心を制御して、心の主となるように」と訓戒したという。
また、「ヨーガ」という言葉の意味は、体操ではなく、心の制御(厳密には「心の働きを止滅すること」)である。さらには、ヨーガという言葉が由来する「ユージュ」という動詞は、牛馬を馬車につなぎとめるといった意味があり、これは、ヨーガの思想が、人の心を牛や馬にたとえて、牛や馬を調御するように自分の心を制御するべきであるということを意味している。