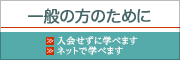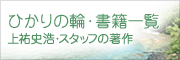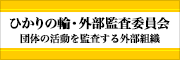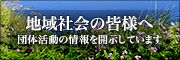2022~23年 年末年始セミナー特別教本「今日の宗教問題の総合解説 仏教の真言と読経の瞑想」
(2025年4月28日)
2022~23年 年末年始セミナー特別教本「今日の宗教問題の総合解説 仏教の真言と読経の瞑想」
第1章 旧統一教会問題:カルトとマインドコントロール
1.安倍氏射殺事件で政治と宗教のつながりが問題に
「新々宗教ブーム」といわれた1990年代の前半に、幸福の科学、オウム真理教、旧統一教会が話題となったが、今年2022年の7月に安倍元総理が山上徹也容疑者に射殺されてからは、一連のオウム真理教事件が発覚した1995年以来、再び宗教の問題が社会の大きな注目を浴びることになった。
その犯行動機が、同容疑者の母親が信仰した旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)への恨みであり、元総理が同教団を後押ししたことであることが、警察の取り調べで判明したといった報道をきっかけとして、同教団と自民党議員などの政治家とのつながりの問題とともに、同教団のさまざまな問題が、メディアで盛んに報道された。
その結果として、2022年12月には、悪質な寄付勧誘を規制する新たな法律が制定された。さらに、今後文化庁は、同教団の宗教法人の解散命令の請求を視野に入れて、同教団に質問権を行使している。また、厚生労働省は、同教団が無許可で信者間の養子縁組の斡旋を行っていたという疑惑の調査をしている。
その過程においては、自民党を中心とした政治家・議員の一部が、同教団のイベントに参加したり、選挙での支援を受けたりしている問題が指摘された。そして、教団と自民党が癒着し、その政策に影響を与えたり、同教団が公安当局が予定していた摘発を免れたりしたのではないかとか、その団体名の改称の申請において(「世界基督教統一神霊協会」から「世界平和統一家庭連合」への改称)、改称を承認する権限を持つ文化庁に対して、政治家が便宜を図ったのではないかといった疑惑が報道された。
こうして、自民党をはじめとする政治家が同教団とのつながりを批判された背景には、以前から同教団が反社会的であるという見方があった。同教団に対する批判は、1970年代にはすでにあったともいわれるが、1980年代には、いわゆる霊感商法といった詐欺的な商法の問題が、最初に注目を浴びた(例えば朝日ジャーナル誌などの批判報道である)。
そして、1990年代初めには、オウム・幸福の科学への批判とともに、同教団の合同結婚式の問題が話題となり、そのころから、オウム真理教とともに、マインドコントロールの問題が話題となった。これは、家族や一般人と強く対立する価値観を信者が持つ過程において、教団が、あたかも信者に気づかれずに、信者の心理を操作し、信者が心ならずも教祖や教団の意思に従うようになるという見解である。
さらに、今年の同教団に対する批判においては、霊感商法に限らず、信者の家族生活を破壊するほどの、教団への信者の過剰な献金の問題や、信者である親が自分の信仰を子供に強制する宗教2世の被害者の問題が新たな注目を浴びた。そして、過剰献金を抑制する新法の制定の際の議論においても、野党を中心として、マインドコントロール状態での寄付を規制するべきだという主張がなされた。
そしてこの問題は、当初は、旧統一教会の問題であったが、その後、同教団と同じように、政治と深いつながりを持つ公明党の支持母体である創価学会や、宗教2世や献金の問題が同教団と同じように指摘される他の新興宗教団体、さらには伝統宗教・宗派の問題も言及されるようになった。
2.カルト問題:カルトと非カルトは明確に区別できない
そもそもの問題は、政治と宗教全般のつながりではなくて、社会問題を起こすような反社会的な宗教団体、いわゆる破壊的カルト団体と自民党などの政治家とのつながりであった。すなわち、宗教一般の政治とのつながりが批判されたのではない。
しかし、旧統一教会への批判の高まりとともに、フランスのように、カルト団体の活動を規制する新しい法律(反セクト法)の制定を求める声が上がった。一般の宗教団体からカルト団体を区別して規制しようとしても、カルト団体の明確な定義、カルト団体とその他の団体を区別する明確な基準を作るのが難しいことが指摘された。
旧統一教会の問題は、1980年代からフランスを含めた欧米でも問題化し、それをきっかけとして、フランスは2000年代になって反セクト法を制定した。なお、セクトないしセクト団体とは、カルト団体と同じような意味で今日は用いられている(本来はセクトとは新派・分派を意味する言葉であり、宗教の世界でいえば、伝統宗派から分離独立する新宗派を指した言葉であった)。
そして、その過程では、1995年などに、フランスの議会が、反セクト団体などの見解を参考にして、セクト団体のリストを作成した。ところが、その対象には、旧統一教会だけでなく、エホバの証人、崇教真光、サイエントロジーに加えて、自民党が連立政権を組む公明党の支持母体である創価学会さえも含むものだった。さらに、ベルギーが作成したセクト団体のリストの中には、禅仏教や上座部仏教など、欧州にとっては伝統宗派ではない、キリスト教以外の宗教が広く含まれていた。
これでは、旧統一教会と自民党の裏の関係の有無を追及する前に、公の連立政権である自民党と公明党=創価学会の関係を否定しなければならなくなる。とすれば、創価学会・公明党はおろか、他の新興宗教団体はこぞって、カルト団体の法的な規制には反対ということになる。
フランスの反セクト法のカルト団体の定義を見ても、例えば「反社会的」という言葉があるが、何が反社会的か否かという点に関しては、明確な定義がないことがよく指摘されている。
こうした問題がある中で、2000年代になって、フランスの首相自身が、そのセクト団体のリストを否定し、法的には意味を持たないことが表明された。また、創価学会に関しては、リストから外れたという情報とそうではないという情報があるが、私の知り合いのフランスと宗教をよく知るジャーナリストである及川健一氏によれば、公明党の粘り強い働きかけによって、その後、創価学会はセクト団体のリストから外されたという。
また、伝統宗派はカルトではないかといえば、小川寛大氏(宗教・政治ジャーナリスト、雑誌「宗教問題」編集長)によれば、例えば、献金集めの問題に関しては、伝統宗派にも問題を感じるという。小川氏によれば、伝統宗派においても、権威主義的な体制による献金集めがあり、旧統一教会などの新興宗教団体のものより洗練されているために社会問題化していないが、今後、伝統宗派・新興宗教問わず、日本では宗教団体が衰退している中で、無理な献金集めが起こる気配が一部にはあるという。
また、池田信夫氏(経済学者)によれば、今や伝統宗派であるプロテスタント教会も、カトリック教会から分裂した時代に、カトリック教会によってカルトと呼ばれており、歴史的に見ても、カルト団体とそうでないものを区別するのは難しいことを主張し、そもそもが、信教の自由がある中では、規制すべきは、団体やその教義自体ではなく、団体の構成員のなす個々別々の犯罪行為・違法行為のみだという原則論を主張している。
そもそも、「カルト」とはどういう意味かというと、原語には儀礼・儀式という意味があり、宗教的な専門用語としては、熱狂的な信仰集団という意味である。その観点から、全ての宗教は、その始まりはカルトであり、世俗的な価値観と対立するという意味で反社会性を持っており、それが歴史の中で社会的に適応し、社会で成功したものが、いわゆる伝統宗派であるという見方がある。すなわち、宗教とは、成功したカルトであるという意味である。
カルトと似たような意味で使われるセクトが、新派・分派という意味があることから考えても、既存の社会や既存の支配的な宗教に対して対立して分離した集団が、セクト・カルトということであれば、その最初は、その時代においては反社会的なものであって、対立・分離するほどの熱心な、熱狂的な信仰が生じたものであることは推測できるだろう。
そして、キリスト教のカトリック教会と対立して離反したプロテスタントの登場を境にして、両者の間に長年の宗教戦争が生じたことは、その典型的な例であると言うことができるかもしれない。
3.宗教に限らず、政治・経済・国家のカルトがある
さらに、カルト団体とは、宗教団体には限られない。実際に旧統一教会にも、関連する政治団体(最も有名なものが反共産主義の団体として設立された「国際勝共連合」)や、関連する事業会社(2009年に刑事摘発を受けた霊感商法の会社「新世」)がある通りである。
実際に、旧統一教会は、日本でこそカルト宗教団体というイメージであるが、韓国では宗教よりも財閥グループとして有名であり、教祖の文鮮明は、教祖としてよりも、事業家イメージが強いという。旧統一教会は、日本、韓国、欧米と、地域ごとに、活動の形態が大きく異なっており、全体として、国際的に企業組織の性質が強い。
そして、一般論として、カルト団体とみなされるものには、宗教カルトに加えて、政治カルト(政治団体)、経済カルト(企業などの経済・事業団体)などがある。陰謀論団体もカルト団体とみなされる場合があるだろう。そして、国家全体がカルト的な思想を帯びる場合もある(国家カルト)。
政治カルトとしては、連合赤軍事件などを招いた極左の共産主義団体があるが、それに加えて、公党である日本共産党も、公安調査庁と現政権によって、暴力主義的革命を捨てきっていないとして、破壊活動防止法の対象となっていることは、最近あらためて知られるようになった。
さらに言えば、国家神道に基づいて、自国を、世界を統べるべき現人神である天皇が統べる神の国と位置付けて、大東亜共栄圏を主張し、中国大陸に進出(侵略)した大日本帝国に対して、当時のアメリカ合衆国政府は、カルト宗教国家と認定していたという。
そして、昔のことを言うならば、ヨーロッパのキリスト教徒が、神の意思(天命)と考えて、アメリカ大陸に進出し、武力をもって原住民のほとんどを抹殺して、合衆国を建国したことは、現代の価値観で言えば、全くカルト的な行為であるといわざるをえない。しかし、こうした経緯があるからこそ、例えば、今でも米国の大統領就任式においては、大統領が、牧師の前で聖書に手を置いて(合衆国憲法を守る)宣誓をし、神の助力を願うのである。
なお、これに関連して、一般に、「政教分離」という言葉・原則があるから、政治と宗教は分離されるべきだというイメージがあるが、これには大きな誤解がある。
政教分離とは、政治と宗教を完全に分断するものではなく、政治が特定の宗教を特別扱いしたり、逆に弾圧したりしてはならないという程度のものである。また、現在の日本の政教分離は、世界の中でも(フランス等とともに)相当に厳しい部類に属し、そもそもが、キリスト教の影響が非常に強かった歴史を持つ欧米諸国の多くは、日本より宗教と政治が結びついている。
一説によれば、政教分離には、分離型・融合型・同盟型の三つのタイプがあるといわれており、日本は分離型である。英国のように、堂々とキリスト教を国教としている国もあり、これは融合型に属するという。さらに、政治とキリスト教会の間に協約を結ぶ同盟型と呼ばれるものもある。
ドイツのメルケル元首相の政党の名前は、キリスト教民主同盟であり、政党名に宗教名が入っているのである(日本で言えば「神道自由民主党」「創価学会公明党」とでも言えばいいか)。アメリカ合衆国は、日本と同じように分離型に属するそうだが、大統領就任式に関して前で述べたように、日本から見れば、キリスト教に対してきわめて好意的な体制である。実際に、米大統領選挙では、キリスト教保守派・原理主義とされる福音派の影響力が毎回よく指摘されている。
そして、当の日本も、戦後のみ分離型であって、それ以前の大日本帝国の時代は、言うまでもなく、事実上、神道を唯一の国教とする国家神道の体制であった。仮に敗戦がなければ、今もそうだったかもしれない。
4.マインドコントロールの問題:定義自体が曖昧
次に、先ほど述べたマインドコントロールに関して言及したい。メディアや政治・政策討論で、マインドコントロールという概念がいささか間違って使われていると思う。
まず、マインドコントロールとは、実は明確な定義がない言葉で、言い換えるといろいろな意味を持つ多義語である。マインドコントロールとは、日本人にとっては英語のため、その意味がそもそも明瞭ではなく、人それぞれ同床異夢のように違ったイメージ・語感を持っていると思う。逆に言えば、英語で意味が不明瞭だから流行しやすかったのかもしれない。
この言葉が1900年代後半に生み出された米国では、後から述べるように、日本ほど流行しておらず、反カルト運動が提唱する仮説であり、怪しい概念というイメージがある。英語で「マインドコントロール → コントロールマインド」を直訳するならば、他者の心理を操るという意味ではなく、心の制御を意味し、その広い定義の中には、セルフコントロールという良い意味を含む場合もあるとされる。
とはいえ、大雑把に言えば、マインドコントロールとは、物理的な力を使わずに、精神的な働きかけのみで、相手に気づかれずに、自分の望む意思・行動に、相手を誘導すること(やその技術)である。しかし、これが、①本当にできることなのか(少しはできるにしても宗教の入信・信仰をさせるほどの効果があるのか、②さらに具体的な集団(教団)がその方法を知り(学び)、それを意図して使っているかについては、実は、科学的な証拠などが乏しく、否定する学者も多く、これまでは、国内外の宗教団体の裁判などで、不法行為としては、認められたことがない。
「マインドコントロールとは、操作者からの影響や強制を、気づかれないうちに、他者の精神過程や行動、精神状態を操作して、操作者の都合に合わせた特定の意思決定・行動へと誘導すること・技術・概念である。マインドコントロール論とも。不法行為に当たるほどの暴力や強い精神的圧力といった強制的手法を用いない、またはほとんど用いない点で、洗脳とは異なるとされる。宗教研究の分野では、国内外でも懐疑的な見方が少なくない。現状、一部の研究者や反カルトを標榜する活動家により、様々な形態のマインドコントロール仮説が唱えられている。」(参考資料:Wikipedia「マインドコントロール」)
ところが、例えば、立憲民主党や維新の会は、メディアの旧統一教会批判の勢いのままに、悪質な献金勧誘による被害を救済する対策として、このマインドコントロール理論に基づいて、信者の意思を無視して献金を取り消し、さらには、具体的に定義されぬMC行為を、犯罪として献金勧誘者を処罰する法案を提出した。
しかし、これに対して、政府与党(や国民民主党)は、「マインドコントロールの定義は困難」などと主張して反対した結果、新法においては、罰則付きの禁止規定ではなく、罰則無しの配慮義務の中に、「自由意思を抑圧し、適切な判断を困難にしない」という抽象的な表現で盛り込まれるという結果に留まった。
5.マインドコントロール理論には科学的な証拠が乏しく、裁判で認定
されていない
このマインドコントロール問題の重要性は、自由意思の問題(自分の自由な意思で献金する、しないを判断することなど)と関係する。マインドコントロールとは、それによって、信者が自分の「自由意志」を教団に奪われて、教団の意に沿って意思決定・行動するようになったということを意味する。
だからこそ、野党の法案では、信者が献金しても、それを信者の自由意思、自己の選択とは認めずに、家族がそれを取り消すことができるとしたのである。本来は、自分の財産の処分は自分が自由にできる財産権が、本人にある(成年被後見人などの一部例外を除く)。しかし、自由意思を奪われて、いわば教団のロボットとなっている信者には、それを認めないというのである。
しかし、繰り返しになるが、マインドコントロールが実際に可能なのか、また実際に特定の集団で使われているのかなどについては、科学的な証拠が乏しく、統一教会やオウム真理教などの国内外の裁判では、これまでに認められたことがない。
宗教学者の大田俊寛博士は、「マインド・コントロール論を用いてオウムという現象を一貫して説明し得たような著作や論文も存在しない。」「社会心理学が指摘したように、近代の社会システムにおいて人間は、受動的・依存的になりやすい。とはいえ、『人間が集団の力や場の力に支配され、あたかもロボットのように精神を完全にコントロールされてしまう』というのは、明らかに現実離れした極論」と述べている(参考資料:「社会心理学の「精神操作」幻想~グループ・ダイナミックスからマインド・コントロールへ」第70回心身変容技法研究会 発表者:大田俊寛 2018年9月2日(於:上智大学))。
〈http://waza-sophia.la.coocan.jp/data/18100401.pdf〉
宗教学者の櫻井義秀教授(北海道大学)も、下記の書籍などで、入信・信仰の原因の説明には不十分と結論している(参考資料:「オウム真理教現象の記述をめぐる一考察」(J-STAGE))。
〈https://www.jstage.jst.go.jp/article/hokkaidoshakai1988/9/0/9_0_74/_article/-char/ja/〉
実際に、統一教会やオウム真理教の裁判では、マインドコントロールに関しては、その事実認定自体がなされていない(一件だけ、信者に有利な情状として減刑の理由の一部として受け入れられたとも思われる事例があったが、その上級審で減刑が取り消されており、マインドコントロール理論は、犯罪を全く正当化・免罪するものとしては認められていない)。(参考資料:Wikipedia「マインドコントロール」)
6.社会心理学的な技術としてのマインドコントールにも根拠がない
ここで、そもそも、マインドコントロールとは何なのかについて整理したい。まず、裁判の判決でも、「マインドコントロール」という言葉は、じつは多義的であり、いろいろな意味で使われていることが指摘されている。そして、我々日本人は、英語で表現されていることもあって、具体的な意味がわからないこの言葉をしょっちゅう聞き、自分でも何となく使う習慣が付いてしまっている。
前出の櫻井教授によれば、マインドコントロールは、第一に、すでにご紹介したように、「破壊的カルト教団による信者の利用」という意味があって、これは価値中立的ではないものと指摘し、第二に、社会心理学的技術の応用(による他人の心理の操作)という意味、第三に、他律的行動支配という意味がある。
この中の二つ目の社会心理学的技術とは、人格の「解凍・変革・再凍結」の理論をベースに、認知不協和理論や影響力論、ジャック・ヴァーノンの感覚遮断実験、フィリップ・ジンバルドーの監獄実験、プライミング効果論などの社会心理学的テクニックを活用して行われるといわれている。
しかしながら、①これらの技術に(入信・信仰に誘導するほどの)効果があるのか、②統一教会等のカルト教団がこれらの技術を実際に使っているのか、という点に関しては、先ほども紹介した通り、米心理学会の判断では、科学的な証拠は乏しく、裁判で認められておらず、日本でも前出の櫻井教授や大田俊寛博士も同様の見解である。
より具体的には、宗教学者のダグラス・E・コーワン や、宗教社会学者のデイヴィッド・G・ブロムリー などが、
①洗脳の技術が、反カルト活動家が言うほどの効果があり、無差別なものであるのなら、対象や時代に関わりなくその技術は機能するはずだが、実際北アメリカでは、新宗教が若い人の勧誘にかなり成功していたのは、1960~70年代の対抗文化運動の間だけであり、以降は劇的に減少していること。
②洗脳を効果的に行うには、おそらくある程度の専門技術が必要なはずであるが、洗脳を行っていると非難されている新宗教では、加入間もない新人メンバーたちが勧誘活動を行っている。時間の経過で技術は向上するはずであるが、そういった成果の向上は見られない。また実際のところ、新宗教は全体として信者を引き付け維持することに失敗していることなどを挙げて、その効果を反論している。
さらに統一教会に関しては、
③1970年代にE・バーカーが統一教会に対して行った最も徹底的で信頼できる調査(期間は6年)で、バーカーは入門者が会員として残る確率は、極めて低いと結論付けている。統一教会に勧誘された人々のうち、実際に会員として加わったのはごくわずかで、新会員もほとんどは短期間で活気を失っていた。
などと報告している(参考資料:Wikipedia「マインドコントロール」)。
7.マインドコントロールは、反カルト運動家が提唱した非中立的な概念
さらに、注意すべきは、マインドコントロール仮説の発祥の経緯である。前出の櫻井教授が指摘するように、「マインド・コントロールという理論は、アンチ・カルト集団が、信者の奪回・脱会を促進する自らの行動を正当化するための議論であり、立論の当初から価値中立的なものではなかった。」という(参考資料:「新宗教の形成と社会変動 : 近・現代日本における新宗教研究の再検討」北海道大学)
〈https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/33694〉
より詳しい経緯は、朝日新聞(デジタル版)が以下のようにまとめている。
米国では60~70年代ごろにかけて、新しい宗教が注目を集め、それに呼応して「反カルト運動」も拡大していった。70年代に米国内で広がった旧統一教会も、こうした流れの中で注目された新興宗教の一つだった。一部の学者やグループは、新興宗教に若者らがのめり込むのは「洗脳」によるものだと主張した。「脱洗脳」のために、信者を無理やり拘束したり監禁したりする「強制脱会」も行われた。子どもを教団から引き離すために、脱洗脳を専門とする反カルト団体が両親に多額の報酬を求めることもあったという。しかし、心理学会などが「洗脳」自体に科学的な根拠が乏しいと指摘し、80年代ごろから「脱洗脳」行為は強く問題視されるようになった。強制的な脱会を違法とする判決も相次ぎ、反カルト運動は衰退した。(「「カルト規制」法整備した仏 消極的な米国、中国は「邪教」認定」2022年9月29日 朝日新聞デジタル版)
〈https://www.asahi.com/articles/ASQ9V31YJQ9JUHBI03K.html〉
こうして、マインドコントロール(ないしは強制説得、洗脳)という主張の始まりは、信者を拉致監禁する強制脱会と結びついていた。その中では、マインドコントロールされた信者は、教団がその本来の自由な意思を奪って操っている状態であり、(信者の自由意思による選択として尊重する必要はなく)信者の意思に反しても拉致監禁して強制脱会してもよいという考え方があったことが推察される。しかし、結果として、それはやはり違法とする判決が相次ぎ、否定される結果となったわけである。
この点に関連して、よく聞かれる質問が、「なぜあんなものを信じるのか」というものである。言い換えれば、信者本人は、自分が好きで信じている可能性があることが、信者でない人には、受け入れがたいという心理があることを示していると思う。さらに、その信者の家族となれば、「教祖にマインドコントロールされて、心ならずも信じさせられている、強いられている被害者なのだ」と解釈しやすいと思う(そう解釈した方が心地よいということもあるだろう)。
8.日本での信者の強制脱会と、それに反対する弁護士や牧師の存在
なお、櫻井教授が指摘した「マインド・コントロールという理論は、アンチ・カルト集団が、信者の奪回・脱会を促進する自らの行動を正当化するための議論」という事実は、米国だけではなく、日本の旧統一教会にも当てはまる。
すなわち、強制脱会を行う牧師や、お金でそれを請け負う脱会屋、それを知りながら受容した弁護士たちのグループが存在したという。教団の主張によると、4300人以上の拉致監禁の強制脱会説得を受けた信者がいるとされる(参考資料:全国拉致監禁・強制改宗被害者の会:https:// kidnapping.jp)。
そして、日本でも、信者による相次ぐ訴訟において違法判決が出て、教団によれば、2016年までには、拉致監禁は解消された状況になっている。その前には、キリスト教会の牧師が旧統一教会の信者を拉致監禁したが、信者が監禁から脱走して、牧師を民事訴訟するとともに刑事告発し、警察の捜査が始まる中で、牧師が自死するという悲惨な事例もあった。なお、軟禁などの緩やかな拘束の問題は、まだ残っているという情報もあるが、その事実は確認できていない(参考資料:同上https://kidnapping.jp)
なお、少しわき道にそれるが、かつてこの拉致監禁の強制脱会をしたり、それを受容した弁護士やジャーナリスト(のグループ)が、今メディアで統一教会批判をしたり、立憲民主党に同教団の問題の参考人と呼ばれる人たちの中心となっているという状況が少なからずある(参考資料:「米本和広氏の陳述書(3)」HP:「拉致監禁by宮村の裁判記録」拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会
〈http://antihogosettoku.blog111.fc2.com/blog-entry-112.html〉
一方、そうした強制脱会手法に対しては、もとから否定的、批判的であって、自主的な脱会の支援をしてきた牧師・弁護士や、そのグループもある。こうして、統一教会への対応・見方は、牧師・弁護士・ジャーナリストでも実際には多様であるが、こうした方々の見解は、今のメディアではあまり報道されていない状況である。
こうして、統一教会などに対する反教団グループの拉致監禁犯罪が、マインドコントロール理論で正当化されることはなかった。その後、1990年代に日本のオウム真理教の事件が発生して、再び教祖にマインドコントロールされた信者という話が出て、裁判でも議論になった。しかし、このオウム裁判でも、教祖による犯罪を信者が受け入れて実行したことが、教祖によって信者がマインドコントロールされた結果だとして、免罪されることはなかった。
9.旧統一教会の勧誘・伝道行為の違法性:正体隠し勧誘
なお、ここまで、マインドコントロール理論に関して、歴史的な経緯から、反教団グループの強制脱会や、教祖の指示を受けた信者の犯罪を正当化するものではないという視点から見てきた。しかし、だからといって、カルト教団の布教・教化活動が正当化されるわけでも、されたわけでもない。
この点に関しては、前出の櫻井教授が、自身のマインドコントロール理論に関する見解の一部が、統一教会の問題を否定するために、教団に使われたことを不本意として、「マインド・コントロール論による入信の説明は、宗教社会学の議論からは認めることができないと年来主張してきたが、『マインド・コントロール』という社会的告発に相当する宗教集団がひきおこした社会問題が存在していることは認めてきた」と述べている。
そして、統一教会の訴訟においては、元信者の原告が、マインドコントロールを不法行為として教団を訴えても認められなかったが、その後、原告は、主張の方法を変え、マインドコントロールではなく、教団の正体を隠して勧誘することなどを不法行為として強調して訴えるようになって、教団が敗訴するようになったという経緯がある。この点は、信者の研究者さえ明確に認めている(参考資料:「『青春を返せ』裁判と『マインド・コントロール理論』」http://suotani.com/archives/346 HP:「『洗脳』『マインドコントロール』の虚構を暴く」魚谷俊輔)。
また、日本の統一教会訴訟の第一人者といわれる札幌の郷(ごう)路(ろ)征(まさ)記(き)弁護士も、最近のテレビ出演で、「マインドコントロールという言葉を自分は使わない」と述べながら、正体隠しの布教が最も重要な統一教会の伝道の違法性だと述べていた(参考資料:YouTube番組:Straight Talk[JBpress]「統一教会の裁判に何度も勝訴した郷路征記弁護士が語る、規制づくりで肝心なのはここだ」)
〈https://www.youtube.com/watch?v=v2CGGKDzNyw&t=440s〉。
これも、統一教会訴訟の経緯と要点を象徴している。こうして、反統一教会の訴訟の第一人者の弁護士と、統一教会の幹部信者の双方が、マインドコントロール説を否定し、正体や目的を隠すなどの不適切な教化行為が裁判で不法行為と認められているものだということで一致している。これは非常に重要な事実だと思う。
さて、多少繰り返しになるが、勧誘の際に自分の正体を明かさないことは、勧誘対象にその判断のために必要で重要な事実を隠すことであり、勧誘対象の「自由意思」による判断を妨げる、抑圧するなどと、民事裁判の判決では考えられている。そのため、特定商取引法などでも禁止されている(氏名明示義務の違反)。よって、それを宗教の勧誘にも適用した弁護士と裁判所の判断は、その意味で従来の法理に基づいたものだと思われる。
政府の寄付規制新法では、自由意思を抑圧して、適切な判断を困難にすることや、正体や目的を隠した勧誘を行わないようにという配慮義務が盛り込まれたが、罰則を伴う禁止規定ではない点が、不足であると批判されている。すなわち、民事裁判では不法行為と認められるものの、宗教の勧誘において正体や目的を秘して勧誘することを禁じる法規はまだない。これに関しては、一般に注意を促す教育・広報政策とともに、規制の強化の検討が必要かもしれない。
実は、私が15年前に脱会したアレフ(旧オウム)では、この10年間ほど、正体隠しの覆面ヨーガ教室で、オウム事件は陰謀だと言う嘘をつくなどの詐欺的な教化方法で、相当数の若者を入会させており、私たちひかりの輪は、その脱会支援を行ってきたという経緯がある。
10.信じる自由と信じない自由の双方を含む信教の自由の確保を
さて、以上を踏まえて、もう一度出発点に戻って考えて見ると、信者が入信する理由が、もっぱら教団からの働きかけ=マインドコントロールの結果としてしまい、信者側の要素、信者の自由意思で入信した可能性を一切否定することは、合理的ではないと思われる。
もちろん、教団に入ったものの、その後にやめた人がいるのも事実であり、その一部は今、メディアで教団を批判している。しかし、教団に入った人の中には、①教団の生き方の方が心地良く、自分に合っている人、②今話題の宗教2世など、自分に合っていないのに入信させられた人、③として、①と②の中間的な人、などがいるのだろうと思われる。
実際に、マインドコントロールを研究する社会理学者の西田公昭氏の論文でも、統一教会信者に関する専門家の研究結果として、「信者は集団に入る直前と直後を比較すると91%の人が神経症的苦悩が低くなり、会員であり続ける過程で神経症的苦悩は減少し、入信で苦悩は減少していた」という結論のものを紹介している(参考資料:「破壊的カルトでの生活が脱会後のメンバーの心理的問題に及ぼす影響」The Japanese Journal of Psychology 2004, Vol. 75, No. 1, 9-15)
〈https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpsy1926/75/1/75_1_9/_pdf〉
逆に、同じ論文の中には、さらに、①脱会者には心理的な問題が生じ、具体的には、鬱、孤独、無抵抗、パニック、体重減少、湿疹、月経異常、悪夢、健忘症、自殺、自己破壊的感情、幻覚 ・妄想、知覚記憶障害など、②これらは、自主的な脱会ではなく、(信者を家族や家族の依頼を受けた脱会屋が信者を拉致監禁するなどした上で脱会を説得する)強制脱会の場合に起こる、という研究結果の紹介もされている。
また、弁護士の野口勇氏も、統一教会等の強制脱会の元信者の調査から、①心身のストレス・PTSDの発症損害、②家族への信頼が失われ,逆に家族の絆が切れる(別離・別居・離婚)、③アイデンティティ喪失の危険が高い、④教団への憎しみが固定化し精神的な安らぎを欠くなどを報告している(参考資料:宗教法学会公式ホームページ「宗教団体からの脱会強制」)
〈http://religiouslaw.org/cgi/search/pdf/200205.pdf〉
そして、今現在、先ほどの分類でいえば、②ないしは③の人が脱会者となって、メディアが取材・報道している。彼らの苦しみはわかるが、教団をやめていない多くの人たちも、彼らと同じように教団にマインドコントロールされたにすぎず、彼らと違って、まだ自分の間違いと被害に気付いていないだけだとするのは、やはり行きすぎではないかと思われる。
旧統一教会の信者数は、10万人(教団広報部)とも、6万人とも、2万強(宗教学者の分析)ともされている。それを踏まえると、メディアに出る脱会者は、その全体から見れば、やはり少数と考える方が合理的、現実的であろう。
さらに、教団が勧誘した全ての人が入信するわけではないという事実がある。統一教会訴訟の第一人者の郷路弁護士の話によれば、統一教会の場合は、信者になる人の10倍から100倍、勧誘しても入信しなかった一般の人たちがいると思われる。この人たちは、結果として、マインドコントロールされずに入信しなかったわけである。だとすれば、やはり自分の自由意思、自分の欲求が、教団とマッチしたために、入信して教団に残っている人が多数に及ぶということを認める方が合理的に思われる。
以上を踏まえると、教団が正しいから皆が信じてよいのか、ないしは、教団は間違っているから皆信じるべきではないのか、という二者択一の問題ではないように思われる。個々人の性格・価値観・体質で、好き嫌いが分かれる問題であって、信じたい人は信じる自由と、信じたくない人が信じなくて済む自由の、双方の自由を実現することが、信じる自由と信じない自由の双方を含んでいる「信教の自由」の実現ではないだろうか。
しかし、その一方で、脱会者や(脱会者を被害者としての顧客に持つ)弁護士の方の発言ばかりに基づいて、「教団での生き方が合っていて、それを続けたい」と思う人達に関しても、マインドコントロールという仮説に基づいて、「教祖・教団にマインドコントロールされ、自分達の被害にまだ気付づくことができない人」とばかり決めつけるのはどうかと思われる。
11.旧統一教会が反省するべき無理な教化活動
しかしながら、これまでの旧統一教会は、少なくとも結果として、教団には合っていないタイプの人も含め、入信させようとしてきたことは、さまざまな事実からして否定できないだろう。特に、親の強い影響のもとで2世信者となったが、その後に辞める人や、献金した後に返金を求める人がいる。
これは、自分たちが信じる宗教の信者を増やせば増やすほど、献金は多ければ多いほど、よいと信じて行動するうちに、やはり、いろいろと無理が生じた結果ではないだろうか。また、その意味で、旧統一教会に限ったことではなく、実際に、他の宗教にも宗教2世などの問題はある。一部の報道で出てくるのが、エホバの証人、幸福の科学、創価学会などである。
また、宗教2世の問題に関連しては、近年新しい信者が増えなくなったために、2世信者の育成に注力し、その割合が増えているのは、他の宗教団体でもよく見られる傾向である。しかし、旧統一教会のようなタイプの教団の場合は、特に、その1世と同じように、その2世が教団に合っているという保証はない。よって、この問題に対する改善・対策が必要なことは確かであり、これに向けて、今いろいろな議論が各方面でなされているのだと思う。
12.マインドコントロール論の弊害
最後に、これまで述べてきた問題を持つマインドコントロール理論の弊害に関して、宗教学者の大田俊寛氏の論考を紹介しながら、以下に言及したいと思う(参考資料:「社会心理学の「精神操作」幻想~グループ・ダイナミックスからマインド・コントロールへ」第70回心身変容技法研究会 発表者:大田俊寛 2018年9月2日(於:上智大学)http://waza-sophia.la.coocan.jp/data/18100401.pdf)
大田氏によれば、マインドコントロールには以下のような弊害がある。
(1)正確な説明の欠如
「カルト」とは、さまざまな問題を解決しようと、多くの人々が特定の思想や考え方、特に単純で偏向したそれを支持するところから生じる。マインド・コントロール論は、カルト問題の本質を誤認させるため、一般社会にいつまでも不全感・不安感が残存する。
(2)対話の阻害
マインド・コントロール論は人々に、カルト的な団体と接触すれば精神操作されるのではといった、過剰な不安感をもたらす。カルト問題を解決するためには、当該団体と冷静で粘り強い対話を継続することが必要不可欠なのだが、それが不可能になる
(3)責任の所在の極端化
カルト的な運動とは、当該団体と周辺社会のあいだ、指導者と信奉者のあいだの、複雑な相互作用から生じる。ところが、マインド・コントロール論に依拠すると、マインド・コントロールした団体が悪い、さらには、その中心にいた指導者が悪いと、責任の所在が極端化してしまい、その後の処遇も著しく不公平なものとなってしまう。
(4)主体性の喪失
「マインド・コントロールされていた」ということを理由にカルトから脱退すると、それによって一時的に自身の責任を免れることができるが、それは同時に、自身の根本的な主体性を否定することにも繋がる。カルトに関与したことを自身の責任と認めず、すべてを団体のせいにしようとする歪(いびつ)な思考回路が生じることもある。
(5)被害妄想の乱反射
マインド・コントロール論は、「見えない敵が密かに自分をコントロールしようとしている」という被害妄想を増大させる。その論理は実は、陰謀論と近似的であり、オカルト的な書籍では、「権力者が大衆をマインド・コントロールしている」という主題が見られることも多い。カルト側と反カルト側でマインド・コントロール論の応酬となり、被害妄想が乱反射しながら昂進してゆくという現象も生じる。
(6)法秩序の瓦解
裁判で扱われるさまざまなケースにおいて、関係者の行動の一つ一つに対し、「マインド・コントロールされていた」可能性を考慮に入れ始めると、審理をスムースに進めることは著しく困難になる。また、そういった理由から犯罪への責任が減免されるということになれば、個人の主体性に立脚する近代の法秩序は、根底から瓦解してしまう。
このようにマインドコントロール理論のもたらす弊害を述べた上で、大田氏は、その理論の背景にある受動的・依存的人間像から脱却し、主体性の確立を目指した地道な努力を重視するべきだと言う。
具体的には、同氏は、
「社会心理学が指摘したように、近代の社会システムにおいて人間は、受動的・依存的になりやすいとはいえ、人間が集団の力や場の力に支配され、あたかもロボットのように精神を完全にコントロールされてしまうというのは、明らかに現実離れした極論」
であり、
「本来われわれが目標とすべきは、近代の人間が受動的・依存的になりやすいという事実を認めた上で、そこから脱却する方途を見出すことであったはず。そのためには、周囲からいかなる影響を受けようとも、最終的には自ら考え、自ら決断し、自ら責任を取らなければならないという、主体性の原理の重要性を強調し続けなければならないし、同時に、健全な主体性を発揮するために必要とされる幅広い知識を身に付ける努力を怠ってはない」
と述べている。