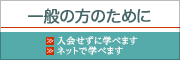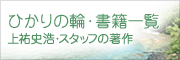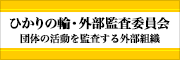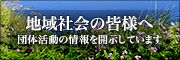2024~25年 年末年始セミナー特別教本 悟りの大衆化の新時代の到来 ゾーンの入り方と心の実態の解明
(2025年4月28日)
2024~25年 年末年始セミナー特別教本「悟りの大衆化の新時代の到来 ゾーンの入り方と心の実態の解明」
第1章 21世紀の意識の革新:大衆が悟る新しい時代の到来
1.はじめに
私たちが住む21世紀の先進国社会は、ごく限られた人だけではなく、大衆が、仏教が説いてきた悟りの境地を達成することができる、新しい時代ということができる。
その根拠は、1990年代ごろから、北欧や日本などの先進国の長寿社会で、社会学者や心理学者によって発見された、超高齢者の老年的超越という心理状態である。調査によれば、広くいえば2割ほどの超高齢者が「今が一番幸せ」という至福の心理状態にあり、我欲が抑制され、寛大で、感謝や無償の愛が強くなり、死の不安や孤独を感じることなく、人によっては、仏道・ヨーガ修行者などによって体験される、宇宙と一体となった心理状態を経験していることが判明した。
我々現生人類(ホモサピエンス・サピエンス)が生まれて以来、約20万年がたち、仏教開祖の釈迦牟(む)尼(に)が悟りを開き、教えを説いて約2500年がたつとされるが、いまだかつて、このように大衆規模で、悟りの心理状態が生じたことはなかったということができる。そうした意味で、人類社会が、いまだに各地において、対立・分断・紛争を抱え、今の社会を「生きづらい」と感じている人が少なくない一方で、我々は、静かに、画期的な新しい幸福の時代を迎えている可能性があるのである。
また、この現象が意味するところは、幸福の価値観、人生観を大きく変革するものでもある。まず、幸福の価値観に関しては、老年的超越の現象は、今現在、主流である「競合的な幸福観」、すなわち、「今よりもっと、他人よりもっと」と、財物・地位・名誉・権力・異性を求めて獲得することが幸福であるという、いわゆる我欲・自己中心的な欲求から離れて(足るを知って)、他と共に幸福になる、他と苦楽を分かち合う利他・慈悲によって幸福になるという、「協調的な幸福観」への転換を促すものである。
さらに、人生観に関していえば、「若い人はいいよね」「人生若いうちにバリバリやって年取ったらピンコロで死にたい」といったような「若い時が幸福」というものから、超高齢期を頂点として、「加齢とともに、より幸福になる」という人生観・ライフイメージへの転換を促す可能性がある。人生の幸福は、尻すぼみになるのではなく、尻上がりになるという新しい人生観である。
この章においては、今、いったいなぜ老年的超越の現象が生じているのか、今後はどうなるのか、老年的超越を得るためにはどうしたらいいのか、ヨーガや仏教などの伝統的な悟りの思想から見ると、老年的超越はどのような位置づけになるのか、ということについて深く考察してみたいと思う。
2.老年的超越に至る人に多い特徴
心理学者が、老年的超越に達する原因を分析するために、老年的超越に至る人に多い特徴を調査した結果としては、①多難な人生を送ってきた人に多い、②より高齢層に老年的超越の割合が多い、ということが判明している。加えて、田舎よりも都会生活を送っている人に多いといった研究結果もある。この調査研究はいまだに進行中であり、詳しくは章末の参考資料を参照されたい。
なお、この点について詳しく検討する前に、老年的超越者が多いとされる超高齢者とは、具体的には何歳以上であるかというと、「老年医学では、高齢者の定義は65歳以上、その中で75歳以上を後期高齢者、85歳以上または90歳以上から超高齢者とする、というのが現在の考え方であり、また、世界的なコンセンサスである。」とされる(東京大学大学院医学系研究科教授 大内尉(やす)義(よし)、第20回社会保障審議会医療保険部会H17.9.21提出資料 出典:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/dl/s1027-5c29.pdf)。
また、日本老年医学会は、65~74歳を准高齢者・准高齢期、75~89歳を高齢者・高齢期、90歳以上を超高齢者・超高齢期と提言している(出典:老年医学会HP https://jpn-geriat-soc.or.jp/proposal/pdf/definition_01.pdf)。
ただし、老年的超越現象が、85歳以上でなければ起こらないかというと、決してそういうことではなく、あくまでもそれ以下の年齢層との比較の問題であり、これについても詳細は巻末の参考資料などを参照していただきたい。
3.老年的超越の背景要因について:多難な人生・人生苦が、幸福観の転換をもたらす
さて、老年的超越が超高齢者に生じており、さらに、より高齢層に老年的超越者が多い以上、老年的超越の背景要因としては、先進国を中心とした、平均寿命が80歳を超える長寿化があることは、間違いないであろう。これに加えて、順風満帆(まんぱん)な人生を送った人ではなく、むしろ多難な人生を送ってきた人に老年的超越が多いということが、老年的超越の背景要因を探るためには重要である。
しかしながら、現在の高齢者心理学においては、長寿化がなぜ老年的超越をもたらすかの明確な研究結果は示されていないように思える。その一方で、老年的超越の心理状態が仏道修行者の悟りの境地と極めてよく類似していることから、仏教思想の中に、長寿化が老年的超越をもたらしている理由を求めるならば、そこには、極めて明確な答えがあることがわかる。
まず、仏典では、開祖の釈迦牟尼の教えとされる初期経典においても、悟りに至るためには、一定の人生苦が条件となる、必要であると説かれている。それは、苦しみがあってこそ、仏法に対する真の理解(信)が生じるというのである(章末の参考文献を参照)。なお、仏典の漢訳用語である「信」とは、現代人が、宗教を信じるとか、信仰するという言葉でイメージするものとは異なり、客観的で知的な理解・確信を意味する。さらに釈迦の説いた初期仏教が、宗教ではなく、実践哲学・心理学の本質を持つことは後に述べる。
これは、論理的に考えるならば理解できることだと思われる。というのは、先に述べた、一般的な幸福観・生き方である「競合的な幸福」、すなわち、我欲の追求がなかなかうまくいかずに、多難な人生を経験する者は、その苦しみを解消するために、それとは異なる幸福観・生き方、すなわち、ブッダが説いた、我欲を抑制して(足るを知って)利他・慈悲に生きて悟りの幸福を得る、という新たな幸福観・生き方に転換する動機が生じると思われる(先ほど述べた「協調的幸福」への転換)。
そして、これを裏付けるように、老年的超越の高齢者の心境として、「人生でこれまでにいろいろ(な苦難も)あったが、それには皆(今の幸福に至る上で)意味があった」という趣旨のものがある。これは、「人間万事(ばんじ)塞翁(さいおう)が馬」という諺(ことわざ)や、「苦楽表裏」といった仏教の教えに通じるものであろう。
4.老化がもたらす幸福観の転換
また、より高齢層に老年的超越が多いということは、老化自体が、心理的に、この幸福観への転換をもたらす可能性があることを示している。単純に言って、老化自体が人生苦の一つである。競合的な幸福観からしても、以前の若い時の自分と比較しても、若い他人と比較しても、劣っている今の老いた自分を経験するのが、まさに老化である。
そして、他に優って得る競合的な幸福は、加齢とともに、それを追求する意欲も能力も低下してくる。老化とともに、競合的な幸福観に留まるならば、苦しみが増えるばかりとなる。これが、競合的な幸福観に見切りをつけ、協調的な幸福観、利他・慈悲の幸福観に転換していくことを心理的に後押しすることになる。さらに、競合的な幸福観とは、我欲の追求・自己中心的な性質を持つが、老化とは、まさにその幸福観の土台である「自分自身」というものが死に向かって徐々に崩れて消えていくことを感じさせる経験である。これも、競合的な幸福を追求することの空しさなどを理解させ、幸福観を転換する心理的な要因になるだろう。
5.老年的超越を助ける、先進国の社会福祉・長寿社会という環境
冒頭において、日本を含めた21世紀の先進国の長寿社会は、人類史上初めて、大衆が悟りを得ることができる時代だと述べたが、ここでは、あらためて、どうしてこの社会が老年的超越(ないしは老年前の超越)を実現しやすいかについて、その要因を述べたいと思う。
第一に、長寿社会とは、人生において、競合的な幸福から協調的な幸福に転換した方が幸福に生きやすい高齢期が長いということである。短命だった時代に比べて、高齢期が長い長寿社会は、幸福観を転換した方が生きやすい時間が長く、転換しなくても苦しみが少ない若い時の時間が、人生全体において相対的に短くなる。
すなわち、「若いころにバリバリやって、年取ったらピンコロで死ぬ」という昔の時代の人生観が通用せず、医療技術の発展のために、悪くいえば、「なかなか死ぬことができず、苦しみの多い高齢期が長く続く時代になった」とも表現できる。これは、現在多くの人が抱く「老後の不安」の背景にあるものだろう。その中で一部の人が、安楽死の法制化を主張さえしているが、暗く長い老後とはいっても、だからといって、その前に自死したいという人は実際には少ない。そのためにも、幸福観の転換の促進、老年的超越の拡充が期待されることになる。
また、この幸福観の心理的な転換には、競合的な幸福観ばかりでは人生が行き詰まってしまうことに気づくために、一定の量の経験が必要であろうし、また、心理的な転換を始めて、それに慣れるための時間が必要だろうと思われる。これらに必要な時間的な余裕が長寿社会にはあるということも、老年的超越現象をもたらしている背景だと思われる。
6.競合的な幸福観の行き過ぎの弊害が強まっている現代社会
第二に、長寿化やその高齢期とは関係なく、現代の人類社会全体において、競合的な幸福観は、その弊害が強まり、行き詰まりつつあるという重要な事実があると思う。
まず、人類の歴史を俯瞰(ふかん)すれば、競合的な幸福観は、人類が弱肉強食の原始時代に生きている際には、ある意味でそれに合っていた価値観である。狩猟において獲物との生存競争に打ち勝って、獲物を捕らえて殺して食することで、生きることができ、打ち負けて食べられなければ、飢え死ぬことになる。
また、原始時代の後に都市文明が発達した後も、人類は長い間、頻繁に戦争を行う時代を生きた。日本も欧米も、第二次世界大戦が終わり、核戦争による人類滅亡が懸念されるようになった80年前までは、欧米の植民地侵略も大日本帝国の戦争にしても、国家の基本政策は、戦争に勝って国家・国民が発展して幸福になるというものであった。
そして、その時代は、国内においても、今日のような社会福祉・医療制度などの社会制度は必ずしも整っていなかった。貧困で死ぬ者、病気で短命に終わる者も多く、犯罪を取り締まる治安制度も不十分だった。より強い者、より豊かな者は長生きし、弱い者・貧しい者は短命に終わり、現在よりも、強国と弱小国、富裕者と貧困者の格差の激しい時代だった。その意味では、弱肉強食の時代ほどではないにしても、他に勝ってこそ生きやすく、負けたら生きにくい面が強かった。
しかし、その後、戦争は、核戦争によって人類全体の滅亡をもたらし、勝者を生まず、皆を敗者にする可能性が生じた。戦争の勝利に替わって、各国は経済競争の勝利を国家の発展・国民の幸福の主たる手段だと考えるようになった。国内では、社会の安定のためにも、経済競争の活性化のためにも、全ての国民が文化的な生活をすることを保障する民主主義・社会福祉国家が現れた。その中では、経済競争の勝者(富裕者)は、以前の戦争の勝者と異なり、敗者の全てを奪うことはおろか、逆に敗者(低所得者)のために、より多額の納税をなし、富の再分配のシステムによって、敗者の生活を助けることが義務付けられた。
一方、敗者の方は、戦争の敗者と異なって死んで終わることはなく、勝者に一定の水準の生活を助けてもらう仕組みの恩恵に授かることはできて、身体的な苦しみは和らいだものの、負け組の苦しみ・コンプレックス・勝ち組への妬み・社会への不満や怒りといった、心理的な苦しみ、ストレス、生きづらさを感じながら生きる多くの人を生み出すことになった。
こうして、大衆全体が生きること自体には大きな障害がなくなった今、他人と比較して自分がより恵まれているか否かが、幸福・不幸を大きく左右することになった。自己愛の充足が幸福・不幸を決めるのである(自己愛型社会)。そのため、家族・仕事場・友人・知人との人間関係の問題が、現代人の主要な苦しみとなった。
また、医療技術が進歩した先進国では、身体的な病気よりも、精神疾患の割合が増え、500万人がうつ病と推計され、500万人のニート・引きこもりの問題があり、自殺が依然として高止まりし(日本では依然として年間2万人台)、自殺を上回る孤独死(年間約3万人とも)の問題が発生している。病気に戻ると、メンタル疾患に加えて、心理的な原因のある各種の生活習慣病が目立ち、依存症、人格障害の問題が目立ち始めた。さらに、近年広がる貧富格差・経済中心主義は、欧米社会に見られるように、国内社会の分断・陰謀論の流行などの混乱、反移民政策・反自由貿易・自国中心主義など、民族間・国家間の対立を招き始めている。
こうして、まとめてみると、「他者に勝ってこそ幸福、負けたら不幸」という競合的な幸福観は、その必要性が減少する一方で、心身の健康や人間関係の問題、国内外の社会の分断をもたらし、その弊害が目立ち始めている。
さらに言えば、勝利至上主義の競合的な幸福観は、皮肉なことに、逆に健全な競争を損なっている面がある。まず、勝てなければ、最初から競争(社会)に参加しないで引きこもってしまう人達(日本では500万人のニートが存在する)、次に、勝つ(利益の)ためには手段を選ばずに、不正・偽装・虚言(陰謀論)を用いる個人・企業・政治指導者である。実際は敗北したのに、「不当に敗者扱いされた」という被害妄想・陰謀論は、政治指導者にまで広がり、選挙制度を含めた民主主義の制度を揺るがしている。勝利を絶対とする競合的な幸福観の行き過ぎは、このままでは、健全な競争環境を維持することができずに、自滅する可能性を示し始めたのかもしれない。
7.高齢者に限らず、若年層(ミレニアム・Z世代)が、競合的幸福観から離れていく徴候
こうした社会の中で、老年的超越に見られるように、高齢者の一部が競合的な幸福観から離れ始めていることは前に述べた通りであるが、それは高齢者層に限らず、若年層に及び始めている兆しがある。この傾向を若い世代の世代別の特徴と共に見ると、以下のようになるという(出典:https://www.cross-m.co.jp/column/marketing/mkc20240301 (株)クロス・マーケティング)
① ゆとり世代(19歳〜36歳前後)
ゆとり世代は、義務教育が従来の詰め込み型からゆとり教育に切り替わったときの世代。ゆとり教育の影響により、ストレスに弱く、競争意識や上昇志向が低いなどの特徴が見られる。その一方で、合理的な考え方を持つ人が多い。ほかの世代と比べて、周りの人から言われたことを素直に受け入れる傾向も。
② さとり世代(18歳〜27歳前後)
バブル崩壊後の不景気の中で育ち、阪神淡路大震災や東日本大震災などの大災害も経験した世代。さまざまな出来事を経験しているため、悟っているような考え方をする人が多く、「悟」世代と呼ばれている。経済状況の良くない時代しか経験していないため、ブランドや名声にはあまり興味を示さない。理想よりも現実を見ており、実利的なものを好み、堅実で安定志向が強め。また、デジタルネイティブといって、生まれたときからすでにインターネットやIT機器が普及。そのため、さとり世代の大半の人はデジタルツールやインターネットの扱いに慣れている。
③Z世代(12歳〜28歳前後)
ゆとり教育の影響により、ストレスに弱く、競争意識や上昇志向が低い。その一方で、合理的な考え方を持つ人が多い。Z世代の人は、人により価値観が違うことを強く認識しており、自身の価値観を大切にするのが特徴。その一方で、他者とのつながりを求める傾向もあり、承認欲求が強い人も多い。また、どちらかといえば、論理的なものよりも直感的なものを好む傾向も。
8.次世代は、競合的な幸福観の傾向が弱くなるとの推測(進化心理学)
進化論の視点に基づく心理学(進化心理学)の学者によれば、今後は、自と他の比較、勝ち負けを気にしない人が増えていく可能性があるという。というのは、自と他の比較、勝ち負けを気にする親は、自分の子供が負け組になることを嫌い、産む子供の数が少なくなり、それをあまりに気にしないタイプの親が、多くの子供を産む傾向があるからだという。多くの子供を産めば、その子供が社会の中の勝ち組になるために必要な養育費・教育費を賄うことができないということである。実際に、比較の文化が強いといわれる隣国の韓国は、現在急激な少子化の危機に瀕している(日本の出生率(男女のカップルから生まれる子供の数)は1.3人弱だが、韓国は0.7人台)。
そして、心理学的な研究では、人の心理的な傾向は、半分が遺伝で、半分が後天的なものだといわれるが、自他の比較、勝ち負けを気にする親の子供は、親からの遺伝の影響にしても、その親の作る養育環境という後天的な影響からしても、親と似た性格になりやすいと思われる。よって、現在、自他の比較・勝ち負けを気にする親が産む子供が少なく、気にしない親が生む子供が多いということは、次世代の子供たちは、気にしない子供が多くなるということになる。
9.多難な人生が老年的超越につながるのは、依然として少数派
さて、老年的超越の現象が現れているといっても、「超高齢者の2割」といわれているように、依然として少数派である。これは、客観的に見れば、長寿社会においては、競合的な幸福から協調的な幸福への幸福観の転換が、幸福になるために重要であると思われても、実際には、なかなかその転換に至らない人が多いことを示している。
また、「多難な人生を経験した人に老年的超越が多い」といっても、多難な人生を経験した人の中には、それに単純に打ちのめされてしまうばかりで、価値観を転換して、それを乗り越えることができる人は、依然として少数派かもしれない。その中には自殺や孤独死などによって、老年的超越が生じうる超高齢期まで生きない人もいるだろうし、自死には至らなくても、人生苦のストレスから病気になって、早死にする人もいるだろう。
さらに、長寿化の中で、日本をはじめとして、高齢者の知的・精神的な疾患が目立ってきているという問題がある。いわゆる、認知症・老人性うつ・感情暴走などである。日本は、認知症大国であるが、95歳以上の女性の8割は認知症であるとされる。超高齢者の2割が老年的超越であるといっても、反対に8割は認知症なのである。すなわち、老年的超越が生じうる超高齢期の前に、老年的超越のような心理的な発達どころか、逆に、心理的に退化してしまう疾患が広がっているのである。
そして、実際には、現在の社会では、こうした高齢者の介護の問題が盛んにいわれる状況であり、長寿が至福の老年的超越をもたらすという側面を、知らない人の方が圧倒的に多いだろう。
10.長寿社会における高齢者の幸福は、個人差が大きい
そして、老年的超越と、認知症・老人性うつ・感情暴走は、心理的には、まさに対極的な状態である。前者は、心理学者によって、人が(超)高齢期に、さらに心理的に発達する現象であると解釈されつつある。思春期に子供から大人になる第一次心理的発達に次ぐ、超高齢期の第二次心理的発達であると主張する学者もいる。一方、後者の認知症等の場合は、わかりやすくいえば、心理的には子供返りをしてしまい、他者の介護なくしては生きることが難しいという状態である。
こうして、長寿社会の高齢者においては、心理的に発達するか、逆に退化するかという二極化の現象があることになる。実際に、老年幸福学の研究者である前野隆司教授(武蔵野大学ウェルビーイング学部長・教授:幸福学など)によれば、調査によれば、一番幸福感が低い年齢層は、高齢者ではなく、中壮年層であるが、高齢者の場合、幸福の個人差が大きいことが非常に重要な問題であるという。
これに関連して、男女とも80歳を超えた平均寿命に対して(2023年で平均寿命は、女性が87.14歳、男性が81.09歳で、女性約87歳・男性約81歳。厚生労働省)、介護を受けたり寝たきりになったりせずに日常生活を送れる期間を示す「健康寿命」は、2022年は男性72.57歳、女性75.45歳(厚生労働省)とされている。
この介護が必要な原因が、身体的な不自由であるケースは、心理状態自体には直接影響がないかもしれない。しかし、先ほど述べた認知症・老人性うつ・感情暴走などの知的・精神的な問題である場合は、現在の男性72歳・女性75歳という健康寿命が意味するところは、多くの人にとって、超高齢期の老年的超越という心理的な発達に至る前の年齢で、知的・精神的な健康を失ってしまい、心理的には、逆に退化する流れに入っていく可能性を示している。
なお、話が多少それるが、平均寿命が男性81歳、女性87歳ということにおいては、実際の感覚とは食い違う部分がある。というのは、現代においても、幼少期に早死にしてしまい、無事成人しない人たちも存在し、その人達を含めたものが平均寿命であるからだ。無事成人した人に限った場合の寿命は「平均余命」といわれ、より正確には、ある年齢の人々が平均的に何年生きられるかという期待値をいうが、厚生労働省の令和5年(2023年)簡易生命表によると、令和5年時点で、65歳の男性の場合は19.52年であり、すなわち平均して85歳以上まで生きると予想され、65歳の女性の場合は平均して24.38年であり、すなわち89歳まで生きることが予想される。高齢者の平均余命は、平均寿命より長く、老後を考える時には、平均余命で考える必要があるとされる。これはまさに、長寿化を示す数値である。
11.老年的超越につながる人生苦とは、相対的な苦しみ
さて、多難な人生を送った人に老年的超越が多いとされるが、ここでいう多難な人生、人生苦とは、具体的には何であろうか。宗教と絡めて、人間の苦しみとして貧(ひん)・病・争という言葉があるが、これを使って考えてみると、①経済問題・貧困、②健康問題・病気、③人間関係の問題・争いや別離ということができると思う。
ただし、老年的超越に至る超高齢者の場合は、経済的問題といっても、長寿社会・福祉国家における経済問題であるから、飢え死ぬような貧困、途上国でいわれる絶対的貧困ではない。経済的困窮者を含めて、すべての国民に文化的な生活ができることを保障する、日本を含めた先進国の民主主義社会・福祉国家では、公的扶助・社会福祉制度がある。よって、この経済問題とは、飢え死ぬような貧困ではないが、お金に苦労したというほどのものだろう。ただし、社会福祉制度があっても、現在の日本社会では、年間数千名の人が経済苦を原因として自殺している。これは、物理的・金銭的に生きていけない貧困にあるわけではないが、経済に関する心理的な苦悩のために、自死を選んだことを意味するだろう。
また、健康問題・病気といっても、実際に、超高齢期まで生きることができたのであるから、途上国のように幼少期に短命に終わるような健康問題ではない。そもそも、先進国社会の長寿化は、栄養状態の改善や高度な医療制度の発達が一因とされており、それに守られた中での相対的な問題である。すなわち、先進国長寿社会の中の平均的な人たちに比べれば、相対的に健康問題で苦労したという意味である。
人間関係の問題・争いや別離に関しても、依然として内戦や他国との紛争が継続していたり、治安状態が悪く犯罪が横行したりしている状態ではなく、日本でいえば、長らく内戦も対外戦争もなく、治安状態に関しては、日本の犯罪発生率は先進国の中でも突出して低い。その中で、人々が一般に経験する人間関係の問題・争いといえば、家族・親族の間や、仕事場などでの不和・人間関係の問題が多い。これに加えて、愛する家族・近親者との死別や別離といった喪失の問題があるが、これも長寿化の中で、以前に比べれば、あまりに早い時期で死別・離別することは減少している。
こうして見ると、老年的超越をもたらす長寿の福祉国家における多難な人生とは、人類社会全体から見れば、「非常に恵まれた社会の中で、他と比較して相対的に恵まれない苦しみ」と表現すべきものではないだろうか。これは、現代の先進国・福祉国家の人々の主な苦しみとは、単純に「生きることができない」という絶対的な苦悩ではなく、「他と比較して相対的に不遇である」という心理的な苦悩であることを示している。そして、それを象徴する言葉が、よく言われることがある、ストレス(社会)、勝ち組・負け組、不満・不安、生きづらさ、生きがいの無さ、自尊感情の不足、自己肯定感の低さ、自己愛(型社会)といったものではないだろうか。
12.負け組から老年的超越が生まれ、勝ち組から生まれにくい可能性がある
多難な人生を送った人に老年的超越が多いということは、逆にいえば、順風満帆な人生を送った勝ち組の人からは老年的超越が生まれにくいということになる。この理由を探ってみると、多難な人生を送った人は、高齢期の前から人生苦を経験しており、それを乗り越えるために、先ほど述べた、老年的超越に向かう幸福の価値観の転換(競合的な幸福から協調的な幸福)が、心理的に促されたということができるだろう。
一方で、順風満帆な人生を送った人の場合は、そうした転換を促される人生苦がなかったということである。「苦しみを経験した上での老年的超越が得られなくても、順風満帆で苦しみがなければそれでいいではないか(その方が良いではないか)」という考えがあるかもしれないが、そうした順風満帆の人生を送った人にも、高齢期には皆、高齢期の喪失体験とも呼ばれるさまざまな苦しみが襲うことになる。
健康・体力は衰え、病気は増えてくる。介護が必要になる場合もある。特に男性の場合は、会社を退職して社会的な地位や仕事関係の友人・知人を失い、地域社会などで新たな人間関係を形成することはできずに、人間関係が家族内に限られるケースも多い。子供たちはすでに自立しているために配偶者との関係のみが残るが、(主に妻側からの)熟年離婚の事例も増えている。必要な介護の程度によっては、長年住み慣れた自宅を離れて、老人ホームに転居するように勧められる。
こうして、自分の体、人間関係、環境において、さまざまな喪失を経験する。そして、これは多くの場合、前向きに生きる意欲や、自分の心身を使う=鍛錬する意欲を低下させ、それが老化を加速させるという悪循環が生じ、認知症・老人性うつなどの知的・精神的疾患の背景要因にもなる。心理学者の和田秀樹氏は、「老化は気から」と主張しており、人は、前向きに創造的に生きる意欲がなくなると、それによって頭や体を使わなくなるので、頭や体を鍛錬しなくなって、例えば、記憶力などの機能が落ちるのが老化のプロセスであり、最初から記憶力などが低下するのが老化のプロセスではないとしている。これは、認知症予防には、高齢期にも、例えば、勤労の継続が有効であると一般にいわれることにも通じる。
さらに、順風満帆、勝ち組であった人の中には、喪失の幅が大きい可能性がある。負け組の場合は、高齢期にさまざまな喪失をするとしても、最初から持っているものが勝ち組の人に比べれば少ないので、喪失の程度は相対的に小さいが、勝ち組の人は、持っているものが多いがゆえに、喪失する程度が大きい。木は、高く登れば気持ちがいいが、高く登るほど、落ちた時には痛いのと同じである。さらに、勝ち組の人は、高齢期になる前に、困難を経験していないがために、高齢期の喪失体験に対しては、心理的に慣れがなく、それに対して脆(もろ)い可能性もある。
13.一定の苦しみがなければ悟りに至らない、という仏教の思想
先ほど述べた通り、仏教では、一定の人生苦を経験することが、ブッダの教えを理解する条件となるという思想がある。これを言い換えれば、苦しみが乏しすぎるならば、逆に悟ることができないということである。もう少し全体的に言うならば、仏教の思想では、悟るためには、文明的な生活条件が必要だが、その一方で、快楽が多くて苦しみが乏しすぎても悟ることができないというものである。
わかりやすく言えば、人間ではなく動物に生まれれば、衣食住が保障されない毎日と、悟りに必要な思考力も得られないし、人間に生まれたとしても、飢えや渇き・病気による死や、殺される危険にさらされる毎日では、生き残ることに精一杯で、やはり悟りの修行は難しいだろう。逆に、仏教が説く天界の世界は、人間の世界よりはるかに快適で快楽が多いが、そのために悟りの教えに向かうきっかけがないままに、一生が終わりに近づき、終わりの時点では大きな苦しみが生じるが、その時にはもはや、悟りを得るには間に合わないという。これは、順風満帆の人生だった人が、高齢期になって、急にさまざまな苦しみを経験しても、その際に例えば認知症などですでに知的・精神的能力が低下していれば、幸福観の転換・老年的超越には間に合わないケースと似ているかもしれない。
(※輪廻転生について:なお、ひかりの輪は、大乗仏教等の宗教・宗派ではなく、思想哲学の学習教室であり、来世や輪廻転生については、否定も肯定もしないという立場(中道)である)。
こうして、悟りを得るためには、苦楽の絶妙なバランスが必要である。そのため、先ほど述べた現代の先進国長寿社会において人々が経験している一定の苦しみ、すなわち絶対的な苦しみではない相対的な苦しみとは、老年的な超越につながるもので、必ずしも悪いことではなく、悟り・老年的超越を得る視点から見るならば、非常に重要で、必要で、尊いものであるということができるのである。これは、仏教の教えでは、苦しみを喜びに変えるという教え(忍辱(にんにく))に通じるものである。
14.幸福観・人生観の変革:尻すぼみ型と尻上がり型の人生
さて、老年的超越の現象は、これまでの勝ち組・負け組の概念を、大きく変えていく可能性があるのではないだろうか。超高齢期とはいえ、歴史的にはごく限られた人間しか到達しなかった至福の悟りの心理状態に至ることができるとすれば、それ以上の人生の幸福・成功・勝利はあるだろうか?
「ハッピーエンド」というが、「老年的超越」というハッピーエンド型の人生が現れた以上、人生の中盤までに財物・名誉・地位等に恵まれた、いわゆる勝ち組であっても、高齢期の喪失体験を経て心理的には子供返り・退化をして終わるならば、それは本当に人生の勝利者・成功者なのだろうか。
長寿化する中では、人生は、昔のように「若いころにガンガンやって年を取ったらピンコロで死ぬ」ことを理想とするスプリント競技ではなくて、長いマラソンであるとするならば、従来型の勝ち組になっても、老年的超越という心理的な発達に至らず、高齢期に心理的な退化をして終わるのであれば、前半は先頭を走ったが、途中で失速してリタイアしたようなものではないか。一方、老年的超越者こそが、マラソンでは、トップでゴールを切った勝利者・成功者になるのではないか。
こうして、老年的超越現象が周知されていくならば、「何が、人生の成功・勝利・幸福であるか」という概念が変革されるのではないだろうか? それは、人生観の変化であって、若い時がいいばかりの尻すぼみ型の人生観ではなく、加齢とともに幸福が増大していく尻上がり型の人生観である。ライフイメージの変革である。こうして、至福の心理状態である老年的超越の広がりは、幸福観・人生観の変革・革新をもたらす可能性があると思う。
今、負け組のあなたには、昔から「人間万事塞翁が馬」「ピンチの中にチャンスあり」「急がば回れ」といわれるように、それを活用して、老年的超越の勝ち組に至る、逆転勝利型の人生の可能性がある。今、勝ち組のあなたは、昔から「勝って兜(かぶと)の緒を締めよ」「油断大敵」「急(せ)いては事を仕損じる」という警告があるように、それに満足・安住して用心・精進を怠っている間に、人生終盤で、どんでん返しの敗北を経験することになりかねない。
さて、こうした中で、次節からは、負け組も勝ち組も、この老年的超越を踏まえて、今後の人生をどのように送るべきかについて考えてみたいと思う。
15.老年的超越を踏まえた今後の生き方:
「意図的・計画的な老年的・老年前超越」の実現へ
さて、これまでは、すでに始まった老年的超越現象について述べてきたが、それを踏まえたならば、今後の人生をいかに送るべきであろうか。重要なことは、これまでに老年的超越に至った超高齢者は、老年的超越に至ろうとして至ったのではない。老年的超越の心理状態や幸福観が、仏教の悟りの境地と共通点が多いとしても、彼らは必ずしも仏道修行者ではないし、仏道修行の経験がある人はむしろ例外的であろう。彼らは、多難な人生を実体験する中で、老年的超越という心理的変化を、いわば偶然にも、幸運にも、獲得したのである。同じく多難な人生を送った人の中には、それに打ちのめされるばかりで、老年的超越に至れなかった人の方が多いだろうし、そのために早死にした人さえ少なくない。では、どのようにすれば、老年的超越を得ることができるのであろうか。すなわち、偶然ではなく、意図的・計画的に老年的超越を得ることができないだろうか。
これに関連して、人生で遭遇する困難・喪失・打撃から立ち直る力(レジリエンス)に関する心理学の調査・研究によれば、人によって立ち直る力は異なり、例えば、多様なものの考え方をすることができる人は立ち直りが早く、その経験に逆に喜びを見出し、幸福感が増える場合があることが明らかになっている。そして、そのレジリエンスの心理学が推奨する、立ち直る力を養う方法の中には、仏教やヨーガの修行と共通する内容が少なくない。
また、ユダヤ人強制収容所に収容されて、父母と妻を失い、自らは生還するという極限的な苦境を経験したフランクルという心理学者が、その経験の中から提唱した「ロゴセラピー」という心理療法では、人が幸福になるためには、生きる意味・価値を認識することが重要であり、苦しみの中にあっても、その中を生きる意味・価値を見出すことができれば、それを乗り越えて成長することができることを説くが、これも仏教の思想・生き方と共通点が多い(ロゴセラピーでは、人が苦しみに見出す価値の典型として、それが自分の精神的な成長や他への思いやりにつながることがあるという)。
こうして、偶然にではなく、意図的に老年的超越を得るためには、心理学や仏教の思想などから、人の幸福・不幸に関する奥深い智恵をよく学ぶことが重要であることがわかる。老年的超越の心理状態の特徴が、仏教の悟りの境地とよく共通していることからしても、それを、偶然にではなく、意図的・計画的に実現するためには、仏教の思想・実践や、それとよく共通している心理学の思想・実践の体系を学ぶことが助けになることは、ある意味で当然だろう。