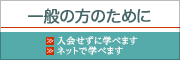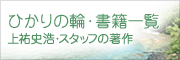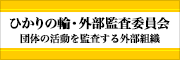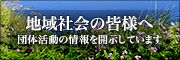2020~21年 年末年始セミナー特別教本「ヨーガ・仏教の修行と科学 人類社会と宗教の大転換期」
(2025年4月24日)
2020~21年 年末年始セミナー特別教本「ヨーガ・仏教の修行と科学 人類社会と宗教の大転換期」
第3章 幸福になる脳科学と仏道修行
1.今注目される脳の「島(とう)皮(ひ)質(しつ)」とは
岩崎一郎氏(脳科学者・医学博士)によれば、今世界の脳科学者たちが「島皮質」という脳の部位に注目しているという。島皮質は、脳全体をバランスよく協調的に働かせるために必要な「ハブ(中継基地)」の役割を果たしている部位である。
従来は、高次機能をつかさどる前頭前(ぜんとうぜん)野(や)、記憶に深く関わる海(かい)馬(ば)、モチベーションに関与する中(ちゅう)脳(のう)のドーパミン細胞などが注目されていた。一方、島皮質は、大脳のひだ奥深くに隠され、他の部位に覆われていることもあり、これまであまり注目されてこなかった。
島皮質は、担当する分野がかなり幅広い。脳では、この部位は記憶を担当、この部位は理性の担当というように、各部位でそれぞれの役割担当が決まっているが、島皮質は、社会的感情、道徳的直感、共感、音楽への感情的な反応、依存、痛み、ユーモア、他者の表情への反応、購買の判断、食の好みなどに幅広く関わるという。そして、島皮質からの情報は、脳の他の部位、とくに前(ぜん)帯状(たいじょう)回(かい)や前頭(ぜんとう)葉(よう)に伝えられて意思決定にも関わり、幅広く活躍しているという。
2.島皮質は人の幸福を左右する
島皮質の大きな特徴は、脳のなかで「ハブ(中継地点)」のような役割をしている点である。自分の外側から来る感覚と内側の感覚をつなぐ、他人の気持ちと自分の気持ちをつなげる、また、過去の自分と今の自分や、今の自分と未来の自分のイメージをつなげるといった時間的なハブの役割もするという。このハブの働きによって、私たちは他者のことを理解したり、他者に共感したりすることができるという。
よって、島皮質の機能を高めると、他の人と心のつながりを持ちやすくなり、たとえば、どんな過去を持っていようと受け入れやすくなる。それだけでなく、島皮質は、脳のいろいろな箇所をつないでいるため、脳全体が活性化され、脳が本来持っている力が引き出される。
そのため、最近になって、この島皮質を鍛えて、脳全体をバランスよく協調的に働かせることが、その人の人生を豊かで幸せにすると科学的にわかってきたという。イギリス・スターリング大学のルイス博士らの研究では、「ウェルビーイング(幸福)と島皮質の厚みは、正の関係にある」という結果を出している。
すなわち、幸せな人というのは、島皮質が厚いということである。これを逆に考えると、島皮質が厚くなるような脳の使い方をすれば、私たちは幸せになれるということになる。
3.島皮質を鍛える6つのポイント
岩崎博士によれば、エビデンスに基づいた島皮質を鍛えるポイントは6つあるという。
第一に、「感謝の気持ちを持つこと」である。誰かに何かをしてもらったときの感謝だけでなく、常に感謝の気持ちを抱くことが、脳の活性化には有効であるという。韓国・ヨンセ大学のキョン博士らの研究では、被験者に「感謝のワーク」を行ってもらい、そのときの脳の状態を調べたが、感謝している時には、脳内で複数の領域がプラスにつながり、脳の活動が活発化したという。そして、脳内の複数の領域をつなげる中継地点の働きをするのが、先ほど述べた島皮質である。
第二に、「前向きになる」ことである。気持ちが前向きだと、脳は活性化され、脳全体が働きやすくなるという。スペイン・マドリード大学のマーチン・ローチ博士らの研究では、「ポジティブな言葉」と「ネガティブな言葉」を投げかけられたときの人の脳波を測定したが、ポジティブな言葉には、脳全体が活性化したのに対して、ネガティブな言葉には、脳はあまり活性化しなかったという。
第三に、「豊かな人間関係を作る」ことである。逆に孤独は人の脳にとって「毒」になるという。アメリカ・シカゴ大学のカチオポーロ博士らの研究によると、孤独の状態が続くと、新しく脳細胞を生み出す脳内ホルモンの生産が減り、他の脳内ホルモンや神経伝達物質も減少することがわかったという。そして、前に述べたように、この豊かな人間関係を作るために必要な部分(言い換えれば、鍛えられる部分)が、島皮質である。
第四に、「利他の心を持つ」ことである。すなわち、「まずは自分」と考えるのではなく、まずは他者のことを考えることである。スイス・チューリッヒ大学のハイン博士らの研究では、利他的な行動をした人は、脳内で島皮質と前帯状回、線条体(せんじょうたい)という3つの部位がうまくつながって活動したことが確認されたという。
第五に、島皮質に限らないが、「マインドフルネス瞑想」が、脳に良い効果をもたらし、特に脳の老化の防止につながるという。アメリカ・ハーバード大学のガード博士の研究では、普段からマインドフルネスを実践する人たちは、70歳になっても45歳のときの脳機能のままで老化がストップしていたことが判明したという。
第六に、「Awe(オウ)体験をする」ことである。第2章で詳しく述べたが、これは、脳を大幅に活性化させ、すでに述べたポイントでもある利他心を増大させたり、マインドフルネスと同じように物事をありのままに受け入れたりすることができる効果があることがわかっている。
これら6つの実践は、昔から説かれている善行など、オーソドックスなものが多い。しかし、だからこそ逆に、「もっと収入を増やしたい」と思う時に、「感謝しなさい」とか「前向きになりなさい」と言われても、納得いかない人も多いだろう。
しかし、岩崎博士によると、博士自身の体験からしても、それは従来のものの考え方と脳の使い方にとらわれているためであるという。たとえば、多くの人が、「もっと収入が増えさえすれば、幸せになれるはず」、「もっと良い学校に入れていたら、違う人生を歩めたはず」などと思うが、これは、こうしたパターンの考え方・脳の使い方を、無意識にしてしまっているということである。
しかし、科学的な研究の結果によれば、実際に豊かで幸せに生きるためには、まずは、先程の6つのポイントなどを実践することで、幸福になるために必要な脳の部分を鍛える必要があるのである。収入を増やしたり、良い学校に入ったりするためには、それを実現するために必要な脳の機能を鍛えなければならない。
4.後悔・不満・悪口は、脳を劣化させる
一方、過去の後悔のために脳を使うことは、島皮質を鍛えるために重要な「前向きになること」と逆方向のものである。また、自分の過去を後悔する人は、卑屈・自己嫌悪が強くなるが、同時に問題を他人のせいにして、他人への不満・嫌悪・悪口も多くなる傾向がある。
しかし、この他への不満・嫌悪・悪口も、科学的に見ると、脳を劣化させてしまうという。精神科医の樺(かば)沢(さわ)紫(し)苑(おん)氏によれば、多くの人は、悪口は「ストレス発散になる」と思っているが、実際は逆であり、悪口はストレスを増やし、最悪の場合、脳を傷つけ、寿命を縮める危険性もあるという。
まず、東フィンランド大学の研究によると、世間や他人に対する皮肉・批判度の高い人は、認知症のリスクが3倍、死亡率が1.4倍も高く、批判的な傾向が高ければ高いほど、死亡率は高まる傾向にあるという。そして、その背景として、悪口を言うとストレスホルモンであるコルチゾールが分泌されるという。コルチゾールというのは、ストレスを感じたときに放出されるホルモンである。
一方で、悪口がストレス発散になると思う理由は、やる気や快楽をもたらす神経伝達物質である「ドーパミン」が放出されるからである。しかし、このドーパミン神経回路は欲張りであり、一度放出されると、その次はより大きな刺激を求める。つまり、悪口の回数を増やしたり、より過激な悪口を言ったりしないと、ドーパミンが出にくくなるのである。
結果として、悪口を言うことが癖になり、悪口を言えば言うほど、ますます悪口の深みにはまってしまい、抜け出せなくなる。これはアルコール依存症や、薬物依存症と同じ原理であり、悪口は依存症と似た側面がある。実際に他の依存症と同じように、依存による弊害がある。前に述べた通り、悪口を言えば、コルチゾールが出るために、それによるストレスが増えていく。結果として、やめられない中で、徐々に利益が減り、弊害の方が大きくなって、不幸になってしまう。
当たり前のことだが、悪口の弊害は他にもある。人は誰かに親切にされれば、親切を返したいという気持ちが湧く(心理学でいう「好意の返報性(へんぽうせい)」)。逆に、悪口には、悪口を返したくなる(「悪意の返報性」)。よって、悪口を言えば、やはり悪いものが帰ってくる。たとえ陰口でも、聞く人には「よく悪口を言う人」という印象を与え、信頼されなくなることもある。その結果、さらに自己肯定感が低くなる悪循環に至る。
さらに、悪口を言う人は、他人も自分を嫌っていると思いやすい。人は、自分の行動・性格を通して、他人のそれも推察する。だから、他人を嫌悪する人は、他人も自分も嫌っていると思いやすい。そして、自分は他に嫌われていると思えば、これによっても、さらに自己肯定感が低くなるという悪循環に至る。
5.人が悪口を好む心理的な理由
悪口をやめられない科学的な理由を先に述べたが、次に、そもそもなぜ人は悪口・中傷を好む面があるかに関して、心理学的な見解を紹介する。
アメリカの心理学者であるレオン・フェスティンガーによれば、人間はついつい他人と自分を比較してしまう生き物であり、特に日本人の場合、集団での和を乱さないためにも、他人の顔色をうかがう、他人の行動や言葉に目を光らせ、自分と他人を比べる傾向が強いという。
そして、人間は、他人と自分を比べたときに自分が優れていると「優越感」を抱き、その逆に、自分が劣っていると感じたときに「劣等感」を抱く。そして、劣等感は強い苦しみであるために、何とか払拭したいという衝動にかられるが、これが悪口や中傷を招く。
というのは、悪口や中傷で、他人をおとしめることができるからである。自分と他人の比較において、他を引きずり下ろすことで、自分の価値を相対的に高めることができる。そうして劣等感を緩和しようという心理が働いてしまう。よって、自己肯定感・自信が低く、劣等感が強い人ほど、実は悪口を言う傾向にある。
逆に、自己肯定感が高い人、自信を持っている人、劣等感の弱い人は、他人と自分をいちいち比較することもなければ、悪口を言うこともないのである。たとえば、「笑う門には福来る」「金持ち喧嘩せず」などと言う通りである。
6.悪口をやめる方法:自己賞賛
よって、周りに悪口好きな人がいた場合に、自己肯定感が低く劣等感に苦しむ人と考えれば、落ちついて受け止めることができるだろう。
また、自分が自己肯定感が低く、悪口が癖になっている場合、それから脱却する一つの方法は、自分で自分を褒めてあげ、自己肯定感を高めることである。すると悪口は自然と減っていくことになる。その為には、例えば、些細な成功だと思うことでもほめることや、多様な価値観に基づいて自分の長所を見つけることである。
劣等感の強い人の場合、理想と現実のギャップが大きいために、大きな成功でなければ、自分を肯定できない癖がついている可能性がある。しかし、大きな成功は、実際には小さな成功を積み重ねることで得られるものであるから、焦らずに、小さな成功をほめていくことが望ましい。さもないと、そういう人は、焦りから一攫千金を狙って、悪いものに手を出して自滅することもある。
また、画一的である社会の主流の価値観にとらわれ過ぎると、自分の長所が見つからない場合も少なくない。競争社会の中でもてはやされる財力・名誉地位・容姿など、他人に勝つ能力ばかりを人の長所だと考えれば、たとえば優しさといった長所があったとしても、それは見つからないだろう。
7.妬みの対象への対処法
また、自分が見下す対象だけでなく、自分が妬みがちな対象にも、同じ背景心理によって、悪口を言いやすい。これに関しては、妬みの対象が、実は必ずしも、自分以上に幸福とは限らないことを考えたり、「自分の幸福を奪う敵」ではなく、「自分の幸福の助力者である」ととらえたりするという方法がある。
自分の妬みの対象である他人は、恵まれているように見えるが、実際には、上には上がいるから、その人も同じように妬みを抱いているものである。そして、得れば得るほど、失う不安は強くなり、上に行けば行くほど、競争も激しくなる。こうして、持つ者が抱える重み・苦しみと、持たない者の気軽さ・幸福がある。
こう考えると、自と他を比較することが、あまり意味がないことがわかる。
また、何かにおいて自分より優れている他人に対しては、「自分の幸福を奪う敵だ」と思うのではなく、発想を変えて、「自分の見本であり、自分の成長を助ける助力者だ」とポジティブに考える。実際、自分が一番優れている存在であれば、それ以上成長することは非常に難しいだろう。これは、自分と他人を同時に肯定する心の働きを作ることになる。
8.感謝がもたらす恩恵
これと同じ作用を持つものが感謝である。自己肯定感が低く、不満と悪口が多い人は、自分の得ている幸福や恵みを認めて感謝することが苦手である。これに対しては、たとえば、これまでは当たり前だと思っていたことでも、感謝する癖をつけるという方法がある。
たとえば、広い視野から客観的に自分を見なおしてみれば、当たり前だと思っていたことでも、大きな幸福・恵みがあるはずだ。たとえば、世界の中で日本人が置かれている状況を見れば、容易に見つかる。自分の理想や、妬みの対象とばかり比較せず、広く客観的な視点から見て、大切な幸福・恵みを見つけて、感謝するようにするのである。
そして、感謝は、自分の幸福を意識して自己肯定感を高めるとともに、それを支える他者・万物を肯定して、自他双方を肯定するポジティブな意識を作り、感謝の対象への愛・利他の心につながり、島皮質を含む脳を活性化させて、幸福になる条件を高めることになる。
9.島皮質を鍛える仏教の感謝の教え
話を元に戻して、あらためて島皮質を鍛える実践を見れば、それが仏道修行とよく似ていることがわかる。
まず、第一の「感謝の気持ちを持つこと」に関していえば、仏教の基本的な法則が、「足るを知って、感謝すること」である。人の欲望は際限がなく、不満や怒りを持ちやすく、満足・感謝が不足しがちである。
さらに、仏教では、高度な感謝の実践を説く。それは、苦しみに対する感謝である。仏教的な思想から見れば、苦しみの体験は、自分の心身を鍛え、苦しみの根本的な原因である煩悩・我欲を抑制する悟りの修行に導き、他の苦しみに同情してそれを取り除こうとする慈悲の心の源になる。よって、大乗仏教が説く「六つの完成」という教えの中には、様々な苦しみに耐えて、それを喜びに変えていく忍耐(忍辱)という修行課題が説かれている。
また、全ての衆生・生き物を利して救おうとする者を菩薩といい、その道を菩薩道というが、その利他・救済の動機は、全ての衆生・生き物への感謝に基づくとされる。菩薩を目指す者も、他者・万物のおかげで生きて修行することができるのであるから、その恩返しとして、恩人である他者・万物を利して救済するという思想である。
10.前向きになる仏教の思想:苦楽表裏
二つ目に、前向きになることに関しては、仏教は苦楽表裏という教えを説く。これは、一つ目の所でも述べたが、苦しみには、その裏側やその先に喜びがあるという思想である。苦しみの裏には恩恵があるというのである。これは、「万事塞翁が馬」「失敗は成功のもと」「死中に活」「ピンチはチャンス」という考え方にも通じる。
ここでのポイントは、多様で多面的な考え方である。後ろ向きになりやすい人は、物事を否定的にばかり考える傾向がある。しかし、いかなる物事にも、様々な見方が可能であり、悪い面も良い面もある。後ろ向きになるということは、否定的な見方ばかりに意識が固定されており、他の見方ができていないということだ。
逆に、前向きになるためには、多様で多面的で創造的な考え方が必要である。具体的な事例は省略するが、仏教を通じてそうした見方を学ぶことができる。これは、仏教が説く智慧の一部である。
11.仏道修行の中核:利他・マインドフルネス・大自然の体験
次に、島皮質を鍛えるとされる実践の中で、第三の「豊かな人間関係を作る」ことや、第四の「利他の心を持つ」ことは、まさに大乗仏教が説く利他の実践そのものである。
また、第五の「マインドフルネス瞑想」は、そもそも仏教の「念(サティ)」の瞑想に由来するものである。実際に、「念」の英訳が、マインドフルネスであり、仏教の禅の修行に傾倒した米国の医学者が、それを土台にして開発したのが、現在広がるマインドフルネス瞑想である。
最後に、第六の「Awe(オウ)体験をする」ことも、大自然の中で営まれてきた仏道やヨーガの修行の中核である。このように、仏道修行は自ずと島皮質を鍛えるものとなっており、最新の脳科学の視点からも、幸福をもたらす実践だと思う。
※第3章参考文献
・『東洋経済オンライン』「自分は不幸だと思う人は脳の使い方を知らない」(2020年10月22日) https://toyokeizai.net/articles/-/383379
・『Newsweek』「悪口をよく言う人ほど『不幸になる』── 言霊の真相を科学で知る」(2020年8月21日) https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94236_2.php