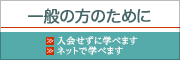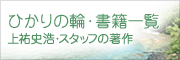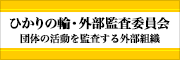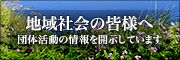2023~24年 年末年始セミナー特別教本「仏陀が説いた革新的な幸福の智慧 健康と悟りをもたらす身体行法」
(2025年4月28日)
2023~24年 年末年始セミナー特別教本「仏陀が説いた革新的な幸福の智慧 健康と悟りをもたらす身体行法」
第1章 悟りの智慧:自他の区別を超える教えと瞑想
1.仏教の悟りの教えのエッセンス
仏教の教えは、仏教開祖の釈迦牟尼が説いた通り、苦しみを滅する教えであるが、そのためにさまざまな教えが説かれている。初期仏教の経典から大乗仏教の経典・密教経典まで、膨大な経典がある。しかし、その教えの恩恵を得るためには、広く学ぶだけではなく、その教えのエッセンスをつかみ取り、それを体得するために繰り返し修行(瞑想)する必要がある。
すなわち、仏教とは、単なる知識の学習ではなく、実際に心身が苦しみから解放されるように、その教えを体得するべきものである。それは、知識が増えるというよりも、その人の価値観・世界観が変わることを含んでいる。現代の科学で表現するならば、脳神経ネットワークの働きが向上すると言えばいいだろうか。
そして、本章においては、あまたの仏教の教えに言及しつつ、これまでの学習と瞑想の経験に基づいて、そのエッセンスとなる中核の思想の部分について、単に言葉で表現するだけでなく、なるべくそれをイメージ的に理解できる、体感できるように、表現してみたいと思う。
2.まず、教えの言葉の意味を正確に理解する:四(し)法(ほう)印(いん)を例にとって
仏教が説く智慧を体得するプロセスには、いくらかの段階があるという考えがある。第一に、まず教えを知識として学ぶことである。そして、この点に関しては、教えを表す言葉の意味を十分に理解する必要がある。この点をよく理解するために、仏教の主たる教えをまとめた「四(し)法印(ほういん)」を例にとって、以下に説明する。
四法印とは、①諸行(しょぎょう)無常(むじょう)、②諸法(しょほう)無我(むが)、③一切(いっさい)皆(かい)苦(く)、④涅槃(ねはん)寂静(じゃくじょう)である。こうして、多くの場合、仏教の教えは漢訳仏教用語によって学ぶことになる。原典はサンスクリット語やパーリ語で表現されているが、それが中国に伝わって漢訳されたものである。その意味を正確に理解することが第一である。例えば、諸行とは、諸々の行いという意味ではなく、「全ての存在」というほどの意味である。漢訳仏教用語の中には、現代的に見ると、あまりうまくない訳がある(一部は誤訳といってもよいかもしれない)。よって、正確な意味を調べる必要がある。
諸法も、諸々の法(法則)という意味ではなく、実は、「全ての物事」といったほどの意味である(正確にいえば、思考の対象となる全ての物事であり、実際に存在しない観念的なものを含む点で、諸行よりも意味が広いとされることが多い)。
無我とは、サンスクリット原語で「アナートマン」といわれ、「アートマン」の否定形であり、釈迦牟尼によって、「私ではない、私のものではない、私の本質ではない」という意味であると解説されたという。こうして、私ではないという意味があるので、このアナートマンは、非我とも訳されることがある。ここで、無我と訳すと「私は無い」という語感となり、非我と訳すと「私に非ざる」という意味で「私ではない」という語感となるが、実はどちらと解釈するかは、歴史的な議論となった経緯がある。しかし、諸法無我という全体で見るならば、全てが私ではない(諸法非我)のであれば、私は無い(諸法無我)ということと同じだと解釈することができるだろう。
こうして、言葉の意味を正確に理解する中では、漢訳がはらむ問題も乗り越える必要がある。例えば、「一切皆苦」の苦は、サンスクリット原語の「ドゥッカ」の漢訳であるが、これは多義語であって、苦しみと喜びのうちの苦しみを意味するのではなくて、不安定・不満足・不完全といったほどの意味がある。さもなければ、一切皆苦とは、全てが苦しみであるという主張となり、苦しみも喜びもあると思われる現実世界の実際に照らして、違和感、矛盾を感じることになるだろう。
こうして、多義語には注意する必要がある。涅槃(ねはん)寂静(じゃくじょう)の涅槃も、少し仏教を学んだ人の場合、釈迦牟尼が死去した時のことを涅槃(正確には大般(だいはつ)涅槃(ねはん)、マハー・パリ・ニルヴァーナ)とか入滅ということを知っているかもしれない。しかし、涅槃寂静という場合の涅槃は、死去の別名ではなく、悟りの境地のことを意味する。悟りの境地とは、煩悩を滅した心理的な状態で、それが寂静(静かな平安な境地)であるというのである。
こうして、まず教えの言葉の意味に関して、場合によっては原語までさかのぼって、十分に正確に理解する必要があるが、ひかりの輪の特別教本などでは、この点になるべく注意して、仏教の法則を解説していることを付け加えておきたい。
3.教えの確からしさを論理的に理解する
さて、言葉とその意味を学んだなら、次に、その教えの確からしさを論理的に理解することが重要である。つまり、教えの言葉の意味を理解したとしても、その教えの主張が、確からしい、道理・真理である、ということを論理的に理解する、納得するプロセスである。ここで重要なことは、仏教の悟りの法則とは、少なくとも釈迦牟尼が説いた教え(初期仏教)に関していえば、それは「信じる」べき対象ではなくて、「悟る」=「気づく」べき対象であるということだ。
これに対して、宗教における「信じる(信仰)」とは、多くの場合、十分に合理的な根拠がなくとも、その教えの言葉を「正しいと思うこと」を意味する。つまり、その教えが正しいことを十分に知ってはいなくても、正しいと思うことである。そうして信じた結果、何かしらの体験をして、救われたと感じて信仰を深めることもあるし、死んでみないと救われるかどうかはわからないうちに人生を終える場合などがあるだろう。
一方、悟りとは、日常用語でも使われるように、気づくという意味がある。これは、今まで認識できなかったことを認識するということである。よって、その教えが正しいこと、確かなことに気づくのが仏教の悟りのプロセスである。よって、まず教えの言葉の意味を理解したら、次に、なぜその教えの主張が正しい、確からしいということができるのかを、よく論理的に検討する必要がある。
この論理的な検討の一部には、教えに対して疑問を持ち、その視点から教えを吟味することも含まれる。実際に、釈迦牟尼自身が、自分に対する崇敬の念から教えを信じるのではなく、まずは疑い、よく吟味し、納得した上で、修行するようにという趣旨のことを説いたとされている。
よって、科学の理論・法則と同じように、仏教の悟りの教えに関しては、その確からしさをしっかりと論理的に検討し、深く納得する必要がある。もし納得できないのであれば、それは悟りの手助けにはならない。それは、悟りとは、信じるという心理状態ではなく、真理・道理に気づいた(発見した)心理状態であるからだ。
そして、仏教の教えは、普通の人が日常の中で気づくことがない人の幸福の道理・真理を説いている。普通の人の常識の中にある大きな錯覚(痴・無智)を指摘するのが、仏教の教えの特長である。よって、これに対して、はたと膝を打つかのように、目からうろこが落ちるかのように納得するまで、十分に論理的に検討する必要がある。
一方、信仰とは、正しいか否かを本人が「知ること」はできない事柄を、正しいと「思うこと」であるから、どんなに信仰が篤い人の場合であっても、少なくとも無意識的なレベルでは、疑念とセットになっているのが信仰の心理状態であると思われる。
そのような疑念をはらんだ心理状態では、悟りに至ることはできない。悟りとは、そうした、いわば思い込みの結果ではなくて、深く気づいて納得し、心理的な葛藤がなく、統一された状態である。そして、最終的には、その気づきを繰り返し瞑想して、一時的なものではなくて、無意識レベルにまで浸透させ、日常の価値観・世界観を根底から変えていくことで、悟りを深めていくのである。
4.仏教のさまざまな教えは、本質的には一体であること
深く納得することの中に含まれるが、仏教にはさまざまな教えがあるものの、その本質は一つであるということができる。異なる言葉で表現されているので、異なる教えのようにも感じられるが、その意味を理解して深く納得する中で、同じ悟りの境地を異なる表現で表したものだと気づくと思う。
例えていうならば、山の山頂は一つだけであるが、山頂に至る道は数多くあることと同じようなものだ。そもそもが、仏教の悟りとは、知識として、その言葉を知ることではなくて、実際に心身の状態に大きな変化をもたらす境地を体得することである。その状態に至るためにさまざまな手段(=方便)がある(なお、方便とは、嘘のことではなく、手段という意味である)。
こうして、教えを論理的に深く納得する努力をする中で、さまざまな教えが、その本質において一つであると理解するプロセスがあると思う。
5.自我執着(我執)を超える悟りの智慧
仏教が説く悟りとは、苦しみの原因を理解し、その原因と苦しみを取り除くことである。その苦しみの根本原因を端的にいうならば、「自と他を区別して、自己に過剰に執着すること」だということができる。そのため、仏教では、自と他を区別せずに、自と他を平等に愛する心理状態を求める。
普通の人が有する自と他を別のものと見る認識を「自と他を区別する無智」などと表現し、それを乗り越えた自と他を一体とする認識力を「智慧」などと表現する。そして、その智慧に基づいて自と他を平等に愛する心の働きを慈悲と呼び、究極的には、慈悲は万物を平等に愛する心の働きとなる。
6.心も実際は自分ではないという智慧
自と他を区別しない智慧の心理状態とは、突き詰めるならば、「自分の思考や感情などの心の働きや、体は、自分ではない」と気づいた心理状態である。これは、先ほど述べた諸法無我の教えに含まれる。心身を含めた全ては、私ではないということだ。
わかりやすくいうならば、自分とは、自分の意識であって、それは、心(思考や感情など)や体を経験しているものであり、心や体は、自分(=意識)に経験されている側であって、自分(=意識)ではないということである。
ところが、普段の自分の意識は、心と一体となっており、心を自分と混同して錯覚している。すると、自動的に、意識は、自分と他人を区別することになる。何かを、自分だと認識するということは、それ以外のものを、他者だと認識することと一体であるから、心を自分だと錯覚した段階で、同時に、自分ではない他者というものが、認識されることになる。
例えば、朝起きる直前など、全く思考が生じていない段階では、自分という認識も、他人という認識も生じていない。単に意識があるだけで、全ては混然一体としている。自分や他人といった言葉による思考が始まると、自と他を別物とする認識(自と他を区別する無智)が生じるのである。こうして、言葉による思考が、自と他を区別する意識状態を現し出すことがわかる。
7.自と他を区別しない心理状態に近づく
さて、ひかりの輪で実習する仏教・ヨーガの身体行法を行うと、思考や感情が静まってくる。具体的には、ヨーガの伝統に基づく体操法・姿勢法・呼吸法やシンボル瞑想(マントラ瞑想)である。これらは、正しく実践すれば、徐々に思考や感情を静める効果がある。
これに成功するならば、意識は鮮明なままに、思考や感情が静まった状態を経験することができる。その時の意識は、思考や感情が静まっているため、自と他を強くは区別していない状態である。ただ、鮮明な意識があり、静かな平安な意識である。これは無我の境地ということもできる。この意識状態は、自分と他人を区別していないから、普段と比較すれば、意識が広がったように感じられるものとなる。静まった広がった鮮明な意識である。これが、仏教が説く瞑想状態(禅定)の本質の一つだと思う。
8.ヨーガの真我の概念
ヨーガにおいては、心の働きを止めて、心を自分だと錯覚した意識が、真実の自分自身を取り戻すことを重視する。そもそも、ヨーガとは、心の働きを止滅すること(サンスクリット原語で「心のニローダ」)という意味である。心を自分と錯覚・混同している主体は、真我(アートマン)ともいわれる。
これが、いわば「真実の自分」であるが、真我は、純粋観照者ともいわれ、純粋に万物を観察(経験)するものであって、観察(経験)される側を一切含まない。よって、普通の意味では、真我自体は経験することができないとされる。これは、目はいろいろなものを見るが、自分の目で、自分の目を直接見ることができないことと同じようなものである。自分の目が、鏡に映った様子は見ることができても、それは本当の目を直接見たものではなく、鏡に映ったものを間接的に見ているにすぎない。
経験する側と経験される側を表現する言葉として、主体と客体という言葉があるが、真我は、あくまで経験の主体であり、経験される客体ではない。この経験の主体は、純粋な意識そのものであり、意識が経験する思考や感情は含まない。そのため、真我は、何かの物と表現するのではなく、「経験する力」などとも表現される場合がある。
そして、ヨーガにおいては、心の働きを止滅することで、最終的に、真我だけしかない状態(真我独存位)を目指し、これを解脱と呼ぶことがある。普段の私たちの意識(真我)は、思考や感情といった心を、自分だと錯覚して混同しているが、心の働きを止めるならば、真我のみが立ち現われてくるということだ。
真我独存位とはいかなるものであるかは、言葉で表現することは困難である。それは、言葉による思考・感情がない状態だからである。経験する真我だけがあって、経験される側がない状態である。自分と他者万物、主体と客体、見るものと見られるものの区別がない状態である。普段の我々の意識は、自分が世界を体験しているが、真我の状態は、経験する自分と経験される世界の区別がない(その意味で、自分が世界で、世界が自分とも表現できるかもしれない)。
なお、仏教の伝統的な教義においては、その真我の概念は用いない。学術的な研究の結果としては、仏教開祖の釈迦牟尼は、真我の存在・概念を、否定も肯定もしなかったともされるが、釈迦牟尼以降の仏教の教学においては、諸法無我の教え、すなわち、私というものは一切無い、という仏教が重視する教義に基づいて、ヨーガが説く真我の存在・概念をも否定することになった経緯がある。
しかし、思考や感情といった心が真実の自分ではなく、それに執着することを否定する点では、ヨーガと仏教は同じであるから、真我の概念を認めるか認めないかは、あまり重要ではないと私は思う。これは、教えの表現の問題であって、両者とも、実際に悟りの境地を目指す上で、思考や感情といった心の働きを、自分とはせず、その心の働きが静まった瞑想状態を目指す点は、全く同じであるからだ。なお、この瞑想状態を漢訳仏教用語では、禅定(ぜんじょう)というが、この禅定という仏教の言葉は、そもそもが、「ヨーガの八階梯」と呼ばれる古典ヨーガの実践課程の最終段階であるディアーナ(=禅)・サマディ(定)の訳語である。
9.自と他の区別を滅した瞑想状態、静かな安定した広がった意識
それでは再び、自他の区別を滅した瞑想状態に関して言及したい。思考や感情が静まりながらも、意識は失わずに鮮明な状態に至るならば、前に述べたように、「自分」や「他人」という言葉による思考や感情は静まり、生じておらず、単に、静かで鮮明な意識のみが存在する。これは、静かで平安な意識状態であるから、前に涅槃寂静の教えのところで述べたように、悟りの境地(涅槃)は、静かで平安(寂静)であるなどと表現されるのだと思う。
この意識状態は、まず、安定しており、苦しみがなく、平安である。日常の心は、さまざまな欲求や興奮とともに、不安・恐怖・怒り・いらだち・嫌悪などの苦しみがあり、絶えず動いており、不安定であるが、それらが静まって、苦しみがなく、平安である。
次に、前にも少し述べたが、この意識状態は、普段の自分と他人を区別する意識から解放されて、広がっている(と感じられることが多い)。これを言い換えるならば、我々の意識そのものは、本来は、自と他の区別を有するものではないが、普段は、自と他を区別する思考や感情といった心の働きを、自分だと錯覚してしまっているがために、非常に狭いものになっているとも表現できると思う。
しかし、自と他の区別をする心の働きを静め、それから意識が解放されれば、いわば、意識が広がっていく。これを「意識の拡大」などということがある。突き詰めれば、世界全体を包むような広大な意識に至ることができるとも説かれる。世界万物を一体として認識する意識である。これをヨーガでは、宇宙意識などと表現することがある。また、仏教が説く仏陀・菩薩の心は、大慈悲もしくは四無量心といわれるが、これは世界万物を愛する心の働きであり、これもまた意識の拡大ということができると思う。
10.静まった広がった意識状態の恩恵:心の幸福、健康、集中力・知能、智慧の向上
さて、これまで、思考や感情などの心の働きが静まった鮮明な意識状態(禅定)に関して、それに自と他の区別がないという点を強調しながら述べてきた。しかし、自と他の区別がないというのは、その状態の一面を表現したものであって、思考や感情が静まっているのであるから、普通の意味での喜怒哀楽がない状態であるということもできる。
ただし、普通の意味での喜怒哀楽がないとしても、それは幸福ではないという意味ではない。意識は、さまざまな苦しみから解放されて平安であるとともに、大きく広がった解放感や温かさ、場合によっては、至福感などが体験される。
この意識状態は、健康にも良く、体は安定し、無駄なエネルギーの消費はない(その意味で休息している)。日常のさまざまなネガティブな思考・感情・ストレスが、いろいろな意味で心身の健康を害することはよく知られているが、その意味で、禅定の状態は、健康長寿をもたらすと思われる。それを示唆するさまざまな医学的調査研究の結果もある。
また、この意識状態は、雑念がなく、意識は鮮明であるから、何かの物ごとに取り組もうとするならば、それに深く集中することができ、そのため、知能などの心身のパフォーマンスの向上をもたらす。そのため、禅定・瞑想状態は、「心の安定と集中」と表現されることもある。パソコンに例えれば、雑多なタスクから解放され、重要なタスクに全能力を集中できる状態と表現できるかもしれない。なお、近年、ストレス解消や仕事の能率を上げるものとされて普及しているマインドフルネスは、禅の瞑想から宗教色を抜いてできた心理療法である。
こうして、禅定の状態は、集中力・知能などを高めるが、それにとどまらず、その本質的な恩恵は、物事をありのままに見る力、仏教で智慧と呼ばれる高度な認識力の土台となることである。ここでいう物事をありのままに見る力・智慧とは、一般的な意味での観察眼とか、知能という意味ではない。前に述べたように、悟り=真の幸福に導く世界の道理を理解する力であり、常識的な世界観の中にあるさまざまな錯覚を乗り越えるものである。
11.自と他の区別に基づく自と他の優劣の比較について
私たちの常識的な価値観においては、自分と他者は別物であることが当たり前になっている。しかし、仏教の心理学においては、これは常識の中にある錯覚であり、さらには、さまざまな苦しみの原因となるものである。そこでまず、どのように私たちの苦しみが、自と他を区別する認識から生じているかについて考察する。この点の深い理解は、前に述べた瞑想状態・禅定と悟りの境地に近づくために、非常に重要である。
まず、私達が日常において喜びとするものは、利他の行為などによって得られる幸福感などを除いては、前に述べたように、「今よりもっと、他人よりもっと」と、自分のために、財物・名誉・地位・異性などを求めて得られた時に感じられるものである。
これは、無意識のうちにも、比較に基づいたものである。今の自分と以前の自分、そして、自分と他人の比較をして、優っていれば喜び、劣っていれば悲しむのである。そして、そのために、この幸福感や不幸感を客観的によく検討するならば、自分の幸福は他人の不幸とセットであり、他人の幸福は自分の不幸とセットになっている。
これを言い換えれば、自分の幸福と他人の幸福は矛盾し、競合関係にある。よって、このタイプの幸福を、競合型の幸福と呼ぶ心理学者もいる。この幸福観においては、無意識的に自と他の優劣を絶えず比較し、自分の幸福と他人の幸福は別のものである、と認識されている。
12.自分の幸福と他の幸福を区別する心の働き
競合型の幸福は、表現を変えるならば、我欲の充足による幸福であり、その追求が合法的なものであっても、客観的に見るならば、他を退けて自分が幸福になろうとする点で、自己中心的な性格を持つ欲求である。そして、仏教では、こうした欲求を煩悩といい、それを満たして得る幸福を、欲楽などという時がある。
例えば、調査研究の結果によれば、自分の給料が30万円であり、知人たちの給料が40万円である場合より、自分の給料が20万円であっても知人たちの給料が15万円の場合の方が幸福を感じるという。そもそもお金持ちの喜びとは、いくら以上のお金を持っていれば得られるという絶対的な基準はない。お金持ちとは、他人よりもお金を持っているという比較の結果である。そのため、例えば、先進国などでは、30年前と現在で、幸福を感じる人の割合が増えていないという(日本では逆に減っているという)。30年前と比べて、実際には、人々の平均所得は向上し、より豊かで便利な社会になっているが、自分と(知り合いの)他人を比較する限り、他人に優っている人と劣っている人の割合は、時代によって、変わることがないためだと思われる。
より精密に検討してみよう。たとえば、飢餓・戦争・疫病に皆が苦しむ状態を経験した人であれば、皆が文化的な生活ができる状態になったならば、その時は、他に優っていようといまいと幸福を感じるが、いったんそうなってそれが続くならば、それは当然のものとなって、幸福とは感じなくなる。そして、すでに一定の文化的な生活を得た先進国などの場合に関しては、他人との優劣の比較が、幸福・不幸を決定する要因となる。
さらに、どんなに大きな恵みであっても、皆が得ているものは、当然のものとして普段は幸福を感じず、その価値を感じるのは、それを失った時などに限られる。また、どんなに大きな不自由であっても、それを皆が持っている場合は、不幸を感じない。例えば、人は、魚のように水の中を泳げなかったり、鳥のように空を飛べなかったりしても、「そうできたらいいな」とは思うだろうが、そうできないことによって、苦しむ人はまずいない。
こうして人は絶えず、自分と、自分に近しい他人との優劣の比較や、今の自分と少し前の自分の優劣の比較によって、幸福・不幸を感じているために、無意識的に、自分の幸福と他人の幸福は別物であるとの意識が、根底にあることがわかる。
13.同じものが幸福にも不幸にもなる背景にある自我執着
こうした意識が根底にあるために、競合型の幸福においては、全く同じものが、幸福にも、その反対の不幸にもなる。すなわち、例えば、異性など、何か自分が欲する対象が自分のものになった場合は、大きな喜びを感じるが、全く同じものが、誰か他人(他の同性)のものになるならば、強い苦しみを感じる。
これは、妬みや憎しみといった感情だが、誰か他人の幸福が、直接的に自分の幸福を妨げて、自分の不幸の原因になっていると感じられる場合である。これは、特定の他人が、特定の幸福を自分から奪うと認識した場合に生じることが多いが、競合型の幸福においては、「負け組」と自分を認識する場合の苦しみのように、特定の他者ではなくても、不特定多数の他者が、自分の幸福を妨げている状況によって生じる。
そして、ここで重要なことは、全く同じものが、自分のものになれば大きな喜び、他人のものになれば強い苦しみになるということである。すなわち、喜び・苦しみの原因が、自分のものになるか他人のものになるか、ということによって決まっている。
この点に関して、仏教の心理的な分析においては、人は、自と他を区別して、自分を他人よりも強く愛する心の働き、自己への愛着、自己愛、自我執着(我執)があって、自我執着を充足した時に幸福を感じ、できない時に苦しみを感じるとする。
そのため、何か自分が好むものを見つけても、その時の初期的で単純な好感・愛着よりも、それを自分のものにした時の愛着は、ずっと大きくなる。この理由は、仏教的な見方によれば、その対象への愛着に、他よりも自己を強く愛する心=自己への愛着が加わるためだからという。
また、この初期的で単純な好感・愛着の対象も、突き詰めるならば、それ自体が好きなのではなくて、それを見たり認識したりした時に、自分自身(の感覚)に与える、何かしらの心地良さが好きなわけである。その意味では、その対象を直接好んでいるのではなく、それをきっかけに生じる、自分の中の快を好んでいるのだ。
これと同じ理由によって、自分に起きるならば、大きな幸福・不幸の原因になることでも、他人に起こった場合には、自分の場合ほどには幸福・不幸は感じないことが多い。特に、自分が直接的な利害関係を有さない見知らぬ他人などに起こる場合には、全く何も感じないことが多い。他人の不幸に関する報道に接した時も、「それが自分に起こったらどうしよう」などと思うと、苦しみが強くなる。
我々の喜び・苦しみの感情の中核には、自分と他人(の幸福)を区別して、他人よりも自分を強く愛する心の働きがある。そのために、全く同じものが、自分のものか他人のものになるかによって、喜びか苦しみという正反対の心の働きが生じたり、全く同じことが、自分に起きた場合と他人に起きた場合とでは、喜び・苦しみの程度が大きく異なったりするのである。
14.競合型の喜びと苦しみはセット:苦楽表裏
こうして、一般的な喜びとは、自と他を区別して自己を偏愛した意識が、自と他の幸福を別物と見なして、自他の優劣の比較において他に優ることによって、その自己愛を充足して得られる幸福であるということができる。そして、重要なことは、この競合型の喜びは、常に苦しみをセットとしてもたらすことになることだ。
まず、その喜びは、長続きせず、「もっと欲しい」という欲求を招く。この際限なき欲求は、必ずしも満たされず、欲しいものが得られない欲求不満や悲しみを招くことになる。また、いったん得た喜びの対象は、「それを失いたくない」という執着・とらわれを招く。それなしではいられなくなるのである。
そのために、失う不安、失うまいとするために生じるストレス、実際に失う時の苦しみなどが生じる。そして、「もっと欲しい」という欲求が増大するに従い、他との奪い合いもそれだけ強まり、他への憎しみ・妬み・不安・恐怖が増大する。いろいろな意味で他人が敵に見えることが多くなる。さらには、時とともに老いるに従って、他に優って幸福になる能力がたいていは減少し、その意味で苦しみが増え、若者をうらやむようにもなる。
15.利他による真の幸福の道
このようなさまざまな苦しみを招く競合型の幸福と替わって、仏教が説くのが、利他による幸福、共栄型の幸福である。これは、他を利することによる幸福である。競合型の幸福が、他に勝って、他に優って得る幸福であり、他と自分のいずれかのみが幸福になるものであることに対して、この共栄型の幸福は、他を幸福にして自分が幸福になる、他と共に幸福になる、他と苦楽を分かち合うことで幸福になるものである。
そして、仏教では、この利他の幸福こそが、自分のためにも真の幸福の道であり、利他の心と行為こそが、賢明な利己の行為であると説く。また、人生全体にわたって幸福を考える幸福学・老年幸福学を研究する心理学者なども、人は、人生のある段階以降は、競合型の幸福の価値観から共栄型の幸福の価値観に切り替えることで、より幸福になることができるとしている。
すなわち、自分の幸福と他者の幸福は、本当は一体のものであり、両者が別物だというのは、錯覚・無智であるということだ。競合型の幸福の際限なき追求は、その錯覚・無智があるがためになされるが、そのためにさまざまな苦しみを招くというのである。そして、人生の幸福の指針としては、際限なく求めがちとなる競合型の幸福の追求は、健やかに生きることができる程度までに留め(足るを知り)、共栄型の幸福、利他・慈悲を心がけながら生きることである。