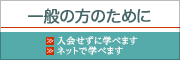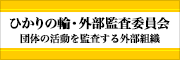②初期仏教の中核の瞑想:四念処
以下は、初期仏教の中核の瞑想である「四念処」について解説した、「2022年GWセミナー特別教本『瞑想法の総合解説 心身の健康から悟りの境地まで』」の第3章です。
-------------------------------------------------------------------------------
第3章 初期仏教の瞑想思想:四念処(しねんじょ)
1.はじめに
ここでは、釈迦牟尼自身が説いた仏教の教え(初期仏教)における瞑想の思想を紹介する。具体的な瞑想法としては、四念処・四(し)無(む)量(りょう)心(しん)の瞑想を紹介する。
この四念処は、初期仏教の最も基本的であり、最も重要な瞑想であり、釈迦牟尼の最初の説法である「四(し)諦(たい)八(はっ)正(しょう)道(どう)」の教えの中で実践すべきとされた瞑想法でもある。これは、今広がるマインドフルネス瞑想の源になった瞑想ともいうことができる(マインドフルネスは「念」の英訳である)。
ただし、こうした初期仏教における瞑想は、世俗化されたマインドフルネス瞑想に対する批判にもある通り、初期仏教全体の目的である悟りのための手段であって、仏教の悟りの思想と共に理解しなければ、その効果は十分には得られない面がある。
よって、初期仏教の思想の概略も共に紹介していくことにするが、それは何かの宗教を信じなければ、この瞑想ができないということではない。というのは、そもそも、初期仏教の思想自体が、理性による批判を退け、科学的な根拠がないにもかかわらず何かを信仰する類の宗教ではない。それは、高度な心理学・心理療法と解釈できるものであるからだ。そして、それは、現代の最新の心理学・脳科学の理論にもよく裏付けされており、その点もあわせてご紹介したい。
2.仏教・ヨーガの無我・真我の思想
仏教・ヨーガの思想の中で、最も重要な思想の1つが無我(ないし非我)というものである。無我(非我)の原語は、アナートマンであり、これはアートマン(我)の否定形である。この意味の解釈には深いものがあるが、最も基本的な意味としては、釈迦牟尼が説いたものであり、それは、「私ではない」「私のものではない」「私の本質ではない」という意味である。
そして、この思想の要点は、諸法(しょほう)無我(むが)という言葉で説かれるように、我々が認識・思考の対象とする一切のものが、無我(非我)、すなわち、私ではないということである(ここで、諸法無我の中の諸法の「法」とは、原語はダルマであり、教え・法則・法律という意味があるが、実は多義語であり、この場合の意味は(一切の思考の対象となる)事柄・存在を意味し、非常に(最大限に)広い意味を持つ言葉である)。
それは、とりもなおさず、私たちが、普通は、私自身だと思っている(私たちの)心や体も含めて、一切が私ではない、私のものではない、という主張なのである。まずは、この点を理解することが、仏教・ヨーガの思想、その悟りや解脱の思想の理解の第一歩となる。
3.仏教・ヨーガが説く、人の苦の原因・自分観・幸福観
ここには、仏教・ヨーガが説く、人のさまざまな苦しみの根本原因が深く関わってくる。というのは、仏教・ヨーガは、人が苦しむ根本的な原因は、本当は自分ではない心や体を「自分だ」と思い込んで、(自分の意識が)心や体と一体化し、苦しみを避けられない定めにある心と体と共に、(意識が)苦しむというものだからである。
よって、ヨーガの指導者の中には、映画の観客が、映画の主人公に感情移入している間に、映画の中で主人公が苦しむままに、自分も苦しんでいるという例えを使う人もいる。この場合、さらに、例えとして説明すれば、映画の主人公の名前は「私」であって、映画は三次元立体映画であって、その映画は主人公「私」の死とともに終わる、ある意味でバッドエンドの映画である。
問題は、映画の観客が、主人公「私」の体の中(おそらくは脳の中)にいる中で、自分が、主人公「私」(という一種の自動操縦のロボットのようなもの)の中にいても、「私」とは別の存在だと気づかずに、その「私」の体や思考や感情が、自分のものだと思い込んで「私」と一体化してしまい、「私」を含めた三次元立体映画を単に見ているだけにすぎない本来の自分(=純粋に観察する者)を、見失っていることである。
この無我の思想は、私たちの常識の自分観とは矛盾するために、直ちには理解できないだろうが、しかし、それは、下記のように論理的・合理的に検討することや、無我の思想を裏付ける最新の心理学の見解を学ぶことで、理解を深めることができる。
まず、論理的に考えてみると、私たちは、自分では、自分の目を見ることはできない(見ることができるとしたら、鏡に映った自分の目に対する可視光線の反射までである)。これを言い換えれば、自分が見ているもの、すなわち、見ている対象は、自分に見られている側であるから、見る側の自分ではない。すなわち、経験の主体と客体という言葉を使うならば、自分は、見る側の主体であり、自分が見ている対象は、見られる側の客体であって、これは別のものであるということになる。
同じように、自分(の意識)は、自分の心や体を経験するが、それだからこそ、心や体は、自分に経験される側であって、それを経験する自分ではないということになる。よって、人が経験するすべての対象は、経験の対象=客体であって、経験の主体ではないのだ。これが諸法無我という思想である。
ここで、仏教と異なって、ヨーガは、この経験の主体の中の主体、精神の中の精神、純粋に経験・観察するだけの意識というものを「真我」(アートマン)などと呼ぶ。経典では純粋観照者といわれ、真我は永久不変の平安(の光明)などといわれる。また、真我は見る側だから、真我を見ることはできないとも説かれる。真我は、(何かの存在というよりは)観る能力そのものとも表現されることがある。
4.最新の心理学・科学が裏付ける仏教・ヨーガの自分観
そして、以上の常識外れの仏教・ヨーガの「自分観」は、驚くべきことに、最新の心理学によって裏付けられつつある。その詳細は、「ひかりの輪2019年~2020年年末年始セミナー特別教本『最新科学が裏付ける仏教・ヨーガの悟りの思想』」に解説したが(本章の末尾の参考資料参照)、その要点を列挙すると以下のとおりである。
第一に、まず総論として、認知心理学と脳科学は、最近数十年間に非常に目覚ましく発展し、下條信輔氏(カリフォルニア工科大学教授)は、認知心理学が発見した人間の意識・心の働き・脳などの実際の在り方は、我々の常識と大きく乖離(かいり)したものになり、認知心理学者を、あたかも現代のガリレオのような立場に置きかねず、今後は、最新の科学的な知見と常識の矛盾の対立をどのように乗り越えるかの智恵が必要となったという趣旨のことを述べている。
第二に、認知行動療法の中の「マインドフルネス認知療法」の臨床の知見では、患者が「自分と(自分の)思考や感情が別のものだ」という感覚に至ると、苦しみが和らぐということが確認されている。これを「思考と感情の脱同一化」といい、自分の思考や感情を見ている自分の意識を、「超越的自我」ないしは「メタ認知」などと呼んでいるが、仏教やヨーガが説く「心の働きは真実の私ではない」という思想とよく通じている。
第三に、最新の認知心理学は、さまざまな意味で、心の働きは自分ではないことを明らかにしつつある。デイヴィッド・イーグルマン准教授(スタンフォード大学精神医学科)は、「意識は傍観者である」とし、さまざまな心の働きは、無意識的な脳活動が司っており、「意識は遠いはずれから脳の活動を傍観しているにすぎず」「私たちの行動をコントロールしているのは私たちの意識ではない」とし、さらに、にもかかわらず意識は、無意識の脳活動が形成する心の働きを、自分がしたことのように錯覚を起こすと述べている。
前野隆司(たかし)教授(慶応大学システムデザイン・マネジメント研究科)も同じように、知覚・感情・意志といった心の働きは、無意識の脳活動が形成しており、意識は、その結果を単に受動的に経験しているだけであるが、意識は、それを「自分のものである」と錯覚しているという。
最後に、下條信輔教授(カリフォルニア工科大学)は、「人は自分でわかり言葉にできる心の働きよりもむしろ、自分で気づかない無意識的な心の働きに強く依存している」とし、「最前線の人間科学は、人間の自由意志の尊厳とそれにのっとった社会の諸々の約束事を根底から覆しかねない」とまで述べている。
こうして、「意識」と、その意識が経験しているさまざまな「心の働き」と「脳」の活動の実際の関係は、私たちの日常の感覚・常識がとらえている在り方と大きく異なり、仏教やヨーガの心理学が2500年頃前から説いてきた在り方に非常に近いことがわかってきたのである。
5.悟りの瞑想「四念処」とは
四(し)念処(ねんじょ)とは、仏教における悟りのための4種の観想法の総称であり、四(し)念(ねん)処(じょ)観(かん)、四(し)念(ねん)住(じゅう)ともいう。これは、釈迦の初期仏教の時代から、悟りに至るための最も中心的かつ最重要な観想法である。また、仏教の主な瞑想である「止(し)観(かん)」の中では、観(ヴィパッサナー)の中核を成す観想法であるともいわれる。この四念処の瞑想は、パーリ語経典の『大(だい)般(はつ)涅(ね)槃(はん)経(ぎょう)』で繰り返し言及され、『大(だい)念(ねん)処(じょ)経(きょう)』(大念住経、長部第22経)、『念(ねん)処(じょ)経(きょう)』(四念処経、中部第10経)で詳しく説かれている。
まず、 四つの念処とは、①身(しん)念(ねん)処(じょ)、 ②受(じゅ)念(ねん)処(じょ)、③心(しん)念(ねん)処(じょ)、④法(ほう)念(ねん)処(じょ)である。ここで、「身」とは身体のことで、「受」とは感覚のことで(感覚器官ではなく感覚自体)、「法」は、思考の対象となるあらゆる事物・事柄のことである(物理的な存在ではなく観念的な存在も含む)。
よって、四念処とは、身体・感覚・心・さまざまな事物に関する瞑想ということになるが、具体的にどういう瞑想をするかというと、主に、以下の2つに分かれるとも解釈することができるが、その両者は本質的に一体である。
第一は、その四つを念(サティ)を持って見る(観る)ことである。この「念」とは何かを説明するのは難しいが、「気づき」と訳されることが多く、これを英訳したものが、マインドフルネスである。マインドフルネス瞑想では、マインドフルネスとは、今現在にある対象に対して、良し悪し・好き嫌いの判断・感情を持たずに、冷静に客観的に注意をする(気づいている)状態である。
そして、これを身体・感覚・心・さまざまな事物に対して行うということは、普通は自分の一部と認識されている身体・感覚・心などに対して、冷静に客観視する意味合いがある。これに対して、普段の我々(の意識)は、自分の身体・感覚・心と完全に一体化しており、身体・感覚・心は無意識的・自動的に動いている状態であって、それらに意図して意識を向けて客観視するといったことは、ほとんどない。
第二に、そのように客観視する中で、①身体の不浄を観ずる(観想する)、②一切の感覚は苦であると観ずる、③心は無常であると観ずる、④あらゆる事物は無我である(私ではなく、私のものではなく、私の本質ではない)ことを観ずるのである。
これは明らかに、普段は自分だと思って、自分と一体化している身体・感覚・心などを、不浄で苦しみで無常であると観ることによって、それらを含めて一切は私ではない(無我・非我)という認識を深め、私・私のものに対するとらわれを取り除こうとするものである。
なお、不浄・苦・無常・無我とは、仏陀の四(し)顛倒(てんどう)という教えに通じるものである。これは、四つの道理に背く見解という意味であり、具体的には、仏の智恵(智慧)から見れば、無常・苦・無我・不浄であるこの世を、凡夫(普通の人)が常・楽・我・浄と思い誤ること、錯覚することを意味する教えである(逆に、悟りの世界が真の常・楽・我・浄である)。
6.四念処の具体的な観想法
さて、四念処の具体的な観想法・瞑想法について述べる。
第一に、「身体が不浄である」と観る瞑想とは、さまざまな形式があるが、一般には、自身や他者の生きた身体が腐敗・白骨化する様を観想し、そこへの執着を断つことなどと説かれる。これを含めて、①身体が老い、病み、死んで醜く変化する無常性を観想すること、②身体の内部の五臓六腑や糞尿などの汚物などの不浄性を観想することなど、多くの瞑想法が存在する。
また、私の考えでは、③身体が、他の生き物を殺生する結果をもたらすさまざまな食べ物なしには維持できない本質(宿業・宿命の悪業)を持つことを、考えることもよいのではないかと思う。そして、この精神は、仏教の不(ふ)邪(じゃ)淫(いん)・不淫の戒律(不倫の禁止や性行為を原則的に断つ法則)の実践に適するものでもある。
次に、「感覚が苦しみである」との瞑想について述べる。これは、感覚は絶えず苦痛を与えるという意味ではない。そもそも、この苦しみと漢訳されたサンスクリット原語であるドゥッカは多義語であり、苦痛という意味もあるが、「不安定な、不満足な、不完全な」といった意味もあるとされる。
そして、感覚には、快と不快があるが、感覚的な快楽も、長期的・総合的には、人にさまざまな苦しみをもたらす性質がある。感覚的な快楽は、多かれ少なかれ刹那的なものであるが、それに対するとらわれを人にもたらす。そして、とらわれた人は、それを際限なく求めて、一種の中毒状態に陥ることが多い。
しかし、際限なく求めるならば、四苦八苦の教えで述べたように、得られない不安や苦しみ、得て執着したものを失う不安や苦しみ、皆が求め奪い合って憎み合う苦しみといった、さまざまな苦しみが生じてしまう。こうして、感覚は、目先の快楽で人を欺いて、さまざまな苦しみをもたらす性質がある。長期的・総合的に観るならば、苦しみに至るものを喜びと錯覚させる。これは、四顛倒の教えが説く、苦を楽と錯覚する場合でもある。
逆に、「良薬は口に苦(にが)し」というように、長期的には良いものが、刹那的な感覚では、悪く感じられることが多い。そもそも、一般に、人が何かの努力をするということは、将来の幸福・快のために、現在の労苦・不快を耐えることである。
以上の感覚の性質をまとめると、感覚によって、人は(長期的には)悪いものを好み、(長期的には)良いものを嫌うことが多く、感覚は人を本当の幸福に導かないから、感覚を苦しみと見ることができる。最後に加えれば、この感覚の苦しみも、身体の苦しみとともに、加齢とともに増大していく。
次に、「心は無常である」とは、瞑想によって制御せず、我欲にとらわれた心は絶えまなく動いている。これは、すでに先ほど述べたとおりである。心が何かを喜びとすると、その対象にとらわれて際限なく求めるが、それは時とともにさまざまな苦しみの原因となる。心に生じた我欲を満たした喜びは、同時に将来の苦しみの原因でもあるために、時とともに苦しみに変わっていくのである。
また、際限ない欲望のために、現在に何かしらの不満を持って、現在に満足して満ち足りない人の心は、たいてい、現在・過去・未来を絶えずグルグルと巡るようにさまよっている。
例を挙げるならば、今日朝起きたら、普段から嫌がっている職場での人間関係にあらためて嫌悪や心配が生じ、その問題に関して、「自分が悪い」と自己を嫌悪したり、逆に「相手が悪い」と不満・怒りを持ったりする。さらに、未来に問題がなくなることを期待するが、そうならないという不安も出てくる。
そうしているうちに、こうして不満を感じる現在の状況をもたらした過去について、後悔や恨みが出てくる。「そもそもなぜ自分がこの職場を選んだのか」、「なぜまだ辞めることができないのか」など。そして、「いや悪いのは自分ではなく、他人である」という恨みも出てくる。
自分でも、日常の自分の心の働きをチェックしてみれば、心には絶えず色々な思いが駆け巡って、本当の意味で、安らいだ平安の時はないことに気づくかもしれない。
7.四法印という教え:無常・無我・苦・涅槃
仏陀の教えは、心だけが無常なのではなく、身体や感覚を含めた一切が無常であり、感覚だけが苦(ドゥッカ)なのではなく、身体や心を含めた一切が(過剰にとらわれれば)苦であり、身体・感覚・心を含めた一切が、無我(私・私のものではない)であると説く。この無常・無我・苦は、仏教では三相(さんそう)といわれ、仏教の基本的な世界観・哲学として最も重要な教えの一つである。
そして、これを含めた仏教の重要な教えをまとめたものが四(し)法(ほう)印(いん)である。具体的には、以下のとおりである。
①諸行(しょぎょう)無常(むじょう):すべては移り変わり無常である。
②諸法(しょほう)無我(むが):すべての事物は私・私のものではない。
③一切(いっさい)皆(かい)苦(く)(一切(いっさい)行(ぎょう)苦(く)):すべての存在は(過剰にとらわれれば)苦(ドゥッカ)である。
④涅槃(ねはん)寂静(じゃくじょう):涅槃(ニルヴァーナ=悟りの境地)は、静かで平安である。
なお、四法印とは、四つの仏教の教えの象徴(「印」のサンスクリット原語は「ムドラー」であり「象徴」の意)という意味で、四つの仏教を代表する教えという意味である。
8.五蘊無我の瞑想:四念処と似た自我執着を超える瞑想
四念処と同じく、無我や無常の瞑想によって、自我執着を乗り越える瞑想として五(ご)蘊(うん)無(む)我(が)の瞑想がある。
まず五蘊とは何かというと、人間の肉体と精神を、五つの集まりに分類して示したもので、その五つとは、①色(しき)蘊(うん)、②受(じゅ)蘊(うん)、③想(そう)蘊(うん)、④行(ぎょう)蘊(うん)、⑤識(しき)蘊(うん)の総称である。なお、ここでの「蘊」とは「集まり」「同類のものの集積」を意味する。そして、「色」は物質的な存在を示し、「受」「想」「行」「識」は精神作用を示すが、具体的には以下のとおりである。
①色蘊:色や形のあるもの。認識の対象となる物質的存在の総称。
②受蘊:感受作用・感覚(感覚器官ではない)。肉体的・生理的な感覚。
感覚器官が、感覚器官の対象と接触することで生じる苦・楽・不苦不楽などの印象。
③想蘊:表象作用。事物の形象を心の中に思い浮かべること(イメージ)。
④行蘊:意志作用。意志形成力。心がある方向に働くこと。
⑤識蘊:認識作用。何かの対象を他と区別・識別して知ること。
そして、仏陀は、四念処と同様に、五蘊も無常であり、無我であるとして、執着しないことを説いた。なお、五蘊の最初が色蘊で、最後が識蘊となるのは、粗雑なものから精細なものへの順序、悪に染められた心を起因として諸法が生じる次第を逆にさかのぼる順序などに従うものとされる。
9.瞑想・禅定による悟りの体得の過程
これまで瞑想の内容を述べてきたが、仏教の瞑想とは、こうした教えの知識を頭で吸収することではなく、実際に精神を集中させ、こうした瞑想を繰り返し修習することである。そして、その過程において、主に以下のような体験によって、心身が無我という悟りの境地が達成されていくと思われる。
まず、普段は身体・感覚・心と一体化している意識が、身体・感覚・心を客観視する瞑想を行って、それに成功すると、瞑想者は、徐々に、身体・感覚・心といった(偽りの)自分を客観的に見ている(本当の)自分の視点を体得するようになる(心理学的にいう超自我・メタ認知)。
次に、思考や感情に没入せずに、それを客観的に観るということは、すなわちその思考や感情を、自分が没入してはならない雑念として観ることであるが、そのように訓練している間に、雑念の思考や感情が静まった意識状態を体験する。それは、思考や感情・心の働きがない意識状態を体験することであるから、これもまた思考や感情は自分ではないという認識を深めることを助ける。
さらに、瞑想が深まる中で、思考や感情に限らず、五感や身体の感覚も薄れていく状態に入る。五感を通した外の世界に意識が向かなくなることを、ヨーガでは制感(プラティヤーハーラ)という。こうして五感や身体の感覚が薄れ、意識だけになった意識状態になれば、身体も自分ではないという認識を深めることを助ける。
10.仏教が説く瞑想・禅定の段階:四禅定・四無色禅定
仏教では、四(し)禅(ぜん)ないし四(し)禅(ぜん)定(じょう)という禅定・瞑想の段階を説いている。これらの個々の禅定は、仏教が興(おこ)る以前の古代インドで知られていたものを、釈迦牟尼が体系化し、取り入れたものであるとされる。しかし、その中で、悟りの境地である想受滅(そうじゅめつ)は、仏陀こそが初めて到達し得た境地だったとされる。
なお、この四つの禅定の境地は、そのまま仏教が説く「色界」という高い世界の住人の状態を表しており、この色界とは、欲望はないが、身体への執着が残っている世界だといわれている。
① 初禅 :尋(じん)(熟考)や伺(し)(吟味)を伴いつつ、諸々の欲や不善を離れることによる喜・楽と共にある状態
②第二禅:尋(熟考)・伺(吟味)が止み、思考や感情が静まり、清浄による喜・楽と共にある状態
③第三禅:喜を捨て、楽と共にある状態
④第四禅:楽も止み、不苦不楽の状態(一切の「受」が捨てられた状態)
この上に、さらに無(む)色(しき)界(かい)の状態に相当する禅定と呼ばれる4段階がある(四(し)無(む)色(しき)定(じょう)ともいう)。無色界とは、色界よりもさらに上の世界であり、身体・物質がなく、意識・想念・心の働き・精神作用によってのみ構成される世界である。
⑤空(くう)無(む)辺(へん)処(しょ):無限の空間(虚空)を感じる境地
⑥識(しき)無(む)辺(へん)処(しょ):無限の意識を感じる境地
⑦無(む)所(しょ)有(う)処(しょ):何もないと感じる境地
⑧非(ひ)想(そう)非(ひ)非(ひ)想(そう)処(じょ):想いがあるのでも、ないのでもないという境地
11.瞑想(禅定)と不可分の学習実践:三学:戒律・禅定・智慧
仏教では、戒(戒律)・定(じょう)(禅定)・慧(え)(智慧)を三学と呼び、仏道修行者が実践すべき三つの重要な修行課題としている。そして、瞑想・禅定は、戒律を守ることと、智慧を深める修行と一体になっている。
戒律は、日常生活を含めて、心・言葉・行動を律するものである。これは瞑想の成功と一体不可分である。瞑想において、(偽りの)自分にとらわれないように瞑想したとしても、日常生活で戒律を守らず、自己中心的な我欲の充足を求めて他を害するならば、瞑想とは逆向きの精神的な影響を形成してしまい、いくら瞑想しても、無我の悟りなどの目的を果たすことはできない。
これを言い換えれば、戒律の実践は、日常生活における瞑想ということもできる。前に述べたように、そもそも瞑想には形はなく、心の安定と集中をもたらすために繰り返し修習されることである。戒律を守ることで、我欲が静まった穏やかな心の状態が形成され、瞑想で、自我執着を乗り越える準備ができる。戒律と瞑想は一体不可分である。
次に、智慧の修行と瞑想も一体不可分である。ただし、智慧の修行には三つほどの段階があると考えられる。
まず、①教えを学ぶ教学の段階である。これがなければ、瞑想をしようにも、どのような目的・意味合いで、どのような瞑想をしたらよいかがわからない。よって、瞑想の前に教学は必ず必要である。
その次に、②教えの正しさを論理的に理解する思索の段階がある。これによって論理的に教えの正しさを確信する。これは相当に高度な段階とされるが、依然として、論理的な思考を媒介して教えを理解している段階である。
最後に、③教えの正しさを瞑想で直観する段階が来る。この③の段階では、禅定と智慧の修行は、一体不可分となっている。
こうして、禅定(瞑想)と戒律と智慧の三つの修行は、そのいずれもが、その他の二つに対して、互いに互いを高め合う関係になっており、一体不可分ということができる。
12.止と観(禅定と智慧)の瞑想
仏教には、瞑想に関連して、止(し)観(かん)という重要な教えがある。これは、瞑想とは何かに限らず、瞑想の実際のやり方・進み方にも関係するものなので、ぜひ理解しておきたい。
仏教では、止観を瞑想の主なものとし、瞑想を「止」と「観」の二つに大別する。まず、止(サマタ)とは、心を静めて静止すること(さらには、それによって意識が真理に住すること)。次に、観(ヴィパッサナー)とは、物事を真理に即して正しく観ることである。
そして、この二つは相互依存の関係、相互に循環する関係になっており、止による不動の心が、観の正しい観察をもたらし、観の正しい観察が、止の心の不動をさらに深める。なお、戒律・禅定・智慧の三学に照らし合わせるならば、止は禅定に相当し、観は智慧に相当する。
仏教のヨーガ行は、止と観が同時に行われる止観である。止だけでなく観を重視するところに、仏教の瞑想法の特徴がある。止観は、しばしば二つの車輪に例えられ、不離の関係にある。この二つに瞑想が大別されるというと誤解があるが、止の瞑想と観の瞑想は、連続した一体のものということができる。
仏教の歴史的にいえば、止観という言葉を重視したのが、天台宗開祖の智顗(ちぎ)だとされ、止観が中国仏教においてヨーガの瞑想を象徴する重要な用語、東アジア仏教を代表する瞑想法となった。なお、他に、東アジアの仏教で特に瞑想における重要な言葉となったのが禅であるが、これは禅宗が隆盛したためである。また、マインドフルネス瞑想は、一般に、観の瞑想に分類される。
止の瞑想の中には、一点に集中して心を静めるものがある。例えば、前章で紹介した入(にゅう)出(しゅつ)息(そく)念(ねん)である。一方、四念処は、四念処観といわれるように、観の瞑想に含まれる(身体・感覚・心・事物をありのままに観る瞑想だからであろう)。また、上座部仏教では、万人万物・すべての衆生を愛し利する四(し)無量(むりょう)心(しん)(仏陀の四つの広大無辺な利他の心)を培う瞑想が、心を静める止の瞑想に分類されている。
13.悟りの境地が解消する、人のさまざまな苦しみ「四苦八苦」
次に、四念処・五蘊無我などの瞑想によって、心身が自分ではないなどを悟ることで、いかにしてさまざまな苦しみが解消されて、幸福になると説くのかについて述べたいと思う。ただし、その前に、人間のさまざまな苦しみを「四苦八苦」という言葉で分類して説く仏教の教えを紹介したい。それによって、悟りの境地が人の苦しみを解消する力があるのかが、わかりやすくなるからである。
四苦八苦の中で説かれている苦しみとは、まず、①求めて得られない苦しみ(求(ぐ)不(ふ)得(とく)苦(く))、②愛着した者と別れる苦しみ(愛(あい)別(べつ)離(り)苦(く))を含め、得て執着した何かを失う苦しみ、③憎しみの対象と出会う苦しみ(怨憎(おんぞう)会苦(えく))を含め、皆が求めて奪い合って憎しみ合う苦しみ、④五蘊にとらわれることによる苦しみ(五(ご)取(しゅ)蘊(うん)苦(く))である。
さらには、⑤生(しょう)、⑥老、⑦病、⑧死の苦しみがある。生(誕生)は、一般に喜びともされるが、実際には、現代でも、出産は母子共に大変な危険を伴う出来事であり、重い障害や短命に終わる運命の誕生もある。そして、老・病・死の苦しみについては、説明は不要だろう。
14.死の苦しみを乗り越える無我の悟り
次に、悟りが、いかに四苦八苦を解消していくかについて述べる。まず、人の最大の苦しみともいえる死に関して述べる。
まず、普通の人のように、自分を体だと思い込み、体と一体になるほど執着していれば、死という体の消滅は、自分の消滅になり、苦しみにほかならない。人が死を恐れるのは、死ぬ際に、病気その他で身体的に苦痛を感じるということもあるが、「自分というものが消滅してしまう」という、精神的な苦しみであるという。
ところが、悟った者は、自分(の意識)と体が別のものだと認識しているから、たとえて言うならば、体は自分の衣服のようなもので、死は一つの衣服を脱ぐこと(衣服の方から抜け落ちること)にすぎないという感覚となる。そして、死んで生まれ変わることは、衣服を着替えることと例えられる。
曹洞宗の開祖である道元は、自分の中国人の師匠が「身(しん)心(じん)脱落」と叫んだ時に、悟った(大悟した)といわれるが、これも同じ境地を意味していると思われる。
さらに言えば、意識にとっては、そもそも体は無常であり、老化・病といった苦しみを避けられない煩わしいものであるが、体は自分ではないと悟った意識からするならば、死とは、逆に言えば、その煩わしい身体から解放される時であり、その意味で喜びと解釈することもできる。そして、仏教では、釈迦牟尼が到達した悟りの境地を涅槃というが、完全な悟りの境地は、釈迦牟尼の身体が滅した入滅の時だという思想があり、それを大(だい)般(はつ)涅(ね)槃(はん)などと呼ぶ。
なお、ひかりの輪では、仏教の六道輪廻・生まれ変わりの思想に関しては、科学的に証明も反証もできないという客観的な立場から、各人にそれを信じる自由も、信じない自由もあるという客観的な立場であるが、仏教の思想を紹介すれば以下の通りである。
すなわち、悟らずに死んだ者は、死んだ後に再び生まれ変わり(六道輪廻)、生まれ変わった先の世界で再びいろいろと苦しむことを延々と続けるが、悟った者が死んだ場合には、生まれ変わりを永久に止める(輪廻から解脱する)ことができ、一切の苦しみから解放されるという思想である。
さらに、悟らなければ、自分の望む来世・転生を選択することはできないが、悟った者は、自分が望むならば、転生を止めずに、自分が望む転生を自在に選択することができるとも説かれる。これについては、また別の機会に述べる。
15.老いをもたらすさまざまな苦しみ
そして、老化について考えると、悟りを得なければ、若い時よりも、老いた時の方が不幸になる。具体的に言えば、求めても得られないことが多くなるし、いろいろなものを失うことが多くなるし、奪い負けることも多くなる。実際に、多くの人は、「若い人はいいよね」とうらやましがる。
統計的に見ても、自殺・鬱病は老人が一番多い。この背景としては、高齢期のさまざまな喪失体験があると推測される。仕事は退職し、自分の社会的なアイデンティティー・価値はなくなり、仕事上の人間関係もなくなり、家庭を見ても、子供は独立して、配偶者に先立たれることもある(近年は晩年離婚も増えている)。さらに、介護を受けるために介護施設に入居する必要があれば、長年親しんだ自宅さえも失うことになる。そして、自分自身の体が、以前の力・機能を失っていく。
さらに、現代の社会には孤独の問題が急増している。長寿となったが、小家族化、結婚・出産の減少、少子高齢化などで、単身者人口が3割に達し、社会的な交際がない孤立した高齢者が増えている。そして、孤独・寂しさこそ、人間の最大の苦しみの一つともいわれる。
その中で、最大の問題の一つが、この高齢期に襲うさまざまな喪失体験が、高齢者に広がる鬱病・認知症・感情暴走といった精神的な問題の一因となることである。現在90~95歳以上の人の8割は認知症であるというデータもある。
こうして、老化によって、多くの場合、自分自身の精神が病んで、最後には、理性が働かない「子供返り」ともいうべき状況に陥る。幸福・不幸を感じるのは、やはり人の心であるから、その心が病んで退化することは、ある意味では、高齢期の人間の最大の苦しみかもしれない。
16.悟りが乗り越える老いの苦しみ
しかし、悟った者は、高齢化したとしても、そもそもが、一切は自分、自分のものではないと認識しているため、普通の高齢者を襲うさまざまな喪失体験からは影響を受けない。それは、もともとが、自分や自分のものではなく、自分が所有しているものではないとして、精神的にとらわれていないために、精神的なショックを受けないのである。
むしろ、身体が自分ではないという無我の悟りを求める仏道修行者にとっては、実際に老いて病み、死が近づいてくることは、その悟りを促す愛の鞭として、悟りを得んとする意欲を強める意味で、「仏の御使い」などとさえ表現され、苦の裏側にある喜びと解釈される。
こうして、仏道修行者は、老いにともなう喪失感などによる精神的ショック等で精神を病んで子供返りする普通の人とは正反対に、老いてますます悟りの境地が深まり、精神的に安定し解放される。仏教開祖の釈迦牟尼が、当時としては80歳の超高齢まで生き、死の間際まで弟子に説法したように、老熟の智恵(智慧)に到達するのである。
この高齢期における生きる意欲の維持・増大は、老化を抑制する上で非常に重要である。というのは、最近の脳科学は、①老化の第一の要因が(新しいことに挑戦することを含めた自分の脳や体を鍛錬する)意欲の低下であり(老いは気から)、②特定の立場・責任のために高齢でも(労働等の)意欲が高い人は、(認知症などの)老化が抑制されることを突き止めている。
この点に関して、仏教僧は、①引退・定年がある世俗の人と異なって、老いてこそ価値が認められる職業であることや、②先ほど述べたように、老いて死ぬ中でこそ悟りを求める意欲が深まることなどから、高齢期にもますます高くなる意欲が、精神的な老化を抑制している。
なお、仏道修行者は一般に長寿であることが知られている。これは、上記の高齢期の生きる意欲に加え、健康的な食生活、歩行や寺の掃除といった健康に良い運動が多いこと、仏道修行の精神的な訓練や経済生活が安定していることによるストレスの少なさなどが原因だといわれている。
実際に、職業別の寿命ランキングでは、常にトップであり、奈良時代前後から近代医療技術が普及する前の明治時代までの期間に、寿命の記録が残っている数千人の公家・大名・仏教僧を比較したところ、公家・大名らの平均寿命が、平均50歳前後であったのに対して、仏教僧は、なんと70歳であったことが大学教授の研究で明らかになっている。
17.心理学者が発見した「老年的超越」現象が仏教の思想を裏付ける
そして、近年、長寿の先進国社会の一部で、社会学者や心理学者が発見した「老年的超越」という現象が、この仏教の老いの苦しみの超越の思想を裏付けている。老年的超越とは、90歳・100歳の超高齢者の一部が、あたかも仏教の悟りの境地を得たかのような主観的な幸福感を感じているという事実である。それは、日本では依然として人口の数%程度とも思われるが、その人たちは、「今が一番幸せです」などと言い、老いは苦しみを増すという常識に反して、人生で最高の幸福を(少なくとも精神的に主観的には)感じている。
もちろん、体は若い時よりも衰えて、あちこち不具合があるのだが、「本当に健康に恵まれて何も悪い所はありません」などと答えると言う。実際に疾患があるのに、その痛みを感じていないかのように思われるケースも報告されている。死の恐怖もなく、逆に、今日朝目覚めて、また一日生きられることに感謝の思いがあるという。息子・孫は遠く離れて一人で住んでいても、遠くから彼らを思う(無償の)愛が深く、孤独・寂しさを感じていない。そして、宗教的には、宇宙意識といわれるが、宇宙全体とつながったかのような意識状態を経験する人や、いわゆる仏教や道教の思想である「無為自然」「あるがまま」を強調する人もいるという。
そして、この老年的超越を得た人々の特徴を見ると、順風満帆の人生ではなく、逆に、病気や別離を含めたさまざまな人生の困難を経ながら、前向きに生き抜いてきた人が多いという。彼らは、「そうした苦しみを含めて、すべては今の状態に至るために必要なものだった」と感じているという。
これらをまとめると、老年的な超越を得た人たちは、仏教の教義・思想に基づいて修行はしていないが(一部にはしている人もいるかもしれないが)、そのさまざまな人生の苦しみの経験の中から、自己にとらわれないことによって苦しみを乗り越えるという、仏教の悟りの思想と本質的に同じものを体得したのではないかと思われる。
彼らには、人生の苦しみの経験自体が、仏教の経典の役割を果たしたのであろう。実際に、仏陀の教えの中には、「苦しみによって仏法に信を持つ」とか、苦しみが(仏法の悟りに導く)仏の御使いであるといった教えがあるが、まさにそれを裏付けるものではないだろうか。
18.超高齢期に心理的発達を遂げる人と子供返りする人の二極化
こうした老年的超越の現象を踏まえて、高齢者心理学者は、人間の脳を含めた心身の機能には、子供が大人になる思春期の「第一の心理的な発達」に加えて、高齢期に「第二の心理的な発達」を遂げることが(潜在的に)可能ではないかという考えに至っている。一方、現在、大半の人たちは、超高齢期には、認知症などによって、逆に子供返りしてしまう。
こうして、一般的な主流の生き方では、人生は、若いときが一番幸福で、加齢とともに徐々に不幸になるものであり、いわゆる「尻すぼみ」である。老人は「若い人はいいね」と言い、若い時に目いっぱい楽しく生きて、老いたら生き恥を晒さずに苦しまずに「ピンコロ」で死にたいと思う。
しかし、実際には、現代は、医療技術の進展などもあって、身体的になかなか死ぬことができない長寿の時代となった。その一方で、老化が、前に述べたような高齢期のさまざまな喪失体験や、心身の疾患をもたらすことは変わりがなく、特に精神的な疾患・問題が、近年は目立ってきている。こうして、精神面・身体面・経済面などのさまざまな意味での不安を抱えた「長くて不幸な老後」が待っており、「寿命は長くなったが、本当に幸福になったのか」という声も聞かれる。
一方、無我の悟りを求める仏教的な生き方は、一般的な老後と比較すると、健康長寿なだけでなく、生き抜く意欲が高く、「今が一番幸せです」という老年的超越の老人の言葉に示される通り、老いてますます幸福感と智恵(智慧)が深まっていき、周囲の評価も高まる。そして最後の、死という身体の消滅に際して、それを苦しみの止滅=幸福の完成の時とさえ解釈するものとなる。これはまさに、尻上がりの人生であり、老い死ぬ中で、人生のクライマックスを迎えるものとなる。
19.加齢とともに不幸になるのは当たり前ではない
なお、一般の人にとっては、若い時の方が幸せで、加齢とともに、いろいろ不幸が増すことは、不可避の必然的なことであり、当たり前のことと受け止められているが、仏陀の教えから見ると、不可避の必然的なものではなく、間違った生き方の結果であって、その意味で、自業自得と解釈されるものである。
これをまとめて言えば、①加齢とともに苦しみが増大していく定めにあるのは、心身であって、私たち自身ではないのに、②本来は自分ではない心身というものを、自分と錯覚する無智・愚かさのために、③あたかも心身という友人と心中するかのように共に苦しむ、ということである。
そして、自分の中にある愚かさによって苦しむという意味で、自業自得と解釈される。しかし、自業自得であるため、それを逆に言うなら、自分の努力で、自分の中の問題(愚かさ)を解消するならば、苦しみは解消することになる。その意味で、自業自得とは、自律的で前向きな価値観・人生観・幸福観でもあるのだ。
これに関連して、仏教では、仏陀の最初の説法である「四諦(したい)八正道」の四諦の教えなどで、「(人の人生の)苦しみの原因は煩悩である」と説かれている。それに付随する十二縁起の教えなどで、その煩悩とは、自分ではないものを自分と錯覚することを含めた「愚かさ」(無智・無明)を根本的な原因(=根本煩悩)として生じる、間違ったとらわれ(執着・取(しゅ)著(じゃく))のことであると説かれている。
そして、前に述べたように、仏教の修行(例えば八正道)によって、その愚かさ(無智・無明)を取り除き、それによる間違ったとらわれ=煩悩を取り除くならば、苦しみの原因が解消し、苦しみが滅すると説くものである。
こうして、仏陀の教えは、加齢とともに不幸になるのは、当たり前ではなく、間違った考えによる間違った生き方の結果であり、正しい考え方による正しい生き方(仏道修行)を行うならば、加齢とともに逆に幸福になるのが人生であるという。
20.不幸の道を幸福の道と錯覚する無智が苦しみの原因
仏典では、すべての人は、「幸福になりたい」と思っているが、なぜこんなにも多くの人が苦しんでいるかというと、幸福になりたい気持ちが足りないのではなく、幸福を求める手段が、逆立ちをしたかのように、実際には、不幸・苦しみに至る手段となっているからであり、実際には不幸に至る道を、幸福の道だと錯覚する愚かさ・無智が、不幸・苦しみ(の原因である煩悩)の根本原因であるというものなのである。
言い換えれば、若者よりも、より長く、幸福になろうと努力してきたのが老人であるから、本来は、その努力の報いとして、若者よりも老人の方が幸福であるべきなのだ。すなわち、加齢とともに不幸が増えることが当たり前なのではなく、本来は、正しい努力をしさえすれば、加齢とともに幸福が増えてしかるべきであり、より長く努力した老人の方が、努力がまだ短い若者よりも、幸福になってしかるべきであり、この方が当たり前であるべきなのである。
しかし、多くの人は、幸福になろうとしてなす努力が、大変嘆かわしいことに、実際には不幸に至る努力であるために、結果として、客観的に見れば、非常に理不尽な、非常に残念なことが起こっているのである。それは、例えるならば、回転する台車の中のリスが、自分としては一生懸命に走っているのに、実際には、果てしなく同じ場所を回転するだけで、一向に(幸福に向かって)前に進むことがなく、最後は疲れ果ててしまうことと同じである(この空しい苦しみの循環のことを仏教では六道輪廻と表現したということもできるかもしれない)。
21.さまざまな苦しみを解消する悟りの恩恵
さて、これまでに老・病・死の苦しみを中心に述べてきたが、仏教の悟りがもたらす苦しみの解消は、中高齢期の苦しみばかりでは当然ない。前に述べた四苦八苦の苦しみは、生まれ次第、直ちに生じるものである。若者であっても、特に現代の競争社会においては、①求めても得られないという不安や、実際に得られない時の苦しみ、②得たものを失う不安や、失った苦しみ、③皆で求め合うがゆえに奪い合って憎み合うという不安・苦しみをたびたび感じている。
そして、21世紀の現代社会は、ますます激しくなる競争に加えて、未だに収束しない新型コロナや、ロシアのウクライナ侵攻を契機に、中国や北朝鮮の将来の動向とも絡んで、日本も巻き込んだ世界規模の安全保障問題の激化(第三次世界大戦のリスクの高まり)など不透明感が強まっている。
その中で、個々の人々は、競争社会、ストレス社会、自己愛型社会といわれる中で、負け組や勝ち組や貧富を含めた格差、コンプレックスの苦悩、鬱病などの精神疾患の増大、ストレスから来る慢性疾患の増大、高止まりする自殺の問題、単身者の孤独の苦しみと自殺者数を上回る孤独死の増大、高齢者の心身の不健康の問題など、さまざまな心身の苦しみ、人間関係の苦しみを抱えている。
これらの不安・不満を含めた個々人の心理的な問題は、日常の人間関係の摩擦・苦しみにとどまらず、昨今目立つ無差別殺人などの特異な犯罪の増大や、日米を含めた陰謀論の流行の原因ともなって、社会を分断している。さらにはウクライナなどでの戦争にも利用されて、戦争激化の一因にもなっている。
しかし、こうした苦しみの根本的な原因には、人が、往々にして自分を他人よりも過剰に愛するという、過剰な自己愛・自己中心・自我執着がある。言い換えれば、健やかに生きることができるだけでは、足るを知ることがなかなかなく、自と他の優劣を比較して、優越感の充足を求めて劣等感を忌み嫌い、「今よりもっと」「他人よりもっと」と際限なく、さまざまなものを求める心の働きである。そして、その基準となる価値観は、例えば、財力・学力・体力・容姿・配偶者等の親族・名誉・地位・権力などであろう。
そして、これらの苦しみは、前に述べたように、加齢とともにますます増大していく。加齢とともに、求めても得られないことが増え、若いうちは得ていたさまざまなものを失う苦しみが増え、いろいろな原因によって他に疎んじられる(愛されない)といった苦しみも増えるからである。
そして、仏教の無我の悟りは、これらの問題・苦しみも解消する。それは、単に心身のみを無我(私ではない)と悟る境地ではなく、それを土台として、自分の財物・家族親族・名誉・地位などに関しても、私のものではない(無我)と悟るものである。よって、そうしたものを過剰に求めることを原因とした心の苦しみや、心身の不健康や人間関係の問題からも、当然に解放される。
22.悟りの恩恵のまとめ
ここで私なりに解釈する悟りの恩恵に関して言えば、以下のとおりである。
第一に、心の安定・平安・広がりである。静まった広い心である。無我の悟りで、我欲が静まると、当然、心は静まる。また単に静まるだけではなく、自分のことばかり考える思考や感情(自我意識)から解放されるために、意識が広がって、他者・万物を包むようになる。これは万物への愛・大慈悲・博愛など、さまざまな宗教が理想とする心の状態である。
第二に、心身の健康・長寿である。心が静まると、ストレスが解消し、ストレスがもたらす免疫力の低下、精神疾患、慢性疾患、老化の加速を和らげることができる。仏教僧の長寿は、科学的に確認されている。
第三に、知性・智恵(智慧)の増大である。心が静まって、過剰な我欲から解放されることは、物事を正しく見ることを助ける。より具体的に言えば、主観的で自己中心的で、刹那的で衝動的な視点や感情ではなくて、合理的で客観的で、長期的で、全体的・総合的・俯瞰的な視点からバランスよく物事を見ることができるようになる。よって、人生の重要な判断においても、大きな間違いはないし、刹那的な欲望のために、他を害して自滅したり、他に騙されたりすることがない。
第四に、人間関係の調和・平和である。幸福になるためには、良い人間関係は重要であるが、悟りによって、心が過剰な我欲から解放されれば、他といたずらに奪い合って害し合うことがない。意識が他者万物にも広がって、慈悲の心が強まるために、他への慈悲の行為・苦楽の分かち合いを行うので、人間関係は良好な、調和したものとなる。
第五に、老いや死の苦しみの超越である。老いて不幸・苦しみが増すのではなく、老いてますます心が成熟して、精神的な智恵(智慧)と慈悲が深まって幸福になり、普通の人にとっては最大の苦しみの一つである死も、精神的な解放の時となる。
なお、最後に、死後の世界があるかどうかはわからないが、仮にある場合には、悟りによって死後の世界・転生・来世を制御することができると仏教は説く。その意味で、仮に死後の世界があった場合には、それにより良く対処できるという意味で、悟りは、死後の保険ともなるということができるだろう。
《参考資料1》仏教・ヨーガの思想を裏付ける最新の認知心理学の詳細
(出典:ひかりの輪2019年~2020年 年末年始セミナー特別教本「最新科学が裏付ける仏教・ヨーガ悟りの思想」)
1.はじめに
本章では、あらためて仏教・ヨーガの思想を裏付ける最新の認知心理学の詳細についてご紹介したいと思う。まず、認知心理学と、それが連動する脳科学の最近数十年間の発展は、非常に目覚ましいものであるばかりではなく、その結果は、研究当事者にとってさえ驚くべきものだったようだ。
下條信輔氏(カリフォルニア工科大学教授)によれば、その結果として、認知心理学が発見した人間の意識・心の働き・脳などの実際の在り方は、我々の常識と大きく乖離(かいり)したものになっている。それは、認知心理学者をあたかも現代のガリレオのような立場に置きかねないほどのもので、今後は最新の科学的な知見と常識の矛盾の対立をどのように乗り越えていくかの智恵が必要だと考えているほどなのである。
2.心を自分とみなさない仏教・ヨーガ・心理学の一致点
認知心理学は、「行動主義心理学」と呼ばれる心理学の流れの中にある。行動主義心理学とは、他の心理学に比較して実験を重視する心理学で、その意味では、心理現象という目に見えないものを扱うがために一般的な科学的な普遍性を保ちにくい一面もある、心理学の世界の中では最も科学的な心理学の分野ということができるだろう。
この行動主義心理学の中で、「認知行動療法」というものが生まれた。認知行動療法とは、人の精神的な苦悩は、その人の認知=物の見方・考え方によるものであるという視点に基づいている。すなわち、うつ病やストレスの多い人は、その人の考え方・ものの見方に極端に否定的な傾向があって、それに自ら気づいて、自分の認知と、認知に基づく行動を変えていくことによって苦悩を和らげることができるというものである。
そして、この認知行動療法の流れの中で、「マインドフルネス認知療法」というものが現れた。マインドフルネスとは、仏教の「念」(サティ)の英訳であり、仏教の禅の瞑想を学んだ医学者が、その中から作り出した体や心の痛みを和らげる心の持ち方・瞑想の仕方のことをいう。本来の念とは、「記憶して忘れないこと」などが原意であり、それから転じて仏陀の教えを絶えず思うことなどと解釈される。
しかし、心理療法としてのマインドフルネスは、「今ここ」の自分の心身などに関して、是非の判断を入れずに、すなわち冷静に客観的な視点から注意を向けることである。そして、心の中の思考や感情に対しても、このマインドフルネスの瞑想を行うと、結果として、「自分と(自分の)思考や感情が別のものだ」という感覚に至り、そうなると苦しみが和らぐということが臨床的に確認されている。これを「思考と感情の脱同一化」という。そして、自分の思考や感情を見ている自分の意識を、「超越的自我」ないしは「メタ認知」などと呼んでいる。自分を見ている自分という意味である。
ここまで書けば、すでに理解いただける方も多いと思うが、これは、仏教やヨーガが説く「心の働きは真実の私ではない」という思想とよく通じている。仏教では、心は無我であるとされている。この無我とは、私ではない、私のものではない、私の本質ではない、といったほどの意味である。この場合の無我は、「私がない」という意味ではなく、「私ではない(私に非(あら)ず)」という意味であり、非我ともいわれることがある。この瞑想によって、心に起因する苦しみが解消するとされる。
3.ヨーガの真我の思想と心理学の深い一致点
また、ヨーガは、「真我」というものを説くが、この真我の思想が、上記の心理学の見解とさらによく一致しているのである。まず、真我とは何かを説明しよう。真我は、ヨーガにおいて、真の自己・真の自我などとされている。別に、「純粋観照者」とも呼ばれる。そして、真我は、単にただ対象を見るものであり、いかなる作業もせず、永久不変である。
それは「見る」という能力からなる純粋精神である。ここで見るといっても、真我が、自分の意思で見るという働きをなすというのではなく、それはただ真我の本来の在り方にすぎないとされる。よって、見るというよりも「照らす」といった方がよい面があり、光が無心にものを照らすように、真我は意思しないで自然に対象を照らすものであるとされる。
そして、ヨーガにおいては、真の自己である真我が、心を自分自身と錯覚・混同することが、苦悩の原因だとしている。すなわち、真の自己である真我は、本来は心ではないのであるが、心を自分と錯覚することで、(心と共に)苦しんでいるというのである。この苦しみを解消するためには、真我が、心を自分とは別のものであることを認識する必要がある(弁別智を得ること)。
そして、その方法が「ヨーガ」なのである。というのは、本来ヨーガとは、「心の働きを止滅すること」と定義されたものであり、心の働きを止滅することで、通常は、心と結合・一体化し、心と共に様々な苦しみを感じていた真我が、心から離れて自己本来の姿・在り方に戻ることができ、それにともない苦しみが消滅するのである。
なお、これを真我の独存の状態といい、さらには解脱ともいう。そして、本来の真我の姿は、自立独存の絶対者であって、時間と空間の制約を受けず、永久不変であり、絶えず平安と光明に満ちた存在であるとされる。
こうして、真我が(思考や感情といった)心の働きと自分を、別のものと認識することで苦悩が消滅するというヨーガの思想は、自分と思考や感情の脱同一化をはかり、自分を見ている自分=超越的自我・メタ認知を得ることで、苦しみが和らぐとするマインドフルネス認知療法の見解と、非常によく似ていることに気づくだろう。そもそもマインドフルネス認知療法自体が、仏教の念・禅・瞑想に由来するものであるから、仏教と深い共通性を持つヨーガの思想とよく合致することは、必然的であるかもしれない。
4.仏教の「無我の思想」とヨーガの「真我の思想」は本質的に矛盾しない
なお、仏教では真我の概念は説かない。それは例えば、仏教には「一切は無常」という思想があるから、永久不変なものとされる真我という概念になじまない。しかし、これは、解脱に至る上で何に力点を置くかの違いであって、両者に本質的な矛盾があるわけではないと考えることができる。ヨーガも仏教も、私たちが「心」と呼んでいる思考や感情などは真実の私ではないと悟って、それに執着しないことで苦しみが解消されると説く点において、全く一致している。
そして、そのために、単に「心は私ではない」と説いて、心に対する執着を脱し、真実の私に関してはあえて論じないのが、仏教(少なくとも開祖のゴータマ・シッダッタ)の姿勢である。一方、真我の存在を強調し、心が真我とは全く別のものであるとして、心に対する執着を脱しようとするのが、ヨーガの姿勢である。その意味で初期仏教は、努めて心理学的であり、それに対してヨーガも同様に、極めて心理学的な思想ではあるが、科学的に検証不能な真我という概念を立てるところにおいて、仏教と比較するとわずかに、より哲学的・形而上学的・宗教的な色彩があるということができる。
5.最新の認知心理学は様々な意味で心の働きは自分ではないことを明らかにしつつある
最新の認知心理学は、様々な意味で、心の働きは自分ではないことを明らかにしつつある。デイヴィッド・イーグルマン准教授(スタンフォード大学精神医学科)は、「意識は傍観者である」とし、様々な心の働きは、無意識的な脳活動が司っており、「意識は遠いはずれから脳の活動を傍観しているにすぎず」「私たちの行動をコントロールしているのは私たちの意識ではない」とし、さらに、にもかかわらず意識は、無意識の脳活動が形成する心の働きを、自分がしたことのように錯覚を起こすと述べている。
前野隆司教授(慶応大学システムデザイン・マネジメント研究科)も同じように、知覚・感情・意志といった心の働きは、無意識の脳活動が形成しており、意識は、その結果を単に受動的に経験しているだけであるが、意識は、それを「自分のものである」と錯覚しているという。
しかし、意識が心の働きを制御していないとすれば、その心の働きと連動してなされる行為が、(私たちの意識の)自由意志によってなされたかどうかに疑問が生じる。この点に関しても、下條信輔教授(カリフォルニア工科大学)などは、「人は自分でわかり言葉にできる心の働きよりもむしろ、自分で気づかない無意識的な心の働きに強く依存している」とし、「人は自分の自由意志によって行為し、当然その責任も全て当人にある」というのが近代民主主義社会の根底にある考え方に近いだろうが、「最前線の人間科学は、人間の自由意志の尊厳とそれにのっとった社会の諸々の約束事を根底から覆しかねない」とまで述べている。
こうして、私達の自覚する「意識」と、その意識が経験している五感・心の中のイメージ・思考・感情・意志・欲求といった様々な「心の働き」と、「脳」の活動の実際の関係は、私たちの日常の感覚・常識がとらえている在り方と大きく異なり、それはむしろ、仏教やヨーガの心理学が2500年頃前から説いてきた在り方に非常に近いことがわかってきたのである。
6.思考は物理的な要素に支えられている
デイヴィッド・イーグルマン准教授が言う通り、私たちが「自分の思考」と呼んでいるものも、純粋に自分の意識が作ったものではなく、自分の脳や体や自分の体以外の様々な物理的な要素に支えられている。その意味で、客観的・合理的な視点から言えば、それが本当に「自分」の思考であるとは言い難い。単に浮かび上がってくる思考を「自分の思考だと考える習慣」があるだけである。
実際に脳が変化すれば、人が考えることの種類が変わる。深い眠りでは思考は生じず、脳が夢を見る睡眠の状態に移ると、思いがけない突飛な思考が生じる。日中でも、アルコールや麻薬、たばこ、コーヒー、または運動を加えることで、脳と思考は変化する。脳という物質の状態が、思考の状態を左右する。脳に打撃を受ければ、様々な精神活動ができなくなる(最悪は植物人間の状態)。
こうして、私たちは、思考は物理的な土台をもたない風に乗る羽毛のようなものだと直感的には思いがちであるが、実は、脳の状態に直接左右されているものだ。
7.私たちの思考・感じることは、意識の支配下にはない
そして、同教授によれば、最新の科学的な研究の結果としてわかることは、「私たちの行動・思考・感じることの大半は、私たちの意識の支配下にはない」ということである。脳のニューロンの広大なジャングルは、私たちの意識が知らないところで、独自のプログラムを実行しており、脳は独自に事を仕切っており、その営みの大部分に「意識」はアクセス権を持っていないのである。言い換えれば、無意識的な脳活動が、私たちの様々な心理作用を形成しているのである。
しかし、私たちの意識は、その脳の膨大な働きを認めずに、それを全て自分の力でやっていると思い込んでいる。実際には、脳はたいてい自動操縦で動いていて、意識はその脳の膨大な活動にほとんど近づけない。この事実の証明として、例えば、衝突の危険をはっきりと意識が認識する前に、足は車のブレーキを踏むという事実がある。また、パーティなどで聞いているつもりもなかった隣のグループの会話に自分の名前が出てくると突然気づくという事実がある(カクテルパーティ効果)。この時に意識に隣のグループの会話を気づかせるのは、無意識の脳活動の結果である。
膨大な無意識的な脳活動が行っている中で、意識が経験すること(できること)は、その「要約」のようなものである。例えるならば、社会の出来事を要約して伝える新聞の見出しのようなものだ。そこには社会の全ての情報などは到底存在し得ないし、その本当にごく一部にすぎない。仮にそれ以上を与えられたとしても、意識には受け取れる容量はないだろう。
しかし、私たちの意識は、新聞の見出しを読んでいるだけなのにもかかわらず、それを最初に思い付いたのは自分であるかのように錯覚する。実際には、その情報が生じる前には、意識の知らないところで、脳が膨大な活動をしていたのである。
8.様々な科学的な発見や芸術活動を生み出す無意識の脳活動
イーグルマン教授によれば、電磁気の法則を発見したマックスウェルは、死の床で、その有名な方程式を発見したのは自分の中の何かであって、自分ではないと告白した。アイディアがただ降りてきたというのだ。ウィリアム・ブレイクも、名高い長篇詩「ミルトン」を「あらかじめ何も考えず、むしろ自分の意思に逆らって、いきなり(何者かが)口述して書き上げた」と言っている。ゲーテは、名著「若きウェルテルの悩み」を、意識的に考えを投入することなく、ひとりでに動くペンを持っているかのように書いたと言っている。
そして、無意識・深層心理学を展開した偉大な心理学者カール・ユングは「私たち一人ひとりの中に、私たちが知らない別の人がいる」と言った。ピンク・フロイドも「僕の頭の中に誰かがいるが、それは僕じゃない」と言ったそうだ。こうして、私たちの心に起こることの大半は、私たちの意識の支配下にはない。
こうして、意識は、たいていの意思決定に関わっておらず、傍観しているだけであるが、それによって私たちは上手く行動できている。例えば、意識がそのプロセスに関与すると、行動が遅くなりすぎてしまい、間に合わないことが度々ある。先ほど述べた急ブレーキを踏むときもそうだが、プロの球技のスポーツ選手などもそうである。目がボールをとらえて意識が認識するまでには0.5秒かかるが、それだけの時間をかけていては遅すぎて、たいていボールを打ち返せないのである。意識に関与させずに、神経系・脳・筋肉が直接的に活動しなければならない。
9.自分の意識は、自分の精神活動の中心にいない
こうした考察の結果は、私たちの意識は、私たちの心の働き・精神活動の「中心ではない」ということである。その活動の主体は、膨大な無意識の脳活動が行っており、私たちの意識は、実際には、その中心から遠くはずれた周辺から、その結果を傍観しているにもかかわらず、その中心にいると錯覚しているのである。
こうして、人間の日常的・直感的な感覚と最新の科学的な発見が、正反対となって鋭く対立することは、人類の歴史において時々起こっている。その典型が、400年ほど前のガリレオを巡る地動説と天動説の対立である。その当時の人間でなくて、21世紀の我々であっても、科学の学習を受けることがなかったら、日々太陽が自分たちの住む大地に対して昇っては降りるのを見ながら、「太陽が地球の周りを回っている」としか思わないだろう。
しかし、ガリレオは、地球の外に出て宇宙から地球と太陽の関係を客観的に見ることなく、地球の中にいながら、地球と太陽の関係を客観的に、すなわち科学的に見ることができたという点で偉大な人物である。
このガリレオの地動説と天動説の教訓からわかることは、要するに、人は、気づかないうちに自己中心的な視点・価値観を有しているということだ。自分がいる地球から見るから、全ては地球を中心に回っているように見える。そして自分の意識が心の働きその他すべてを体験するから、意識が心の働きの主体・中心であるかのように見える。
これを言い換えると、自分の中から、自分を客観的に見ることは難しいということだろう。地球の中ではなく、仮に、地球の外=宇宙から太陽と地球を見ることができたならば、容易に両者の関係を正しく見ることができただろう。同じように、自分の属している家族・集団・組織・民族・国家などの性質も、その外側の存在である他の家族・集団・組織・民族・国家と客観的に比較するならば、より正しく理解することができるだろう。
極めつけに、自分の目を自分では見ることはできない(鏡に映った自分の目の姿は見ることはできるが)。そして、目の中の盲点(網膜の中で光線の受容体の細胞のない部分)の存在を発見した科学者も、自分の目の観察から盲点を発見したのではなく、他人の目を覗き見ているうちに盲点を発見した。
なお、この盲点の話には、もう一つ重要なポイントがある。それは、人間が自分の目の経験から盲点の存在に気づかなかったのは、意識に立ち上る視覚の映像は、意識の知らない無意識の脳活動が、盲点の周りの映像で盲点の部分を埋め合わせた映像を作った上で、意識に見せるようにできているためである。すなわち、視覚の映像の体験においても、私たちの意識は、無意識の脳活動がなしていること(いわゆる視覚に関する編集作業)を知らないのである。
《参考資料2》四念処の仏陀の説法
比丘たちよ、では、比丘は、どのように気づいて(サティ)いるのか?
比丘はいま、身(k?ye)について、身を観つづけ、正知をそなえ、
気づき(サティ)をそなえ、世における貪欲と憂いを除いて住む。
受(ヴェダナー)について、受を観つづけ、正知をそなえ、気づきをそなえ、
世における貪欲と憂いを除いて住む。
心(チッタ)について、心を観つづけ、正知をそなえ、気づきをそなえ、
世における貪欲と憂いを除いて住む。
法(ダルマ)について、法を観つづけ、正知をそなえ、気づきをそなえ、
世における貪欲と憂いを除いて住む。
比丘たちよ、比丘はじつにそのようして、正念のものとなる。
(パーリ仏典, 長部大念処経, Sri Lanka Tripitaka Project)
《参考資料3》諸行無常・一切行苦・諸法無我の仏陀の説法
「一切の形成されたもの(行)は無常である」(諸行無常)と
智慧をもって観るときに、ひとは苦から厭い離れる。これが清浄への道である。
「一切の形成されたもの(行)は苦である」(一切行苦)と
智慧をもって観るときに、ひとは苦から厭い離れる。これが清浄への道である。
「一切の事物は無我である」(諸法無我)と
智慧をもって観るときに、ひとは苦から厭い離れる。これが清浄への道である。
(パーリ仏典, ダンマパダ20, Maggavaggo, Sri Lanka Tripitaka Project)
《参考資料4》五蘊無常・五蘊無我
アッギヴェッサナよ、私はこのように弟子たちを戒める。このように頻繁に語る。
「比丘たちよ、色は無常、受は無常、想は無常、行は無常、識は無常である。
比丘たちよ、色は無我、受は無我、想は無我、行は無我、識は無我である。
すべての行は無常である、すべての法は無我である。」と。
(パーリ仏典, 中部 35 C??asaccaka Sutta, Sri Lanka Tripitaka Project)
比丘たちよ、これらの五つの取蘊がある。それはいかなる五か?
色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊である。
また比丘たちよ、もろもろの沙門・婆羅門にして、このように色を知り、このように色の生起を知り、このように色の滅尽を知り、色の滅尽にいたる道を証知して、色を厭離し、貪りを離れ、滅尽に向う者たち。
彼らはよく解脱した者である。
よく解脱した者たちは完成した者であり、完成した彼らには、もはや輪廻は設定されていないのである。(受・想・行・識について同様に説く)...
(パーリ仏典, 経蔵 相応部蘊相応,取転経(Up?d?na parivatta sutta?)Sri Lanka Tripitaka Project)
《参考資料5》四無色定に関するブッダの説法(『大般涅槃経』より)
アーナンダよ。これらの八つの解脱がある。その八つとは、どれどれであるか?(中略)
〈物質的なもの〉という想いを全く超越して、抵抗感を消滅し、〈別のもの〉という想いを起こさないことによって〈(すべては)無辺なる虚空である〉と観じて、〈空無辺処〉に達して住する。これが第四の解脱である。
〈空無辺処〉を全く超越して、〈(すべては)無辺なる識である〉と観じて、〈識無辺処〉に達して住する。これが第五の解脱である。
〈識無辺処〉を全く超越して、〈何ものも存在しない〉と観じて、〈無所有処〉(=何も無いという境地)に達して住する。これが第五の解脱である。
〈無所有処〉を全く超越して、〈非想非非想処〉(想いがあるのでもなく、想いが無いのでもないという境地)に達して住する。これが第七の境地である。
〈非想非非想処〉を全く超越して、〈想受滅〉(表象も感受も消滅する境地)に達して住する。これが第八の解脱である。アーナンダよ。これらが八つの解脱である。