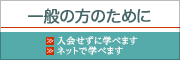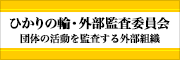③大乗仏教のマントラ瞑想(シンボル瞑想)
以下は、大乗仏教のマントラ瞑想(シンボル瞑想)について解説した、「2022年GWセミナー特別教本『瞑想法の総合解説 心身の健康から悟りの境地まで』」の第4章です。
-------------------------------------------------------------------------------
第4章 大乗仏教の瞑想:シンボル瞑想
1.はじめに
前章では、初期仏教の瞑想の思想と、具体的な瞑想法を紹介したので、ここでは大乗仏教の瞑想法を紹介したいと思う。もちろん、大乗仏教こそ、さまざまな宗派があり、それに応じて大きく異なるさまざまな瞑想があるので、そのすべてを紹介することは不可能である。そこで、自分が思うに、その中で特に、現代の人に合っていると思われるものを提供したいと思う。
大乗仏教の中で、特に中国仏教史上に展開した、禅定(瞑想)の理論と実践といえば、比叡山天台宗の始祖である伝教(でんぎょう)大師(だいし)最澄(さいちょう)が日本にもたらした「天(てん)台(だい)止(し)観(かん)」が、大きな存在であり、また、日本の仏教史では、中国禅の伝統を継承しながら、天台止観も採り容れた曹洞宗の始祖の道元のいわゆる「道元禅」があるが、先ほどの理由でいずれも、本章では紹介を省略する。
その一方で、弘法大師空海が中国からもたらした、真言宗の印相(いんぞう)を結んで真言を唱える、身体性を重視した瞑想(真言瞑想)に関しては、現代でも実践しやすいと思われるので触れたいと思う。
2.シンボル瞑想という概念
シンボル瞑想とは、真言瞑想などの瞑想の本質を踏まえた上での、ひかりの輪オリジナルの概念である。ここでの(聖なる)シンボルとは、悟りの境地に近い意識状態を引き出すようなもので、主に五感の対象となるものである。その主なものとして、視覚的なシンボル・聴覚的なシンボルなどがある。また、五感の対象に加えて、体の形・姿勢にも一部、シンボルがあると解釈している。
さて、シンボルは必ずしも仏教に限らず、すべての宗教において、その宗教の聖なるシンボルがあるということができる。その中で、例えば、拝んで心が静まるような仏像・仏画は、視覚的なシンボルであり、密教で用いられる曼荼羅もそうであろう。
自ら唱えることで心が静まる効果のある言葉(仏教・ヨーガのマントラ・真言)は、聴覚的な(字音の)シンボルである。また、嗅ぐことで心が静まる効果のある瞑想用のお香があれば、それも嗅覚的なシンボルということになる。
こうして、シンボルは、宗教芸術と結びついている面がある。特に仏教の密教などは、その瞑想・悟りのために密教芸術を発展させ、さまざまな仏画・仏像・曼荼羅・金剛(こんごう)杵(しょ)や金剛(こんごう)鈴(れい)といった法具を生み出したことで知られる。
3.シンボルは決して崇拝対象ではない(宗教的な概念ではない)
しかし、ここで特に強調しておきたいことは、ひかりの輪の「シンボル」という概念は、仏教やその他の宗教における崇拝の対象と、異なる概念である。シンボルは、あくまで、それに人間が触れることによって、その人間の中に、より高い意識、より悟りの境地に近い、静まった広がった意識などを生じさせるものであって、それ自体は、神や仏ではない。
仏画・仏像・曼荼羅は、神や仏ではなく、宗教芸術品であって、木や金属や紙にすぎない。しかし、それが感覚器官等の身体を通して人の心身に好ましい影響を与えるものである。いかに優れたシンボルとしての効果を発揮する仏像があったとしても、その仏像自体を、仏として崇拝することは、一種の偶像崇拝の宗教・信仰であって、ひかりの輪の思想と異なるものである。
4.人類共通の普遍的なシンボル
こうして各宗教には、それぞれの聖なるシンボルがあるが、精神科医・深層心理学者のカール・ユングは、人類普遍の聖なるシンボルがあると主張した。ユングは、人類が民族・人種によらず、共有している集合的無意識や元型(アーキタイプ)といった概念を提唱した。
この元型とは、夜見る夢のイメージや象徴を生み出す源となる存在であり、集合的無意識の中で仮定されたものである。元型の像(イメージ)は神話的で、人類の太古の歴史や種族の記憶に遡るように考えられる。
主な元型としては、①意識の中心の自我(Ego)の元型、②心(魂)全体の中心として仮定される「自己」(Selbst)の元型(宗教的には「神の刻印」などと見なされる)、③女性の心の中の理性的な要素の元型で、男性のイメージでよく認識される「アニムス」、④男性の心の中の生命的な要素の元型で、受容的特徴を持ち、女性のイメージでよく認識される「アニマ」、⑤全てを受容し包容する大地の母としての生命的原理を表す「太(たい)母(ぼ)」(グレートマザー)、⑥太母と対比的で、理性的な智慧の原理を表す「老賢者」などがある。
5.人類普遍の聖なるシンボル:円・輪・マンダラ
そして、ユングは、世界の諸宗教・諸文化を調査研究する中で、人類普遍の聖なるシンボルの一つとして、円・輪・マンダラという概念を見出した。マンダラは、丸いという意味で、ユングがマンダラと見なすものは、輪の形状を持っている。
そして、ユングの研究を見ると、マンダラ・シンボルの中に、光の輪があることがわかる。光の輪というのは、ユングの主張をだいぶ簡略化した表現であるが、中心に太陽・月・星などがあって、その周囲に輪が描かれ、中心からはスポーク上の光なども描かれたものである(詳細は参考資料を参照)。
6.普遍のシンボル:光の輪
さらに、ユングも発見したように、仏像・仏画やキリスト教美術などで、神仏や聖人の体から発せられる光明を視覚的に表現した光輪(光背・後光ともいう)がある。そして、これは、宗教全体で普遍的なものであると考えられており、仏教以前のゾロアスター教のミスラ神などにも見られ、ネイティブアメリカンの権威者や戦士が頭に着ける羽根冠も、元来は放射光状の光背を表していると伝わっている。
これに関連して、光の輪の形をとる大気光学現象の一つとして、太陽の周りに現れる虹色の光の輪があり、英語ではハロと呼ばれる。このハロは、キリスト教美術などで、イエス・マリア・十二使途・天使と共に描かれる光の輪を指す言葉と同じである。また、ひかりの輪の団体名の由来の一つが、その創設メンバーが、聖地を巡って瞑想する中で、重要な気づきとともに、この太陽の周りの虹の光の輪を見ることが不思議と多かったという経緯である。
もう一つの光の輪の形をとる大気光学現象としては、太陽等の光が背後から差し込み、影の側にある雲粒(くもつぶ)や霧粒(きりつぶ)で光が散乱され、見る人の影の周りに、虹と似た光の輪が現れるものがある。よくブロッケン現象といわれるが、英語では、光輪を意味するgloryともいわれる。そして、日本では、これを御(ご)来(らい)迎(ごう)などと呼び、影を阿弥陀如来、周りの光の輪を仏の後光として、聖なるイメージをもって解釈された。
7.太陽とその光は、人類普遍の根元的な聖なるシンボル
そもそも、光自体が、さまざまな思想や宗教において、超越的な存在者のシンボルであった。古くから宗教に光は登場し、より具体的には、太陽と結びつけられることが多かった。古代エジプトの神のアメン・ラー、太陽神があり、プラトンは、光の源である太陽と最高原理「善のイデア」とを結びつけた。
『新約聖書』では、イエスが「私は、世にいる間、世の光である」(ヨハネ福音書 9:5)と語り、キリスト教世界の思想にさまざまな形で影響を与え、しばしば光が正義、闇が悪のたとえとして用いられた(グノーシス主義などでも)。
仏教では、光は、仏や菩薩などの智慧や慈悲を象徴するものとされた。また多くの主要な仏陀・菩薩が、太陽・光と結び付けられている。釈迦牟尼は太陽族の末裔とされ、大日如来はまさに太陽の仏であり、弥勒菩薩はその由来がミトラ教の太陽神であり、阿弥陀如来も別名を無(む)量(りょう)光(こう)仏(ぶつ)、薬師如来も正式な名称は薬(やく)師(し)瑠(る)璃(り)光(こう)如来といい、その脇侍は日光菩薩である。観音菩薩も光(こう)世(ぜ)音(おん)菩薩という別名があり、光に結び付けられている。
さらに、神道でも天界の総帥であり、皇祖神として最も重要な位置づけを持つ天(あま)照(てらす)大神(おおみかみ)も太陽の女神である。そもそも、どの宗教の思想ということなく、日本人は、太陽をお日様と呼び、お日様を拝むと言い、太陽に向かって手を合わせる伝統的な習慣がある。
8.太陽信仰やシンボルとしての太陽の背景
この背景としては、古代から人類全体にとって、太陽とその光は、自分達が経験する自然の中で圧倒的なエネルギーと運動を持った最大の現象であるとともに、自分達の生命・生活を支えるこの世界の中で最も重要な存在であるから、太陽とその光に対する信仰があったと思われる(いわゆる太陽信仰)。
その圧倒的な存在感は、世界の中心・絶対者・神・王というイメージを形成したであろう。加えて、古代人にとっては、自分たちに生命を与えるものが神と認識されるのが自然だろうと思われる。日本語でも、「命」という文字は、神棚の前で神のお告げを聞く人をかたどったものだという。命とは神が与えるものという解釈である。
なお、地動説を発見した近代の人類にとっては、太陽の位置づけは、古代よりもさらに大きく増して、地球は、太陽を中心として、その周りを周っている多くの惑星・無数の天体の一つにすぎず、直径にして、その約100分の1の大きさの天体となったことはご存じのとおりである。
そして、神や仏の重要な属性である万物への愛と大いなる叡智が太陽とその光に象徴されることも、同じく、ごく自然なことだったと思われる。万物に降り注ぐ陽光は、すべての生き物を温めてその命を支えるから、自ずと神や仏の万物への愛・博愛・大慈悲の象徴となる。
また、人は、その光によって、世界の万物を目で見て、よく知ることができるから、自ずと神や仏の全知・智慧の象徴となったのだろう。なお、太陽・光・火と、陰陽のセットで信仰されたのが、太陽が沈んだ後に夜空を照らす月、そして水ではないかと思われる。日本語の神=カミは、火と水に由来するとの説もある。
9.仏教・ヨーガの真言(マントラ)瞑想
さて、シンボルを使った具体的な瞑想に話を移したい。
最初に、仏教・ヨーガで行われる真言(マントラ)の瞑想に関してである。この真言(マントラ)は、真実の言葉との意味があり、神秘的な力があるとされ、呪術的な効能もうたわれた。
しかし、科学合理性を重視するひかりの輪では、この思想をそのまま受け入れることを避けながら、発声と心の状態の関係を研究する身体心理学の研究結果に注目した。それによると、特定の音、例えば、アー音などが、心の安定・解放をもたらす生理的な効果があることが確かめられている。
なぜそうなのかという科学的な因果関係までは明らかにされているとは聞いていないが、アー音は、口を開けただけで発生できる音であって、日本の50音でも、サンスクリット語でも、アルファベットでも第一の文字の音になっている(サンスクリット語でのア音は、宇宙の根元・始まりといった意味があるという)。
そして、マントラの中には、仏教で最も基本的な真言とされる三宝真言(ナマ・ブッダ・ヤ、ナマ・ダルマ・ヤ、ナマ・サンガ・ヤ)があるが、確かにアー音の連続でできているし、アーメン・アラーといったキリスト教やイスラム教のキーワードも同様である。
さらに、一般の真言・マントラを拒絶する浄土真宗の念仏である「南(な)無(む)阿(あ)弥(み)陀(だ)仏(ぶつ)」も同様であり、さらにそれが訛った「なんまいだー」になると、さらにアー音が増えている。これは、人が経験則から、自分の心が静まるような音を選択してきた結果かもしれない。そして、その生理的な効果を、マントラの神秘的な効果と解釈してきたのかもしれない。
ともかく、ひかりの輪においては、信仰に基づいた真言・マントラではなくて、生理学的な根拠に基づいた発声による心理療法・健康法として、マントラ瞑想を位置づけている。
10.真言瞑想の際の姿勢(座法)・手の組み方(手印(しゅいん))
さて、真言を含めて瞑想を行うときには、その座り方・手の組み方が教示される。仏教の座法や手の組み方では、仏陀がその座法で成道した(悟りを得た)という蓮華座法(パドマ・アーサナ)や、左手の上に右手を乗せる形である「定印(じょういん)」と呼ばれる手の組み方が勧められることがある。
この手の組み方は手印(ないし印相)と呼ばれ、これはサンスクリット語のムドラーの訳語であるが、このムドラーとは象徴(シンボル)という意味があり、手印は、仏の悟りの内容を象徴するものとも解釈される。
また、真言瞑想では、身体と言葉と意識(身(しん)・口(く)・意(い))の三つ(=三密)に関して、身体において特定の座法や手印を組み、口において特定の真言を唱え、意識において仏を観想するならば、仏の三密と相応して(=結びついて)、仏陀の加護を受け、仏陀と合一すると説かれる。
これは、密教的な信仰であって、科学的な根拠はないが、経験上は、特定の座法や手の組み方は、心が静まる一定の生理的な効果はあるのではないかと思う。
また、仏を観想するというが、それは、その仏の視覚的なイメージが、その人の聖なる意識を引き出す生理的な効果があるか否かによって、効果が異なってくるのではないかと思う。よって、その人が、自分の経験上、静まった心の状態を引き出すようなシンボルとなる仏像・仏画・曼荼羅などを見つけることができれば、それを活用することができると思う。
11.雄大な自然という人類普遍のシンボル
しかしながら、ひかりの輪の考え方としては、視覚的なシンボルは、何も仏教の宗教芸術の中だけに見出す必要はないと思われる。というのは、悟りの境地である静まった広がった意識状態に近づくための人類普遍のシンボルとでもいうべきものとして、大自然があるからである。
これに関しては、「2020~21年 年末年始セミナー特別教本『ヨーガ・仏教の修行と科学 人類社会と宗教の大転換期』」で、「Awe(オウ)体験」として、すでに紹介しているが、人が、特に雄大な大自然の中に身を置くと、①エゴが減少して謙虚となり、②心身がリラックスして静まり、③自分を支える他者・万物への感謝や愛が生じ、④免疫力が高まり、⑤脳の活動が活性化され、⑥刹那的な衝動が抑制されて長期的な利益を重視するようになり、⑦他人に騙されることがなくなる、といったことが科学者の研究によって確認されている。
実際に、多くの求道者が大自然の中で修行をしている。釈迦牟尼は広大なガンジスの自然の中で修行し、最後は菩提樹の下の瞑想で悟り、ヨーギーはヒマラヤの山々の中で修行し、若き日の空海や最澄などの日本人の求道者も山などの自然の中で修行したとされる。そして、大乗仏教の教義では、大自然・大宇宙は仏の現れであるとか、すべての生き物を仏になる仏の胎児として慈悲をもって慈しむ巨大な仏の子宮であるという思想がある(大日経の胎蔵界思想・地蔵菩薩の思想など)。
この自然を重視する宗教の一つが、日本の国産宗教といわれる山岳仏教・修験道(山伏)かもしれない(神道・密教などが混合した教義を持つ)。修験道では、聖山に登拝する修行を行うが、聖山を、やはり仏の母胎と見て、白装束をまとって入山して下山することで、それは一種の精神的な死と再生の儀礼の過程ととらえている。
12.大乗仏教が重視する一元的な世界観:意識の拡大の瞑想
さて、大乗仏教の瞑想は、当然、大乗仏教が説く世界観と結びついている。これは初期仏教の四念処の瞑想が、初期仏教の世界観である無常・苦・無我と密接不可分であることと同様である。その世界観とは、その仏教宗派における仏の世界観・仏の世界の見方=智慧を反映したものであり、瞑想とはその境地を体得するためのものであるから当然である。
一方、大乗仏教全般に共通する世界観として特徴的なものは、私の考え方では、万物が相互依存で、同根であり、一体であるという思想である。ただし、これは初期仏教の無我の思想と表裏一体の関係にあり、別のものではない。同じ思想の二つの表現ということもできるほど本質的なところで結びついている。
というのは、無我の思想は、この世界に私・私のものはない、という思想であるから、これを言い換えれば、自他の区別を否定しているものである。無我を悟ることができなければ、私・自分が存在すると錯覚し、それと同時に、この世界のすべてを自分と他者・外界の二つに分けてしまう意識が生じる。
これを「自と他を区別する無智」と呼び、これが、自分と他人を区別して自分を偏愛する自我意識(自我執着・我執)などと呼ばれる自己中心的な意識と、それを原因とした煩悩・我欲を生み出し、他と欲楽を奪い合うなどの結果を招く。
一方、大乗仏教の世界観を悟って、自分と他者・外界の万物が一体と見るならば、他と区別される「自分」は存在せず、自と他を区別して自己を偏愛する自我意識は生じない。その代わりに、仏の心の働きである万物への愛・四無量心・大慈悲が生じることになる。よって、無我の悟りを得た時と同じ結果となる。
13.大乗仏教の縁起の思想
さて、大乗仏教の世界観を理解するために、縁起の思想に注目したい。縁起の法とは、仏陀の根幹の思想・哲学であり、無常・苦・無我の教えも、縁起の思想と一体不可分である。そして、初期仏教、部派仏教、大乗仏教では、それぞれの縁起の思想が展開した。言い換えれば、釈迦の時代から、少しずつ縁起の法が発展したということができる。よって、各段階の仏教の縁起の思想を見れば、それぞれの根幹の思想・世界観を理解することができるのである。
14.縁起の法
縁起とは、縁によって生起するという意味で、この縁とは、原因・条件などを意味する。よって、縁起とは、物事が何かの原因・条件によって生じることを意味する。そして、これを言い換えるならば、縁起とは、物事が、その物自体の力によって、他から独立して生じるのではなく、何かの他者を縁=条件・原因として生じるということを意味する思想となる。
これは、仏教の根本的教理・基本的教説の一つであり、釈迦の悟りの内容を表明するものとされるが、前に述べたように、釈迦が説いた縁起の法に加えて、その趣旨を踏まえながらも、釈迦の死後に、様々な縁起の法が発展し、拡張されていった。
そして、大乗仏教の成立に至るまでに、縁起の思想は、一部の物事ではなく、この世界のすべての現象に適用されるものとして拡張された。すべての現象が、原因や条件が相互に関係しあって成立し、独立自存のものではないと考えられるようになった。
これは、前に述べたように、無常の教えと一体となる。というのは、どんな現象も、他の何かを条件や原因として生じたものであり、そのものだけの力で他から独立して絶えず存在していたのではなく、そのため、その条件・原因が変化すれば、それに依存している自分も変化することになる。そして、この世界の万物は、すべて相互に依存し合って存在しており、それゆえに、万物が無常に変化するという世界観が成立する。
さらに、無我の教えとも一体である。万物が相互依存であって、何ものも他から独立して存在しないということは、自分と他者・外界の区別も実在せず、この世界には相互依存の一体の万物のみが存在し、他とは別の自分、自分とは別の他人は実在しないことになる。
15.初期仏教や部派仏教の時代の縁起の思想
初期仏教および部派仏教までの段階の縁起説は、迷いの世界のみを説明するものであり、悟りの世界は縁起の中に含まれなかった。この段階までの縁起説においては、悟りは、縁起を超越して、縁起の滅した世界であるとされた。
そして、初期仏教時代の縁起説は、苦しみ悩む生き物が主題であったため、老死という苦しみの原因を無明に求める十二支縁起(十二因縁)説が、代表的なものであった。また、これと本質的には同じ思想であるが、四諦の教えが説く「苦しみの原因は煩悩である」という、心理的な因果関係を説く此(し)縁性(えんしょう)縁起(えんぎ)と呼ばれるものが中心であった。以下に、その釈迦牟尼の言葉の経典を示す
「(世間の)人々は、執着に歓喜し、執着を愛し、執着を好ましく思っている。
そのような執着に歓喜し、執着を愛し、執着を好ましく思っている人にとって、
此縁性、縁起の法という理論は受け入れがたいものである。」
(パーリ仏典, 経蔵中部 聖求経, Sri Lanka Tripitaka Project)
釈迦の死後に、仏教教団が分裂したが、その時代を部派仏教の時代と呼ぶ。部派ごとにそれぞれのアビダルマ(論書)が書かれるようになるにともない、釈迦が説いたとされる「十二支縁起」に対して、さまざまな解釈が考えられた。それらはおおむね、衆生(生き物)の業(カルマ)を因とする惑(わく)縁(えん)(煩悩)によって、苦しみの結果がもたらされる因果関係が説かれるので、業感(ごうかん)縁起と呼ばれる。
そして、この部派仏教の時代には、人の業と煩悩と苦しみの間の心理的な因果関係に限らず、客観世界や客観的な現象まで説明しうる縁起説として説(せつ)一切(いっさい)有部(うぶ)の〈六因(ろくいん)・四(し)縁(えん)・五果(ごか)〉や、南方上座部の二十四縁も説かれるようになった。また、説一切有部では、十二支縁起を過去世・現在世・未来世の三世に渡る業の因果関係とみる三(さん)世(ぜ)両(りょう)重(じゅう)の業感縁起説が説かれた
16.大乗仏教の縁起の思想:万物一体・万物同根の一元思想
大乗仏教の中(ちゅう)観(がん)派(は)を創始した龍樹(りゅうじゅ)(ナーガールジュナ)は、説一切有部の説を批判する形で、無常な現象(被造物・諸行)に限らず、恒常的・観念的な存在(非被造物)も含めたすべて(諸法)が、相互に依存して存在すると説いて(いわゆる相(そう)依(え)性(しょう)縁(えん)起(ぎ))、大乗仏教全般に多大な影響を与えた。なお、これは、後で述べる華厳宗の法界(ほっかい)縁起(えんぎ)の思想に非常に類似しているとされ、法界縁起の思想の先駆と見られる。
中観派と並ぶ大乗仏教の学派である唯(ゆい)識(しき)派(は)では、縁起は、識の転変の意味であるとし、阿頼耶(あらや)識(しき)・末(ま)那(な)識(しき)・六識が、相互に因果となって転変することを指すとした阿頼耶識縁起が説かれた。特に法相宗では、この阿頼耶識からの諸法が縁起する頼耶(らや)縁起(えんぎ)が説かれたが、これは、万物が阿頼耶識という同根から生じると観る思想とも解釈できるだろう。
また、同じように、現象世界を、真如(しんにょ)(如来蔵(にょらいぞう))が縁に従って現れたものと見る真如縁起(如来蔵縁起)が説かれた。さらに、三界(さんがい)(欲界・色界・無色界)の縁起を一心(いっしん)(唯心)の顕現として唱える説(三界一心、三界唯心)が説かれた。
中国の華厳宗では、華厳経の思想に基づいて、前に述べたが、現象界をそのまま真如であると見る法界縁起(重々(じゅうじゅう)無尽(むじん)縁起)が形成された。これは、世界の一部が世界の全体に、世界の全体が世界の一部に、極めて密接不可分に関係しあっていることを説くものであり、先ほど述べた相依性縁起に通じるものがある。
密教においては、空海が、法界縁起説をふまえて、それぞれに性質と作用を持つ六大(地・水・火・風・空・識)が、大日如来の本質として実在し、また世間の生物や事物としても実在して、相互に無碍融通しながら万法に遍在しているとする「六大縁起説」を大成した。
17.ひかりの輪の読経瞑想
万物を相互依存しあって一体であり、同根と見る大乗仏教の思想は、私たちの固定観念的な常識とは矛盾する面があるが、物理学・生物学といった自然科学の視点でいえば、まさに正しい世界観である。
この世界のあらゆる存在は、宇宙自体が百数十億年前に誕生してから絶えず変化しているように、それぞれのスピードの差こそあれ、変化している(諸行無常)。私たちが住む大地も、その下のマントルの対流にともなって動き続けるプレートの上に乗っていて、たえず形や大きさを変えている流動的なものだ(諸行無常)。
その中の生き物に関しても、自分だけの体を構成する分子などは一つもなく、数年の間に、体を構成する分子は外界のものと入れ替わってしまうことがわかっている。こうして、分子生物学的にいうならば、人間の体には絶えず多数の分子が流出入しており、そのため、どこまでが私であり、どこからが他者・外界であるということができる境界などは、科学的には存在していないし(無我)、以前と全く同じ私というものも存在しないのである。
こうして、大乗仏教の一元的な世界観は、科学的な事実であって、それを体得することは、世界をありのままに観る仏の智恵(智慧)を体得することになる。よって、このような一元的な世界観を現代的な表現で簡明に表そうとしたものが、ひかりの輪の「輪の読経瞑想」である。ただし、その思想の詳細の解説や瞑想の方法に関しては、それに詳しい他の特別教本(※)に譲りたいと思う。
※「輪の読経瞑想」の詳細を記した教本
「2015年~16年 年末年始セミナー特別教本『総合解説 一元の智慧 万物一体の真理』」
《参考資料1》円の象徴(『人間と象徴』C.G.ユング著 河出書房新社より引用)
円はいろいろと多面的な心の全体性をあらわしており、そこには人間と自然全体とのあいだの関係まで包含されるのである。原始人の太陽崇拝や近代宗教、あるいは神話や夢、さらにはチベットの僧が描いたマンダラや都市計画図といったものにみられる円の象徴であれ、(中略)常に、円は、生命の唯一の至上の重要な側面――つまり生命の究極的な全体性を指し示している。(中略)
インドや極東の美術のなかで、4つまたは8つの方向性を持つ円は、一般的に宗教的なイメージとして、瞑想に役立つ道具でもある。(中略)これらのマンダラは、聖なる力と関係を有している宇宙を表現したものである。(中略)円形のマンダラが持つ意味(中略)これらは、意識と無意識とを大きくそのなかに含み持つ心の全体性、すなわち自己をあらわしている。(中略)
抽象的な円は、禅の絵図にも描かれている。有名な禅僧の仙厓が描いた「円」と題する絵について、ある禅の老師は次のように述べる。"禅宗では、円は悟りをあらわす。円は人間の極致の状態を象徴しているのだ。"
抽象的なマンダラは、ヨーロッパのキリスト教芸術にも見られる。そのなかで最もすばらしいものに、教会の大会堂の円(えん)花(か)窓(まど)がある。円花窓は、人間の自己を、言わば宇宙の平面に移しかえたものだ。(中略)その他、宗教画にあるキリストの後光や、キリスト教の聖者たちもマンダラとみなすことができる。(中略)
非キリスト教系の芸術では、こうした円は"太陽の輪(sun-wheels)"と呼ばれている。この太陽の輪は、車輪がまだ発明されていない新石器時代の岩壁の彫刻にまでさかのぼってみられる。
《参考資料2》『エッセンシャル・ユング ユングが語るユング心理学』
(アンソニー・ストー著 創元社より引用)
西洋のマンダラにおいても、<たましいの火花>すなわち人間の内奥の神聖な本質は、神のイメージすなわち世界、自然、人間のなかに浸透することのできる象徴によって特徴づけられているのである。(ユング自伝)
《参考資料3》マンダラ・シンボルの形態的要素
(『個性化とマンダラ』 C.G.ユング著 みすず書房より引用)
1.円ないし球、または卵の形。
2.円の形は花(薔薇、水蓮――サンスクリット語ではパドマ)あるいは輪として描かれる。
3.中心は太陽・星・十字形によって表現され、たいていは四本、八本ないし一二本の光線を放っている。
4.円、球、十字形はしばしば回転しているもの(卍)として描かれる。
5.円は中心を取り巻く蛇によって、円状に(ウロボロス)または渦巻き状に(オルフェスの卵)描かれる。
6.四角と円の組み合わせ。すなわち四角のなかの円、またはその反対。
7.四角または円形の城・町・中庭(聖域)。
8.眼(瞳孔や虹彩)。
9.四角の(および四の倍数の)形姿のほかに、きわめて稀ではあるが、三角や五角の形姿が現れる。それは以下に見るように「歪んだ」全体像と考えられる。
《参考資料4》光背(光輪)(ウィキペディアより)
光背(こうはい)とは、仏像、仏画などの仏教美術や、キリスト教美術などにおいて、神仏や聖人の体から発せられる光明を視覚的に表現したものである。後光とも呼ばれる。仏教美術における光背は、インド仏教では頭部の背後にある頭光(ずこう)に始まり、その後体全体を覆う挙(きょ)身(しん)光(こう)が生まれた。仏教が東伝するにつれて、頭と身体のそれぞれに光背を表す二重円光があらわれ、中国仏教や日本仏教において様々な形状が発達した。日本では胴体部の背後の光背を身光と呼んでいる。
形状による分類として、光を輪であらわした円光(輪光)、二重の輪で表した二重円光、またそれら円光から線が放たれている放射光、蓮華の花びらを表した舟形(ふながた)光背(舟(ふな)御(ご)光(こう))や唐草光、宝珠の形をした宝珠光、飛天が配せられているものを飛天光、多数の化(け)仏(ぶつ)を配置した千仏光、不動明王などのように炎を表した火焔光などがある。
これらの「光輪」は、仏教に限らずキリスト教の聖人図画などにも見受けられ、宗教全体で普遍的なものであると考えられており、仏教以前のゾロアスター教のミスラ神の頭部にはすでに放射状の光が表現されている。ネイティブアメリカンの権威ある者や戦士が頭に着ける羽根冠(ウォーボンネット)も元来は放射光状の光背を表していると伝わっている。
《参考資料5》ブロッケン現象・光輪・御来迎(ウィキペディアより)
太陽などの光が背後から差し込み、影の側にある雲粒や霧粒によって光が散乱され、見る人の影の周りに、虹と似た光の輪となって現れる大気光学現象。光輪(グローリー、英語: glory)、ブロッケンの妖怪(または怪物、お化け)などともいう。ブロッケン(Brocken)の由来はドイツのハルツ山地の最高峰ブロッケン山(標高1,142m)でよく見られたことに由来する。
その一方で、日本では御来迎(ごらいごう)、山の後(御)光、仏の後(御)光、あるいは単に御光とも呼ばれ、如来と結びつけられた聖なる現象と解釈された。具体的には、日本では、この現象で出現する影は、阿弥陀如来と捉えられ、『観無量寿経』などで説かれる空中(くうちゅう)住(じゅう)立(りゅう)の姿を現したと考えられていた。前田直己山形大学客員教授は、この現象に世界で初めて名前(来迎)を付けたのは出羽三山の修験者であるとの説を2017年に発表している。御来迎については槍ヶ岳開山を果たした僧播(ばん)隆(りゅう)の前に出現した話が有名である。
《参考資料6》光(ウィキペディアより)
光は様々な思想や宗教において、超越的存在者の属性を示すものとされた。古くから宗教に光は登場しており、より具体的には太陽と結びつけられることも多かった。古代エジプトの神、アメン・ラーなどはその一例である(太陽神も参照)。プラトンの有名な「洞窟の比喩」では、光の源である太陽と最高原理「善のイデア」とを結びつけている。
新プラトン主義では、光に強弱や濃淡があることから、世界の多様性を説明しようとしており、哲学と神秘主義が融合している。例えばプロティノスは「一者」「叡智(ヌース)」「魂」の3原理から世界を説明し、「一者」は、それ自体把握され得ないものであり光そのもの、「叡智(ヌース)」は「一者」を映し出しているものであり、太陽であり、「魂」は「叡智」を受けて輝くもので月や星であるとし、光の比喩で世界の説明を論理化した。この新プラトン主義は魔術、ヘルメス主義、グノーシス主義にまで影響を及ぼした、とも言われている。
『新約聖書』ではイエスにより「私は、世にいる間、世の光である」(ヨハネ福音書 9:5)と語られる。またイエスは弟子と群集に対して「あなたたちは世の光である」(地の塩、世の光)と語る。ディオニュシオス・アレオパギテースにおいては、父なる神が光源であり、光がイエスであり、イエスは天上界のイデアを明かし、人々の魂を照らすのであり、光による照明が人に認識を与えるのだとされた。この思想はキリスト教世界の思想に様々な形で影響を与えた。しばしば光=正義、闇=悪の二元対立としてたとえて語られた。
グノーシス主義では光と闇の二元的対立によって世界を説明した。仏教では、光は、仏や菩薩などの智慧や慈悲を象徴するものとされる。
《参考資料7》太陽神(ウィキペディアより)
太陽神とは、太陽を信仰の対象とみなし神格化したもの。古代より世界各地で太陽は崇められ、崇拝と伝承は信仰を形成した。(中略)主な世界の太陽神の事例は以下の通り。
アイヌ神話 -トカプチュプカムイ
インカ神話 - インティ
エスキモー・イヌイット神話 - マリナ
エジプト神話 - アテン、アトゥム、アメン、ケプリ、ホルス、ラー、ハトホル、セクメト
ギリシア神話 - アポローン、ヘーリオス
ケルト神話 - ベレヌス、ルー
スラブ神話 - ダジボーグ、ベロボーグ
中国神話 - 東君、金烏(三足烏)、羲和、日主、太陽星君
日本神話 - 天照大神、天道、天火明命、天之菩卑能命、稚日女尊、八咫烏、饒速日命
ペルシア神話 - フワル・フシャエータ、ミスラ
北欧神話(ゲルマン神話) - ソール
リトアニア神話 - サウレー
メソポタミア神話 - シャマシュ
ヴェーダ神話 - インドラ、ヴィヴァスヴァット、ダクシャ、バガ、ミトラ、サヴィトリ、プーシャン、ヴィシュヌ
ローマ神話 - アポロ、ソル、エル・ガバル
ヒンドゥー教神話 - ヴィシュヌ、スーリヤ、サヴィトリ
仏教 - 大日如来、日天、日光菩薩
フェニキア神話 - バアル、シャプシュ
メキシコ神話(マヤ・アステカ) - ウィツィロポチトリ、ケツァルコアトル、トナティウ、キニチ・アハウ、イツァムナー
《参考資料8》真言(ウィキペディアより)
サンスクリット語のマントラの訳語で、仏教では、「(仏の)真実の言葉、秘密の言葉」という意味である。最初は、バラモン教の聖典である『ヴェーダ』に、神々に奉る讃歌として登場し、反復して数多く唱えることで絶大な威力を発揮すると考えられていた。後に、バラモン教に限らず不可思議力を有する呪文をことごとくマントラと言うようになった。このバラモン教等の信仰であるマントラが、徐々に仏教にも採り入られた。
真言の多くは、密教経典に由来し、日蓮宗、浄土真宗を除く、多くの大乗仏教の宗派で用いられる呪術的な語句である。これを観想しこれに心を統一することで、仏の真理の教えに触れ得るようにしたものが、真言であるとされる。空海は、真言について「真言は、不思議なものである。本尊を観想しながら唱えれば無知の闇が除かれる。わずか一字の中に千理を含む。この身のままで真理を悟ることができる。」と記しているという。仏尊ごとに真言があり、それぞれ出典となる経典が存在する。
《参考資料9》三(さん)密(みつ)加持(かじ)(ブリタニカ国際大百科事典より)
三密加持とは、密教用語。衆生と仏とは本来同一であるから,衆生が身に印を結び (身密) ,口に真言を称え (口密) ,心に本尊を観じる (意密) とき,それがそのまま仏の三密と相応して,仏の加護を受け,仏と同一となること。